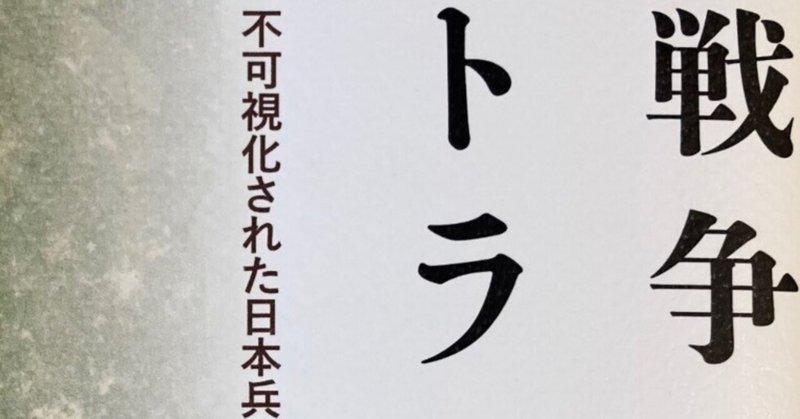
中村江里『戦争とトラウマ 不可視化された日本兵の戦争神経症』 (と塚本晋也『野火』)
横浜にある「シネマリン」という小さな映画館では、毎年8月になるとひとつの映画が再上映される。塚本晋也監督『野火』である。これはもはや風物詩のようなもので、上映の知らせが届くたびに日本の夏がやってきたことを感じる。好きな映画なのでなるべく予定を合わせて観に行くようにしているが、それはやはり娯楽としてだけではなく、戦争の記憶を風化させないためのアクションに参加しているのだと認識している。
『野火』はもともと1951年に発表された大岡昇平の小説が原作で、1959年に市川崑が映画化している。市川崑版も、戦地で飢餓に追いつめられる兵隊の存在を記録した素晴らしい反戦映画だと思う。しかし、塚本晋也がリメイクした2014年版には、市川崑版には記録されていなかった人間の姿がある。記録されていなかったというよりも、1959年の時点では誰もそれを発見することができなかった人間の姿である。それは戦争体験を生き延びた帰還兵のその後、つまり「戦争によるPTSD(心的外傷後ストレス障害)」である。
中村江里『戦争とトラウマ 不可視化された日本兵の戦争神経症』は、現存する限られた資料を集めてその記憶を蘇らせる。国家規模で忘れようと努力した記憶を蘇らせる。この本のなかでも塚本晋也版『野火』について触れられているが、あくまで参照程度に留められている。ここでは、あらためて『野火』をひとつの軸にしてこの本の内容を要約してみたい。なぜならば、この本は1959年と2014年のあいだをつなぐ一冊だと言えるからだ。
総力戦における人的資源の確保を第一目的として、軍事心理学はその治療を発展させてきた。しかし治療が本当に必要とされるのは戦時中だけではない。敗戦を迎えて帰国したあとも、帰還兵たちはそれまで置かれていた残酷な環境との落差に適応できない。そのタイムラグにこそ戦争神経症の困難があるのだが、その実態が公に認められることはなかった。
『野火』の主人公である田村一等兵には戻れる場所があったようだ。しかし、「有職で既婚である=社会適応」という限定的な理解が現実の障害を不可視化してしまう。田村一等兵の場合、特に食事に関するトラウマが深く、晩年に至ってもなおフラッシュバックが起きているようだ。これは、トラウマ体験から六ヶ月以上経過して発症する「遅発性PTSD」、もしくは沖縄戦を生き延びた高齢者のあいだに見られるような「晩発生PTSD」だと考えられる。
また、田村一等兵はその後、文筆家として生計を立てているようだが、おそらく自身の体験を治療的に言語化する機会には恵まれなかったのだろうと考えられる。戦争帰還兵による自己治療としての言語化は、「男らしさ」「恥」「ウィークネス・フォビア」といった社会規範によって封殺されてきた側面も大きいからだ。特に「ヒステリー」は女性特有の症状であり、まして誇り高い日本兵男子には起こりえないものだと宣伝されてきた。日本人だけでなく、世界全体がこの誤解から解放されるのは1970年代、ベトナム戦争帰還兵による証言を待たねばならなかった。
そしてラストシーンにおける田村一等兵の異様な動作は、祈りをささげているようにも、自傷行為をしているようにも見える。おそらくそのどちらも正解なのだろう。塚本晋也監督もそれについては答えを示さず、観た人がそれぞれ考えてほしいと語っていた。言語化して自分の体験を統合したいという願望と、すべてなかったことにして忘れてしまいたいという願望が、田村一等兵のなかで葛藤しているのではないだろうか。それは戦後社会全体が強いる忘却のムードに対する、個人の生命による抵抗と言えるかもしれない。
以上が、映画『野火』を通して読み解く「戦争とトラウマ」である。あくまで俺個人が体験した『野火』を拠りどころにしてその要旨を嚙み砕いたつもりだ。
それ以外にも、この本にはもっと幅広い情報と複雑な示唆が含まれている。精神疾患に対する差別。上位階級に対する優遇。社会資源の不足や地域格差。そして、傷痍軍人の恩給制度について言及されていることはこの本の特筆すべき点である。戦時中の日本においては軍医が重要な役割を果たしており、戦争神経症の解釈は精神科医療の観点だけでなく国家財政的な影響を強く受けていた。戦争神経症の存在を認めることは、国家への責任追及を許すことでもある。個人の問題なのか国家の問題なのか。これは公害や自然災害の二次被害、貧困や自殺などの様々な問題と重なるところも大きいかもしれない。「戦争の記憶を風化させない」のはもちろん大切なことだと信じているが、この本を読んで感じるのは、私たちが今まさに戦争の記憶のなかに生きているかもしれないという可能性である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
