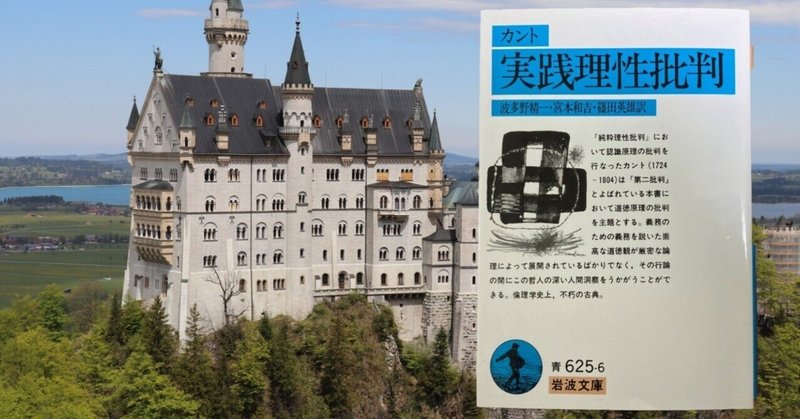
もしも高校倫理の先生がカントだったら。『実践理性批判』
カント「こんにちは。私はイマヌエル・カントといいます。近代のドイツから来ました。この授業では私の道徳哲学を皆さんに紹介します。テキストは私の著書である『実践理性批判』を使います。今日はよろしくお願いいたします。」
生徒一同「よろしくお願いいたします。」
みんなに通用するマイルール
生徒A「カント先生と言えば【君の意志の格律が、いつでも同時に普遍的立法の原理として妥当するように行為せよ】って言葉が有名ですよね。どういう意味なんですか?」
カント「みんなに通用するマイルールに従って行動せよという意味です。【意志の格律】とは簡単に言えばマイルールのことです。そして【普遍的立法の原理として妥当する】とはみんなに通用するということです。みんなに通用するマイルールに従って生きることが道徳的に生きることだと私は考えています。」
生徒A「みんなに通用するマイルール…すぐには思いつかないですね…」
カント「そんなときは逆にみんなに通用しないマイルールを考えてみましょう。みんなに通用しないマイルールには①条件付きである②主観に基づいているという共通の特徴があります。」
生徒A「条件付きって【○○ならば××せよ】みたいな感じですよね?」
カント「そうです。例えば【可愛い女の子ならば優しくせよ】のような主観的条件が付くルールや、【お年玉をもらうために親戚には愛想良くせよ】のように行為の結果得られる成果を目的としたマイルールはみんなに通用しません。」
生徒A「確かにどんな女の子がタイプかは人それぞれだし、お年玉目的で親戚と付き合うなんて不純ですもんね…じゃあ【幸せになろう】とかどうですか?条件付きじゃないし、みんな幸せになりたいはずです。」
カント「幸せの基準は人それぞれですから【幸せになろう】は主観に基づいています。みんなには通用しません。」
生徒A「うーん…難しいですね。そもそもみんなに通用するマイルールなんてあるんでしょうか?」
カント「私たち人間は感情や欲求から完全に自由になることはできません。主観から離れることはできないのです。しかし、みんなに通用するマイルールを探し続けることはできます。見つからなくても探し続けることをやめてはいけません。道徳的に生きようとする努力をやめてはいけません。」
道徳的に生きようとする努力
生徒B「先生は先ほど道徳的に生きようとする努力をやめてはいけないと仰いました。具体的にはどんな努力をすればいいんでしょうか?」
カント「まずは行為の動機を考える習慣をつけてください。」
生徒B「動機…ですか。」
カント「行為の道徳性を判定するには動機を知ることが必要です。例えば部活動で顧問がいるときだけ一生懸命練習する生徒がいたとします。行為としては一所懸命練習しているわけですが動機は顧問の評価を上げることです。これでは真面目に練習しているとは言えませんよね。」
生徒B「なるほど、内容や結果ではなく動機に注目することで行為の道徳性が判定できるというわけですね。」
カント「その通りです。よくあるのは行為としては道徳的でも動機が快楽であるというパターンです。例えば別れたさみしさに付け入ろうと振られた女性の話し相手になろうとする男性がいたとします。行為としては女性の心を癒しているのでしょうが、彼の動機はその女性を手に入れることです。これでは道徳的とは言えません。」
生徒B「実体験ですか?」
カント「違います。」
カント「動機に注目することが習慣になると、快楽に惑わされずただ道徳的であろうという動機による行為に出会います。そのとき私たちは尊敬の感情を抱きます。または道徳的行為者と自分を比べて羞恥心を抱きます。」
生徒B「ドキュメンタリー番組を見ているとたまにそんな気持ちになりますね。特に同年代ですごく頑張っている人が紹介されていたら、この人に比べて自分はなんて怠け者で軟弱な人間なんだと思ってしまいます。」
カント「そして尊敬や羞恥心といった感情は私たちに自分も道徳的に行為せねばならないという義務の意識を生みだします。あとは義務の意識に従って行為するだけです。ただし、義務の意識に従って行為することはかなり大変です。なぜなら快楽を求める人の本能に真っ向から対立する場合がほとんどだからです。」
生徒B「なんだか救いのない話ですね。道徳的であることと幸せになることは両立できないんでしょうか?」
カント「できます。義務の意識に従って行為することを続ければ自分の人格に満足できるようになります。自分は道徳的に善い人間だという意識です。自分を肯定できるというのはとても幸せなことだと私は思います。しかもこの幸せは快楽に頼らない幸せですから自分の心以外を必要としません。最近の言葉で言えばサステナブルな幸せです。皆さんもぜひ自分の人格に満足できるようになってください。では、今日の授業はここまでとします。ありがとうございました。」
生徒一同「ありがとうございました。」
参考文献
カント著 波多野精一、宮本和吉、篠田美雄訳 『実践理性批判』 1979年 岩波書店
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
