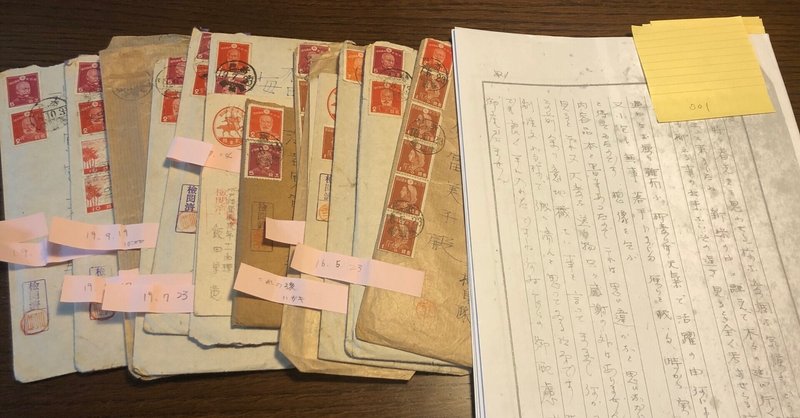
亡くなった方の恋文をもとに本の制作をする
昨年の秋、「蔵から古い手紙が出てきた」とたけよさんから連絡があった。
それは、戦時中に交わされた結婚前の祖父母の恋文。全16通。
祖父母としての姿しか知らなかった彼女は、時を超えて若い二人の愛に触れて、これを一冊の本にしたいと思った。そこで、私のことが頭に浮かび、本の制作を依頼した。
恋文は、残念ながら軍にいた祖父側のものしか残っていなかった。
若かりし祖母が大切に保管していたのだろう。女心を感じてキュンとなる。
材料はそれだけ
「どんな形がいいかは任せるから好きにやってほしい」
話を聞いたとき、”面白そう!やってみたい!”と思った私は、二つ返事で引き受けた。好きで文章を書いていると、こうした思いもよらないオファーが舞い込んでくるんだとワクワクした。
・
・
まずは送られてきた恋文に目を通すことにする。
まさか赤の他人の私に読まれると思わずに手紙を書いていたEさん。ちょっと照れているかもしれないなあ。人の手紙を勝手に読むことへの複雑な思いが湧いてくる。「お二人の物語を書くために読ませていただきますね」と手紙の束に向かって頭を下げる。
封筒の”検閲済み”のハンコが戦時中であることをリアルに感じさせる。宛先には”女子挺身隊”の文字が。おそらく祖母のFさんは国のために工場で働いていたのだろう。
手紙を何通か開いてみると、きれいな字が並んでいた。達筆で、しかも昔の言葉を使っているため、読み解くのに時間がかかりそうだ。
恋文の解読と同時並行で、祖父母を知っている子や孫たちにインタビューし、記憶の中の二人の姿を語ってもらった。
二人が暮らした家で、過去のアルバムを眺めた。
お墓参りをさせていただいた。
古い言葉が使われた恋文を16通解読した。
・
・
さあ、これをどう料理しようか。
この手紙のやり取りをしていた時期に、二人はどのような関係性だったのかは結局不明のままだった。
恋人関係だったのか、婚約していたのか、手紙の途中で関係性が変化していったのか。そして、祖母のFさん側の手紙はどのような内容だったのか。
推測して、想像を膨らませながら物語を書いていくのは楽しい作業だった。
戦時中で楽しみもほとんどなく、固定電話も限られた場所にしかなく、携帯電話もないこの時代に、好きな人から手紙が届くことがどれほど嬉しいことだったか。
限られた休みの日に会おうとして待ち合わせをするにしても、すべて手紙でやり取りしなければならない。予定の変更も葉書で伝える。
不便で大変な時代だったからこその喜びがあったに違いない。
恋文、写真、インタビューを一つ一つ紐解いていくと、二人の人物像が浮かび上がってきた。そこには、手を取り合って懸命に生きてきた二人の歴史があり、有形・無形の愛があふれていた。私自身も、自分の祖父母に思いを馳せて、愛されていたことを思い出した。
そして、写真撮影が好きだったEさんが残した写真が、実は物語を書く上で大きなヒントになった。写真は、時に言葉よりも雄弁に語るのだと知った。
直接二人を知らない私も、言葉を紡ぎながら泣きそうになる。
二人から子や孫、ひ孫へのエールを感じた私は、それを文章に込めた。
"愛しているよ"
"好きなように生きなさい"
"大丈夫、いつだって応援している"
・
・
・
2月4日、原稿が完成した。
やれることは精一杯やった。
ドキドキ、祈るような気持ちでたけよさんに原稿を送った。
最初の3行で泣いた、とたけよさん。全部読み終わったところで電話をくれた。
インタビューに答えてくださった皆さんも喜んでいるとのこと。
「池田さんに頼んで本当に良かった」
「池田さんは色んな人を幸せにする技術があるね。素晴らしいライターです」
嬉しい言葉をシャワーのように浴びて、挑戦してよかったと思った。私を信頼して、好きにやってと任せてくれた彼女のおかげだった。
本の挿絵は、版画家の友人に依頼するとのこと。
叔母様たちの生きる希望になっている本の完成は、まだもう少し先。本が完成し、笑顔の皆さんが一堂に会する日がとても楽しみだ。
初めて会った時から、見ず知らずの私を温かく迎えてくれて、話を聴かせてくれたたけよさんの親族の皆さん。私も、茨城に遠い親戚ができたようでなんだか嬉しい。
自分が好きなことでこんなに喜んでもらえるなんて、なんて幸せなんだろう。こういう仕事をこれからもしていきたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
