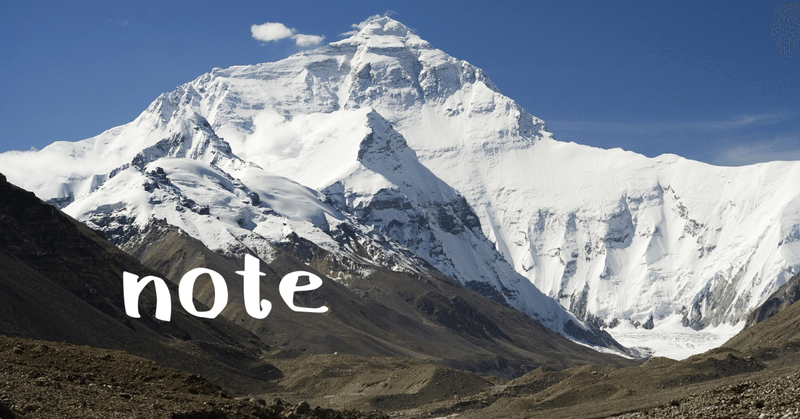
河合薫「40歳で何者にもなれなかったばくらはどう生きるか 中年以降のキャリア論」
初めて部下を持ったのが45歳って、どうなのか。うちの職場は昇進が遅い。特に私たちの世代以降(ポスト団塊ジュニア的な?)は、人数の多い上の世代に阻まれ、係長になるのがどんどん遅くなっている。他の自治体の人の話す時に少し恥ずかしくなったりもする。ああ、仕事できないやつと思われるかな、とちょっと頭をかすめる。私は育休を計4年取得したこともあるし、全般的に女性は遅いというのもある。40歳の時に私は何者にもなれなかったわけで(まあそもそも係長で何者かになれたとも思わないけれど)、そんな自分にぴったりの本だと思った。
河合薫氏はたまにネット記事で読むことがあって、いつもなるほど、と思わされる内容だった。結構過激なことも書いてあり、すっとした気分になった記憶もある。とはいえ、ちょっとここまで普段もやもやとしていたことを言語化してくれるとは想像していなかった。
まあ、なんとなく予想していたことではあったということもあり、私は45歳まで係長になれなかったことを卑屈に思っているわけではない。むしろ、誰かを部下に持つことを想像する期間が長かった結果、10人の直属の上司の仕事ぶり、マネジメントぶりを見ることができた。こんなところを見習いたいと思ったこともたくさんある。けれど、ああはなりたくない、今の発言はないでしょ、とか色々思ったこともある。だから自分がなった時には、こんな風になろう、というイメージがちょっとできたりしていた。
実際に部下を持ってみると、こんなに係長としての仕事が大変だとは思わなかった。
何が大変って、もちろん係の仕事のマネジメントというのもある。いつも部下には恵まれていると思っているし、それが大変なのは当たり前のことだと思っていた。実際に一番大変なのは、何となく自分より若い世代である部下たちと話した中で、こうだよね、と思ったことが、上に話を持っていくと、真っ向から否定されることがあるからだ。たいてい、上の世代は、時代が変わっていることに気付いていない。
河合氏は「"ジジイ”の壁」という言葉を使っています。
「ジジイの壁」は「おじさんの壁」と言い換えられるほどやわじゃありません。ベルリンの壁よりも厚く、チョモランマよりも高い。そもそもここでいう"ジジイ"とは年齢的なものを指しているわけでも、男性のことを批判しているわけでもありません。組織内で権力を持ち、その権力を組織のためではなく「自分のため」に使う人たちが「自分の保身のため」に築き上げた壁を意味しています。
河合氏によれば、最初からジジイはジジイだったわけではないそう。権力を得たことで、「何者かになった」錯覚により、ジジイの壁に巣食う輩となり下がってしまった、と言っています。
とはいえ、若い人の意見を、という話も出ています。ちょっとそれは羨ましかったりもする。私たちはただ黙っていれば従え、みたいな感じだったのに、Z世代とか、子ども・若者、というワードがあちこちで掲げられていて。
「僕たち氷河期世代は、パワハラ、長時間労働、低賃金の三重苦に耐え、精一杯生きてきました。その後は働く環境も改善されましたが、恩恵を受けるのはいつも次の世代です。報われなさに絶望します」
こんな話をした方の話も紹介されていて、そうだよ、と頭の中で思い切り同意しました。
でも一方で、子ども・若者の意見が、ひょっとしたらいいように使われちゃうのではないか、と心配になったりもする。
つまり、自分の考えと合致した部分だけをZ世代、子ども・若者の意見として取り上げたりするんじゃないか、とか、うまくいかなかったらハシゴを外すんじゃないか、と思うことが多々ある。
なので、私たちの世代がやるべきことは、それなりに身につけてきた実現力を駆使し、間に入っていいように利用されていないか見張ったり、実現できるようにサポートしたりすることなのじゃないかと、考えたりもする。
こういうのを、ジェネラティヴィティっていうそうです。ああ、自分のしてたことって、そんなに変わったことじゃないのなら、ちょっと安心した気持ちになれる。
ジェネラティビティ(Generativity)」は心理学者のエリクソンが、成人後期(40~65歳)の課題(発達課題)にあげた造語で「次世代の価値を生みだす行為に積極的に関わること」を意味しています。
エリクソンは名前は聞いたことがあったのだけど、多分、耳にしたのは学生時代の心理学の講義。ということはそんなに新しい人のはずじゃなくて、調べてみると、1950年に出した本の中で、発達段階論について説明していて、その中でジェネラティビティという言葉が出てきているそうです。新しい言葉ではないのか、と思うと、ジェネラティビティという課題はそんなに簡単に成し遂げられるものでもないし、広くみんなが取り組むものでもないのかなという気も。
そもそも、上の世代がそれを課題だと思ってくれていればもう少し私たちも生きやすくなったはずで。
さらにいえば、仮に若かりし頃はよい未来を作っていきたいという心がけでいたとしても、権力を得ることでおかしくなってしまうということもあるのかもしれない。
実は私自身、少しだけ不安にかられています。若い人のことを応援したい、考えを一緒に実現したいと思いながらも、ひょっとしたら、上の世代に対して自分たちの力だけではうまくいかなかったことをもてはやされている若者の言葉を借りて実現しようとしているのではないか、とか、若者の言葉をまるごと受け止めているのではなく、自分に都合のいいことだけ抽出しているのではないか、結果として潜在的に利用しようとしていることになっているのではないかと。
この不安を常に意識しつつ、これからの人生を歩んでいきたいな、と思いました。
ここに紹介したのはほんの入り口の話です。私もまだきちんと咀嚼しきれていないのですが、会社のためにではなく、人生のために働こう、生きていこうと河合氏は言っています。そこで大切になってくるのが、「強い自己」。何もそれは力学的な強さを言っているのではなく、タマネギの皮をむき、身となっているものもむいていき最後に残る芯のような、そういう「強い自己」だといいます。
そこにたどりつくための7箇条が掲げられていて、その一つ一つについて、インタビューで得られた様々な人の生き方を紹介しながら、説明しています。
この本を読んだからといって、"ジジイ"の壁に対抗できる強さが簡単に得られるわけではありません。でも自分自身を見失ってはいけないと河合氏は言います。私たちは、幸せになるために生きなければいけないのです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
