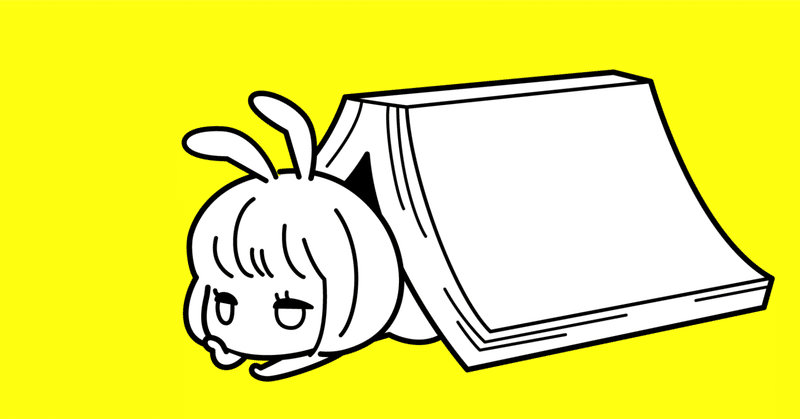
軽い軽やかさ〜panpanya讃
panpanyaと聞いてどれだけの人が、オッ! と目を見開くのだろうか。
これまで刊行した単行本や作品の掲載誌「楽園 Le Paradis」、そして本人が運営しているらしいブログから窺い知れる情報のほかは、まったく素姓の知れない人物である。本名から性別、年齢、経歴、出身、資格、専門、顔立ち、声色、身のこなしに至るまでの何一つとして伝わってこない。巻末とかどこかのメディアで「明かさない美学」を掲げるような周到な素振りも見せない。制作にあたる自分の背中や手元だけを写す、素姓不明のアーティストにありがちの思わせぶりなポーズを氏が取ることは決してない。あたかも、明かす・攻める・示す・バラす、あるいは、秘める・守る・隠す・バレるということが少しも念頭にないかのようだ。
noteを書く者がいちどは直面する問題が、panpanyaにとってはなんでもない。
愚問、秘密、ノーコメントと斥けるまでもなくひたすら「無記」。
「無記」(avyākata, avyākṛta)とは、形而上学的な問題について判断を示さず沈黙を守ることである。無用な論争の弊害からのがれ、苦しみからの解放という本来の目的を見失わないためにとられた立場である。
なんでもないことさ、と口にされることさえない、究極の何気なさは、触れる者をしばしば呆気にとる。書籍のブランディングに欠かせないはずの販売部数表示も、意外な著名人による推薦文も載っていない代わりに、新しい夢の世界に招き入れるようなコピーが書かれた本の帯を眺めるだけでも、事の重大さが実感できる。
「みんな読んでるんだ」「あの人も読んでるんだ」
ビッグでインフルエンサーなファクトのエビデンスに倚りかからない書籍のあり方は、出版不況を切り抜けるべく案出されてきた戦略が盛り込まれている本に慣れた目には留まりにくい。
しかしひとたび留まったが最後、ぶわりと噴き出す呆気に呑まれる。
あえなく呑まれてしまった人が一定数いるから、丸善やヴィレッジヴァンガードの一角に特設のpanpanyaコーナーが開かれているのだろう。被害者は増えているのだろうか。問うても返答はない。独り、読書本来の静けさに立ち返ろう。
わが家の書棚にpanpanyaの単行本が加わったのはいつのことだったか。
仙台随一の大型新刊書店であったジュンク堂書店のほの暗い漫画コーナーでたまたま見つけた憶えがあるから、少なくとも、同書店が仙台から撤退する2021年以前のことだ。手塚治虫か藤子不二雄か、とにかくpanpanyaに関係ない漫画を物色していたところで背表紙に目を奪われた。「足摺り水族館」「蟹に誘われて」「動物たち」「二匹目の金魚」……恐怖や興奮といった明瞭な感情を喚起しないものの、そのぶん内容勝負を挑もうとするタイトルに興味を覚えたし、panpanyaという謎めいた雅号も然り(そのままパンパニャと読んで事足れりとしていたが実際はパンパンヤである。そうかといって相変わらず何がなんだか分からないけれど)。ほかの漫画では見たこともないような、過剰と素朴のバランスで描かれた表紙にも感心した。一冊あたり千円という、漫画にしてはかなり強気の値段設定ゆえしばしためらったけれど、けっきょく買った。
最初に読んだ単行本はpanpanya初の単行本『足摺り水族館』だ。
なんでもないことのように、おぼろげな不安やざらついた手触りのする砂埃を巻き上げながら運行して進むなにかに、各話揺られるような感覚があった。ほとんどの話のあいだに関係は見られないから、ぶつりぶつりと終わる物語の背後に、ビックリマンチョコ的大局観を持てない。氏の作品の帯コピーによく単語が現れる「夢」のごとく、物語世界にたいして醒めた理解や操作を加えたり、現実世界に適用できる教訓を引き出そうとする取り組みは本書の前でことごとく弾かれる。本を開いているあいだだけがpanpanyaとの接点である。夢想と現実のいずれかに無理に振り分けて考えようとすると破綻が生じる。
そういうわけで原理的にうまくまとまらない宣伝文句もそこそこに妹にも勧めた。たちまち彼女は惚れ込み、ふたりでpanpanyaの他の単行本を買い揃えることと相成った。水面下に引かれたかのように揺れる描線を特徴とし、ノワールで憂愁を帯びた初期作から、ぎっしりした描線が定着し如実にユーモア要素を深めつつも、安易な笑いに回収できないざわつきを残す近作まで、全て追っている。
最近はいよいよ母も読んでにやにやしている。
panpanya作品にたいするぼくの入れ込みっぷりも我ながら大したものだと考えている(何かにつけpanpanyaの作品を引き合いに出してその話題と関連させてしゃべるなど)が、妹の向ける熱情とて見逃せない。
発売中の「楽園」第33号からご紹介その5はpanpanya「魚社会」。「ニューフィッシュ」以来の鶴見漁港が舞台の物語です。
— 楽園編集部 (@rakuen_info) July 6, 2020
最新コミックス『おむすびの転がる町』絶賛発売&配信中!
色紙プレゼントもご応募お待ちしてます♪ 詳しくは本誌第33号巻末をご高覧下さい。 pic.twitter.com/LGT5yQ8O7Y
panpanya作品の掲載誌「楽園 Le Paradis」が2020年に挙行した色紙プレゼント企画がある。「楽園」33号巻末にある応募券が貼付され締切までに白泉社に届いたハガキから抽選で一名に直筆色紙を贈るというもの。
運悪く消印有効前夜にその存在に気づいたわれわれ兄妹はまず、情報に疎かった己を呪う叫び声を団地一帯に響かせた。ひとしきり哀号したのち、どちらからともなく「まだ間に合うか……?」と言い出した。ふたりとも押し黙り、鉄を溶かすほど赤熱した目頭で要項を読み込む。そもそも手元に33号がなく、仙台市内で取り扱いがあるか定かではない。そこでぼくが改めて泣き言を漏らすより早く、妹はペンを執り、ハガキに向かいはじめた。手元にpanpanyaの単行本を積んで。
黙々と机に向かう彼女を横目に収めつつ、膝に猫君をのせてふたりむっつりと座り込んでいたら、日付変わって1時ごろだったろうか、卒然と妹が立ち上がりハガキを寄越した。寝ぼけ眼で猫君と見てみると、ハガキ下半分にpanpanya作品おなじみの登場人物(+犬のレオナルド)が並んで焼き芋を食べるオリジナルの場面が、氏と瓜二つの画風で描かれていた。抽選の場とはいえ完全な中立はむづかしく、熱意の籠もった目を惹くデザインのハガキが比較的当たりやすいというのがもっぱらの噂である。是が非でも当選する心意気を感じ取り、応と答えた。
翌日ぼくは市内の書店を駆け巡り、ようよう33号を買い求め、震える手で切り取った応募券をハガキに貼りつけたのち、読む者の心に縋り、この上なく哀切に訴えかけるような嘆願文をびっしり書き添え投函した。「ワタクシドモ家族ミナアナタノ作品ヲ愛読シテオリマスノデナニトゾナニトゾヨシナニシキシチョウダイ」云々。逆効果じゃないか? という諫言が脳裏をかすめたが、良くも悪くもこれが文学部の精一杯である。
さて、なんにせよ当選した。われら兄妹の宛名までしっかり記されている。
panpanya作品に頻繁に登場する、前後左右に四本の短い管が伸びた奇妙な球体のイメージがでかでかと中央に描かれている。そばには水墨画のような淡いタッチの立木があるかとおもえば、panpanyaらしい細か〜い描き込みが堪能できる歩道の側溝もあり。球体のそばに立つ、漫画の主人公格を張るにしてはぎりぎりに切り詰められた描線を特徴とする顔立ちの登場人物は、なにを見ているのだろう。
ココナツを割るバイトに従事したかとおもえば、模型づくりに熱中し、ブロック塀を作ったかとおもえば、缶詰を売り出し、ラーメンを茹でたかとおもえば、ベッドを改造し、漁師として勤務したかとおもえば、小学生になり、高校生になり、時間を飛び越え、職業を跨ぎ越え、論理を乗り越える。リアリスティックな画風と曖昧な筆致の混在。いちいち断らないままに自由闊達に繰り広げられる、軽い軽やかさに今後もぼくは魅せられるに違いない。
「恋愛系コミック最先端」を掲げる「楽園」に、なぜpanpanyaがいるのか。
あのとき買った33号をぱらぱらめくりながら考える。
当人がまったく違和感を覚えている素振りがないのは気持ちいい。
以下に挙げるは白泉社からのpanpanya既刊。
一年に一冊、夏が巡ってくるたびの刊行と考えていいようである。
購入した暁にはいちど書籍カバーをめくっていただきたい。価格が納得されよう。
氏の公式サイト。「surmiclusser」とはなんなのかはあくまで示されない。
ホームページのバナーにある「photo」と「link」はまさにpanpanya。
町並みへの目つきを知らず知らずのうちに捻じ曲げてくる仕掛けが豊富。
panpanyaが装幀・挿画を手がけた学術書がこのたび発売された由、重ねて宣伝。
以下、レッツ無記無記な本。
I.M.O.文庫から書物を1冊、ご紹介。 📚 東方綺譚/ユルスナール(多田智満子訳)
