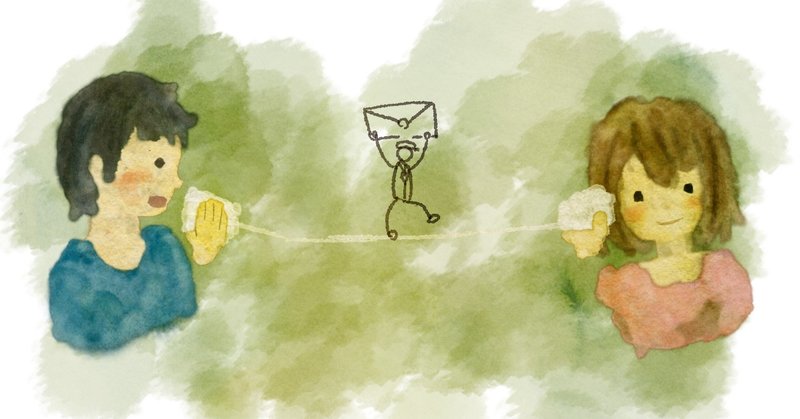
五千キロ向こうの瞳 【短編小説/#旅のようなお出かけ】
遠距離恋愛。
時男はこの言葉の持つもどかしくていじらしい肌触りだけで安易な憧れをもっていた。
そしてその罰が簡単に当たった。
東京の時男が神戸のみどりと落ちた恋。
それは実際にまんざら悪いものではなかった。
かけがえのない人が必ずしも近くにばかりいるとは限らないではないか。
むしろ運命の人と遠い距離にいるのに繋がれるなんて素晴らしい。
障壁はある。しかし恋愛自体が目的ではない。
二人が苦難を克服しやがて思いを成就することができたなら、今の何百キロどころか何十センチいや何センチの距離に毎日一緒にいられるのだ。
それが「結ばれる」ということではないか。
正々堂々とゼロセンチだって。ヒヒ。。
そのいやらしい笑顔が神の目に触れたか、さらなる厳罰が下った。
インドネシア共和国ジャカルタへの海外赴任辞令。
神は柔和な表情一つ変えず、その距離にゼロを一つ追加すると告げ給われた。
「名前は時男といいますが生まれは横浜です」
いったいこれまで何度このフレーズを使って自己紹介をしてきたことだろう。
今回は海外だけに「TOKIO」と強調したのだが、あれほど冗談好きと聞いていたインドネシア人スタッフたちの反応は話と違い水を打ったように静かなものだった。
しかし、持前の快活さ、そして適度の無責任さで彼は数々の難局を乗り切って、契約期間三年の残り一年を切るところまでたどり着いた。
さて、時男とみどりは彼のジャカルタ赴任後わずか一度しか会っていない。
時男の年二回の一時帰国のチャンスを大いに利用したいところだが、五千キロの距離を詰めたところで、元の東京と神戸の遠距離恋愛に戻るだけなのである。
その一度にしても時男がジャカルタへ戻る空港の搭乗前ほんの僅かの時間のことだった。
みどりが仕事を終えたその足で神戸から羽田空港へ超高速移動し滑り込みで叶えることができたものである。
余裕をもって到着した時男よりもむしろ搭乗するのはみどりの方でないかというほどのそれは見事な走りっぷりであった。
時男はあるコーヒーのプロジェクトを任され北スマトラ州のメダンに一時滞在をすることとなった。
日頃からなにかと突発的に振り回されがちな身分だが、収穫期を中心としたプロジェクトということもあってか今回は早々にプログラムが示された。
時男はこの期間に突入する前にみどりをバリ島に呼んで数日間を一緒に過ごそうと考えた。
みどりはその話を聞くと小躍りして喜び、その日のうちに職場の上席先輩同僚後輩全員に話を通し平和的に有給休暇承認を取りつけた。
しかし、その頃世界中に及び始めた忌まわしき新型疫病は二人のこのささやかな楽しみをも奪ってしまうのであった。
みどりが今度は自身の搭乗のために空港構内を走る光景は儚くも幻となってしまった。
みどりは荒れた。
「いつ会えるのよ!」
こっちが訊きたいよ。
時男の背景に彼の今の絶望感を演出するように一日を締めるアザーンが鳴り響いた。
すでにここはメダンである。
時男にとってこのバリ島旅行はとても重要な意味をもっていた。
みどりに結婚を申し込もうと思っていたのである。
さすがの時男もこの頃には遠距離恋愛にうんざりしていた。
自分はいい。みどりがあまりに不憫であった。
みどりは熱病に罹ってうわごとを言うように、
「一緒に現地料理試して、一緒に道に迷って、一緒に伝統芸能観て、一緒にお土産もの選んで、、」
「おい!みどり!それだ!旅をしよう!一緒に食事して、一緒に路地を散歩して、一緒に買い物をしよう!」
今日はみどりがこの状態なので後日仕切り直すこととした。
日曜日の昼下がり、時男は街中からビデオコールでみどりを呼び出した。
「さあ、一緒に昼食だ。何が食べたい?」
「マルガリータピザ」
「いや、そこは本気で答えるんじゃない。あえて現地食を冒険するんだ。どうせ食べられないんだから」
「変なの」
それなら、とガイドブックで見たナシゴレンの現物を一度ライブで見てみたいという。
何をしたらあんなに茶色い色に仕上がるんだ。素直にそういう観点らしい。
では、と言って、時男は撮影方向を自撮りから正面方向に切り替えた。
この先に時男自身が一度試してみたかった人気のナシゴレン屋台がある。
到着すると店の男が注文を急かすように火を大きくしてお玉で鍋をカンカラと鳴らした。
時男は、今からある国の重要な方が直接あなたにオーダーなさりたいと言う、両国の今後の関係を思うと何があろうと一発で聞き取るようご助力をいただきたい、と重心を落とし彼の耳元で呟いた後、みどりに戻って、
「ミンタ・ナシゴレン・サトゥ(ナシゴレン一人前ください)、と言ってごらん」
「ミンタ・ナシゴレン・サトー?」
自信のなさが語尾を上げた。
男が画面に向い胸に手を当て深々と頭を下げた後、敬礼をした。
みどりが五千キロ向こうから、わぁ通じた!と騒いでいる。
ナシゴレンの包みを公園で開いてみどりに見せる。
「口に入らないトホホなナシゴレン」とみどりがぼやく。
では私が代表して、と時男はナシゴレンを一口頬張る。
「なるほど、、」
バターだ。あの屋台の評判の理由はアジア料理にして意外なこの濃厚なバター感だったのだ。
何がなるほど、なのか教えろと画面の奥でみどりが騒いでいる。
ナシゴレンを平らげたあと時男は公園から路地に入る。
路地裏からまた路地裏へと迷って見せながら進み、最後に元の大通りに抜ける。
夕景に少しずつ傾き始めた通りの風景を披露してその日のみどりとの小さな旅をまとめた。
口に入らなかったリベンジをぜひ晴らしたいと意味不明の言葉を添えて、みどりが今度は自分が神戸を案内するという。
この「旅」のいいのは日常の交信と同じようにお互いのわずかな時間を利用し分けて行えることである。
小柄な彼女の背の高さでローカルの商店街の風景ががたがた揺れつつ、今日の旅が滑り出す。
ある店先で立ち止まる。
中に入ると店のど真ん中に主のごとき風格の大きな鉄板が見える。
画面は鉄板のままで、撮影承諾を得たあと注文を入れるみどりの声が聞こえる。
鉄板上でまず肉と野菜、さらにご飯と刻んだ中華そばが炒められ、続いてソースがぶっかけられ攪拌される。
騒がしく暴れて湯気を発していた具材がやがて香ばしくまとまっていく段になってやっとみどりが感じた不完全燃焼感を思い知った。
みどりは「そば飯」の包みをトロフィのように掲げて勝ち誇った。
メダンってバリと全然違うよね。
「地味」
そもそもバリに一度も行ったことがないのにおかしいことを言うなあと時男は思ったが、そうかワクワクしながらガイドブックを何度も何度も読み返したのだな、と少し悲しい気持ちがした。
「民族、宗教、文化、慣習が全く違うからね。その短い一言で全部まとめて言っちゃったね」
時男はプロジェクトでサポートしてくれているイスラム教徒の知人に次にご登場願おうと心に決めた。
勝手に心に決められた気の毒な知人はインドネシアの正装をまとい少し固い面持ちでイスラム寺院の前にいる。
その前でスマホを構える時男の合図に従いイスラム世界についてミニ解説を始めた。
わぁ、雰囲気ある!とみどりが反応した。
「時男!そこに行きたい、と彼に伝えてよ」
「みどり、旅しているのは君だから自分で言うんだよ」
時男はインドネシア語の簡単なしおりも用意していた。
「サヤー、マウ、えーとなんて書いてるの、ペルギー・ク・サナー(そちらに行きたいです)」
すると知人の方がえらく舞い上がって、ウェルカム!ミドリサン!サヤ・ジュガ・マウ・ク・サナ!(私もそちらに行きたいです)と、よく考えたら全くすれ違いの二人の会話であった。
この遊びによって時男とみどりは旅情を共感し旅の記憶を集めたのである。
みどりがアプリタクシーを呼び、夕陽を背に屋台街まで走る。
時男がみどりの先輩が買った新車に乗せてもらう。みどりが新車の匂いをレポートして足す。
みどりが土産物屋店内で可愛い木彫りのアートを見つけて、時男より巧みに値段交渉する。
時男が神戸の港で二人が初めてデートしたその場所を探し、そこで記念撮影をする。
彼らが気づいたか気づいてないか、神は二人に船の汽笛をプレゼントした。
時男はメダンから山を六時間ほど駆け上がったところのとある町にいた。
プロジェクトがいよいよ具体始動となり、今回はまず一週間ここをベースにして事前情報と現況との突き合わせを行う予定である。
部屋の小さな机でその日の記録をまとめ終わり、スマホで通信履歴を確認するとみどりからメッセージが入っていた。
可能なら今ビデオコールを繋いでみてほしい。
時計を見たあとコールすると、突然画面は騒がしく眩しい情景を映し出した。レストランからのようだった。
ガサガサとこすれるような音がして半拍遅れでみどりが映る。
「あ、繋がった!プロジェクトの成功を祈念して乾杯しよ!」
相槌を打とうとしたその時、みどりの隣に男がいるのに気がついた。
男は、あ、と自分が映っているのに気がついて、落ち着いた様子で自己紹介をしたあと、
「私はみどりさんとは、、」と言いかけると、みどりが止める様子が伺えた。
「ああ、二人きりではありませんから心配しないでください」
と彼はごく自然にまとめて、みどりからスマホを受け取りパンしながらみどりを含めてその場に男女2人ずついる様子を写した。
「トキオさん、でしたね。一緒にやりましょう!みどりさんがボーイフレンドを海外から招いて一緒に乾杯したいということでしたから」
ボーイフレンドか。。
スマホがテーブルに置かれたか、何も狙っていない気のないショットになった。
当人たちは知ってか知らずか画面のぎりぎり端になんとなく映っている。
男がみどりに少しもたれかかるようにして耳打ちした後「店員さん!こちらの女性にグラスワイン一つお願い!」といかにも慣れた振る舞いを見せた。
時男は通信を切って、湯量をいつもより強くしてシャワーを浴びた。
少ししてみどりからコールがあった。いったん外に出たようである。
「どうして切ったの?みんなで乾杯しようって言ってたのに」
あの男の側に立って言っているように聞こえた。
「会社もそろそろ在宅勤務を取り入れるっていうし、私も当分神戸案内できないかも知れないのに」
「合同コンパの実況中継が今日の神戸案内か?」
「まさか時男。。」
みどりがぼろぼろと泣き始めた。
「だからバリ島に行きたかったのに!なんでこんな時に変な病気が流行るのよ!」
ああ、旅の途中の喧嘩までついているとはどこまでリアルなお遊びなんだ。
時男はため息をついてベッドに倒れこみ、窓の外の星空を見た。
切るのも躊躇われ放置したスマホからみどりのミソミソ泣きすする声が聞こえ続けた。
産地ワークは暗いうちから早起きし詰めて動いたくらいでそうそう思うように前進してくれるものではない。
午後からの局地雨でたちまち時間効率が落ちる。
どこに移動するにも距離がある上に悪路である。
日本から質問と課題が頻繁に発され入れ変わる。
生産者側との神経質な意思調整に本音が見えない。
そして、前進しようがしまいがとにかく一日は終わる。
立てつけの悪い窓から入る小虫を払いながらベッドにもぐって明かりを消す。
みどりの表情と声が浮かぶ。そしてあの男の落ち着いた口調。
夜の静寂というものは時々残酷なものである。
みどりが言っていた通り彼女は在宅勤務となり外出が激減し神戸の旅はお預けとなった。
たまにベランダからの眺めや手作りの料理の写真を送ってはくれたが、本人自身がつまらなかったと見えてそれも途絶えてしまった。
時男もコーヒー農園の風景をビデオコールでみどりに見せてやろうと思っていたがそんな簡単なこともさぼって、コーヒーチェリーの写真を一枚送っただけであった。
時男からなんとなく疎遠ぎみになったには一つわけがあった。
このところ明らかにみどりと繋がりにくくなっていたのだ。
きちんと折り返し連絡はくれるのだ。
ただ何となく自分の優先順位が下がったように感じるのであった。
特に夜の特定の時間、どこか特定の相手に積極的に繋がっている。
そんな感じがするのであった。
今回の予定を終えてメダンに戻る日の朝、時男はみどりにコールした。
「おはよう。今日下山するから出発前に一度連絡しようと思ってね。こないだはごめん。白けさせたな」
「こないだコーヒーの写真を有難う。コーヒーの実て可愛いのね」
みどりはこないだのことに触れなかった。
「考えてみたら僕たちの「旅」って出口を決めていなかったね。
旅には必ず終わりがある。でもその次には、あの旅は楽しかったなあ、とそういう余韻がある」
「賛成。時男は本当にいろんなことを思いつくね」
みどりは小さく笑ったあと、
「じゃあ時男も今日が一つの区切りだし、私たちの旅も今日をお開きということでどうかしら」
意外にもあっさりした反応だった。
「では後でもう一度連絡をするよ。何か飲み物を用意しおいてくれ。打ち上げの乾杯をしよう」
スマホを置いて時男は荷物をまとめはじめた。
旅が終わる寂しさまで再現できて人間とはなんと簡単に錯覚するように出来ているものかと思った。
みどりとはあれからも何気ないチャットのやり取りが続いてごく当たり前の日常を過ごしている。
ただ、夜の時間になると繋がりにくいのは相変わらずだった。
しかし、繋がったところでみどりに明日会う約束をして、安心させてあげられるわけでもない。
そんな風に考えることも多くなってきた。
プロジェクトは順調であった。
あまりに順調に運び過ぎて、昨日本社から駐在任期延長の内示があった。
どこか遠くに聞こえるアザーン。
本当にみどりと旅をしたかのように神戸の情景が懐かしく思い出される。
港から臨んだ海の青さ、坂の並木道の若葉の緑、中華饅頭やそば飯などローカルグルメの熱々の湯気の白さ、みどりがかぶりついたケーキからこぼれ落ちそうなフルーツの赤黄橙。。
思い出は短編フィルムのように映写され、お祈りが終了した瞬間それらは吸い込まれるようにブラックアウトした。
静寂。
今まで経験したことのない例えようのない不思議な気持ちであった。
もしこれを寂しさというなら自分は今まで寂しさというものを知らなかった。
翌日、みどりからチャットで連絡があり今夜ビデオコールを繋ぎたいとあった。
その用件については何も書かれていなかった。
久しぶりのビデオコールだ。
ちょうどいい。今夜任期延長のことも伝えよう。
彼女がどういう結論を出そうが自分は彼女の意思を尊重する。今まであまりに彼女を振り回し過ぎた。
コールが鳴り、時男は反射的に応答する。
みどりの髪型は今まで見たことのないショートカットに変わっていた。
そしてこれも今まで見たことのない神妙な面持ちをしている。
彼女は自宅でなく小会議室のようなスペースにいた。
そして、座っているみどりの隣には見守るようにしてあの男が立っていた。
時男はかける言葉を失った。
みどりは彼に、二人きりにしてください、と退出を促した。
彼が完全に部屋から出たのを確かめた後、また時男の方を向いて、
「こないだの旅はこれが抜けていたよね。静かな場所で二人きりで向かい合うこと」
と苦笑いしながら言った。
「悲しかったのはバリ島に行けないことなんかじゃないの。このまま時男に会えなくなるんじゃないかと思ってそれがとても怖かった」
みどりは涙を拭ったあと、
ここからインドネシア語で、
「時男君、本当にありがとう」
バリ島に自分を呼んでくれたこと。
いろいろユニークな仕掛けで自分を慰めてくれたこと。
どんなわがままを言ってもけして叱らず自分を可愛がってくれたこと。
どんなに忙しくてもいつも自分に都合を合わせてくれたこと。
自分にやきもちを妬いてくれたこと。
と、時男に対する深い感謝の気持ちを表す言葉が続いた。
時男が呆気にとられていると、日本語に戻して話を続けた。
バリ島旅行が決まった頃からインドネシア語を習い始めた。
職場近くの外国語学校でまず短期コースを修了し、コースを変更して続けようと思っていた矢先に新型疫病の影響で一時休校となった。
他の学習方法がないものか学校のアドバイザーを務めるある大学講師に相談をかけた。留学生コミュニティに顔が広いと聞いていたからである。
それが彼である。しかし、これ以上関わるのはよそうと思っている。
「時男が心配してくれたこと残念ながら当たってた」
学校がインドネシア語講座をオンラインで再開したので、最近は夜の時間を使いこれを受講しているという。
今日は久しぶりに学校に来て空いている部屋を使わせてもらっている。
「インドネシア語のこと内緒にしたかったけどね。でも続けるよ。時男とこれからもずっと仲良くしていたらインドネシア語が必要になりそうだからね」
といたずらっぽく笑う。
今が「その時」だ、と時男は反応した。
「回りに誰もいないのか?」
いないよ。
「廊下に僕たちの声は聞こえないか」
聞こえないよ。
「時間をあと少しだけもらえるかな」
大丈夫よ。
時男は五千キロ向こうのみどりの瞳を見つめて大きく深呼吸をした。
つくづく不思議なものだな。
味覚や匂いを伝えるのにあれほど苦労したのに、この思いならどんなに離れていても真っ直ぐに伝えられそうな気がする。
遠距離恋愛万歳!
今度は神に見られないようににやりと笑い、
その笑顔を止めて顔を上げもう一度みどりの瞳を見つめた。
