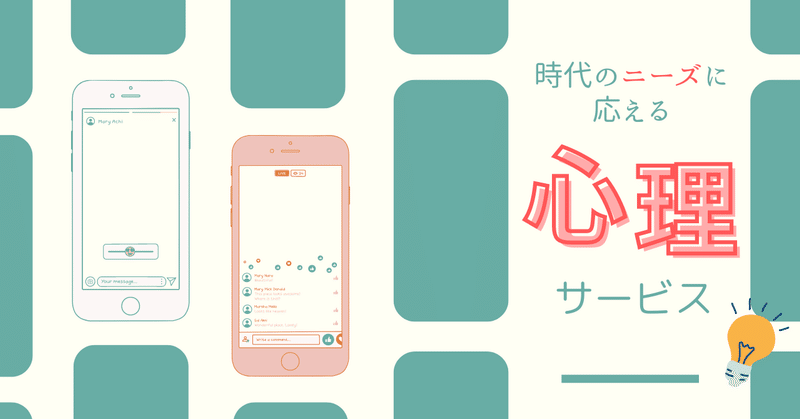
30-4.時代のニーズに応える心理サービス
(特集:生まれ変わる臨床心理iNEXT)
下山晴彦(臨床心理iNEXT代表/跡見学園女子大学教授・東京大学名誉教授)
Clinical Psychology Magazine "iNEXT", No.30-4
【ご案内中の研修会】
緊急企画:「公認心理師試験の解題と対策」研修会
「第5回試験結果から公認心理師試験の動向を読む」
■9月3日(土曜) 9時〜11時
■講師 宮川純 河合塾K A L S
【申込み】
[臨床心理iNEXT有料会員](無料):https://select-type.com/ev/?ev=OyXQkmeXZSQ
[iNEXT有料会員以外・一般](1000円):https://select-type.com/ev/?ev=XxAkQPNk_5o
[オンデマンド視聴のみ](1000円):https://select-type.com/ev/?ev=zbV32bxoMnw

「注目新刊書」著者オンライン研修会
「ゲームやネットへの依存と認知行動療法」
■9月11日(日曜) 13時〜16時
■講師 神村栄一 新潟大学教授
【申込み】
[臨床心理iNEXT有料会員](1000円):https://select-type.com/ev/?ev=GqSgSQoE1N4
[iNEXT有料会員以外・一般](3000円):https://select-type.com/ev/?ev=nAuhxXdyey0
[オンデマンド視聴のみ](3000円):https://select-type.com/ev/?ev=9DrA882joeU
【新刊書】『公認心理師のための「心理支援」講義』(北大路書房)
https://www.kitaohji.com/book/b607714.html

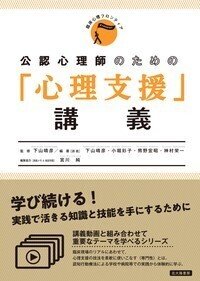
1.今という時代のニーズに応える心理サービス
臨床心理iNEXTの新ビジョン「みんなの心理サービス、選ばれる心理職へ」には、“今という時代において多くの人が必要とする心理サービスを提供する”という意味が込められています。そこで、9月11日(日)に、神村栄一先生の「ゲームやネットへの依存と認知行動療法」研修会を開催します。
近年、インターネットの普及で、子どもや若者のゲームやネットへの依存が大きな問題になっています。不登校、引きこもり、昼夜逆転などの背景には、ほとんどの場合、ゲームやネットへの依存が維持要因として関わっています。このような依存に対する心理支援サービスは、心理職だけでなく、現代社会を生きる誰にとっても最重要のテーマです。
なお、9月3日(土)は、緊急企画として河合塾KALSの宮川純先生の「第5回試験結果から公認心理師試験の動向を読む」研修会を開催します。8月26日は第5回試験の合格発表です。今回は出題傾向が変わり、受験生の戸惑いが広がっています。まさに心理職を目指す皆様や心理職教育に携わる皆様のニーズが高いテーマです。

2.ゲームやネットへの依存と認知行動療法
神村栄一先生は、『公認心理師のための「心理支援」講義』(北大路書房2022年7月刊※1)において、「認知行動療法の実践的理解と介入の工夫」として「適応障害」「強迫症」「ギャンブル障害」に関するケースフォーミュレーションの使い方を解説されています。
そこで、神村先生に「ゲームやネットへの依存と認知行動療法」というテーマで「注目新刊書」著者研修会の講師をお願いしました。ご存知のように神村先生は、日本の認知行動療法のリーダーの一人です。また、ゲーム、ネット、ギャンブルなどへの依存行動や習慣行動の変容のための認知行動療法の第一人者です※2)。最近では、よい睡眠をとる習慣づくりについて子どもと一般保護者に向けたYouTube動画も公開されています※3)。
なお、今回の研修会に向けて『公認心理師のための「心理支援」講義』を購入希望の方は、「臨床心理iNEXTからの紹介」と明記して、下記の北大路書房のホームページの商品ページ※4)から直接ご購入いただければ、特典付きで同書をご提供できるとのことです(ご注文→直接購入(カートへ)へとお進みください)。
多くの皆様のご参加を期待しています。
※1)https://www.kitaohji.com/book/b607714.html
※2)https://psych.or.jp/publication/world091/pw09/
※3)https://youtu.be/TXtT0etUGe8
※4)https://www.kitaohji.com/book/b607714.html

3.射幸心を煽るゲームやSNS
[下山]研修会の参考書になっている『公認心理師のための「心理支援」講義』(北大路書房)は、臨床心理フロンティアシリーズの他書に比較して、専門性が高い内容となっています。心理職として現場に出た人にとっては、とっても役立つ本です。そのため、もっと詳しく知りたいと望む読者が多いと考え、本研修会を企画しました。
今という時代においては、射幸心を煽るゲーム※5)やS N S等のネット環境の中で、誰もが依存の魔の手に堕ちないように対処していかなければいけません。子どもや若者の心理支援に関わる心理職にとって、ゲームやネットへの依存に対する介入は必須テーマです。そこで神村先生に今回の研修会のポイントについてインタビューさせていただくことにしました。
近年、ゲーム、特にオンラインゲーム、そしてティックトックといったSNSメディアが子どもや若者たちの間で広がり、どんどんそこにのめり込んでいく。以前は、ゲームやネットは、問題の維持要因であったように思います。しかし、最近では、それらが不登校や引きこもりの原因になっているのではないかと感じることがあります。
※5)ゲームが射幸心を煽る仕組みについては、ゲーム作成者のバイブル本である下記書籍が参考となる。
「ゲーマーズブレイン -UXと神経科学におけるゲームデザインの原則」(ボーンデジタル)
https://www.borndigital.co.jp/book/13127.html

4.ゲームやネットへの依存の現れ方
[下山]神村先生としては、問題行動としてのネットやゲームへの依存っていうのは、どんなふうに考えておられますか?
[神村]おっしゃる通りで、小・中・あるいは高校までの不登校、あるいはちょっと広げて専門学校や大学生までも、登校や就学が順調でない場合、ネットやゲームへの依存が問題発現のきっかけの一つになっていますね。それから、問題の維持要因としても、もう生活習慣の問題として切り離せなくなっています。どうしても生活リズムが夜型に移行します。目が覚めた頃には一日の半分が過ぎちゃっている、とか。だから「もう、今日はいいや」という気持ちになる。もともと考えていたのとはまったく異なる、一日になってしまう。その繰り返し。
最近の睡眠研究によると、若者では特に、夕方から夜にかけて1日の中で最もテンションが上がるようになっているそうです。昔からよくある話で、不登校の子が、朝から昼過ぎまでは調子よくないけど、夕方から夜になると妙にテンションが上がってきて、家族とよく喋りたがるようになってくる。「いいかげんにしなさいよ、それより明日の登校はどうなの?」と訪ねられると、「うん、明日はちゃんと起きて朝から学校に行くよ」と応える。
それは決して嘘や言い逃れ、ではない。ご家族も、淡い期待をかけたりする。ところが、そのテンションは、寝るべき時刻になっても落ちていかない。眠くならないのでやることといったら、ネットとかゲームとかSNSとなる。やりはじめれば夢中になり、ますます目が覚めてしまう。しかも、家族が寝静まると、思い切って好きなようにできる。気がつくと、寝落ちするのが2時から3時、時には朝方までになる。その結果、やっぱり朝は調子が悪い。登校は難しい。その繰り返し。

5.ゲーム・ネット依存を生活習慣の問題と捉える
[神村]そのような依存の問題を生活習慣病的な形で捉えられるかどうかが、認知行動療法を効かすための肝となります。鬱でも強迫でも不安症でも嗜癖の問題でも、生活習慣病的な形で捉えることが大切ですね。「ゲームやネットへの依存」においても、その生活習慣の特性をどう理解し、どのように変えていくかが重要となります。
特に若い人の不調は、どうしてもゲーム・ネット、SNSへの没入とつながりやすい。そこで、睡眠のリズムを一日24時間全体のリズムの中で整えていけると良い、ということになる。ただ、若い人に、「ネットやゲームを止めよう」と提案すると、だいたい嫌がられますよね。支援の関係がつながらない。「またそこね、それだけは無理」となって先に進まない。
だから、ゲーム・ネット依存の完全排除を目指さず、生活習慣全体を整えるのが課題、と捉えていけると良いでしょう。感情的にさせなければ、本人も、整えたい、という気持ちはある。「やりたいことのための時間は残してもいいんだけど、睡眠はしっかりとったほうがよいし、そのためにリズムを整えよう」と導いていったほうが、かえって進みやすい。そんなことがあると思います。
[下山]ありがとうございます。ゲーム・ネット依存を生活習慣として捉えるという見方はなるほどと思います。昔ならば、夜に家族でテレビを見て、ある時間になると「さあ寝るか」となる。しかし、今は、ゲーム、ネット、SNSが生活の中に入り込んできていて、睡眠のチャンスを奪っている。

6.日常生活に入り込むゲーム・ネット依存
[神村]今の時代はもう、家庭での「チャンネル争い」って死語ですよね。テレビを見るのは中高年から高齢者だけ。子どもも、20代の若者も、もう自分のスマホ画面がすべて。
[下山]そうですね。数年前までは、「なんか学校行きたくないなぁ」といった状態から段々不登校になって行くというプロセスがあった。そこでは徐々にゲームにハマって行くという前段階があった。しかし、今はそうじゃない。ゲーム、SNS、インターネットが生活の中に入り込んでいる。ちょっと油断すると、もうそこに引き込まれていく。そういう危険な状況。神村先生がテーマとしていたギャンブル依存に近い刺激環境が、子どもたちの日々の生活の周囲にあるということですね。
[神村]そうですよね。
[下山]毎日パチンコ屋で生活しているようなものですね。ところで、ギャンブル依存とゲーム・ネット依存との違いはありますか。
[神村]幼い頃からゲーム、機械ものが大好き、という方でそのままパチンコにハマる方もあるようですが、すべてがそう、とは言えないかもしれません。ギャンブルの場合は借金をこしらえて、それが生活や人間関係の破綻みたいなことになりかねない。中にはそれが背景となって犯罪、職場のお金の使い込み、一家離散みたいなことになったりするケースも。かなり深刻になる。そこで、そこまでいけば、それでも改善したいとなれば、契約してかなり強力に介入することもあります。例えば、家族に事実上の金銭管理をしてもらうとか。
ただ、ゲームとかスマホを見る、YouTubeを見ちゃうなんていうのは、まぁそれ自体で生活破綻する、家族全体に深刻なダメージ、ということにはまずならない。それは本人の自由、価値の問題みたいなところもある。ただ、コントロールがなかなか効かなくなる、ということはあるわけで、それがきっかけで、不登校や引きこもりに移行していくということはあると思います。この8年ほど、小中の不登校は急激に増えていますが、少なくともその急増したぶんは、「10年前だったら不登校になるまではなかった」子どもたち、とも言えるのかと思います。こんな単純な計算の議論には、抵抗ある方も多いでしょうが。
[下山]なるほど、よくわかりました。やはりゲーム・ネット依存はギャンブル依存とは違いますね。

7.ギャンブル依存とは異なるゲーム・ネット依存の怖さ
[神村]ゲーム・ネット依存は、引きこもりや睡眠の問題とかにつながっている。あっという間に、時間が過ぎてしまい、葛藤を感じる時間が奪われている、みたいな印象があります。ギャンブル依存では、生活破綻するほど深刻ではなくても、「ギャンブルを止めないといけない」といった動機で相談に来られる人もいます。しかし、10代の子で、面接室で本人が、「こんな時間のつかい方はもう止めたいんです」と語ってくれることはありません。「子ども本人からどうなりたいのかをしっかりと聞き出してそれを尊重したい」、とかいう一見して耳に心地よい言い方は、どこか現実と乖離しているようにも思います。
最近、認知行動療法でも「価値観」ということが話題になっているみたいです。どういう人生を送っていきたいかっていう、クライエントさんの価値観を再確認していく。そして、その価値観に基づいて「少し生活を整えていくよ」といった話をする。そんな進め方が良いのかと思います。ただ、これも10代で、ネットやゲームへの依存が激しくなっている状況だと、じっくり対話していくのはとても難しいですね。
[下山]ゲーム・ネット依存は、ギャンブル依存と違って分かりにくいという特徴がありますね。今は、誰の周囲にもゲーム・ネットが、少なからずそれに興じている。だから、それとは分からずに依存が始まっていく。だからこそ、その人の価値観が重要になるわけですね。
[神村]ギャンブル依存は、「このお金の減り方はおかしい!」となって気付きやすい。それに対してネットやゲームは、普段の生活でみんなやっているからと安心してやり続けることができる。昔から、「みんなやっている」は10代の子の常套句。そして、気づいたらそこから抜けられない事態となっていたり。しかも、子どもや若者の場合、それは、不登校や引きこもりにつながり、その後の人生において、そこそこ深刻なリスクとなります。メディアで積極的に発言されているような、不登校になったおかげで人生が開けた、みたいな境地に到達できるのは、かなり少数派かと思います。多くの不登校の小学生や中学生は、不登校になって1年もすれば、「やっぱり登校していた方がよかったかな」と後悔しはじめる割合が最も多い、という文部科学省の調査もあります。

8.ゲーム・ネット依存は家庭問題への導火線となる
[神村]子どもさんの場合、やはり家庭状況や親御さんの生活スタイルと切り離せない。今、格差社会と言われます。インターネットに接続すること、端末を手にすることに関しては、生活的に苦しいご家庭でも Wi-Fiくらいは備えられている。おじいちゃんおばあちゃんのスマホを夜は孫のもの。ですから、今は、家庭の格差っていうと、むしろ、リアルを体験させてもらえるかどうかの違いになっていますよね。
経済的に余裕ない家庭や仕事が忙しい家庭では、「相手もしてあげられない、連れてってもやれないが、ネットで過ごしてくれ」となりがち。子どもは、「あぁ、それでいいよ。ゲームとスマホさえあれば何も文句言わないよ」となる。このようにゲーム・ネット依存には、家庭状況も関わっている。だから、家庭状況に即したスモールステップの課題、段取りを考えていくことが現実的には重要かなと思います。
[下山]親が子どもに対して「ネットとかゲームばかりやるのを止めなさい」「使う時間を区切ろうよ」と言うのは定石ですね。そして、そこに反発が出てきて、潜在していた親子間の問題が顕在化してくる。例えば、それまで親が子どもの世話をしてこなかったとか、親への不満を我慢していたといった潜在的な問題が顕在化し、時に親子喧嘩になって爆発する。だから依存の問題は、親子関係や家族関係の問題に発展する導火線になる。
[神村]そうですよね。本当にそこが難しい。今電車に乗ると、そこに座っている人の10人に9人はスマホをいじっていますね。ですから、何をどう問題として認識していくか、そしてそこにつながっている家庭の問題とか、生活習慣の問題をどのように捉えていくかがテーマとなる。どの子においても同じところを目指す、ってわけにもいかないでしょう。そこが、セラピストの腕の見せどころになるかと。どのように問題を整理し、何を目標として設定し、それをクライエントさんとどのように共有するかが重要になりますね。

9.研修会に向けて
[下山]なるほどです。改めてこの「ゲームやネットへの依存と認知行動療法」というテーマは面白い。というか重要ですね。
[神村]そうですよね。子育て行政も、安易に世論にすり寄っているように見えますが。
[下山]多くの心理職がうすうす感じているゲーム・ネット依存の問題の分かりにくさ、そして深刻さへの対処は、現代社会で特に求められている課題ですね。このテーマに関わるケースは、どんどん増えている。ところが、心理職の意識や技法は、現実の変化の速さについて行っていない。頭が切り替わっていない。
「ゲームやネットへの依存にどのように対処するのか」は、社会的ニーズが非常に高まっています。しかし、心理職は、その問題をまだ直視できていないですね。改めて、当日の先生の講義を楽しみにしています。ぜひよろしくお願いいたします。

■記事制作&デザイン by 田嶋志保(臨床心理iNEXT 研究員)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
