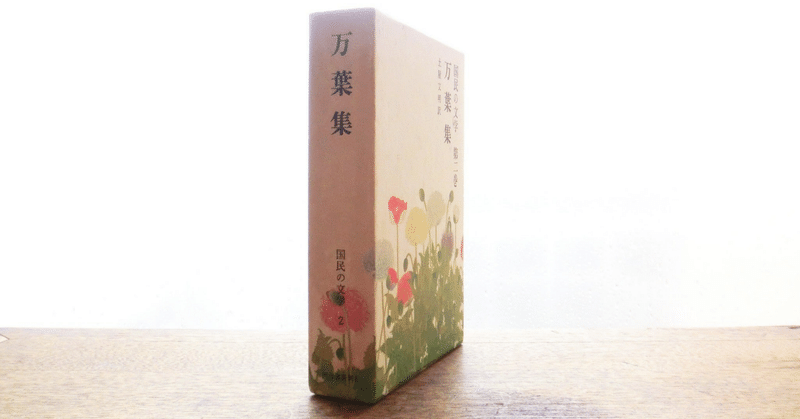
5分 de 読む『万葉集』入門【全文無料】
『万葉集』とはどのような古典作品なのか、そのあらましや魅力を5分で読めるテキストにまとめました!
【5分 de 読む『○○』入門】は、音声配信Voicy「毎朝古典サプリ」上で好評を博したシリーズ「10分 de 〇〇~日本の名作古典文学を学ぶ~」を文章化したものです。記事作成にはみみずくさんにご協力いただいています。
『万葉集』の概要
『万葉集』といえば現存最古の歌集です。
『古今和歌集』や『新古今和歌集』など、和歌集にはいろいろありますし、が、現在残っている和歌集で最古のものは『万葉集』です。奈良時代の終わりに完成したとみられています。
『古事記』や『日本書紀』といった歴史書の中に少し歌が入っているので(記紀歌謡)、そちらが最古の歌と紹介されるケースもありますけれども、歌集としては『万葉集』が最古です。
奈良時代の終わりというとまだ平仮名が発明されていない時期です。ですから、万葉仮名という漢字による一種の当て字の形で表記されています。
例:春されば=波流佐礼婆
パズルが好きな方は、万葉仮名での表記が載っている本を買ってきて、それと訓読されている文を対応させて解読を楽しんでみるというのも、『万葉集』の楽しみ方の一つではないかと思います。
『万葉集』はできてきた経緯などにわからない部分も多いのですが、最終的な編纂者は大伴家持とみられています。とはいえ、大伴家持一人が短い間で完成させたものではなくて、昔からずっと編まれてきたものが家持のときに完成したとみる方がよいと思います。
入っている歌はなんと4500首ほど。百人一首の100首でさえ「多いなあ」と感じている人もいるでしょうから、4500首というと『万葉集』の規模の大きさがわかると思います。
本人が本当に作った歌かどうかは怪しいところもありますが、最古の歌としては仁徳天皇の皇后、磐之媛(いわのひめ)の作が入っています。仁徳天皇は3世紀半ばに生まれ、西暦400年前後に崩御したとみられる天皇ですので、その歌がもし本当に磐之媛が詠んだものであれば、西暦300年代の作から、奈良時代の大伴家持の作まで、大体350年から400年もの長い期間の歌が収められていることになります。
しかも、貴族や皇族といった高貴な人だけでなく、東歌(あずまうた)や防人歌(さきもりのうた)には庶民的な階級の歌も収められています。
最近の私たちには、元号「令和」が『万葉集』の「梅花の宴」の序文の部分から取られたということでも馴染み深い歌集です。
万葉集ここがスゴイ!
『万葉集』ですが、何がすごいのかというポイントを一言で言うと、現存最古の大歌集であるということです。
今日有名な百人一首がまとめられたのと比べても500年近く前であり、『万葉集』はとにかく古いアンソロジーであることがわかります。今日から見れば1250年近く前です。そんな古に完成した歌集であるという点が、やはり何よりもすごい点です。
その特徴から、吉田の個人的なお気に入りポイントの2つも生まれています。
吉田裕子の万葉集お気に入りポイント①古い時代の和歌の役割
『万葉集』で私の個人的なお気に入りポイントの1つめが、古い歌集であって、まだ和歌が文学や芸術として確立する前の、共同体の中での歌であった時代の空気がふんだんに残っているということです。
もともと和歌というのは、共同体の中でのコミュニケーションであるとか、神への祈りであるとか、支配者のセレモニーであるとか、そういったところで役割・機能を果たしていたと考えられます。その空気が『万葉集』の歌、特に1巻から3巻などの歌には多く残っていると感じます。
たとえば、天智天皇が亡くなったときに、その后である倭大后(やまとのおおきさき、倭姫王(やまとひめのおおきみ)とも)が詠んだのが次の歌です。
天の原振り放け見れば大君の御寿(みいのち)は長く天(あま)足らしたり
この歌は天智天皇が危篤のときを迎えて、いよいよ亡くなってしまう直前に、天皇が元気になることを祈って作られた祈りの歌です。
「見て見て。辺りを見渡してみると、天地には天皇の命が生き生きと満ち溢れて、永久に続くような感じがしていますよ、見てください」
という和歌です。
しかし、現実には天皇は弱っていて、今にも命の火が燃え尽きようとしています。言霊の力を借りて、「ほら、天皇の命が世界に満ち溢れている」と詠むことで、天智天皇の魂が元気になることを祈りました。
このように、文学としての和歌というよりは、神に祈る言葉としての和歌が『万葉集』には入っています。
他にも、行き倒れの死人の魂を慰めるような和歌や、心細い旅をしている人がその土地の土地神様に祈りを捧げて無事に通してもらおうとする和歌なども入っています。
国見をする歌も『万葉集』に特徴的です。「国見」というのは「国を見る」と書きます。天皇やその代理人が国土を見渡し、「ここは自分の国である」ということを確認します。そんな支配のセレモニーの中での歌が国見の歌です。
ここで舒明天皇の長歌をご紹介します。リズムが少し独特の五七調になっていることにも注意していただけたら嬉しいです。
大和には群山(むらやま)あれど
とりよろふ天(あめ)の香具山
登り立ち国見をすれば
国原は煙(けぶり)立ち立つ
海原は鴎(かまめ)立ち立つ
うまし国そ蜻蛉島(あきづしま)大和の国は
何となくゆったりとした雰囲気を感じていただけたでしょうか?
途中で出てきた「蜻蛉島」という言葉は日本列島を称えて言う言葉です。他にも、「国原は煙立ち立つ」は、民の竈が調理のための煙を出している様子で、民がきちんとご飯を食べられているという国の繁栄を歌っています。こういう風に我が国を見渡し、我が国の素晴らしさを称え、これからもそういう国であるようにと祈りを込めて詠んでいるのが、天皇の国見の歌です。こういう歴史ロマンを感じるのも『万葉集』の特徴です。
吉田裕子の万葉集お気に入りポイント②素朴でストレートな思い
もう一つの吉田お気に入りポイントをご紹介します。
『万葉集』は古い歌集だけに、言葉の吟味であるとか、和歌の技巧であるとかという部分がまだ十分に発達していません。だからこそ、ストレートにバンッと歌が詠まれていて、却って現代人には素朴に共感しやすい歌が多いというところがあります。
特にそれが顕著なのが恋の歌です。私が好きなのは次の歌です。
思ひにしあまりにしかばすべをなみ出でてぞ行きしその門(かど)を見に
「あまりにも君のことを思って、好きだから、どうしようもなくて、家を飛び出していったよ、その子の家を見に」という意味です。
このように「中学生男子か?」と思うくらいストレートな恋の歌がたくさん詰まっているのも『万葉集』のおすすめポイントの一つです。
というわけで、『万葉集』は、古の歴史ロマンを感じたい人、もしくは、恋の歌などで自分も共感できる歌を探したい人におすすめです。
万葉集 古典初心者向けの参考文献
最後に、「『万葉集』を勉強したいな」と思った方に入門となる本をご紹介します。
私が執筆監修しました『万葉集が丸ごとわかる本』というムックが晋遊舎から出ています。また、読みやすい入門書としては、鈴木日出男先生の『万葉集入門』が岩波ジュニア新書から出ています。リンクを張っておきますので、よろしければチェックしてみてください。

本記事は全文無料で読めるようになっていますが、今後、合計40の記事が投稿される内、30本が有料(1本100円)、10本は無料となる予定です。全て個別に買うと3000円になりますので、たくさんの記事を読みたい方は、有料マガジン「5分 de 読む古典入門~日本の名作古典文学を学ぶ40~」での一括購入(2000円)の方がお得です。
ここから先は

5分 de 読む古典入門~日本の名作古典文学を学ぶ40~
音声配信Voicy「毎朝古典サプリ」でご好評いただきました”10分de○○”という古典入門シリーズがこのたびテキストの形でも楽しめるように…
サポートは、書籍の購入、古典の本の自費出版に当てさせていただきます。
