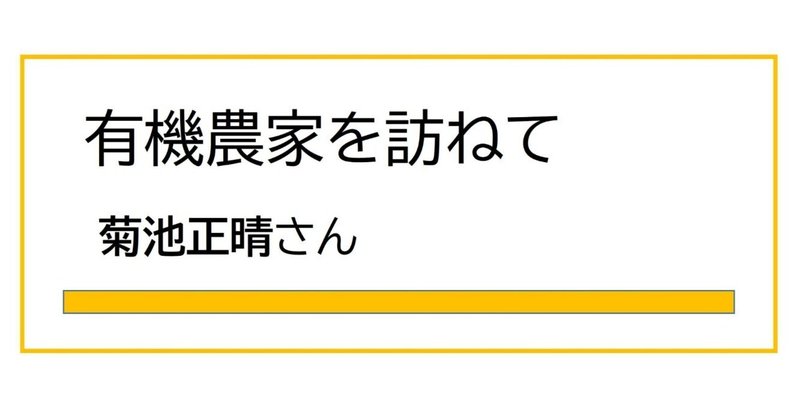
有機柑橘を主幹別隔年交互結実方式で栽培する菊池正晴さん
畑作物に比べ多くの病害虫が発生しやすいため、有機農業では困難とされている永年作物の栽培事例です。
2013年9月に、柑橘とキウイフルーツを有機農業で栽培している愛媛県八幡浜市の菊池農園・菊池正晴さんを訪問しました。
省力化と品質向上を実現した剪定法
菊池さんは、柑橘を主幹別隔年交互結実方式を採用し、省力化を図りながら、品質面でも安定した栽培を行っています。
菊池さんの主幹別隔年交互結実方式とは、1本の樹を生産する幹と生産しない幹とに分け、2年に1度交互に収穫を行う栽培方法のことです。樹ごとではなく、園ごと分ける方法もあります。
園地の改造
作業の省力化と園地の栽培環境の改善並びに豪雨による土砂崩壊防止のため、急傾斜の園地はユンボで4m幅、高さ1~1.5mの階段畑(テラス)方式へと順次改造しています。
園内の風通しがよくなり、病害虫の発生を抑制する効果もあります。

温州ミカン栽培の品種および収量
主な品種は、早生では興津早生、あけぼの早生、中生では愛媛中生です。
成園すべてで有機JAS認証を取得しています。収量は慣行栽培並みで、1、2割の裾物(質のよくないもの)をはねた出荷量は10aあたり2.5t程度です。
主幹別隔年交互結実方式の実際
柑橘の1年枝には病害虫はほとんどいません。これを利用して1本の樹の半分を交互に選定する主幹別隔年交互結実方式を取り入れ、有機JAS認証で認められた農薬による病害虫抑制を併用しながら、収量の向上・安定ならびに省力化栽培を実現しています。

具体的には、1月から3月頃までに1本の樹の半分程度を小指ほどの枝の大きさを目安に葉を出来るだけ付けないように剪定することで、幹半分の病害虫を減少させる効果があります。
この剪定により夏の摘果作業を軽減する効果もあります。しかも、半分の枝にはほとんど果実はならず、残り半分の枝にはいくら結果させても摘果の必要はありません。
主幹別隔年交互結実方式の利点として、次の点も挙げられます。
剪定のマニュアル化ができる。初心者でも、少しの時間で作業の習得が可能で、作業者に確保が容易になる
結果過剰な状態で収穫まで出来るので、果皮が薄く、じょうのう(果肉の粒を包んでいる房)が薄く口触りの良い果実になる
毎年、樹の半分を全剪定することで、樹高が調整できる
果実の収穫に要する時間が半分になる。通常の2倍ほど結果しているので、収穫作業が効率的である
剪定を工夫し農薬を減らした栽培に挑戦してください
剪定法を工夫し、省力化と品質向上を実現した柑橘栽培を紹介しました。
作物やそれを取り巻く病害虫など栽培環境の観察を通して、事例の少ない永年作物でも有機農業で経営可能な栽培ができてます。
慣行農業でも参考にしていただき、農薬の使用量を減らした栽培に挑戦していただきたいと思います。
参考資料
菊池正晴(2022)「キウイフルーツと柑橘の有機栽培の安定生産への取り組みと課題」有機農業研究者会議2022資料集:20-25.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
