
統合デザイン学科卒業制作インタビュー#02岩瀬太佑さん
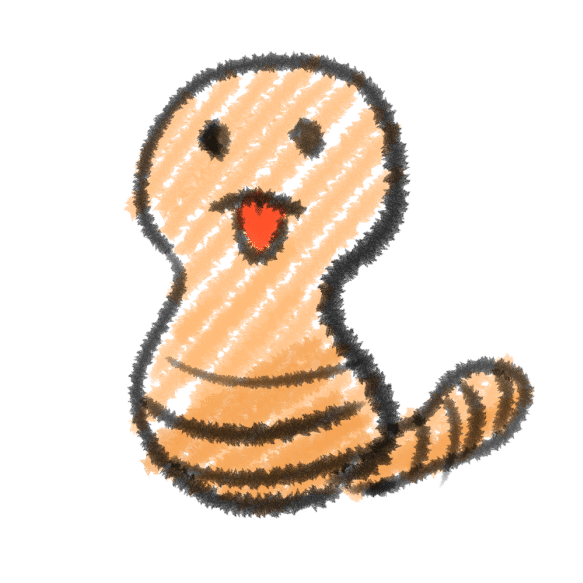
岩瀬 太佑(いわせ たいすけ)
多摩美術大学統合デザイン学科5期生
中村勇吾プロジェクト所属
_卒業制作で制作した作品の紹介をお願いします。
この作品は無機物に生物的な動きを与えることで生命の生々しさを際立たせて表現できるのではないかというテーマをもとに作成したコマ撮りアニメーションの作品集です。
巾着や鉛筆削り等、身の回りにあるものをモチーフとし、それに「捕食」、「羽化」のような生物ならではの行為を組み合わせたものを5つ制作しました。
さらにただのコマ撮りアニメーションでは終わらせないよう、動きに質感を持たせるためにモチーフが擦れる音等の音声を収録し、映像に入れています。
_この作品を作ろうと思った経緯について教えてください。
自分が所属している中村勇吾プロジェクトでは主に生物をテーマにしたアニメーション作品を多く制作していたので、卒業制作もアニメーションを活かした方向でやれればいいなと考えていました。
具体的に定まってきたのは3年生最後に出された「方法論の抽出と展開」という、他の作品や作家、デザイナーから方法論を抽出し、ただなぞるだけでは無く、それを別の形に展開、発展させた作品を制作するという課題がきっかけです。自分は「エキソニモ」の作品に感じた無機物を生き物のように見立てることから現れる生命の生々しさを表現したいと考えました。
はじめはコマ撮りアニメーションを使うなんてことは全く考えておらず、普通の2Dアニメーションで制作していましたがあまり納得いくものが作れませんでした。どうしたらいいか勇吾先生と話し合った結果、実際の物を使ったコマ撮りアニメーションで制作した方がいいのではないかということになり、今の表現方法になりました。
しかし、その時自分はコマ撮りアニメーションは一度もやったことがなく、時間もあまりない中で完全に手探りな状態で制作を進めなければならず、結局この課題では内容はまとまったものの、思うような成果物は作れませんでした。個人的にとても良いテーマになったと思っていただけにとても悔しい思いをし、同時にこのままこのテーマを終わらせてしまうのはもったいないと思いました。卒業制作に何を作るか色々悩んだ結果、このテーマにリベンジしたいという気持ちが強くあり、制作しようと決めました。
_テーマが決まってからどのように制作していったのか、制作過程をお聞きしたいです。
まず行ったのはモチーフの選定とその動きの探究です。3年時の課題では時間がなく、パッとできそうなものでなんとなくやってしまっていたので、卒業制作ではコマ撮りの練習も兼ねて、そこからじっくりとやっていこうと決めました。誰がみてもこれが何か分かる物であるのはもちろんのこと、コマ撮りアニメーションにするときに動かしやすいかを考えた時に、やはり可動する部位が多い物の方が良いということになり、それを軸に探しました。
良さそうなものを見つけては実際にコマ撮りアニメーションで動かして試してみてを繰り返した結果、鉛筆削りと巾着、スマホ用の充電器をモチーフに決定しました。それぞれ動かせる部位が多かったり、動きの自由度があったことが要因です。モチーフを決めた後はそれらに合う動きをひたすら探究し続けました。
中間講評が近づき、今までやってきたことを1度、作品としてまとめる段階になりました。この時点ではストーリー仕立てでモチーフの日常を描くという方向で制作し、講評に臨みました。
動きも含めて全体的に表現が生き物ではなくキャラクターによってしまっているとの指摘を受け、確かにコマ撮りでモチーフを動かすことに精一杯で、生物ならではの動作をそこに落とし込み切れていなかったことに気づきました。そこからまず、YouTube 等で動物の動画を手当たり次第見て、生き物ならではの細かな動作を抽出し、今までの動きに組み込んでここでもう一度動きのスタディを重ねました。
それに合わせて今までストーリー仕立てで映像を作っていたのですが、それもキャラクターに寄ってしまっている要因になっていると考え、生物の行為だけにフォーカスを当て制作することにしました。巾着であれば弁当箱をしまう動作とカエルが虫を食べる動きを、鉛筆削りなら犬やうさぎに餌をあげた時の動き、充電器はコンセントにたくさん刺さっている状態を犬などが赤ちゃんに授乳している様に見立てたりしました。ここで現在の作品コンセプトの大元が確立しました。
見せたいところだけをストレートに見せられるようになった反面、その変更に伴って今まで作ったシーンのほとんどがカットになったことで作品全体の尺がかなり少なくなってしまいました。そのため新しいモチーフを追加しようと考えました。初めの頃に行ったモチーフ選びとは異なり、動かせる部位よりも生き物の行為との組み合わせを意識して選定しました。そして選んだのがティッシュと裁縫針です。ティッシュはビニールを割いて紙が出てくる様をセミの羽化に見立てました。
裁縫針は布を水面、針をそこで泳ぐイルカや魚に見立てました。針が進んだところに足跡のように糸が残るところも面白いと感じています。
裁縫針に関してはそれだけでは要素として弱いと感じ、「座礁」というテーマにして布にいる時と机の上にいる時とで動きの対比が出るようにしました。
あらかた構成が出来上がってきたところで次に考えたのは音声の収録です。動きをさらに際立たせるために音を入れたほうが良いという案自体は中間講評の時点で勇吾先生から提案されていたのですが、ただ闇雲にやるよりは全体の構成が決まってからの方が良いと判断して後回しにしていました。収録方法は作った映像に合わせて使ったモチーフを擦ったり、動かしたりして音を録音するという方法をとっています。しかし中にはそれだとよく音が取れないものがあったのでその都度、試行錯誤して録音しています。例えば、針が布を縫う音はあまりにも音が小さく録ることが難しかったため、指の爪で布を擦ることで出しています。
個々の作品が出来上がっていく中、次に考えたのはそれらをどう繋ぎ合わせて観せるかについてでした。オムニバス形式の作品なのでそれぞれを順々に流してループさせることは決まっており、悩んだのはそれぞれのタイトルをいつ入れるかについてです。分かりやすい映像の前か、それとも映像の後にするかの2択で考えていましたが、どちらを選んでも初見の驚きと分かりやすさ、どちらかが犠牲になってしまいます。それをどうにかしたいと考えたどり着いたのが、まず映像を流してからタイトルをいれ、その後にもう一度同じ映像を流すという手法でした。1度目と2度目で映像の見方が変わるので1つの映像で2回楽しめる点も良いと思いこの繋げ方に決定しました。
この後は期限まで個々のクオリティを上げる作業を延々と繰り返していきました。
_展示空間はどのように考えていきましたか?

映像が主体の作品なので、より良い体験をしてもらうためにもできるだけ大きいディスプレイで映像を流そうと考えました。また、音もこだわって入れているのでスピーカー等の音響設備も必要になってくるなと考えていたところ、2号館の視聴覚室というまるで映画館のような場所で展示できることになりました。上映時間が7分くらいあるため、その間立ち止まって鑑賞し続けてもらうのは難しいのではないかという問題もありましたが、視聴覚室の座席に座って鑑賞してもらうことで解消できたので自分の作品にとって理想の場所でした。この場所を提案してくれた卒展委員の方にはとても感謝しています。
_展示を行った感想を教えてください。
座席があるので大丈夫かなと思っていても、やはり上映時間がそれなりに長いのでもしかしたら最後まで観てくれる人はあまりいないのではないかと始まる前は少し不安でした。もちろんすぐ出て行ってしまう人もいたのですが、多くの来場者の方々が最後まで鑑賞してくれていたのでとても良かったです。
自分がこだわったり、苦労して収録したところで驚いたり、笑ったり、ここの動きがよかったと一緒に来ている人と楽しそうに話し合っているのを見て、本当に頑張ってよかったなと思いました。
何より不安だった公開講評会でも教授陣に面白さを伝えられたようでとても嬉しかったです。
_この作品を通して、今後やっていきたいことなどあれば教えてください。
1年間卒業制作をして、とても貴重な時間を過ごせたなと感じました。長い時間をかけて自分が作りたいと思ったものを作り上げることができるということはとても実りのある経験でした。作品をもっと良くするためにはどうしたら良いかを考え、どんなに細かいことでも実行し、時には今までの考えに囚われず、自分がまだ入ったことのない領域に足を踏み入れ、行動していくことの積み重ねが作品のクオリティをあげることに繋がっていくんだなと本当に実感しました。それに伴ってどんどん自分の視野が広がっていく感じが作品と一緒に自分も成長できている気がしてとても楽しかったです。この経験はきっとこの先も自分の人生を支えてくれるような気がします。
作品自体についてはまだ動きに関して納得いっていない箇所が何箇所かあり、まだまだ改善の余地があると感じています。また、別のモチーフと行為の組み合わせのアイデアも探していきたいと考えています。スケジュールの関係上、カットしてしまったアイデアもあるので時間があれば作ってみたいです。
今回の制作では動き以外にもそれに合わせた音や、そもそもの映像作品としての見せ方などのいろいろな学びがあったので、それもまた別の形で将来活かしていきたいです。
(インタビュー・編集:海保奈那・加藤百華)
今回インタビューした作品は、3月13日から八王子キャンパスで開催される、美術学部卒業制作展・大学院修了制作展B(ピックアップ卒展!)でご覧いただけます。
他学科の作品も同時に鑑賞できる展示となっております。是非ご来場ください!
多摩美術大学 美術学部卒業制作展・大学院修了制作展B(ピックアップ卒展!)
会期
3月13日(日)〜3月15日(火)
10:00 - 18:00(最終日15:00まで)
場所
多摩美術大学八王子キャンパス アートテーク
東京都八王子市鑓水2-1723
交通
JR・京王相模原線「橋本」駅北口ロータリー6番バス乗り場より神奈川中央交通バス「多摩美術大学行」(運賃180円)で8分、JR「八王子」駅南口ロータリー5番バス乗り場より京王バス「急行 多摩美術大学行」(運賃210円)で20分
詳細:2021年度 多摩美術大学 美術学部卒業制作展・大学院修了制作展B
次回の卒業制作インタビューは…!
「光の質感とスクリーン」
山口 敏生(やまぐち としき)
多摩美術大学統合デザイン学科5期生
中村勇吾プロジェクト所属
スクリーンによって質感が生成される映像表現の探求をした山口さん。
単純な映像を形状や素材に手を加えたスクリーンに投影することで、その光に質感を生み出そうとしたそうです。
この作品を作ろうと思ったきっかけは何だったのでしょうか?
卒業制作インタビュー第3弾は明日公開です!乞うご期待!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
