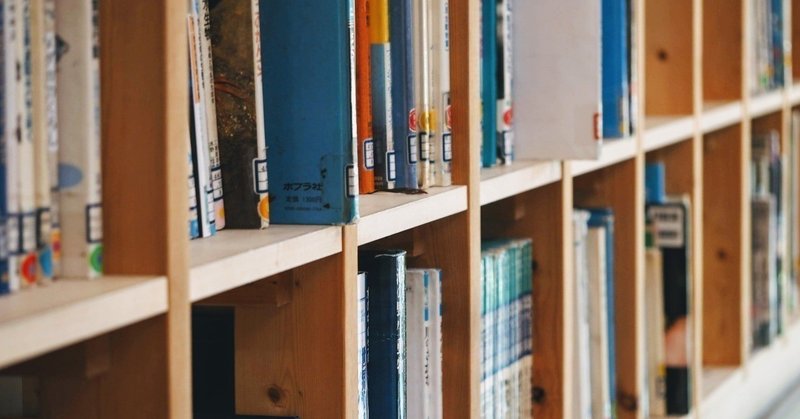
ビジネス理論書は、ケース(事例)を覚えて読みこなす。
クリステンセン『ジョブ理論』を再読した。とても明快で、思考の軸にしたい1冊だ。
こうした「理論」の本は、理論自体をがんばって覚えようとするよりも、例示されているケースをストーリーとして覚えて、そのケースの裏にある解説を思い出す… という読み込み方がいいと思う。
ジョブ理論では、冒頭の『ミルクシェイクのジレンマ』の話が有名だけれど、マクドナルドなどのファーストフード店を通るたび、「人々はシェイクを何の目的で雇用するんだっけ…」という問いを思い出せる。(アメリカと文化が違う点、日常)
通信制大学としてユニークな立ち位置を占めるSNHU = サウスニューハンプシャー大学の、ユーザーに合わせて問い合わせ対応を変えた話は、大学の広告やニュースに触れるたびに「自分たち独自のターゲットが切実に得たい情報・『進歩』は何なのか」という問いを思い出せる。
インドの診療所を迂回する、独自の心臓ドックというチャネルを開拓して成功したメドトロニック。患者に「通し」で1人のスタッフがつくメイヨークリニック。この2つは、病院の待合室などで「患者である自分が必要とする『進歩』を、どんなサービスが解決してくれるだろうか」を考えることにつながる。
挙がっている事例の中にも、ピンとくる事例/あまりピンとこない事例があるけれど、とにかくまずはピンと来たものを覚えて関連する解説を読み込み、2周目3周目で「ピンとくる事例の数」を増やしていくような読み方がオススメだ。本によっては同じケースが複数回出てくるので、何回も目に触れるたびに理解が深まる。
***
このスタンスは、例えば『ティール組織』にも当てはまる。ビュートゾルフ、モーニングスター、FAVI、パタゴニア。本だけ読んでイメージが湧かない場合、その会社のことをwebで調べて、写真や人物が出てくる情報に接すると、一段と理解が進むと思う。
難しめのビジネス書でも大概、いろいろな事例が出ている。事例に挙がっているブランドを目にしたとき、内容を思い出せるよう、「ケース重視」の読み方をしてみてはどうだろう。
🍻
