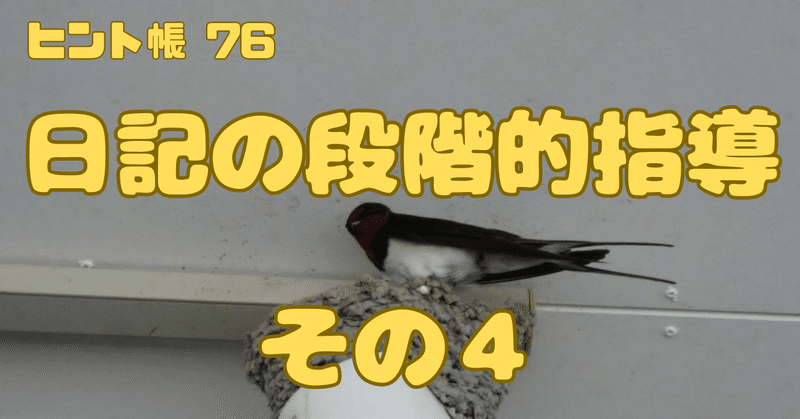
どの子も日記 第5段階「思ったこと・考えたこと」をどう指導する?
日記が苦手な子供に対する段階的な指導方法の紹介を続けてきたが、実は前回ぐらいから、もう「苦手な子」が対象というよりも、一般的な日記指導の内容に入っている。それだけレベルが高くなってきたということだ。
前回で、第4段階まで進んだ。
第1段階 読むことと言葉で言うこと
第2段階 「したこと」を書けば十分!
第3段階 「したこと」を5W1Hで書く 【くわしく書く1】
第4段階 五感を使って 【くわしく書く2】
(ここまでの説明にご興味のある方は、ぜひコチラ↓↓ ↓↓ ↓↓からどうぞ!)
今回は、いよいよ、
第5段階 「思ったこと・考えたこと」を書く 【くわしく書く3】
である。
この段階に至るまでの指導で、既に「思ったこと・考えたこと」を織り交ぜて書いている子もいると思う。
既にお伝えしたように、私の示している「指導段階」は、ある意味形式的なものなので、子供が進んで「思ったこと・考えたこと」を書いても全く問題はない。
ただ、それでも、私が「思ったこと・考えたこと」を「5番目」の指導段階に置いたのには、二つの理由がある。
第一に、「思ったこと・考えたこと」を書くことは、「難しい」からであり、第二に、その難しいことを実現するのに、前段階の五感を使うことが役立つからである。
そこで、その「難しい」、「思ったこと・考えたこと」をどの子も書くことができるようになるために、私は次の四つの方法を行っていた。
第5段階 「思ったこと・考えたこと」を書く 【くわしく書く3】
(1)初めは簡単に、とにかく書く
難しいことに対して、いきなり質を求めてはいけない。近くの丘すら登ったことがない子供をいきなり富士登山に連れて行くようなものだ。
初めは、「うれしかった。」「楽しかった。」「またやりたいです。」のレベルで十分である。これを、日記の文章の最後に書かせるだけでいい。
「思ったこと・考えたこと」を書くという経験を重ねさせることが第一であると私は考えてきたからだ。
そして、「思ったこと・考えたこと」を書くことが当たり前と子供が思えるようになってから、次へ進むのだ。
ところで、「うれしかったです」や「楽しかったです」が、日本語として「誤り」であることはよく知られている。
「うれしい」「楽しい」という形容詞に、敬体による丁寧な表現「です」を加え、それを過去形にした時に、このように書く子供が(大人も)多いのだが、「かった」と「です」は繋がらない。過去形にしたいなら、「うれしいでした」「楽しいでした」と、しなくては、おかしいのである。
しかし、現在、こういう表し方をする人はいないだろう。
だから、「うれしく思いました」「楽しく感じました」などとするのが、「適当」であろう。
けれども、「うれしかったです」や「楽しかったです」は、かなり市民権を得ているように思う。従って、子供がそのように表した時に、「それはバツ!」とは、言い難い。
ゆえに私は、あえて注意をすることはせず、機会を見計らって、「本当はこうだよ。」と教えてきた。
(2)子供に共通の出来事を一緒に書く
「遠足」「運動会」「プール開き」などの、学級の子供たちにとって共通の出来事があった時、そのことについて、皆で一緒に日記を書く場を設定する(私は、低学年なら、月に1、2回、高学年でも数か月に1回は、学級全体で日記を書く場を設けていた)。
その際に、その出来事について「思ったこと・考えたこと」を出し合い、日記に書かせる。
共通に体験した出来事に対して、自分とは異なる見方や感じ方のあることに気付かせたり、それを表現する言葉について知識を増やさせたりするのである。
高学年になると、意見文に近い日記になっていく。
(3)「したこと日記」や五感を使って書く日記で、「思ったこと・考えたこと」をふくらめさせる。
「したこと日記」や「見たこと日記」を書き、その「終わり」に、まず簡単に「思ったこと・考えたこと」を書かせる(言わせる)。その後で、その「思い・考え」をくわしくさせる。
もしも、「楽しかった。」と書いた(言った)のなら、「何が」「どんなふうに」楽しかったのか、「だからどう思った」のかを、お尋ねしたり、付箋などに書き出させたりする。
さらに、「その気持ちにぴったりの言葉」を探させる。
五感を使った日記の場合は、とにかくくわしく「見る・聞く…」ことをさせると、「思ったこと・考えたこと」が、子供から出て来やすい。
これを、上記(2)のように、学級全体で行っても良い。
理科や生活科は、大いに「使える」。「理科+日記」「生活科+日記」の時間のイメージである。
(4)「題材見つけ」をさせる
「思ったこと・考えたこと」を書くことが、なぜ「難しい」か。それは、そこに一番、その子らしさが出るからである。
その子供ならではのものの見方や感じ方が最も現れるところであり、教師はそうした個性的な「思ったこと・考えたこと」を書かせたいと思っているだろう。それこそが、日記を書かせる中心的な意義であると考えている教師が多いに違いない。
けれども、友だちと遊んだことについて書いた日記に、「個性的な」思ったこと・考えたことを期待しても、それは難しい。
子供の方も、そうした教師の期待を敏感に察知しているのだろうか、書く材料選びに苦労する。
「書くことがない」「何について書いていいか分からない」という子供の声を、よく聞くのではいか。「日記に書くことがないから、どこか連れてって」と、保護者にせがみ、日記のためにお出掛けをするという笑い話のような本当の話をよく聞く。
しかし、実は、日記の材料は子供にとって身近なところにたくさんあるし、それを見付けることのできるアンテナを高くさせたいとも、教師は願っているはずである。それも、日記を書かせる中核的なねらいだからだ。
つまり、子供たちに「思ったこと・考えたこと」をよりよく書かせるためには、「題材」を見付ける「目」を育てる必要があるのだ。
そこで私は、「題材見つけ」をさせた。
早速その方法を紹介したいところだが、この「題材見つけ」は、私の指導観では、もっと先の指導段階である。つまり、それぐらい、「難しい」ことだと考えている。
従って、説明はその折に譲り、今回はここまでにさせていただく。
