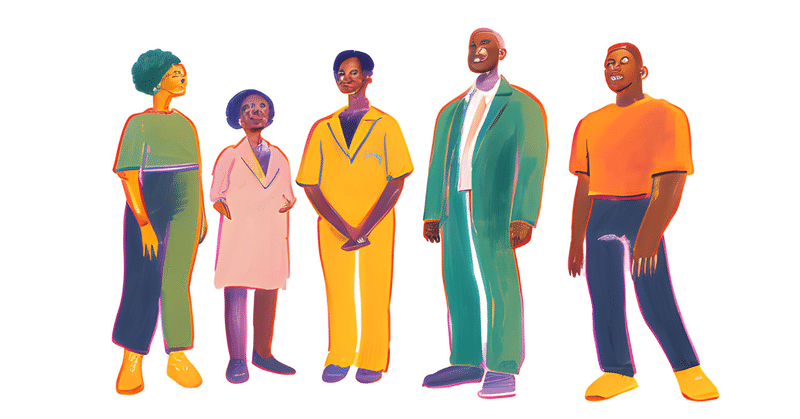
多様性の科学
多くの平均値、すべてにピタリと当てはまる人は存在するのか?
一つの側面に秀でた集団は、多くの視点を持ち得るのか?
非常に面白い本でした。
一方で、会社の中にいると同一性が生じやすい、あるいは上役の意見に従いがち。
これはこれで頭から否定するものではないが、集団として近視眼的になってしまう。
ではほかの視点をむやみやたらと取り入れればいいのか?といえば、それもNo.
三人寄れば文殊の知恵とは言うが、課題解決したいところの知見を持たない人が三人寄っても歯が立たない。。。
歯が立たないなら、取り組んでるだけいいのかも。そもそも課題と認識することも難しい。
難問に取り組むときにはどうするのか?
一歩下がって、自分たちのチームがカバーできていないのはどこか。
カバーできてないところを指摘できるメンバーをいれる → そんな相乗効果を生み出す視点を持っている人たちを見つける。
会社は社長の能力以上にはのびない、などと言われたりもするけどそのまま受け取ると、多様性が足りていないということか、と。
外からの耳の痛い諫言は、人なら聞きたくないだろうし。。。
多様性とか、組織の心理的安全性とかいろいろな表現があるけど、何をするにせよ、自分とは違うことが得意な人と一緒によりよいことを目指すようなチームにする。
ホモサピエンスの脳のサイズは最大ではなかったが、他の種族を抑えて進化した。それは多様性を受け入れ、過去の経験をベースに次の世代はそれを先に進める種族だったため。
いろいろ考えることの多い良書でした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
