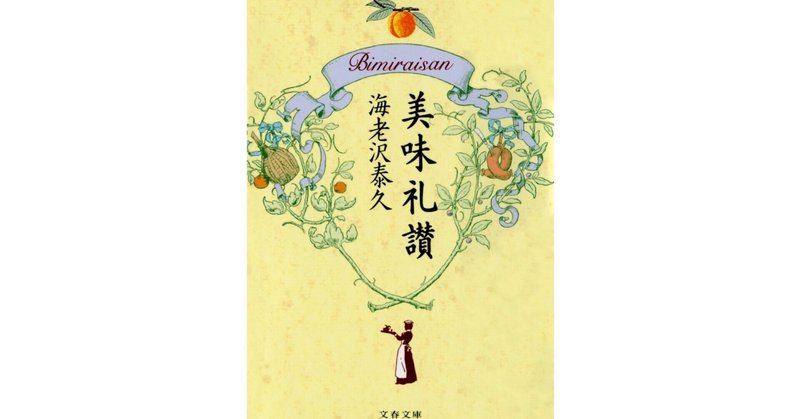
美味礼讃 後編
パン屋さん時代に考えたこと、やってみたこと、使ったもの 18.
ぼくが感銘を受け、ずっと印象に残り続けている描写がある。
「きょう、これから教えるフォン・ドゥ・ヴォーは、材料もつくり方も、もうこれ以上のものはないという最高のものです。それでは、はじめます」
辻静雄さん(副校長)が教壇に立ち、生徒にフォン・ドゥ・ヴォーを教える場面。
実演後、完成したフォン・ドゥ・ヴォーを小さなボウルに入れ味見をさせるために生徒に回す。
「このフォン・ドゥ・ヴォーだが、スプーン一杯に換算するといくらになると思う?」「値段ですか?」「そうだ。きみはこの学校を出たらコックになるんだろう。コックになったら、ひとつひとつの料理をいくらで客に売るか考えなければならない。それには原価を知っておく必要があるだろう。いくらだ?」生徒はしばらく考え、やがて自信がなさそうに答えた。
(中略)
「それではこのフォン・ドゥ・ヴォーを使って、チキンのワイン・ヴィネガー風味という料理をつくったとしてみよう。料理の値段はいったいいくらになるか」と副校長はいった。
(中略)
これにさらに鶏やワイン、バター、生クリームといった材料が加わるわけだから、全体の売り値はどうしたって八千円から一万円ということになる。二人で食べて五千円だ。きみはこんな料理を注文するか?」
(中略)
「きみがいま就職したら、初任給はいくらぐらいもらえるんだい?」「一万四、五千円だと思います」「たった一品の料理に給料の三分の一は使えないよな」「はい」「じゃあ、きみがコックだったらどうする?」小宮哲夫は考えた。「もっと安くつくります」「どうやって?」「分りません」「手抜きをするんだよ」副校長はにっこり笑っていった。
そして、生徒に口頭でフォン・ドゥ・ヴォーの手抜きの仕方を教え、授業をこう締め括られる。
もしきみたちが、将来これ以上はないという料理をつくったとしても、それを食べてくれる客がいなかったら、商売として成立しないからだ。その場合、きみたちは店の立地条件や客層を考えて、それに合った原価で料理をつくらなければならない。しかし、どういう場合でも、こうあらねばならぬという本物の料理は知っておかねばならない。それを知らなかったら、どのぐらい手を抜くかということも分らないからだ。つぎの授業では、フォン・ドゥ・ヴォーの上手な手の抜き方をじっさいにやってみます。きょうはこれで終ります」
初任給を訊かれた生徒が「一万四、五千円だと思います」と答えている他にも、省略したけれど「町の中華料理屋でいつも食べているラーメンは、百円だったのだ。」ともある。
物語の舞台は昭和40年(1965年)だから現在とは物価も違えば当然貨幣価値もかなり違うけれど、ここで辻静雄さんが生徒に教え伝えられている本質は現在であってもきっと何ら変わらない。
またそれはフランンス料理だけでなく、食べもの屋さん全般に共通することでもある。
辻静雄さんの話されている手抜きとは、ぼくの思う正しい効率化、合理化のことに他ならないし、材料選択にしても同様の話が出てくる。
ぼくがここまで書いてきたものが一連のものであり、この小説を紹介したいがための伏線だったというのもおわかりいただけるのではと思う。
またぼく自身がこういった思考になったのには、いま思えばこの作品を若いころに読んだことが少なからず影響があったのかも知れない。
ぼくが食の専門誌の取材を受けると、特に相手がベテランライターさんのときには雑談の中でよく話していたことがある。
「ぼくは、辻静雄さんと齋藤壽さんがおられなかったら、いまの日本のフランス料理はなかったと思っています」
『美味礼讃 』は、フランス料理屋さんだけでなくすべての食べもの屋さんにとって示唆に富む作品であり、辻静雄さんが残された偉大な功績を知る機会にもなる物語なので料理人の方はもちろん、食べもの屋さんを生業とされている方には、ぜひ一読をお薦めする。
食に携わらない方であっても読みものとして、とてもおもしろいのでお薦めです。
つづく
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
