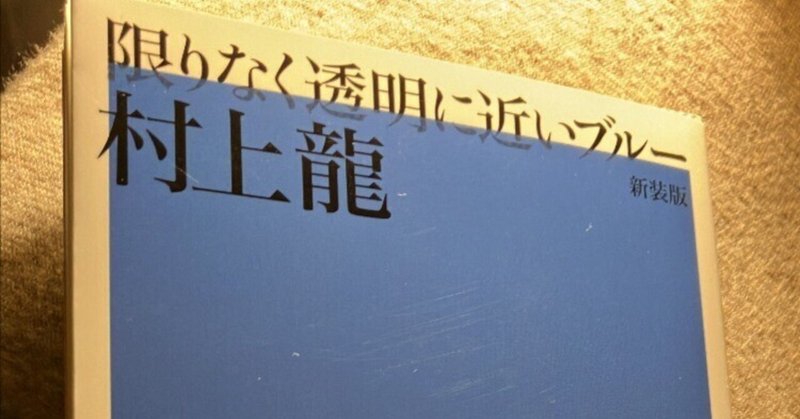
限りなく透明に近いブルー
深夜2時、この本を読みきった。
喉が渇いたのですでに祖母が寝ている中、リビングにお茶を汲みに行った。
コップは半日使って洗ってないものが机の上に置いてあった。
その薄汚れたコップに僕は、半分ほどお茶を淹れてやった。
ふと気になってカーテンを開けてみる。祖母を起こさないようにそっと小さな音で開けてみる。
そこには確かに、リュウの言う通り黒い鳥がいた。
雲と、都会特有の小さな星と共に、黒い鳥がいた。
ただ、僕にはその黒い鳥を視認することができなかった。
鳥がいることはわかっても、鳥を見ることはできなかった。
はっきり言って本書はまあまあ読みづらい。
特に集中力が乏しく、日頃ライトな本しか読まない自分にとっては尚更だった(この本もライトな方に入るのかな?)。
セリフと語り手の言葉があやふやであったり、そもそも結構前の著書なので時代背景が分かりにくかったり。あとは今この場面が行われている「場所」がわからなくなることが多かった。
病院なのか、みんなが行き来するハウスなのか、はたまた日比谷音楽堂なのか。なにせ登場人物が皆ヘロインを打ってやがるから、今進んでいる話が本当なのか妄想なのかもわからない。
その中でも大半がリュウの妄想なのではなく、実際に起こっていた現実だとわかるのは、常々リュウが世界を淡々と見つめていたからなのであろう。
おそらくこの本を読んだみんなが考えることは、リュウが話していた「鳥」とはなんだったのかと言う話だと思うが、僕はそこまで「鳥」の詳細について気になりはしなかった。
一応この文章を読んでる人の中にもこの本をこれから読む人がいるかもしれないので、極力ネタバレはしたくないのだが、僕が思う「鳥」は、リュウがラストシーンで話していたことが全てなのではないかと思う。
良い意味で、リュウが話していたことのそれ以上でもそれ以下でもないような媒体であった気がする。
ある意味「鳥」は、この著書の落とし所をつけるために、リュウの哲学を終わらせるために、駆り出されただけの動物と言っても良いかもしれない。
何よりも僕がこの著書で好きだったのは、物語全体が、「青春物語」であったことだった。
セックスにドラッグに不法侵入に暴力。やりたい放題の彼らはある意味それら自体が青春であり、それはそれは歪なブルーだったのではないかと僕は感じる。
彼らの生い立ちに言及される場面は決して多くはないが、人それぞれにブラックな過去をもち、そんな彼らだからこそ歳の近い人間と享楽に堕ちていく行為が楽しかったのではないかと僕は考察したい。
いや、彼らは楽しかったと言うよりも、そうやって自分自身を享楽で騙すことしかできない生き物であったとも感じる。
そして何よりも僕は、この著書のラストシーンが好きだ。
彼がヘロイン中毒者であるからこそ、色んな読み取り方や考察ができる内容だったと思う。ぜひそこは皆さんも本書を読んで確認してみてほしい。
きっと僕がここに書いても多分わからないと思うし。
僕は携帯の充電を切って本を読む時間が好きだ。
その時間だけ僕は僕自身でいられるような気がするから。
でも実際はちがう。SNSを眺めて心を痛める時間こそが、本当に自分らしい時間だ。携帯の充電を切って本を読む時間は、痛み止めを飲んでいることと一緒だ。言い換えると、他所行きの自分で自分をコーティングしているだけなのだ。
リュウは作中で、腹の痛みは昔からずっとあって、ヘロインで痛みを忘れているだけであり、痛みはずっと内在している。その痛みが懐かしい。
といったことを話していた(正確にはリュウの友達なのだが)。
その痛みこそがリュウとリュウの友達にとっては、腹の痛みであり、現代人である僕にとっては周りの評価をただ気にする痛みなのだと僕は解釈した。
激しくおすすめしたい本ではないが、僕自身人生で忘れられない小説になったことは間違いない。
よければ読んでみてください。
限りなく透明に近いブルー/村上龍
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
