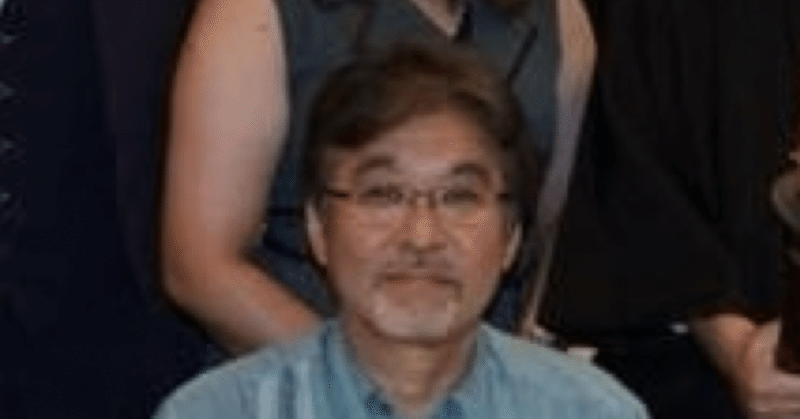
文化人物録33(津堅信之)
33津堅信之(アニメ研究者、2015年)
→日本アニメ史研究における現代の第一人者。特に日本アニメ全体を大きくとらえた分析や見方が明瞭かつ分かりやすく、個人的には取材などで大変助けていただいた。世界で日本のサブカルがこれだけ広まる中、ますます重要な研究分野になるのは間違いない。
*日本アニメ、カラー化の歴史
・海外ではディズニーがカラーでアニメを作り始めたのが1935年。初のカラーアニメとされているのが1937年の白雪姫になる。日本では1958年に試作という形でカラー化が試みられ、手塚治虫の「鉄腕アトム」は56話だけカラーだったのだが、本格的なカラーアニメとなったのが同じ手塚の「ジャングル大帝」だ。ここからセルアニメ専用の絵の具が増えていき、その後デジタル化時代の着彩に替わるまでがカラー化技術の流れになる。
・脱・白黒「ジャングル大帝」テレビ放送、映像技術の最先端
1965年10月6日、手塚治虫が設立した虫プロダクション制作のテレビアニメシリーズ「ジャングル大帝」の放送が始まった。日本のテレビアニメシリーズとしては、初の本格的カラー作品で、今年はそれからちょうど50年にあたる。
虫プロはこの2年前の63年に、これも日本初の本格的テレビアニメシリーズとなった「鉄腕アトム」を制作している。この作品で虫プロは「毎週1本30分、連続放送」という、それまでの常識を覆すアニメ制作に打って出た。「ジャングル大帝」はその虫プロが、まだ白黒ばかりだったテレビアニメの世界へ、初めて送り出したカラー作品だ。
・2つの革命的変化
かつて、映画やアニメーションなど「動く映像」の世界で、革命的といえる変化が二つあった。一つが、無声映画(サイレント)から音付き(トーキー)への変化である。チャップリンの短編作品に代表されるサイレント映画に代わって、20年代後半からトーキーが普及し、映画作りの方法が根本的に変わった。サイレント時代のように、役者の感情表現を身ぶり手ぶりで表現せずとも、台詞(せりふ)を録音すればよくなったし、効果音やBGMの添付も、映画の演出法を大きく変えた。
・もう一つが、白黒からカラーへの変化である。映像のカラー化技術はサイレント時代から試みられてきたが、定番化したのは30年代に入ってからで、赤青緑の三原色によるカラー映像技術を使った世界初の映画とされる作品が、ディズニーの短編アニメーションシリーズ「シリー・シンフォニー」の1本、「花と木」(32年)だった。つまり、映像のカラー化では、アニメーションが最先端を突き進んでいたのである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
