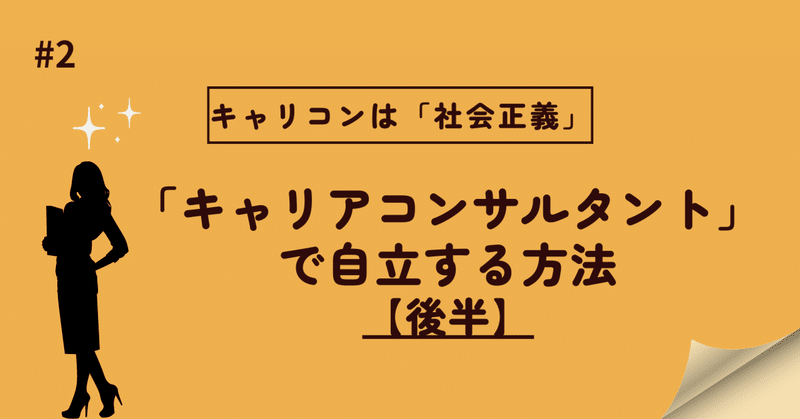
📚#2「キャリアコンサルタント」で自立する方法【後半】(佐渡 治彦)
異業種×異職種転職を3回経験。
現役ベンチャー企業人事のキャリアコンサルタント 岩澤 望(@hope_3n)
です。
たくさんの「いいね」をいただき大反響の前半に続きまして、
後半をお届けします。なお、前半の内容はこちら👇
続編は、第5章からの内容から取り上げます。
既にキャリアコンサルタントの方も、これから取得を目指している方にも、企業領域でのキャリコン活用を考える方には大変オススメできます。
事例から読み解こう
リファーできる関係構築だけでは足りない
キャリコン実務家&第一人者 東海ライフキャリア 代表 藤田廣志さんの事例が取り上げられていました。長年ご活躍されているからこそ滲み出る、大変読み応えのある内容です。
【「Weak Ties」の構築】
「Weak Ties」を構築すること、それほど親しくはないもののいざという時に協力してくれる人との関係を築くことは、キャリアコンサルタントにとって大切なことです。
キャリアコンサルタントの養成講座では、「倫理綱領」を学びます。その中でも、リファーについて書かれています。一体、自分が何ができて何ができないのか、明確にしておくべきです。
第2章 職務遂行上の行動規範(任務の範囲)
第8条 キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルティングを行うにあたり、自己の専門性の範囲を自覚し、専門性の範囲を超える業務の依頼を引き受けてはならない。
2 キャリアコンサルタントは、明らかに自己の能力を超える業務の依頼を引き受けてはならない。
3 キャリアコンサルタントは、必要に応じて他の分野・領域の専門家の協力を求めるなど、相談者の利益のために、最大の努力をしなければならない。
よくあるのはメンタルヘルスの問題ではないでしょうか。時に命の危険性が伴いそうな場合は、早急に判断・リファーする必要があります。
ただ、本書では、リファーできる関係性の構築だけでなく、コーディネーター力も必須だとされています。
いざという時に協力してくれる関係性は、すぐに作ることはできないものですが、早く気付いて今から取り組んでいく気概があると良いですね。
環境への介入がカギとなる
今後、キャリアコンサルタントは企業・教育・行政など、組織の環境へ働きかける介入・支援の役割が重要になると強調しています。
JCDAをはじめ、様々なセミナーを拝聴して思っていることがあります。それは、「キャリコン=1on1」支援のみに留まらない、ということです。
今までの勝手な思い込みや、仕事的に対人支援に携わりたい想いが強い人が多いため、このように捉えられてきたのかもしれません。
しかしながら、今では働き方が大きく変わりました。個人としては、「キャリア自律」が必要ですし、企業としては、「人手不足」や「生産性向上」など事業継続・成長に向けて、より一層取り組まなければなりません。
環境へ介入する広い視点を持ちながら、今後もキャリコンとして活動していきたいと考えます。
【環境に介入するとは】
『企業の人事部や上司、さらには社会に働きかける』ことのみを指すのではなく、『クライアントが環境に働きかける力を身につけること』を支援することも大切な要素
続いては、キャリコン養成講座でお世話になった日本マンパワーさんの事例です。この部分が最も心に響きました👇
キャリアコンサルティングの仕事を得るには「社会問題に正面から対峙して、その問題解決に寄与し成果を上げることが先であり、その結果として、社会から認められるようになれば、収入は自ずとついてくる」
現在、社外活動として、中堅・中小企業のキャリア開発支援を進めています。今までの経験をもとに、課題提起をしつつ貢献・成果を出すように微力ながら取り組んでいきたいと思っています。
全員知りたい! キャリコンとして活躍するには
結局、一人では何もできない
少し極論過ぎるかもしれませんが、一人でできることには限界があるし、効率も悪いなと思います。もっと言うと、真のキャリアコンサルタントとして活動するならば、自分以外の協力者・仲間が必要だと考えます。
その方が、広がりが出ますし、質も担保できるからです。
ビジネスパートナーを見つける
SNSで情報発信をする
スーパーバイザーを探す(*)
(*)スーパービジョンとは
指導レベルのキャリア・コンサルタント(スーパーバイザー)は、キャリア・コンサルタントが抱える個別問題の本質を理解したうえで、キャリア・コンサルタントの相談者に対する対応が適切かどうか判断し、相談者に対する支援の適切さ、あるいは不十分さ、自己の問題点等に気づかせ、より高度な視点から指導してキャリア・コンサルタント自身による問題解決を促すことを行う。
(特定非営利活動法人キャリア・コンサルティング協議会):
【キャリア・コンサルタントの活動】から一部抜粋
厚生労働省としても、キャリコン10万人計画という「量」の確保はもちろん、次の課題として専門性を備えた「質」の向上にも言及しています。
ただ、このスーパーバイザー。1級キャリアコンサルティング技能士のことを指します。人数としては、全国で621人しかいません(2023/3/31現在)。
ということは、キャリコンを取得したけれども、それ以降、スーパーバイザーを受けたことの無いキャリコンがいかに多いか容易に想定されます。
システマティック・アプローチを推奨
キャリコンを勉強した方であれば、恐らく保有しているであろう木村周さんの著書『キャリアコンサルティング 理論と実際』。木村さんは、システマティック・アプローチを推奨しています。
①カウンセリングの開始
②問題の把握
③目標の設定
④方策の実行
⑤結果の評価
⑥カウンセリングとケースの終了
4つの課題とは
上記 木村さんが挙げていらっしゃる4つの課題が興味深いです。
私の場合は、特に2番に関心・課題意識があり、現在の仕事と社外活動の両輪で取り組んでいます。
1. 雇用の場の確保と現場力再構築に貢献すること
2. 中小企業と地域に活動を拡げること
3. 障害者、高齢者、メンタルヘルス不全者、外国人労働者などに対する活動を強化すること
4. 支援者として官民を超えた『公』の視点を自覚し、『労働の人間化』と『快適な職場づくりに貢献すること』
世界の潮流「社会正義のキャリアコンサルティング」
「社会正義」のキャリアコンサルティングという言葉について、聞き馴染みがないかもしれません。この概念が生まれた背景としては、社会が不安定で流動的になった環境下、社会に目を向けて個人を支援していくべきではないかという反省があったからです。
難しいのは、企業領域キャリアコンサルタントとしては、企業の利益追求が目的になることです。資本主義社会の中、企業としても生き残りを図らなければならないため、当然といえば当然です。
そのため、この競争原理からドロップアウトしてしまう人が出てきてしまうのは必然であり、そのような方々も考慮すべきということを「社会福祉的なキャリアコンサルティング」といいます。
資本主義社会において、社会福祉的キャリアコンサルティング、社会正義のキャリアコンサルティングをいかに企業に普及、定着させることができるかが、これからの日本のキャリアコンサルタントの課題だと思います。
↑この部分については、実践者として、探求していきたいです。
いよいよ最後です。
第6章など、何度読み返しても、その時々で気づきを得られる・気づきが変わる1冊だと思います。
もしニーズがあれば、企業領域のキャリアコンサルタント同士(事業会社の人事含む)で、意見交換等でもしてみたいなぁ…。
\「いいね」や「フォロー」いただけると、更新への励みになります/
いつもありがとうございます
企画イベントをタイムリーに知ることができます
クローズドなお話もしていきます

◆note:https://note.com/iwsw_nzm/
◆Twitter:https://twitter.com/hope_3n
◆LinkedIn:https://www.linkedin.com/in/nozomi-iwasawa/
◆stand.fm:https://stand.fm/channels/5f5430766a9e5b17f76121e8
一つ一つの積み重ねが、明日のあなたを創る…。
あなたの可能性をクリエイト。
以上、ほぷさんでした。
👉stand.fm📻配信中
お悩み・ご質問大募集。レター📨お待ちしています。
スキマ時間にどうぞ📱

noteの記事執筆に役立つ、情報・ネタ仕入れに活用します!
