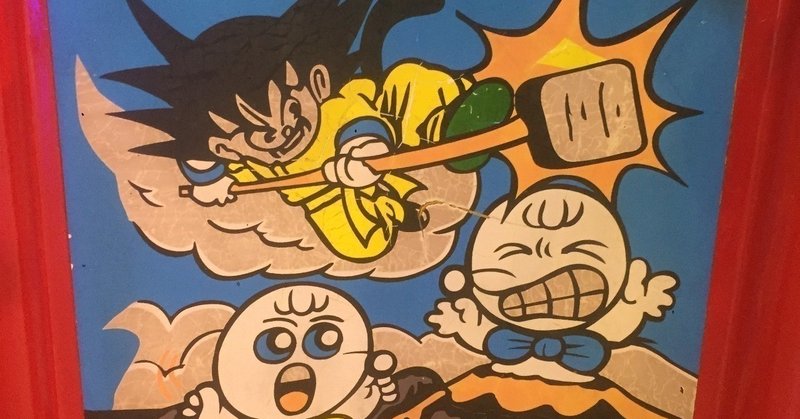
「ドラゴンボールハラスメント」に見る、オタク文化伝承のむずかしさ
DBを必要以上に神格化する先輩と、マウンティング(?)に対峙する後輩。
ちょっと前の記事ですが、話題になりましたね。
週間で切れ切れに読んできた世代と、まとめ読みした世代。
クラスのみんなで話題にしてきた世代と、歴史の勉強をさせられる世代。
本件は、コンテンツ制作に携わる人間が知っておくべき「歴史」の問題でした。しかし、先輩も後輩も、双方がピンとがズレていて、残念な結果になったような……。
先輩は、とにかくDBを神格化してしまい、この作品や作家からどんなエッセンスを吸収して欲しいのかを言語化出来ず、ハラスメントにしてしまった。
マウント取りたいだけなのでは、と後輩氏に見透かされていたようですが、実のところはわかりません。
結局、先輩がどういうつもりで読ませたのが最後まで分からないままですが、少なくとも後輩氏にとって成分の9割はハラスメントだったのでしょう。
そして後輩は、反骨心からもあるのでしょうが、読みつけない古いマンガを読破して、若者視点で分析されたまではいいのですが……、頑張られたけれども惜しかったです。
以下、後輩氏の指摘について僕なりの反論です。
※個人的なドラゴンボールに対する感想は一旦置いておきます。
ストーリーに難
まず子供向けです。少年ジャンプは子供向けのマンガ雑誌です。後輩さんは成人していますので、この視点が欠けています。
そして、週刊少年ジャンプのシステムについての考察が足りません。
毎週毎週のアンケートシステムが作家と作品を強烈に縛ります。
その結果、通しで読むと蛇行したり矛盾したり意味不明になることも少なくありません。
しかしこの点を踏まえてDBを読ませなかった先輩にも問題があります。だって今の人にはよく分からないもの。
当時、毎週ワクワクしながらDBを読んでいた世代にとって、DBは一コンテンツではなく、ビッグな共通体験だったわけです。
先輩が、それをひたすらスゴイスゴイとマウンティングに使ってしまったら、DB嫌いを量産する結果になってしまいます。
まあ当然よね。どうスゴイのか説明してみろよ、ということに当然なります。
作品単体で通しで読んでしまったら、そこには体験やムーブメントは付随しないわけで、作品単体で読ませたところで伝わりようがないのです。
さて、鳥山氏は投稿を始めてからマンガの勉強をした人なので、お話については多くを望んではいけない気もします。
私自身、高校時代美術の専門校に通い、現在は絵も小説も描きますが、これらは左右別の脳味噌で生み出しているという実感があります。同時進行は出来ません。脳を乗り換える必要があります。
片方を高く育ててしまうと、もう片方は微妙になる。マンガの世界ではありすぎるほどありふれたことで、絵の上手いマンガ家は往々にして、原作をつけられて作画担当になりがちです。
両方クッソ高い能力の人は少なく、分業にした方がより効率化かつ高品質化出来るという話です。
さて、絵のレベルが突出している鳥山先生の場合は……。というね。
鳥山御大を「よくある絵」よばわり
ちげーよ。元祖だよ。
おま、そういうとこやぞ。という気持ちになりました。
分かってて言ってるのかもしれませんが、絵描き目線で言っても、鳥山フォロワーは現れても、大きく越える人はなかなか見当たりません。
イラストレーターレベルの漫画家、というのも認識不足で、元々デザイナーも兼ねるイラストレーターで、数多くのキャラクターデザインもしている方。さらにカートゥーン風味の絵柄ではあるが、3Dに落としても破綻の少ない高度な絵である、というのが私の認識です。ためしにドラクエのフィギュアでも見てください。どこから見ても「鳥山絵」そのままに見えるでしょう。
そして今日、こんなお知らせがTLに流れてきました。
来月公開の劇場用DBの予告編と主題歌が公開されたというものです。
主に海外セールスを狙ってのこととはいえ、ビッグネームであることは間違いありません。
いまだに新作アニメ、劇場映画、ゲーム、と大量のコンテンツが発表され続けるモンスターコンテンツが「ドラゴンボール」です。
後輩氏はこの現実をどう解釈するのでしょうか。
本当に何か見落としていることはないのでしょうか。
結局、後輩氏は表面的な見方しか出来ていないとしか言えませんね。
せめて作品や作者に関するwikiにでも先に目を通していれば、もっと吸収出来ることも多かったかもしれません。
世界中に数多くのファンを持つクリエイター「鳥山明」、作品「ドラゴンボール」に関する認識がまだまだ足りないと思いました。
ぶっちゃけ「ナメてんな」と。
それとも、チャラけたWEBコンテンツ制作者なんか、その程度の認識で上等だ、と見下したほうがよろしかったですか?
これからはWEBの時代なんですけども。
これを受けて、次のような記事もありました。
実は、この記事が今朝ツイッターのTLに流れてきて、当該ハラスメントに関することを思い出したのです。
(映画のお知らせとは前後しています)
概要としては、コンテンツというのはその時代のムーブを含有するものだから、時代がズレてしまったら伝わらない。
だから、自分の世代が熱狂した作品でも、今の人には勧めないよ。
というものです。
たしかに、DBハラスメント先輩のようなオタク老害になりたくない、というお気持ちも重々分かるのですが、このままではコンテンツの系譜に関する情報が断絶してしまうなあ、とも思った次第です。
なぜなら、クリエイターは過去接してきたコンテンツ群、作家たちから、影響を受けて自分の作品を作っているからです。
この事実を表面的にしか認識出来なかった最初の記事の後輩さん、コンテンツ制作に携わりながらもこの基本が抜けているので、私は「惜しい」と評したわけです。
当時の空気感などにも触れているので、こちらも合わせてご一読されるといいかな、と思いました。
*****
クリエイターは誰かの血脈、コンテンツは何かの子孫
ここからは私の持論です。
名作を勧めないの件、クリエイターはその限りじゃありません。
何故なら表現とは、古の時代から連綿と繋がっているものだからです。
良い、と思わなくてもよい。だが、学ぶ価値もない、と吐くなら戦争になるし、最低でも、自分は学ぶ姿勢がございませんと公言するようなもんです。
数多くのクリエイターが過去の多くの作品に影響を受け、その末にリスペクトした作品があまねく存在しているわけで、ともすれば今のクリエイターをも愚弄する結果になるのです。
たとえば、あなたに好きな作家さんがいたとします。
あなたはその方の作品を褒めました。
なんてオリジナリティに溢れているんだ!見たことない!等と。
……しかしその作品が実際には、作家さんが愛してやまない作品のリスペクトしたものだったとしたら。
結果、作家さんは恥をかいたり、怒ったり、勉強不足なあなたに失望する。
クリエイターが過去作に学ぶことには大きな意義があります。
それは、先達の学んだエッセンスをまとめて受け取ることが出来るからに他なりません。
学んだ人は、学んでいない人よりも、はるかに広大な引き出し、つまりヒントやお約束や黄金比やテンプレートを手に入れることが出来るのです。
それらは自分の創作におけるアドバンテージになったり、他者から尊敬を受けることにも繋がるでしょう。
コンテンツやノウハウの継承は、かつてクリエイター同士やオタク同士の交流の中で、自然に行われてきたものでした。
ある種、一子相伝にも似たこの継承は、とても非効率でお節介に思えるかもしれませんが、その時々の熱や空気を伝える、血の通ったものであることもまた事実です。
現在では、数多くの伝承が、次の世代へとバトンを渡されることなく忘れられていくのみとなっています。
何故なら、彼等に必要とされていないからです。
この継承の末端たる私たちは、最後の伝承者になってしまうのかもしれません。
我々がいなくなれば、伝承の仕方を知るものが消え失せるからです。
*****
2018/11/10追記
今のようにネットで知識やアイテムを自由にゲット出来なかった時代のオタクは、物量や知識で競い合う、悪く言えばマウントを取るのが常でした。
それが当時のオタクのアイデンティティであり、行動の原動力にもなっていたからです。
その時代のオタクが年とって、ネット時代が到来し、知識量が誇れなくなりました。結果、老害化してしまうケースを散見します。
己のアイデンティティが崩壊することほど悲惨なものはありませんが、後の世に無様な形で憂いを残すのは嘆かわしいことです。
知識は解放してこそ次代に受け継がれるのですから。
上の記事に付け加えですが、かの後輩さんは、自分は名作を吸収した今のクリエイターが作ったものを見ているから、過去の作品を吸収する必要はない、と考えているように見えます。
一見正解に思えますが、果たしてそうでしょうか。
作品をただ鑑賞するだけの人ならそれでも構いません。
興味を持ったら、ルーツを探ればいいだけのことです。
しかし、後輩さんは普通の人と同じ態度で本当にいいのでしょうか。
確かに、今の作品には過去の名作のエッセンスが含まれています。
しかしそれは、今のクリエイターが摂取し、咀嚼し、取捨選択し、自分の感性で出力したものに過ぎません。
つまり、元のごく一部、それも個人のフィルターで加工されたものです。
ここで求められる態度は、源流を辿り、今のクリエイターがどの部分に心震わせ、どの部分を自分なりに解釈して出力したのか。
それを知ることが一番大事なことだと、私は思います。
有名クリエイターのラフや覚え書き、プロットなど、製作途中の産物が有り難がられるのは、そのクリエイターたちの考え方や個性に触れることが出来る重要アイテムだからではないでしょうか。
後輩氏の、曲がりなりにもコンテンツ製作に関わる人間の態度としては、それらの価値を軽く見過ぎていると感じざるを得ないのです。
ゲームの伝承はもっと難しい
さて、ここで継承の難しいジャンルとしてゲームを挙げたいと思います。
上記では触れませんでしたが、愛好者の数で言えばマンガやアニメに引けを取りません。
しかし、物理的な意味で継承が難しくなってしまいました。
それは、ゲームにはハードが必要だからです。
過去のゲームは、互換性のないパソコンや、ゲーム専用機、そして営業期間が過ぎれば片付けられてしまうアーケード筐体がなければ遊べません。
今世紀のゲームでも、ガラケーやスマホ、ネットゲームなどはサービスが終了してしまえば、形すら残りません。
現代に至り、ゲームはもはや物体ですらなくなってしまいました。
そのため、ゲームの楽しさを気軽に若者へと伝えることが、アニメやマンガよりはるかに難しいのです。
このままでは完全に失われてしまう、と危惧をした、日本をはじめ世界中のゲーム愛好者が様々な手段でゲームを保存しようと努力しています。
しかし、場所や電気を喰らうゲームたちを保護することは容易ではありません。
この状況をメーカー側も手をこまねいて見ているわけではありません。
昨今、家庭用ゲーム機や携帯用ゲーム機のダウンロードコンテンツの形で、過去のゲームを復活させています。
全てを遊べるわけではありませんが、少しでもサルベージされるなら、ありがたいことです。
これらの過去作を、親が子供の前で遊んでみせると、案外喜んで遊んだりします。子供には先入観がありませんので、興味が持てる、親が夢中になっている、等の理由で遊び始めるのです。
子供に限りませんが、年長者が夢中になって楽しそうに遊んでいる様、読んでいる様、視聴している様を見せることで、若年者に興味を持ってもらえることは多いと思いますし、実際に手に取ってもらえる結果がそれなりに得られています。
やはり最高の伝承方法は、押しつけなどではなく、伝承者が楽しでいる姿を見せることに尽きますね。
今回の記事はここまでです。
よろしければ投げ銭をお願いします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
