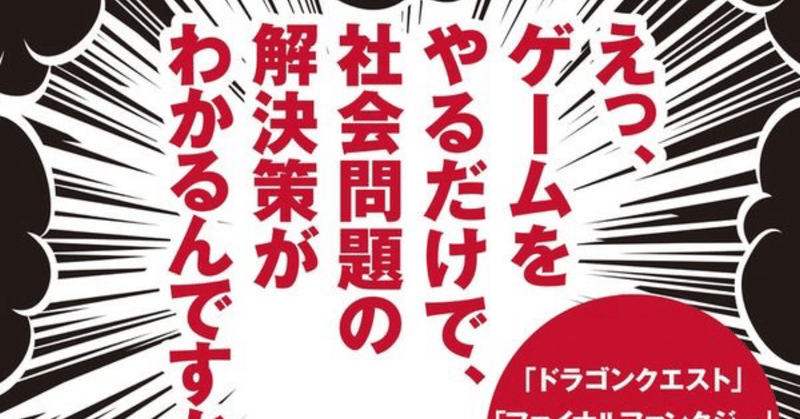
FFは環境テロで、ドラクエのテーマは歴史修正? 最前線のゲーム批評に心が躍らない理由──藤田直哉『ゲームが教える世界の論点』を読む
2023年1月17日に発売された評論家・藤田直哉さんのビデオゲーム評論集『ゲームが教える世界の論点』(集英社新書)が、各界からかなりの好評を得ている。この記事では、その内容を筆者の解釈を交えて紹介する。

■日本を代表する評論家の、類を見ないゲーム評論
藤田さんは、日本映画大学准教授で、『東日本大震災後文学論』『シン・ゴジラ論』『攻殻機動隊論』などで知られる文芸評論家。これまで、アニメ・ゲーム・マンガ・映画・文学・現代アート……と多岐に渡る分野を論じてきた。
1983年生まれで、そろそろ40歳になる。かつてこの界隈の最先端を走っていた東浩紀さんや宇野常寛さんが書籍でのサブカルチャー批評から半分身を引きつつある今、日本を代表する(特定のジャンルに属さない)評論家であると言っていいだろう。
今日の毎日新聞朝刊文化面に「ゲームが教える世界の論点」(集英社新書)を出した批評家・藤田直哉さん(39)登場。メディアとして社会を動かすゲームの力、ゲーム批評の重要性と役割などについて語っています。朝日新聞では土曜夕刊で月1回「ネット方面見聞録」連載中。 pic.twitter.com/eSjkd5Rykt
— 小原篤/アニマゲ丼 (@botacou) February 12, 2023
本書は、著者曰く「〔ますますゲームの存在感が増していくこの先の〕未来の展望を探るため、ゲームというメディアの問題点と可能性を吟味する。その上で、私たちがどのようであればよいのかを考えるための本」だという。
だが、これだけでは漠然としている。より詳しく言えば、その最大の特徴は、ビデオゲームが「自ら意図している(であろう)批評性」について、評論家が社会問題や思想の分野で扱われてきたテーマと繋げて論じている点にある。この点で言うと、おそらく(特に新書では)類書はほとんどない。
これまでも、評論家がゲームの批評性について書いたり、クリエイターが自ら作品に込めた意図を語ったりする書籍は数多く存在してきた。しかし、前者は評論家が一方的にゲームを批評的に考える場合がほとんどだったし、後者は評論のプロでは無いため、込められた意図がどのような価値を持っているのかについてはほとんど踏み込めていなかったり……要するに、ゲームを扱った評論としては片手落ちになっているものが多かった。
本書は違う。『デトロイト:ビカムヒューマン』や『FFⅦ』など、作り手が明確に批評性を込めた作品について、評論家がその意図を汲みつつ、既プレイのゲームファンの評価をも変えるような、新しい見方をもたらす分析をも展開している。
もちろん、こういう本が書かれるためには、現代アートや文学と並べて語ることができるような意識の高い作品と、ゲーム文化に対して敬意と知識を持つベテラン評論家の存在が不可欠だ。それが本書において、ようやく揃った。つまりこれは、ゲームの世界において、評論する側とされる側が共に成熟したからこそ成立した、記念碑的な意味をもつ評論集なのである。
■「歴史修正願望の変換器」としての『ドラクエⅪ』
だから、一見してギョッとしてしまう『ドラクエⅪ』(以下『Ⅺ』)が描いているのは「歴史修正」である──というような読解も、たんなる決めつけではなく、作品の意味の忠実な解釈を元にしたものとなっている。
『Ⅺ』は、「失われた時を求めて〔フランス文学からの引用である〕」というサブタイトルからもわかるように、時間をテーマにしたストーリー作品である。

作中では、時間を戻して誰かを救うということが、何度も繰り返される。さらに、本作の世界が、(ガンダムシリーズにおける『∀ガンダム』のように)他の『ドラクエ』シリーズの前日譚であるかのような描写もある。また、いかにも善良そうな人物が実は魔王だったり、というようなどんでん返しもしばしばある。そこで行われているのは、総じて言えば「歴史の書き換え」だ。
もちろん、この事実をもって「この作品は歴史修正主義的である」というような短絡は犯さない。むしろ藤田さんは『Ⅺ』を、歴史修正への欲望を持ちがちな現代社会への「処方箋」の役割を持つ作品として解釈している。
ここでビデオゲームは「作品の内部で自律的な時間が(中略)流れるものであり、かつ、プレイヤーが時間の操作を恣意的に行いうる」という特徴を持つメディアとして扱われる。つまり「時間操作=歴史修正」を楽しく味わうのに最適なメディアである、ということだ。この特徴のために、『ドラクエ』を含むゲーム作品は、しばしば外野から「(プレイすると)リセット感覚でものを考えるにようになる」などといった批判を受けてきた。
その批判は必ずしも間違っているわけではない。たしかにゲームは人間の感覚に影響する。しかし藤田さんは、『Ⅺ』が与える影響を、人間社会にとってポジティブなものであるとみなす。本作における歴史修正は、ホロコーストを無かったことにしたり、黒人奴隷を所有していた偉人の銅像を破壊したりする実際の現象とは違い、ゲームの中での擬似的なものである。それは、現実における歴史修正願望を安全に受けとめ、肯定的なものに変換する器になりうる。
(前略)レトロトピア〔歴史修正につながる、未来を悪夢として捉え過去をユートピア化する思想〕の心情に介入し、現実へと接続させ、家族や子どもや生命の価値を伝え、プレイヤーに世界のために利他的な行動をさせ、より大きな流れのなかの一人であるという宗教的な感情を感じさせようとするのが本作の思想であり、戦略である。
作中においてプレイヤーは「命の大樹」という生命の輪廻を司る存在を守るために歴史を書き換える。このようなゲーム内神話は、プレイヤーの宗教的な不安を癒す効果を持つ。また、作中では「結婚」や「出産」が繰り返し描かれる。それはプロデューサーである堀井雄二さん自身が「ゲームには、一作品ごとに“仲間”“人生”“親子”といったテーマを設定しています。友情や血縁の大切さを、ゲームを通して子供たちに伝えたいから」と語っているように、人を共同体に(擬似的にでも)帰属させる。
つまり『Ⅺ』は、ゲームならではの特性を活かして、現代社会特有の不安から来る歴史修正願望に応えた上で、それを前向きな形に昇華してくれる(ここに自己批評性がある)「励まし」のゲームだと説明できるのだ。
■環境テロリズム(を内省する)ゲームとしての『FFⅦ』
日本史上最大級のヒット作である『ファイナルファンタジーⅦ』(以下『Ⅶ』)も、同じく「ゲームならでは」を活用した自己批評的なゲームであると論じられる。

細かい設定は省略するが、本作の前半における主な敵は「神羅カンパニー」という世界を支配するエネルギー企業である。企業城下町である「ミッドガル」には貧富の差があり、スラム街の住人の命は企業の気まぐれで奪われてしまう。「神羅カンパニー」が所有している「魔晄炉」という(ほぼ原発)施設は、メルトダウンを起こして主人公の仲間の村に多数の犠牲者を出している。『Ⅶ』は、主人公がテロリストとしてこの「魔晄炉」を爆破するところからスタートする「反原発、環境テロリスト、反資本主義、反帝国主義のゲーム」だ。
当然、それだけでは終わらない。物語後半、プレイヤーが操作していた主人公が、才能のない負け犬であるにも関わらず自分を「才能のある英雄的存在」だと思いこむ精神疾患を抱えた中二病的青年だったことが判明し、彼はアイデンティティの危機に直面することになる。また、主人公が加担していたテロ組織のリーダーも、テロの目的は「星を救うため」というのは建前であり、真の目的は「自分の復讐のため」であったと内省を深めていく。
そして敵は資本主義の象徴だった「神羅カンパニー」から、むしろその資本主義的世界を滅ぼそうとする環境テロリスト的存在・セフィロスへと変わっていく。プレイヤーは前半と後半で、立場を180度回転させることになる。だが、このラスボス・セフィロスすら、自分を特別な種族だと思い込んでいるだけの存在だった。
藤田さんは『Ⅶ』のこの展開を、RPGの特徴である「(ヒーローへの)なりきり」への自己批評であり、カウンターカルチャーで描かれがちな「革命」「叛乱」への内省のドラマと評価する。
自身の究極の目的すら勘違いの産物、フィクションでしかないという設定を、あえて主人公とラスボスに担わせている点が、本作の批評性である。それは、本当は剣を振るったり、戦ったりできるわけではない一人の人間なのに、ゲームのなかで強いキャラを演じて同一化している我々の姿である。それを、さまざまな〔テロや虐殺を誘発してきた〕二〇世紀の悲劇的な思想と重ねているのだ。
この二人の違いに、『ファイナルファンタジーⅦ』が提示しようとした思想がある。クラウドは精神崩壊にすら陥りながらも、自身の「なりきり」に気づき、考え方を変更した。(中略)このような、弱さを認めて、なりきりを理解することが重要なのだ、というのが、本作の重要なメッセージだ。
RPGならではの特徴である「なりきり」を、○○主義に被れるテロリストのそれに重ねて描写する。そうすることで「自分の弱さに向き合う」という、同時代の作品(『エヴァ』や『ファイトクラブ』)にも共通するような普遍的な自己批評性と、オウム真理教のテロを生み出したようなカウンターカルチャーへの批評性と、反原発・反資本主義といった社会批評性を同時にもつ。『Ⅶ』は、そんな同時代の思想を見事に凝縮した作品だったのだ。
■ゲームには「評論家」が居なかった
上記の読み解きはいずれも論理的な飛躍を控えた保守的なもので、国民的作品において作り手が意識的に行っている(であろう)自己批評的な表現を扱っている。そのため、真面目に作品に向き合ってプレイした人であれば「ああ〜言われてみれば確かに」と思えるような内容になっている。
もちろん、誰もが藤田さんのように内容をうまく言語化できるわけではない。が、例えば映画や文学のようなジャンルでは、その畑の評論家が作品の持つ良さをリアルタイムで分かりやすく説明してくれる制度(新聞・雑誌評やパンフレットや文庫解説)が整っている。時には書籍として刊行もされる。ファンはそれを読み、解説を通して語彙力や分析力を身につけ、より批評的な作品を受け入れうるような強固な地盤を構築していく。やがてはそれが作り手の更なるチャレンジを支える土壌にもなるわけだ。
ところが、ゲーム業界には、そのような制度は(業界の規模の割に)かなり手薄かったように思える。私の知る限りでは、(海外でどうかは知らないが)日本では、本来批評性を込めて作られたはずのビデオゲーム作品が、その批評性について黙殺されたまま「無味無臭なエンタメ」として商品紹介的レビューの対象とされてきた。そしてその状況は、たとえば「ゲームが子どもに悪影響を与える!」というような批判に対して、「社会(政治)とエンタメは別物なので…」と半笑いで反応してしまうような土壌を産むことにつながったのではないか。

一昔前は、このようなゲーム批判が根強かったという
社会(政治)とエンタメを切り分けるこの姿勢を、完全に否定することはできない。ジャンルによっては、そういう態度を取らざるをえない場合も確かにあるからだ。しかし、少なくとも『FF』や『ドラクエ』は、ゲームが持つ悪い(と見なされうる)特徴に自己批評性を持ち、それを乗り越えようと努力してきた。そこには、社会に対するメッセージも込められていた。そういうゲームを論じる時くらいは、真正面から「いや、このゲームは良い影響を与える作品だ!」と言うべきだろう。
2010年代になって、ようやく日本でもそのような体制が整いはじめてきた。その代表選手は、(この本の元となる連載が掲載された)IGNジャパンやゲームスパークやオートマトンといった一部ネットメディアだ。ほか、『ゲンロン』『エクリヲ』など人文誌の特集や、『ゲームラボ』のコラムや『ユリイカ』『SFマガジン』の単発記事としても見かけることができる。藤田さんは、そのような新しい潮流、つまり「社会(政治)とエンタメを切り分けずに、真正面から評価できる作品を評価する」潮流の代表的存在である。あなたがもし、ゲームをくだらない暇つぶしではなく、語る価値のある素晴らしいものであると思っているなら、彼の書く文章には触れておいた方が良い。
■やりきれない「遅さ」の問題
と、ここまでベタ褒めしてきたつもりだが、私自身は、この本(元連載もちょこちょこ読んでいた)に感心しながらも、イマイチ心が躍らないところがある。理由はたぶん、語られている内容に「遅さ」と保守性を感じるからだ。
『ドラクエⅪ』は堀井さんが64歳でディレクターを務めていたし、『FFⅦ』が出たのは四半世紀前だ。他に扱われているゲームも多くは50歳前後のクリエイターが主導するもので、特に日本のゲーム──『ペルソナ5』『DEATH STRANDING』『イースⅧ Lacrimosa of DANA』──の主なクリエイターは全員45歳を超えている。タイミング的にも、批評性の内容的にも、2023年に読むには遅い。
冒頭で「評論する側とされる側」の成熟がこの本を生んだと書いた。『FFⅦ』は当時から既に批評性を持っていたので、足りなかったのは評論家の方だ(この記事を書くにあたって当時『ゲーム批評』に載った評論も読んだが、典型的な商品レビューで落胆してしまった)。
FF7について当時の批評を見てみるのも面白いな。
— 皐月ひろあき (@bt_hiroaki) January 12, 2020
ゲーム批評的にはシナリオが不満だったみたいな内容だけど。 pic.twitter.com/Ay7yX7NQtU
『FFⅦ』の場合、当時リアルタイムでをプレイしていた藤田さんが成長して一流の評論家になって、ようやくその真っ当な評論が書かれているのだが……いくらなんでも遅すぎる。そりゃ、内容も古くなる。今どき、革命に対する内省と言われても……。革命を起こそうとしている集団なんて日本にはもう存在しない。テロを起こす主体は、出口不在の社会で苦しむ普通の人だ。評論家サイトが追いつくまでの間に、『FFⅦ』の持つ批評性の大部分は、随分と時代遅れなものになってしまった。
比較的最近に発売されたゲームの方は、そもそもの感性が古い。40歳を超え、家族や仕事や社会に責任感を持つ真っ当な作家は(評論家も)、自然と保守的な批評性、保守性な作品へと流れていく。それは別に悪いことではないが、20代の読者(私)にとっては退屈だった。大きなゲームのディレクターをしている40代男性はその時点で「体制側の勝者」でしかないわけで、むしろ保守的なメッセージを持つのが中年の責務だろうから、それは仕方ないが。
■「メディア不況」のなかで
自分が楽しんでいる作品の評論は、できることならリアルタイムで読みたい。四半世紀後に読むのは嫌だ。やはり若いうちに、同世代(か少し上の)評論家による同世代の作家に対する評論を読んでおきたいし、それができないのは困る。
だが、状況は良くない。先ほど、2010年代にゲームにも評論の基盤が整ってきたといったが、それだっていつ崩壊するかわからない。紙の雑誌や書籍や新聞がますます売れなくなる一方、ネットメディアも景気が悪い。分野は違うが、バズフィードやハフポストといった主要ネットメディアの記事の質は(おそらく経営の悪化と並行して)恐ろしいほど劣化している。かつて良質な書き手を支えていた広告費や購読料がGAFAやネット広告代理店に送金されている今、儲からないレビューの立場なんて、風前の灯火だ。
そんな「出版不況」ならぬ「メディア不況」の状態では、若者向けのまともな評論本の出版は数少ない。去年新書市場で一番売れた本は『80歳の壁』、二番目に売れた本は『70歳が老化の分かれ道』、三番目は85歳の養老孟司さんが書いた『ヒトの壁』だ。中年向け(と私は感じた)の本書が出版されているだけでも御の字である。こういう背景を考えると、帯の「えっ、ゲームをやるだけで、社会問題の解決策がわかるんですか?」という、なかなかな煽り文句も味わい深くなってくる。

去年のベストセラー。ちなみに同ランキングには瀬戸内寂聴の本もランクインしている。
こんな環境下で発売された、貴重なゲーム評論集である本書。上の紹介では雑に要約してしまったが、本文ではゲームと社会的文脈が丁寧につなぎ合わされている。読めば、今後ゲームに対する楽しみ方の幅は間違いなく広がるだろう。合わなそうだからといって読まないのは、損だし、(未来の評論本の可能性を摘むという意味で)罪である。発売からかなり時間が経ってのレビューになってしまったが、まだ遅くない。今すぐ買って読むべし、である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
