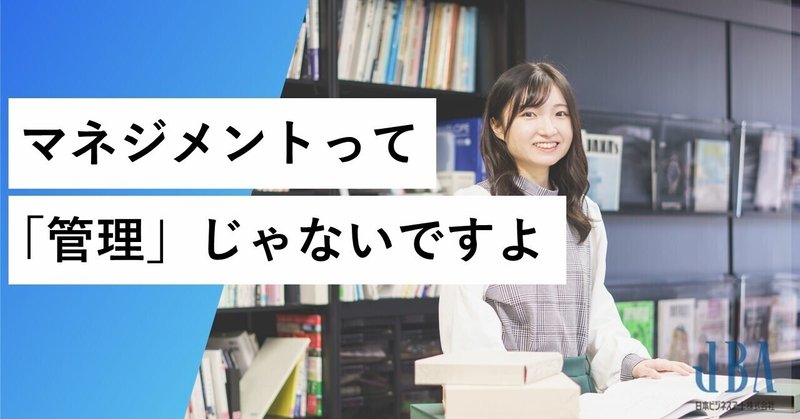
アートとは縁遠い普通の文学部生でもクリエイティブにお客さまの課題を解決できる話【前編】
こんにちは!慶應義塾大学3年の岩﨑です!
今回はタイトルの通り美大生でもなんでもない、なんなら中高の美術の成績は全教科の中で一番悪かった私が、クリエイティブの力でお客さまの「〇〇したい!」に立ち向かい奮闘した時の話をしたいと思います!
前回のお話
前回、「フリーマガジン好きがJBAに入社してみた」
という旨の記事を書きましたが、読んでくださった方はいますでしょうか?
サークル活動でのフリーマガジン制作が好きな私が、その延長線上でビジネスの世界に飛び込んだリアルな現実、経験したいくつもの衝撃体験を語らせていただきましたので、気が向いた方は是非チェックしてみてください!
今回の前編では、その「編集」についてもう少し詳しくご紹介しながら、出会いの経緯についても少しお話しします。
後編では、編集業務で携わった実際の案件の中で、訪れた転機について、気づきについてお話ししたいと思います!
What’s 編集???
私は前回の記事で、編集は「お客さまの抱える「伝えたい!」を伝わる形に落とし込む段階」であるとお伝えしました。でも、これだけだと実際の様子がイメージしづらく、編集という仕事が何をしているのか、イマイチ理解できないですよね。
もう少し具体的に説明すると、お客さんがJBAに持ち込んでくださる「伝えたい!」を分解していって、
なぜ伝えたいのか(目的)
どういった経緯で伝えたい!になったのか(背景)
なぜ伝える必要があるのか(課題)
伝えた先で相手にどう思ってほしいのか(期待効果)
などなど、伝えたい!の解像度を上げて上のような要素ごとに考えていきます。
その結果、どういった媒体で伝えるのが適切なのか(手段)を考え、伝わる形に落とし込んでいくのです。
編集では、次の4つの要素を検討して、お客さまの「伝えたい!」の解像度を上げていきます。
①なぜ伝えたいのか(目的)
②どういった経緯で伝えたい!になったのか(背景)
③なぜ伝える必要があるのか(課題)
④伝えた先で相手にどう思ってほしいのか(期待効果)
最終的に、これらの要素を含むコンテンツを、どういった媒体で伝えるのが適切なのか(手段)を考え、誌面や動画、セミナー、ポスターといった様々なアウトプットに落とし込んでいくのです。
編集って出版社っぽい響き?
編集と聞くと、「編集者」「雑誌編集」など、紙に関連するキーワードを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか??
私自身、サークルでフリーマガジンを制作していたこともあり、最初は紙の意識が強かったです。
ページレイアウトやページデザインを考えるのが編集なのか!なるほど!
雑誌みたいに面白みのある誌面だったら、確かに読者も読みやすそうだし、難しい内容でも伝わりそうだし、いいじゃん!
でも、実際の「編集」はこれと全然違いました。
ここで念頭に置いておきたいのが、JBAがビジネスを展開する上でのスタンスです。
JBAはコンサルティングとクリエイティブの力を掛け合わせてお客さまの課題を解決する、ことを掲げています。
つまり、目的はあくまでお客さまの課題解決であって、冊子作りではありません。
たとえば、お客さんとする大手企業のブランディング、という課題の解決するためには、紙の社内報を発行することよりも適した手段があるかもしれません。
様々な選択肢を検討した上で最適解を導き出す必要があります。
最適解は紙からweb社内報への切り替えかもしれない。あるいはポスターや貼り紙かもしれない。
そもそも紙ではなく動画かもしれない、はたまたワークショップや研修・セミナーであるかもしれない。
紙媒体から離れたとしても、お客さんの「伝えたい!」という課題に対して「伝わる形」を提案するのであれば、それは等しく編集と言えるのです。
初期の希望はライティング!?
このパートからは私が編集へたどり着いた紆余曲折の道のりをご紹介したいと思います。
突然の告白にはなりますが、私はJBAへ入社した当初、ライターを志望していました。
フリーマガジンを制作していた私が所属していたのは、文字書きのパート。主に執筆担当でした。
「伝える」にも色々種類がありますが、JBAがインターン採用で「伝えるのプロ集団」と呼称していたのを見た私は「言葉の力でもっと伝えたい!!」と意気込んでライターを志望していたのでした。
ライティングからプロマネの道へ
入社後数週間が経った私は研修期間を経て、まずプロジェクトのマネジメントをいくつか経験させていただきました。社内報制作のフローの中で、様々な業務がありますがスポットごとに少しずつ関わらせていただきました。
プロジェクトのマネジメントをある程度経験した私は、ライターを志していた入社時から一転し、プロジェクトの進行を管理する仕事に携わる場面が増えました。
マネジメントに楽しさを感じつつあった私は、この先もっとマネジメントについて極めようかな...もっと関わりたいかもしれない...などぼんやりと思っていたのでした。
その気持ちをとある社員さんに伝えたところ、「プロジェクトマネジメントといっても、ただスケジュールを管理するだけではない」ということを教わったのです。
よくよく考えればそれは至極当然のことで、予定通りにプロジェクトを進行させるのは当たり前で、その上で付加価値を提供しなければいけません。
マネジメントという全体を俯瞰する立場でこそ見えてくる課題に対して、解決のために様々な提案をすることで、ただ予定を管理するだけにならない、価値が生まれるということです。
しかしながら、
その提案の際に求められているのが、クリエイティブの力であること。
しかし、現状クリエイティブな提案をする力は自分にはまだないこと。
そして当時は、社内にクリエイティブな提案をできる学生が非常に少なかったこと。
そのような理由から、マネジメント業務ではなく予想外にも編集に関わることを提案いただいたのでした。
嬉しいお話でしたが、ストレートに編集にいくことを受け入れられたわけではありませんでした。
「マネジメントしたいかも...!」という自分の気持ちに対してフィードバックをいただき、それを踏まえた上で気持ち切り替え、いざマネジメント頑張ろう!と決意を新たにしようとした矢先だったため、編集に関するお話をいただいた当時は少し驚きました。
そして、なぜアーティスティックな才能のない自分がそのようなポジションを打診していただけたのか、わかりませんでした。
美大とは程遠い総合大学のごく普通の文学部生、しかも美術の成績は全教科中で最悪。
そんな自分のステータスを考えると、安易にお返事して良いものなのか、葛藤しました。
プロマネから編集の道へ...?
ただ、学生の中でクリエイティブな提案ができる人材が少ないという状況を聞いたとき、自分たちがJBAに在籍していることの価値ってなんなんだろう、それってクリエイティブな提案ができることなのではないか?という考えに思い至りました。
JBAという組織全体を見た時に、そういった人材が増えるに越したことはありません。
未知なる領域への挑戦で少々不安を抱いた自分の気持ちよりも、集団としてより高みを目指したいという思いに天秤が傾いた私は、編集を学ぶ決心をしたのでした。
いよいよ編集へ参入していくにあたり、クリエイティブという言葉から、クリエイト→クリエイター→アート→芸術→デザイン…?と想像を広げていきました。
それに加えて編集というワードから連想する雑誌のイメージも相まって、
「ページレイアウトとかだよね、デザインとかグラフィックとかをやる世界なのかな…」と編集のことを捉えていたのです。
ある種、アートな領域に対して若干のコンプレックスさえ感じていた私は、そのような傾いた思いを先行させながら実際の案件に対して取り組んでいくことになります。。。
ささやかにも決断を下した割りに、早速暗雲が立ち込めている状況ですが、
そんな私が
・どのようにして現在持っている編集への価値観にたどり着いたのか
・そこに到達するまでに実際の案件の中でどう乗り越えていったのか
について後編と称してお話ししたいと思います!
最後までお読みくださりありがとうございました!
後編はこちらからお読みください!
JBAに興味を持たれた方は、こちらから採用説明会にご参加いただけます!
