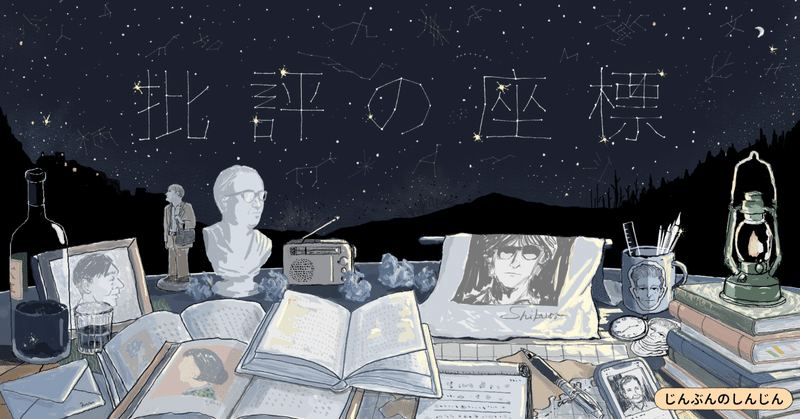
【批評の座標 第18回】名をめぐる問い――柳田國男『石神問答』において(石橋直樹)
民俗学の祖、柳田國男。吉本隆明や柄谷行人をはじめ、歴代の批評家によって論じられてきた評価の分かれる人物でもあります。知識人との往復書簡集『石神問答』を読み解き、柳田の思想の核心「名への欲望」に迫るのは、「ザシキワラシ考」でデビュー、「〈残存〉の彼方へ」によって第29回三田文學新人賞を受賞した石橋直樹です。
――批評の地勢図を引き直す
名をめぐる問い
――柳田國男『石神問答』において
石橋直樹
1、はじめに
かつての批評家たちの数ある文章のうちに、時折、あちらへこちらへと引き摺り出されるようにして、その特異な名は据えられてある。その名に批評家はあるとき出会い、あるときには決別し、またあるときにはその名前を読み替えていく。その不意の一撃が批評という営為のなかに絶えず現れるならば、その名の主は、批評という横断としての営為が位置する三重点そのものを指し示しているといってよい。明治という近代日本の到来とともに訪れたその巨人の伝説を、右往左往するようにして、わたしたちはあの名について差し向けられているのである。そしてわたしもまた、このようにふらふらと柳田國男(1875-1962)という名の渦の中心へと近づきつつある。
柳田國男について口を開くということは、今やほとんど不可避的に論争に身を委ねるということになりえて、論者の数だけ存在するといってよい柳田像――肯定[1]、批判[2]、読み直し――がひしめきあっているなかに、われわれはおそらく何かを賭けなければならないだろう。例えば、著名な花田清輝と吉本隆明による柳田をめぐる論争においては第三世界革命的な可能性の中心として論じられ、政治の季節において繰り返し、ほとんど肯定的に論じられてきた。しかし九〇年代には、ポスト・コロニアリズムの影響を真っ向に受けて柳田批判が子安宣邦らによっておこなわれ、国民国家論及び帝国主義批判に並行するようにして柳田民俗学は糾弾されていくこととなる。しかし現在においては、むしろ東日本大震災の衝撃のなかに柄谷行人の遊動論を中心として柳田國男は復権しつつある。およそここでは紹介しきれないほどの「柳田國男論」が文壇に何度も現れ、何度も書き換えられてきたのである[3]。
しかしそうした「象徴論争」のなかに自らの位置を見出すのではなく、柳田を問う者であり問われる者として、批評的謎解きの行為のただなかにあるものとして読み直すことは可能であろう。それは、「名」を集め、「名」を合わせ、「名」を解く者であったという柳田の、「名」の謎を解いていく作業にあたる。言文一致のまさにその裏側において、柳田は音として残っていた「名」を集め、異様な形でそれを書き残している[4]。そこで発見されたものは確かに「風景」[5]にも増してもっぱら言語的な「名」であったとしたならば、柳田論はどこまで書き換えることができるだろうか。日本思想の系譜のなかに柳田國男を再附置していく研究も新たに進められている昨今の状況[6]において、膨大な研究的裏付けのなかで柳田像はより現実的なものとして複合的になりつつある。あのあまりに近く、あまりに目眩のするような距離の上を、自由に飛び回ることさえ可能なあの批評の名のもとに、わたしもまた柳田國男を論じてみたい。
2、柳田の「名」への方法論
柳田はいつだって「名」について問うていたのではないか、そのような感覚が柳田を読むということにつきまとってならない。そしてそれはただの名ではない。言物一体ともいうことができるような呪術性を帯びたものとしての「名」が柳田の著作のなかに頻出している。
柳田は命名に関する研究を多く発表しており、『蝸牛考』(一九三〇)、『地名の研究』(一九三六)、『野草雑記』『野鳥雑記』(一九四〇)、『風位考資料』(一九四二)など物別にどのような呼称が用いられているのかという論考や、『歳時習俗語彙』(一九三九)、『分類山村語彙』(一九四一)、『族制語彙』(一九四三)などの行為や行事を視野に入れた全国的な「分類習俗語彙」の編纂に取り掛かっている。「柳田の命名研究は、命名の結果としての名前への関心にとどまらず、その背景にある老若男女の日本人の造形力の考察にあった」[7]ものとして、それは中期柳田民俗学の中心に据えられているといってよい。こうした著作においては、〈言〉と〈物〉[8]における分離を謳うようなここ一世紀の言語観において、ほとんど質を異にした問いが立ち現れている。
では柳田の言語学的方法論とはどういったものかというに、柳田は次のように語っている。それは政治的な問題と紙一重な方法論であったため、繰り返し論じられてきたものである。
国語の改良は古今ともに、先づ文化の中心に於て起るのが普通である。故にそこでは既に変化し、又は次に生れて居る単語な物の言ひ方なりが、遠い村里にはまだ波及せず、久しく元のまゝで居る場合は幾らでも有り得る。その同じ過程が何回と無く繰返されて行くうちには、自然に其周辺には距離に応じて、段々の輪のやうなものが出来るだらうといふことは、至つて尋常の推理であり、又眼の前の現実にも合して居て、発見などゝいふ程の物々しい法則でも何んでも無い。私は単に方言といふ顕著なる文化現象が、大体に是で説明し得られるといふことを、注意して見たに過ぎぬのである[9]。
これはまさに、中心としての京都などから最も離れた北方と南方に方言の一致を見出し、中心からの距離が時間的な古さになるという「方言周圏論」[10]であり、柳田は自らの民俗学的方法論と言語学的方法論を重ねるようにして語っている。一九二七年『人類学雑誌』四月号から掲載されたこの「蝸牛考」では、これによって「蝸牛」の言葉が京都を中心に同心円状に伝播し、遠隔地ほど古い形が残るという法則を示している。

ここで指摘しておかなければならないのは「蝸牛考」で述べられる「方言の地方差は、大体に古語退縮の過程を表示して居る」[11]というような仮定は、おそらくドイツ比較言語学に由来するものであろう。ダーウィン的進化論を輸入して「系統樹説」を唱えたドイツの比較言語学者アウグスト・シュライヒャー(August Schleicher)の門弟、ヨハネス・シュミット(Johannes Schmidt)の「波動説」は、奇妙にも周圏論に酷似しているのである[12]。「波動説」とは、言語の改新が波の動きのようにして同心円状に発生するものという説であり、印欧語に数本の等語線があることがこれによって指摘された[13]。
ここにおいて、波のイメージによってその伝播を考える「波動説」のシュミットに対して、木の枝のイメージによって言語改新を描く「系統樹説」をとるシュライヒャー、およびその継承者たるマックス・ミュラー(Max Muller)が大きな対立軸として捉えることができよう。そして、これは「方言周圏論」によって言語的変化を捉える柳田に対して、「発生」という樹木のイメージで言語的変遷を捉える折口信夫の対立に付合しているといわなければならない[14]。このようにしてわかる通り柳田の民俗学自体が、言語学の正統な子どもであって、その目線は第一に言語という問題をどのように扱うかということにあったのである[15]。
このようにみると柳田の民俗学とは西洋的言語学の変化形でしかないようにみえるが、しかし柳田のほとんど徹底した独自性は「神の名」において現れるといってよい。例えば、青森県八戸市に現れるとされるメドチという妖怪について柳田は次のように述べる。
さし当たり御知らせをしたいと思うのは、メドチという語の分布及び由来である。北海道の土人が水の神をミンツチと呼び、その怪談には若干の一致があることは、夙く金田一教授がこれを説いておられる。この蝦夷のミンツチと八戸などのメドチと、同じ語であることはおおよそ明らかだが、問題はどちらが真似たか採用したかである。…(中略)…それから最後にはずっと懸離れて九州南部、薩摩と日向大隈の一部ではまた確かにミヅシンといっている。ガアラッパまたはガオロといっても通ずるが、此方が多分新しかろう。こういう霊物には忌んで名を言わぬ場合があるので第二の呼称が起こりやすいのである。ガオロ・ガアラッパは共に「川童」の日本訓みであるが、九州では現在またカワノトノもしくはタビノヒトなどと称えてこの語を避けようとする傾向も見えている。ミヅシンは土地の人たちが「水神」の湯桶よみだと解しているらしいが、これを八戸方面のメドチや蝦夷地のミンツチに比べてみると、初めて古語のミヅチと同じ物であり、ただこの国の三方の端々にのみ、たまたま保存されていたことが判って来るようである。ミヅチは蛟と書きまた虬と書いている。だから蛇類では無いかという人もあろうが、それに答えては支那ではそう思っていたというより他は無い。日本のミヅチという語には水中の霊という以外に、何の内容も暗示されておらぬ[16]。
これは柳田の有名な妖怪=神の零落説を如実に反映する箇所である。もともと神とも神に準ずるようなものとして信仰されていたものが、忘却と合理的思考の発達によって妖怪として恐れられ、退治されるようになったという仮説を例証するものとして「メドチ」は論じられる。しかし、これは何よりも「神の名」、すなわちその名前の活用変化によって触知されるものとして現れているのである。この「メドチ」という妖怪を分析するにあたってここで柳田が論じていることは、アイヌの「ミンツチ」や九州南部の「ミヅシン」などの事例を参照しながら、古語としての「ミヅチ」へと接続させていく。「ミヅチ」というのは「水中の霊」という意味をもつものとされ、時間的・空間的変遷によって語彙変化し「メドチ」という言葉へと変わり、具体的内容も付与されていったとする。
「日本のミヅチという語には水中の霊という以外に、何の内容も暗示されておらぬ」という箇所は、おそらく柳田の「神の名」の問題を深めていくにあたって欠かせえぬ記述であるといえよう。「ミヅチ」という「水中の霊」は古代より生き残る〈言〉なのであるが、けれども内容としての〈物〉を欠いている。〈物〉としてのある対象を指すのではなく、むしろ漠然として〈言〉としての「神」が信仰されているのであり、ここにきて〈物〉は〈言〉に対して非本質的なものとしてあらわれる。したがっていうなれば、柳田の「神の名」において、その特異な呪術性から名とは本来その神の本質そのものであり、本質に対する媒介項が必要とされえないとすらいうことができるのである。
そしてまたより踏み込んで述べるならば、柳田の妖怪とは語彙変化なくしてあり得ないものですらあった。妖怪とはここにおいて、〈言〉そのものとして捉えられ、むしろその活用変化のなかで神に結び付けられているのである。西洋的言語観を通過しながらも、しかし柳田の言語観は呪術的な問題として奇妙に変容しているということができるだろう。
3、名をめぐる問い
一九一〇年五月、『遠野物語』の草稿を書き終えて清書に入るまでの間[17]、柳田國男は『石神問答』を上梓した。この論考とも名状し難い特殊な文章には、一九〇九年から一年間、柳田が周辺の知識人と交わした三四通の書簡が収録されている。これは柳田が発した「石神」に関する質問に対して、当時民間信仰や古事に詳しかった知識人たちが応答するという書簡集であり、それらをひとまとめにして出版したものである。
柳田が質問状を送った人物は、次のような顔ぶれである。旧幕臣で庶民生活と漢籍に広範な知識を有する牧師の山中共古(山中笑)、邪馬台国北九州説を唱えた歴史学者の白鳥庫吉、遠野の人類学者の伊能嘉矩、『遠野物語』の語り部を務めた昔話研究者の佐々木喜善(佐々木繁)、考古学者の和田千吉、ミネルヴァ論争を展開することになる歴史学者の喜田貞吉、神風連の乱に加わった八代宮宮司の緒方小太郎、柳田の弟で日本画家の松岡輝夫である。
この書簡集は、民俗学前史を辿る上で柳田が学んだ先人たちの足跡を追うことができる論考として読むことができるが[18]、今回はこの書簡集全体に通底する「シヤクジ」とは何かという「名をめぐる問い」について、柳田の「名」への欲望を参照してみたい。
拝啓 清秋の候御左右如何時 時々御上京のよしを承知仕候へ共 私用に妨げられ其都度拝眉を得ず背本懐候 偖久々掛ちがひ居候間に 御高教を仰ぎ度問題沢山たまり申候 諸国村里の生活には書物では説明の出来ぬ色々の現象有之候中に 最も不思議に被存候一事はシヤグジの信仰に候 之に就きて何か曾て御取調又は御聞及のことは無之候や伺度候
小生は最初右は関東数国の間に限られたる信仰とのみ存じをり候ひしに 此頃注意致候へば西国の端々迄之に因ある地名分布致居 愈好奇の念に勝へず候例へば
若狭三方郡の三方湖の西岸より常神岬の方へ越ゆる峠に「塩坂越」とかきてサコシ
播州の海岸備前境に接して坂越 これは今日サカゴエなど申す者も有之候へ共実はサコシにて 以前はシヤクシに近く唱へ候か幽斎の狂歌に しほは早よき程なれや鍋が島しやくしの中に入れて見つればなどども有之候…[19]
まず柳田は一通目、九月一五日の山中への手紙で冒頭次のように問いかけている。村里の生活に書物を読んでもわからないことがあるから教えて欲しいとのことをいい、何かというに、「シヤクジ」なる名前の信仰が至る所に存在するのだといって、各地に点在する「シヤクジ」の名前を挙げている。それに対して、山中は柳田が例示しなかった「シヤクジ」の信仰などを紹介した上で次のように説明する。
偖此等に就きての諸説は
(イ)神体石故石神と書せしと云ふもの
(ロ)昔時田畑の尺を計りし後に其尺を神に祀りし故尺神又は尺地と云ふなりとするもの
(ハ)社宮司と云ふは神官の義には非ざれど神に奉仕する神なりと云ふもの
等にて 社護と申すのには別に説も承り不申候何れもオシヤモス、オシヤモヅ、オシヤモジ、オシヤモと申居候も 一村の者が両様に唱へ居る例も有之候て必しも其一に限りたる事には無之候…
此等の事は昔の流行物と見なし可申か 一地方にオシヤモジ流行すれば同信仰諸国に広がり候事に候はずや 神仏ともに或時代に同一のもの諸国に起り候事ありと存じ候 如貴説民俗学進み候はば解釈出来候ことも多く御座候ことと存候 右等何の御参考にも不相成ことは奉存候へども 御返信迄に申上候 頓首[20]
山中はシヤクジに対する問いかけに対して、その名の由来を三つの説で応答している。一つは御神体が石であるため、二つ目は計測の尺を神として祀ったため、三つ目は社宮司から転じて神に奉仕する神を表しているためとする。その上で、ある一時代の流行物である可能性が高いと述べ、一地方で流行したものが諸国へと広く伝播したものとしている。山中の知っている情報を踏まえながら自説が展開されている手紙を見て、普通ならば柳田の問いはこれによって満たされるはずだ。しかし、問いは問いを呼び、この手紙は三四通にまで膨れ上がっているのである。その流れを追っていかなければならない。
柳田は一〇月六日の山中への返信で[21]、シヤグジの起源を石の神に求める山中の説に疑問を呈して、「(イ)大多数のシヤグジは石神とは書かざること」「(ロ)石神は後世からのあて字らしき節々」「(ハ)シヤグジにして石を祀らざるもの多きこと」「(ニ)石を祀りてシヤグジと言わぬもの亦多きこと」[22]と反論理由を挙げながらシヤグジは石神でないのではないかと述べるのである。続けて「そんなら何かと云う考も定まらぬうちに無責任のやうに候へ共 シヤグジの名の由来はどうも外にあるやう存ぜられ候に付試に申置候」[23]と、山中にシヤグジの語源が石という素材から来たものではなくて、外に意味があるのではないかということを尋ねている。ほとんど直感ともいえるレヴェルで、柳田はシヤクジに何か別のものを投影しようとしているかのようである。
しかし山中の返答は「人気に投ぜし流行神は意外に分布も広く候ものにて 秋葉の火防御嶽の盗人除又は近頃の招猫の如く 諸国流行相成候事も候へば 一地方の流行殊に江戸高輪のオシヤモジの大流行は諸国にても婦人に伝はり出せしこと存じ候」[24]とあくまでも近世的な一流行としてシヤグジを解釈している。江戸戯作文化などに通暁した山中にとっては妥当な判断といえよう。柳田はこうした山中の返答に対して、「シヤグジは決して近代の神にては無之候」[25]として次のように自らが考える核心的仮説を提示してみせている。
佐久と申す地名は信濃の佐久郡を始め諸国に有之 尾張の海上に佐久の島 下野那須野に佐久山も有之 又安房其他に佐久間と申す地名も 其意義今以て不明に候へ共 多分は佐久神と同源かと愚考仕候 日本語にて「遠ざくる」のサクなりとも可申も 現代アイヌ語にてもサクは隔絶の義有之かと存じ候 恐くは古代の生藩即ち所謂荒ぶる神と新に平野に居を占めたる我々の祖先とを隔絶する為に設けたる一の隘勇線ならんかと愚考致候が 御意見如何承り度侯
此頃新編相模国風土記を検し候に 彼地方にては石神多く社宮神又は佐護神少く 且二種併存する村は一も無之ことを発見致候 さ候へば近世となりては石神シヤグジは同じ神とせしことは疑なく候 唯最初より此二つの神同一なりきとは未だ信じ難きのみならず 少なくもシヤグジの名義は石の神に基かざることは延喜式之を証するかと存じ候 或は式の佐久神は今のシャグジに非ずとも申すべきも 現に御地三保の松原なるシヤグジの如きは新風土記に佐久神と記し有之候[26]
柳田はここにきてシヤクジは石神という名が持つ想像力を超えて、古代における境界の神であるサク神と何か関係あるのではないかという疑惑を提出しはじめる。柳田はそれがもともと同一の神であるということを言い渋っているが、音韻、すなわち音声の比較によってみえてくるものは、まごうことなく過去のなにがしかの境界なのであるとするのである。どうにも「古代の生藩即ち所謂荒ぶる神と新に平野に居を占めたる我々の祖先とを隔絶する為に設けたる一の隘勇線」と関係あるのではないかと柳田は続ける。すなわち、平地人としての農耕民と先住異族であるかもしれないような山人たちの境界線、いわゆる「日本人」というものが画定する列島の輪郭を、この音声が時間を超えて残存し、指し示しているのではないかと述べるのである。
柳田の問いの視野はここで、時間的に大きく膨らみ始める。それは、ほとんど日本列島の境界線を時間的に切り始めるかのように、爆発的に名前の謎へと迫っていく。すなわち「隘勇線」という空間的境界線は、シヤグジという時間を超えてやってきた〈言〉によってはじめて提示されていくのである。もはやシヤクジとして看取される音声はただの名ではない。歴史のその先から意味を失わずにやってきた名であり、依然境界として力を有し続けるような「神の名」として立ち現れるのである。
4、変容する読解
一通り山中への質問によって問題が整ったこの段階で、考古学者である和田千吉にもし柳田の仮説が正しかった場合重要になるであろう遺跡について尋ねている[27]。それは「将軍塚」や「十三塚十三本塚十三坊塚」「スクモ塚」などについてである。おそらくこれはもし「隘勇線」というものが存在したならば、その境界に立っていたであろう遺跡群であり、柳田は前述の山中への手紙と同日に興奮を抑えられないかのようにして送っている。
十一月九日に山中から柳田へ応答が返ってくる。山中の答えは、柳田の説はあるいはその通りかもしれないが「小生一向考も無御座候」[28]として若干の驚きとともに受け入れている。そしてサク神の「サ」というものが自分から距離のあるものを指し示す語であることを考えるに、さもありなんと続ける。十一月二三日から柳田は山中と白鳥庫吉に書簡を書き、道祖神や山神、そしてサグジなどを挙げて代表的な民間信仰について教えを乞うというように、問いは問いを呼んでいく[29]。最初はほとんど身の回りにあるような石神についての簡略な問いは、全国に広がる数多の名前の差異のなかで増幅し、ほとんど想像もつかないかのような古代へとさかのぼりはじめていったのである。
三十四通もの手紙のやり取りを通じて、柳田は一番最後の山中への手紙において次のように大きく結論づけている。
塞をソコと申すこと古く日本及韓国にてしかなりしのみならず、支那にても塞、柵共にサクの音有之候にや、稲葉君山氏話に、満州にて故の辺境の地をチヤカ又はチヤハと申し候も、支那の塞の音なるべしとのことにて候、沼垂柵、石船柵などの柵の字、在来の訓はキにて候へども、或はサクにて柵戸はサクノヘかも知れず候、又守公神はソコの神即ち塞神なりしを、ソクジともスクジとも申候より、いつと無く「公を守る」など云う無理なる文字を附会せしものに候はん。…(中略)…サクも亦日本語にて辺境のことなりしを想像すべく、現に信州の佐久郡の如き、上毛の渓谷と高からぬ山脈を隔て、もと湖水ありて土著の早かりし地方と見受け候へば、蝦夷に対立して守りたる境線の義なるべく候。従ってサグジ又はシヤグジも塞神の義にして、之を古代に求むとせば、式の石神とは直接の聯絡無く、却って甲斐などの佐久神と同じ神なるべきか。唯石を祝して神と祀るは相同じく候へば、之を石神と混ずるも亦事実を誤らずと云ふに止るべく候[30]。
柳田は結局のところ、シヤグジが石神であるという説を退け境界の神であるという説を採用した。ある古代において存在したであろうし、今も存在し続けているかもしれない「いくつもの日本」[31] (赤坂憲雄)を見出した。そしてこれはもっぱら〈言〉の集積の名の下に、「神の名」の発見としてやってきたものなのである。
石神とシヤグジの関係性は、柳田の〈物〉と〈言〉の関係性に対応するものということができるだろう。ある物質的な徴である〈物〉としての石はここにおいて、十分条件であれど究極的に付属物でしかありえない。むしろ名において与えられる〈言〉が〈物〉を神へと変形せしめているのである。そしてその〈言〉のひとつの完全な状態である「神の名」は、語彙変化しながらも意味を失うことなく信仰によって力を保持し続ける。〈物〉は柳田においてこうした位置付けにおいて語られるのである。
そのように考えたとき柳田を問う枠組み自体は大きな変容を迫られるだろう。もはや世界は数多の物質的基盤としての〈物〉に〈言〉が与えられるものとしては立ち現れない。むしろ、信仰によって今なお力を発揮し続ける「神の名」が、そうした〈物〉を成り立たせしめているとさえいうことができるのである。そしてこれはある言語を用い、ある観念のなかに生きるならば、〈物〉を〈物〉としか呼称できないし、そうでないように口を開こうとしても〈物〉という言葉に回帰してしまうことに端的に表れているようなあの魔力性を担保するものでもある。そのうえで〈言〉のなかに、結局のところ「神の名」の正体であった、ある普遍の一点たる〈物〉を柳田は探し求めるのである。
もし柳田國男という「名」とともに、その「神の名」の言語がわれわれの均質なはずの言語に散りばめられていたならば、あたかも偽物の金でつくったはずの貨幣に本物の金が紛れ込んでいたかのように、交換そのものの神話は音を立てて崩れてゆくだろう。未だ力を失うことのない〈言〉の発見は、われわれが書き、読み、話す言語をでこぼこの平面へと変えていく。わたしたちは砂金採りのようにして、流れゆく川の浅瀬のなかにそれらを拾い集めることができる。「名をめぐる問い」、この二重写しの思考を柳田からどこまで読み取ることができるのか、それがわたしたちに課せられた読解の「名」のように思われる。
付記、柳田國男という「名」
柳田という「名」によってどうしようもなく捉えられてしまった最初のひとりは、間違いなく柳田國男その人であった。「僕の詩はデイレツタンチズムだつた。僕はもう覚めた。戀歌を作つたツて何になる!その暇があるなら農政學を一頁でも讀む方が好い」[32]。田山花袋の『妻』においてこのように言い切る西少年は、まだ名字が松岡であった柳田をモデルとしているといわれる[33]。松岡國男を模して叫ばれる言葉は、過去の詩を描く少年たる自己から決別し、公に入ることへの重みを文学青年たちに叩きつけるものであった。花袋のスケッチが示すように、一八九九年五月『帝国文学』に二篇の詩を発表したのを最後に、松岡國男は詩作の筆を折ってしまう。一般に「歌のわかれ」として知られるこの文学からの離別は、民俗学者・柳田の原点を語る際に必ず参照されてきた問題であるが、ここにおいて松岡國男が「柳田國男」という名を用いはじめたという、「名」の問題が分かち難くまとわりついていることは指摘しておかなければならないだろう。
一九〇〇年に農商務省に入省が決定すると、松岡國男は大審院判事・柳田直平の養子として入籍し、柳田姓を名乗りはじめる[34]。柳田が柳田國男になるのは「歌のわかれ」と、そして大々的に農政學研究に打ち込んでいくのとほとんど同時期のことであった。柳田にとって「名」の変容は、自らがその後〈物〉に対して〈言〉の優越を主張していくのと並行するかのようにして、柳田自身を蝕んでいったように思われてならない。
松岡國男から柳田國男へ、なんの断絶もないと考えるならば、人は柳田学の奥にひそむ或る微妙なものを見失い、それをまっとうすぎて、いささかよそよそしいものと解するだろう。しかしそこに断絶を見るならば、柳田学を陰翳に富んだ、身近なものとして発見するのである。柳田國男は松岡國男を否定した。そして松岡國男の心にまといついていたすべてのもの、つまり私的にすぎるものや、幼児的なものや、女々しいものや、弱々しいものや、社会に背をそむけがちなものや、暗さや、厭世観といったものを追放した。そして柳田國男の読者は松岡國男を忘れ去る[35]。
岡谷公二によってこのように語られる柳田の改名は、「名」のみが神性を伝えるとする柳田の立場をほとんど完全に反映しているといってよい。「名」が詩人たる松岡國男を侵食していくその苦痛のなかに、柳田民俗学の特異性は回収されていくのである。
柳田の「名をめぐる問い」は連鎖し、言語の上を巡っていき、そうして自らの元へ跳ね返っていく。柳田の改名は、ここにおいてもはやただの改名ではない。「柳田」という大いなる問いかけの場が誕生した瞬間へと、必然的に変容しているのである。「柳田國男」という渦の中心は、柳田という〈物〉の上に張り付けども〈物〉は徹底的に顧みられることはない。〈言〉の探究が柳田がもはや自らのことがわからぬまでに分解してしまっていくというだけではなく、本質を付与するような「名」が柳田本人をも変えてしまったということでもある。そうして、柳田自身をももはやわからなくなってしまっていたであろう、柳田とは何だったのか、という問いは、今日にも繰り返し説かれ続けるのである。それは柳田自身が提出した「名をめぐる問い」の自食作用的帰結だったのではないかと思われてならない。
[1] 代表的なものには、花田清輝「柳田國男について」『近代の超克』講談社文芸文庫、一九五九年や、吉本隆明「共同幻想論」ほか『柳田國男論集成』JICC出版局、一九九〇年。
[2] 代表的なものに、ポスト・コロニアリズムの影響を真っ向に受けてなされた九〇年代の柳田批判が存在する。これには、川村湊、村井紀などによって帝国主義に関与したことを取り沙汰されてなされた批判と、子安宜邦によって行われた国民国家論的に批判するものの二つの潮流が存在する。しかしこれらは赤坂憲雄・柄谷行人らによって反批判がなされている(赤坂憲雄・柄谷行人「柳田國男の現代性」『atプラス18』太田出版、二〇一三年ほか)。
[3] 絓秀実『アナキスト民俗学』筑摩選書、二〇一七年において柳田論争は「総括」されるが、柳田が言語という問題に注力しているのに対し(絓氏は)日本のモノ性を持ち出して柳田批判を支持している。
[4] 「いわゆる言文一致はまだ途上にあって、声の語りにふさわしい文体も生まれてはいなかった。柳田は『聞く』ことよりも、じつは『書く』ことに試行錯誤を重ねなくてはならなかったのだ。その苦心の痕は草稿類のいたるところに見いだされる」(赤坂憲雄「はじめに」『原本遠野物語』岩波書店、二〇二二年、Ⅲ頁)
[5] 柄谷行人『日本近代文学の起源』講談社文芸文庫、一九八八年などにおける柄谷の一連の議論では、風景と主体が分離・構成されていくという均質的言語の発見によってなされた近代論に焦点が当てられ、柳田はそれを成立させる下部構造の発見者として評価される。この論点と同一平面上に存在している問題は、単に柳田が近代的言語観を貫通してしまう言語観を提示していることにある。すなわち、歴史から切り離されて常に特権的であり続けるような「名」を柳田が据えることによって、言語の交換は困難なものとして書き換えられているといってよい。
[6] 代表的なものに、渡勇輝「柳田国男の大正期神道論と神道談話会」『佛教大学大学院紀要文学研究科篇』佛教大学、四九号、二〇二一年、八一―九八頁、および同著者「柳田國男と『平田派』の系譜」『平田篤胤―狂信から共振へ』法蔵館、二〇二三年、二三七―二五九頁。例えば前者における神道私見論争の読み直しにおいて、次のように述べられるのは重要だろう。「柳田の議論は、民間宗教者への視点を閉ざして『常民』へ転向していったのではなく、はじめから『国民』の信仰を明らかにするために、同時代の『国民道徳』論と対峙するべく議論が展開されていたのである。しかもそれは、同時代の学者たちが理想とする近代的な『国民』像とは異なる、別の『国民』像を、近代以前の民間信仰から照射しようとした点で、近代社会そのものを相対化する射程をもっていた」(渡、2021:93)
[7] 田中宣一『名づけの民俗学―地名・人名がどう命名されてきたか』吉川弘文館、二〇一四年、一五頁。
[8] 本居宣長の次の方法論を参照して、柳田の問題系を〈言〉と〈物〉に絞った。「抑意と事と言とは、みな相稱へる物にして、上代は、意も事も言も上代、後代は、意も事も言も後代、漢國は、意も事も言も漢國なるを、書紀は、後代の意をして、上代の事を記し、漢國の言を以、皇國の意を記されたる故に、あひかなはざること多かるを、此記は、いさゝかもさかしらを加へずて、古より云傳たるまに記されたれば、その意も事も言もままに、相稱て皆上代の實なり」(本居宣長「古事記傳一之巻」『本居宣長全集第九巻』筑摩書房、一九六八年、六頁)
[9] 柳田國男「蝸牛考」『柳田國男全集第五巻』筑摩書房、一九九八年、三〇二頁。
[10] 「方言周圏論」とは「中央部としての近畿地方から東西・南北に同じように離れた対象地点には同じような民俗が伝承しているものと予想し、その中央からの距離の相違が新旧を表現しているという考えを支柱にして民俗学の方法を確立した」(福田アジオ「比較研究法」『柳田国男の民俗学』吉川弘文館、一九九二年、七六頁)ものである。
[11] 柳田國男「蝸牛考」『柳田國男全集第五巻』筑摩書房、一九九八年、一九六頁。
[12] 柴田武「方言周圏論」『講座日本の民俗1総論』有精堂、大藤時彦編、一九七八年。
[13] ミルカ・イヴィッチ『言語学の流れ』みすず書房、一九七四年、二九頁。
[14]岩竹(一九九九)においては、フィンランド学派などを経由してこうした方法論が柳田に輸入されていることについて指摘されている。 (岩竹美加子「『重出立証法』・『方言周圏論』再考」『未来』未来社、三九七号、一九九九年)。
[15] ここで一つ注釈を入れるならば、民俗学の哲学的潮流について紹介したい。新体詩におけるロマン主義的潮流の影響を大いに受けた柳田は、〈言〉が全てを照らしていくような言語観を発明した疾風怒濤運動の流れ着いた末裔でもあった(注釈中注釈①)。疾風怒濤運動をゲーテに「吹き込んだ」ヨハン・ゴッドフリード・ヘルダー(Johann Gottfried von Herder)の言語観とは、「言語は単なる悟性の道具以上のものであり、逆に言語こそ『人間の認識全体に限界と輪郭を与えるもの』として、人間の全精神活動を規定する本質要素とみなされている」(注釈中注釈②)ものであり、それまで神学・啓蒙主義の観点から絶えず議論が循環的に繰り広げられてきた言語の問題について、理性即言語という観点を打ち出したものといえる。こうした〈照らし出すもの〉としての言語観は、上古研究・神話学・法制史・言語学を広範に取り扱うヤーコプ・グリム(Jacob Grimm)とヴィルヘルム・グリム(Wilhelm Grimm)によって実証的方法論に整えられてのち、ヴィルヘルム・マンハルト(Wilhelm Mannhardt)による農業儀礼の研究と文献資料の照らし合わせという民俗学的基盤とヴィルヘルム・ハインリヒ・リール(Wilhelm Heinrich Riehl)の国家学提唱を待って、やがて近代科学としての民俗学へと橋渡しされていった(注釈中注釈③)。
注釈中注釈①:島村恭則「民俗学とは何か」『民俗学を生きる―ヴァナキュラー研究への道』晃洋出版、二〇二〇年、八頁において、ヘルダーの対啓蒙主義を受け継ぐものとしての民俗学が示される。
注釈中注釈中注釈①:生きた世界との失われた中間項、すなわち自由という欠陥を乗り越えるために誕生する〈言〉こそ人間の理性そのものであり、人類を発展し続ける世界認識の一環としての「辞書」の持続的形成過程に見出すヘルダー的言語観は、このようにみるならば民俗学の隠れたる主題ともいうことができる。
注釈中注釈中注釈②:柳田がメドチの問題を零落説によって解くが、これはヘルダー的言語観においては価値が反転している。すなわち、偶然的原因などによって語彙変化する言葉そのものを神として記述したのであって、妖怪とは語彙変化した語根の現在的形態である。
注釈中注釈②:J.G.ヘルダー「解説」『言語起源論』法政大学出版局、一九七二年、二三九頁。ヘルダーの民俗学への強力な影響関係は、志村哲也「ヘルダーの『民謡集』と民謡論:最近のヘルダー研究の一側面」『上智大学ドイツ文学論集』上智大学、二〇〇三年などにも詳しい。
注釈中注釈③:河野眞『民俗学のかたち―ドイツ語圏の学史にさぐる』創土社、二〇一四年参照。
[16] 柳田國男「盆過ぎメドチ談」『妖怪談義』角川ソフィア文庫、二〇一四年、一〇八―一一〇頁。
[17] 石井正己「石神問答」『柳田國男全集第一巻』筑摩書房、一九九九年、八〇一頁。
[18] 後藤総一郎「柳田学前史の意義」『柳田学前史』岩田書院、二〇〇〇年、一六―一七頁。
[19] 柳田國男「石神問答」『柳田國男全集第一巻』筑摩書房、一九九九年、五〇四頁。
[20] 前掲書、五〇七―五〇八頁。
[21] 前掲書、五〇九頁。
[22] 前掲書、五〇九―五一〇頁。
[23] 前掲書、五一一頁。
[24] 前掲書、五一二頁。
[25] 前掲書、五一五頁。
[26] 前掲書、五一六頁。
[27] 「柳田の『石神問答』における考古学の位置づけは、考古学という学問そのものの体系をふまえたものではなく、あくまでも民俗的な小祠の信仰や石造物、自然石によせる信仰の歴史的展開を考えようとする際の、いくつかの視点のひとつであっただろう」(小池淳一「柳田民俗学の形成と考古研究」『国立歴史民俗博物館研究報告』国立歴史民俗博物館、二〇一七年、二一五頁)
[28] 柳田國男「石神問答」『柳田國男全集第一巻』筑摩書房、一九九九年、五二一頁。
[29] この頃の柳田と白鳥の関係は「再刊序」に次のようにある。「この一巻の書の成った頃には、私は市谷で白鳥先生の隣の町に住んで居た。家がポストの距離よりも近かつた故に、自分で手紙を持参して懇ろな批判を受けたことを覚えている」(柳田國男「再刊序」『柳田國男全集第一巻』筑摩書房、一九九九年、六二七頁)
[30] 柳田國男「石神問答」『柳田國男全集第一巻』筑摩書房、一九九九年、六〇〇頁。
[31] 赤坂憲雄『一国民俗学を越えて』五柳書院、二〇〇二年、九―五〇頁。
[32] 田山花袋『田山花袋全集』一巻、文泉堂書店、一九七三年、二九三頁。
[33] 岡谷公二『殺された詩人―柳田國男の恋と学問』新潮社、一九九六年。
[34] 鶴見太郎『柳田國男』ミネルヴァ書房、二〇一九、六二頁。
[35] 岡谷公二『柳田國男の恋』平凡社、二〇一二年、七二頁。なお、ここには柳田の秘された恋人たる伊勢屋の娘・よね子が夭折したことが指摘されている。
人文書院関連書籍
その他関連書籍
執筆者プロフィール
石橋直樹(いしばし・なおき)2001年神奈川県生。民俗学・批評・現代詩などについて。論考「ザシキワラシ考」で2020年度佐々木喜善賞奨励賞を受賞、および論考「〈残存〉の彼方へ―折口信夫の『あたゐずむ』から―」で第29回三田文學新人賞評論部門を受賞。その他、論考「『二重写し』と創造への問い―『君たちはどう生きるか』の引用の思考」(『現代思想』10月臨時増刊号所収)、論考「看取され逃れ去る『神代』―平田篤胤の世界記述を読む」(『現代思想』12月臨時増刊号所収)など。X(旧Twitter):@1484_naoki
次回は1月後半更新予定です。
岡田基生さんが西田幾多郎と三木清を論じます。
*バナーデザイン 太田陽博(GACCOH)
*編集部:文中の誤記を修正いたしました。お詫びして訂正いたします(1月15日)
・第1章 子安宣武→子安宣邦
・第2章 「ほとんど徹底的した独自性は」→「ほとんど徹底した独自性は」
・注1 講談社学芸文庫→講談社文芸文庫
・注8 「…その意も事も言も相稱で」→「…言もままに、相稱て」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
