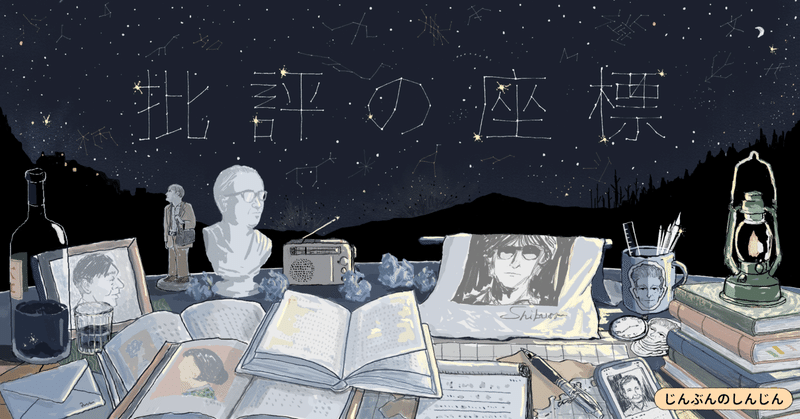
【批評の座標 第19回】「戦場」から「遊び場」へ――西田幾多郎と三木清の関係性を手がかりに「批評」の論争的性格を問い直す(岡田基生)
独自の哲学体系を創出し「京都学派」と呼ばれる思想の系譜を生み出した西田幾多郎と、西田の『善の研究』に影響を受けながらも時事的な評論及び実践へと次第に開かれていった三木清。二人の関係性から、哲学と批評の緊張関係や「遊び」としての批評のあり方を論じます。執筆者は、宮沢賢治をはじめとして、哲学や文学を批評のフィールドで論じながら、蔦屋書店コンシェルジュとして人文系の学問を社会に開くことを実践している書店員・岡田基生です。
――批評の地勢図を引き直す
「戦場」から「遊び場」へ
――西田幾多郎と三木清の関係性を手がかりに
「批評」の論争的性格を問い直す
岡田基生
1. 「論争」が「戦争」に変わらないために
「批評」という営みが、批評の対象(言論、作品、活動など)の問題点を指摘する、という側面を含んでいる以上、それは論争的性格を離れることができない。この性格をどう捉えるのか。それが問題である。問題点を指摘することは、直ちに対象のすべてを否定することではない。しかし、しばしば論争という構えを取ると、問題点を指摘する以上のところにまで足を踏み入れてしまうことがある。そうなると、相手を叩き潰すこと、その価値を全面的に否定することにまで進んでしまうことも少なくない。「論争」は「戦争」になってしまうのである。このように批評の論争的性格を問い直すのは、国と国の間であれ、人と人の間であれ、分断を感じることが少なくないからである[1]。
どうすれば、批評が生み出す「論争」が「戦争」になることを避けることができるか。私は、自らの思想的な参照軸である西田幾多郎(1870-1945)と三木清(1897-1945)に立ち返りながら探究している。当初、私は大学の哲学科で西田を研究していたが、大学院の博士前期課程で、その弟子の三木に研究対象を変更した。それは、理論の領域で根本的な立場を追求する西田の哲学に対する姿勢に限界を感じ、理論と実践の往復を重視し、批評家として活動する三木の姿勢に可能性を感じたからである。三木は西田とは大きく異なる哲学に対するスタンスを取ったが、西田と継続的に向き合うことを通して、独自の発展を遂げることができた。
私は、西田と三木の関係性の中に、「論争」が「戦争」になることを避ける手がかりがあるのではないかと考えている。
2. 哲学に対する西田幾多郎の姿勢
西田と三木は、哲学についてどのような点で対立していたのか。まずは、西田の哲学に対する姿勢を理解する必要がある。
小林秀雄が「学者と官僚」(1939)の中で、西田の文章を「日本語では書かれて居らず、勿論外国語でも書かれてはゐないといふ奇怪なシステム」と評したことは広く知られている[2]。このように評された文章の特徴は、哲学に対する西田の姿勢に由来している。ようやく自らの「根本的思想」を明らかにしたと感じた時点で書かれた『哲学論文集第三』(1939)の序では、西田は下記のように自らの哲学の目的を語っている。
私はいつも同じ問題を繰返し論じて居ると云はれるが、「善の研究」以来、私の目的は、何処までも、直接な、最も根本的な立場から物を見、物を考へようと云ふにあつた。すべてがそこからそこへといふ立場を把握するにあつた。[3]
西田の哲学の目的は、根本的なリアリティを徹底的に明らかにすることである。彼は、欧米の哲学や宗教の考え方を理解するとともに、禅の修行を行うなど、東アジアに継承されてきた精神的伝統を深く体得することを目指しながら、自らの思想を形成していった。それらの思想の対立を、自らの内に引き受けながら、それらの思想が、私たちが生きている現実のどういう面を捉えたものなのかを、整合的に位置づけることができるような立場を見出すことが、西田の課題であった。そのような立場に至るには、さまざまな立場をコラージュ的に折衷することではなく、無批判に前提されているものを乗り越えていく必要がある。
そのような志向をもつ西田の思索という場では、従来のドイツ語や英語で書かれる思考のスタイルも、従来の日本語で書かれる思考のスタイルも解体されることになる。西田の思索から生まれた現実把握のシステムが、既存の思想的伝統を前提とする立場から見て「奇怪」に見えることは自然なことである。西田もそのことを自覚した上で、自分の思索が理解されることよりも、さらに根本的な立場に至ることを追求していたと言える。そのような優先順位は、彼の理論と実践に対する姿勢に基づいている。
彼はその最初の著作『善の研究』(1911)の「考究の出立点」をめぐる章の中で「我々は何を為すべきか、何処に安心すべきかの問題を論ずる前に、先ず天地人生の真相は如何なる者であるか、真の実在とは如何なる者なるかを明にせねばならぬ[4]」と述べている。つまり、理論と実践の間には順序があり、まず理論に取り組み、その後に実践を考えるべきだというのである。
このような理論と実践に対する態度は、晩年に至るまで続いており、先に言及した『哲学論文集第三』(1939)でも西田は、理論的な問題の探究にまず取り組むことの重要性を強調している。西田が、この論文集の後に『日本文化の問題』(1940)や「世界新秩序の原理」(1943)などでの時局に対する発言という実践へと踏み出した[5]のも、『哲学論文集第三』で自らの「根本的思想」を明らかにしたという実感を持てたからである。西田は、実践的な問題に取り組む前に、まず理論的な問題に取り組むという順序を重んじ、実際にその順序に従ったのである。
だが、西田自身、例えば『哲学論文集第五』の「知識の客観性について」(1944)の中で「哲学は我々の自己が真に生きんとするより始まる。我々の自己の自覚の仕方であり、生き方である。対象的学問と異なつて、民族や個人の体験が基礎となると思ふ」[6]と語っているように、哲学が単なる理論的な営みではなく、生きるという営みから生まれるものであることを認めている。生きるとは、特定の目的をもって行為することであり、理論もまたそのような行為の一種にすぎない。西田の思索も日本の近代化という時代状況の中で生まれたものである[7]。そのように考えるとき、理論が先、実践が後という順序は実情に即しておらず、そもそもそのような順序で哲学を行う必要があるのかという問いが湧いてくる。
3. 哲学に対する三木清の姿勢
この問いは、私が大学院の博士前期課程に入った頃に抱いていたものである。これは、私が西田の著作を読み解くなかで生まれたものであるとともに、東日本大震災や、大学の中で「哲学対話」をはじめ、哲学を社会に関わらせる新たな試みが盛んになってきたことなど、時代からの影響を受けて生まれたものである。実践と関わりながら遂行される哲学は可能なのか。そのような問題意識が深まったとき、自ずと理論と実践を等しく重視する三木の姿勢に惹かれるようになった。
三木は、理論と実践を行き来することを重視しながら哲学を行った。その考え方は、マルクス主義の影響下で形成された。三木が西田から距離を取り、マルクス主義に接近していた時期の論文である「ヘーゲルとマルクス」(1928)では、以下のように論じられている。
理論と実践との弁証法的統一の上に立つ哲学のみが真に具体的なる哲学である。未来への展望を含むか否かが学問の現実性の基準である。我々はこのことをマルクス主義から学ばねばならぬ。[8]
「理論と実践との弁証法的統一」とは、理論と実践が、一面においてそれぞれ独立性を有するとともに、他面において、互いが互いの前提となるという事態のことである。理論は価値判断から自由に、実践的な目的や応用と無関係に求められる知識であり、理論の目的は概念、原理、法則のような一般的なものである。それに対して、実践は価値、理想、規範にかかわるものであり、つねに特殊的なものに関係する。しかし、このように対立する両者が「実践は理論を要求し、理論は実践によつて発展する」[9]という相互依存的な関係にある。それは、そもそも理論は単に純粋にそれ自身のために求められるのでなく、むしろ実践的な課題の中から生まれ、そのようにして生まれた理論の真理性は実験の成功や産業の発達によって確かめられる、ということである。このように理論と実践の間に往復関係を認め、「未来への展望」を重視する点で、三木は西田と大きく異なっている。
三木は、1930年に治安維持法で逮捕された後、マルクス主義から「転向」した。そして、大学を追われ、在野の知識人となった。そのことにも後押しされて、文芸、思想、政治などの観点から時代を批評するという仕事に取り組むことになる。彼は、自らが遂行していた批評という営みをどのように理解していたのだろうか。
三木は『改造』に発表した「批評の生理と病理」(1932)において「批評の根本的な機能」を論じている。それは「人間の精神をその自然的傾向に属する自働性に対して防御すること」だという。そして、「批評の精神は或る意味では懐疑のこころである、懐疑のこころは相対性の感覚である」と語った。つまり、他人の考えに対してだけでなく、自分自身の考えに対しても、それを相対化して検討することが批評の機能だというのである。
その上で批評と実践の関係について下記のように語っている。
好き批評家は身体をもてる精神でなければならない。しかるに批評家が真に身体をもつとき彼は批評家以上のものとなる、彼は実践的指導者となり、或ひは文化の諸領域における創作家、創造者となるであらう。しかしまた他の方面から見ると、批評の精神なくして指導者も創作家もないであらう。[10]
ここでいう「身体」というのは、価値判断の基礎となるスタンスやスタイルのことだろう。それらがなければ、何かを評価することはできない。しかし特定のスタンスで現実に働きかけるという方向を徹底すると、その人はもはや単なる批評家ではなくなり、実践を導く者や自ら創作する者になるという。だが、そうなったとしても批評が不要なわけではない。その実践を盲目的なものにしないためには、自分の立場を相対化して検討すること、また他者から批評を受けることが必要になる。それゆえに、実践にもまた「批評の精神」が必要である。実践しながら、自分の実践を相対化する、そんなアクロバティックな行為が、指導者や創作家にとっての批評なのである。その上で、三木は、指導者や創作者とならない批評家の役割も認めており、それを「啓蒙家」と捉えている。ここでいう「啓蒙」とは「古いイデオロギーに対する新しいイデオロギーの宣伝及び普及」を意味している。三木は、批評家がもつ実践的関心を重視しているのである。彼は、批評と実践の関係を重視し、二つの極として、批評の精神をもつ実践家と、実践的関心をもつ批評家を考えていたと整理することもできる。
このような批評と実践の理解にもとづいて、三木自身は、どちらかと言えば、批評の精神を備えた実践的指導者になることを目指していたようだ。彼は『夕刊大阪新聞』に掲載された「哲学と教育」(1937)において、哲学者を「教育者」として捉える哲学観を提示している。
哲学者は責任を負はない観想者でなく、世界を動かす者、世界を形成する者でなければならない。かかるものとして哲学者は教育者でなければならない。[11]
ここでいう「教育」は、「世界を、社会を、人間を形成する」という意味で理解されている。当時、彼が行っていた「教育」は、まずこの文章が新聞に掲載されているように、言論によって世の中に働きかけることである。また、彼は、岩波文庫の設立に関わるなど、言論のプラットフォームをつくることにもかかわっていた。他にも、三木は、近衛文麿のブレーントラストである昭和研究会で政策決定に関わろうとしたり、理化学研究所が母体となった新興財閥・理研コンツェルンの刊行する雑誌『科学主義工業』を通して産業界に対して将来の技術に関する提言を行ったりしている。
4. 西田幾多郎と三木清の関係性
先に引用した「哲学者は責任を負はない観想者でなく、世界を動かす者、世界を形成する者でなければならない」という一文には、「観想者」、つまり理論的認識にとどまっている哲学者に対する論争的な姿勢が込められている。この箇所に、三木による西田批判を読み込むこともできるだろう[12]。
これは1937年の時点であり、1939年に『哲学論文集第三』を出した後、当時の政治や文化状況について西田が積極的に発言するようになった背景には、西田自身が実践の段階に移行したという側面だけではなく、このような三木の要求に対する応答という側面もあると考えられる[13]。それ以前にも、西田が『無の自覚的限定』(1932)以降、マルクス主義への応答を行うことによって、自らの哲学を形成していった背景には、三木をはじめとするマルクス主義に傾斜した世代からの影響がある。西田から三木への影響があるだけではなく、三木から西田への影響があるのである。
西田と三木の関係を考える上で、さらに興味深いことは、1930年代後半以降、西田とは明確に区別される哲学観にもとづく活動をしている三木が、理論的には、西田に接近していることである。これは、三木が実践の見地に立ち、新たな社会を構想するために、自分自身も含めて当時の人々の思考の前提となっている世界観や人間観を問わざるを得なかったからだと考えられる[14]。
三木が西田に反発しつつも西田に接近したのは、西田の弟子への態度に由来する部分もある。西田の門下からは、欧米の哲学者の研究という域を超えて、独自の哲学を構築する哲学者が多く育ったことの要因の一つもその態度にあるのだろう。三木は「西田先生のことども」(1941)で以下のように綴っている。
弟子たちの研究に対しては、先生はめいめいの自由に任されて、干渉されることがない。その点、無頓着に見えるほど寛大で、一つの型にはめようとするが如きことはせられなかつた。先生は各人が自分の個性を伸ばしてゆくことを望まれて、徒に先生の真似をするが如きことは却つて苦々しく感じられたであろう。こんなことをやつてみたいと先生に話すと、先生はいつでも「それは面白かろう」といって、それに関連していろいろ先生の考えを述べて下さる[15]。
ここに見られるのは、弟子たちを自由に遊ばせ、弟子たちが望む方向に進むのを、師としてサポートするという姿勢である。ここには、意見の対立や論争を潰し合いにしないヒントが見られる。
西田と三木の関係性[16]を手がかりにしつつ、批評の論争的性格が戦争のようなものにならないようにするにはどうすればよいか、という私が最初に提示した問いに答えよう。それは、異質な立場の者同士がぶつかり合う場を、「戦場」ではなく「遊び場」とすることである。試みにボードゲームというメタファーで説明しよう。ボードゲームには、対戦型ゲームと、協力型ゲームがある。対戦型ゲームは参加者同士で勝ち負けを競うものであり、協力型ゲームでは参加者同士が同じ目標を共有し、それを達成することに挑戦するものである。いずれにせよ、それは遊びであり、対戦する場合でも相手を叩き潰すことは目指されない。あくまで対戦するという役割を演じているだけである。批評も、論争という対戦型ゲームのような要素と、相手から影響を受けたり相手に助言したりという協力型ゲームのような要素がある。
遊びは不真面目なもので、余裕があるときにしかできないものとも思われる。しかしそれは、遊びと仕事を区別する場合の話である。仕事を遊びとして捉えるとき、遊びはもはや不真面目なものではない。真剣に全力を出し切るものである。それによって、楽しさと相手へのリスペクトが生まれる。批評が現実の改善を目指す仕事と区別された遊びとなるならば、それは真剣さを失った馴れ合いとなる。
ゲームは、「特定のルールに従って行われる遊び」であり、遊びの一形態だが、遊び自体は、ゲームという在り方に限定されない。三木が西田に対して、時に論争的になり、時に接近したように、遊びはゲームのルールを書き換えることもできる。遊びにとって、ルールは仮のものであり、ルールに従うことがゲームの条件であるとともに、遊び自身はそれに縛られない。批評は、特定のルールに従うゲームの中で真剣にプレイしつつ、それを相対化するという、アクロバティックな行為である。それを遊びとして遂行するとき、その営みは真剣であることによって楽しいものとなり、また自分の思想的立場は役割となり、思想的立場への執着から解放される。
このような遊びは、一人ではできない。自分は自分自身を相対化できない。自己を相対化することは、同時代の立場の異なる人、さらには過去の人々と格闘することによって可能となる[17]。そのように他者とともに遊ぶ場である批評の空間は、単に何でもできる場所ではない。最初に勝利条件や禁止行為を合意しないと、トランプゲームやスポーツの試合を楽しめないように、他者とともに遊ぶためには、さまざまな権力関係を考慮しながら、場のルールを合意していく必要がある。
5. 哲学と経営が交わる遊び場
西田と三木の関係性を分析することから、「批評を遊びとして遂行する」という着想が得ることができる。私はこの着想にもとづき、また、西田や三木の著作を参照しながら、哲学と経営を結びつける探究を行っている。
私は、博士前期課程の時、批評の精神を備えた実践を重視する三木の研究をする中で、アカデミアで研究することよりも、社会の中で哲学を活用する道を模索したいと思い、修士論文を出した後、IT企業に就職した。その後、三木が新しい文化の構想を目指したことも意識しながら、新しい文化のインフラをつくっていくことを目指す企業に入社し、「生活提案型書店」という場で働いている。雑貨やアパレルのフェアを企画したり、ビジネスジャンルの書籍の担当として書籍の紹介やトークイベントの企画を行ったり、といった仕事を行う中で、私は哲学と経営が交わる領域である「世界観」という観念の形態に関心を持つようになった。
「世界観」という語は、今日のビジネスの中でブランドのコンセプトや雰囲気、組織の風土や文化といった意味合いでカジュアルに使用されることが多いが、もともとは哲学用語である。この概念を活用している三木の定義を参照すれば、それは「世界の全体及びそのうちに於ける人間の位置に就いて或る人間もしくは人間の集団が有する観念、見解」[18]である。つまり、特定の個人、または特定の集団が、世界全体をどのようなものとして、また、その世界の中で自分たちをどのような存在として捉えているか、ということである。世界観は、自然観や人間観、社会観などさまざまな物の見方(イメージや信念などを含む)が網の目のように結びつくことによって構成されている。私たちは多くの場合、自分がどんな世界観を通して物を見ているか、自覚していない。
私は、特に「組織の世界観」に注目し、働いている人たちが自らの組織の世界観を自覚し、発展させたり、改定したりするための理論と方法を探っている。私が組織の世界観に注目しているのは、企業が社会課題を解決する主体となりつつあるからである。かつて企業の社会貢献は、企業の目的は利潤追求だという前提にもとづいて、「フィランソロピー」や「メセナ」のように利益の一部を社会に還元するものが主だった。しかし今日では「ESG投資」や「パーパス経営」の考え方のように、企業の経済活動自体を社会貢献的なものに変えていく流れが広がりつつある。自社のサービスによってどんな社会課題を解決できるかが問われる時代に変わりつつあるのである。「何を目指すか」を決める上で(しばしば無自覚な)前提となるのは、「世界をどのようなものとして観ているか」である[19]。
また、世界観を自覚し、発展させることは、文化の多様性を高めることにつながる。それも、私が組織の世界観に注目する理由である。一つの立体を見るためのさまざまな視点があるように、世界という複雑な構造体を捉える世界観は多数存在しうる。国内外のさまざまな地域の食文化が共存し、影響を与え合うことによって、私たちの食文化が豊かになっているように、多数の世界観が共存し、影響を及ぼし合うことによって、さまざまな視点にもとづくサービスやプロダクトが生まれるだろう[20]。
私は組織の世界観に関する探究を進めるため、経営者やコンサルタントなど実地経験のあるメンバーと研究会を行っている。その研究会では、哲学の理論と、組織の世界観に関するケーススタディを行き来しつつ、組織の世界観に関する理論と、それを自覚して改定する方法の構築を目指している[21]。このような探究の場は、哲学と経営という異質なものが、ぶつかり合いつつ、協力し合う遊び場となっている。
6. 世界観が自覚される遊び場
実践には批評の精神が必要である。そのため、集団の世界観が自覚されることをポジティブに捉えて、その可能性を探る私自身の実践にも、批評の目を向けてみよう。集団の世界観を自覚することによって、どのような問題が生じる可能性があるだろうか。集団の内部に対しては、同じ世界観を持つように強要すること、集団の外部に対しては、別の世界観を持つ人たちを排除したり、同じ世界観を持つように強要したりすることが起こりうるだろう。これは世界観に限らず、価値観にせよ、ルールにせよ、「共有をめぐる暴力」に妥当することである。共有される観念のなかで、世界観が持っている特色は、それが知情意、真善美のすべての側面が結びついたものとして、人間の知性にも美意識にも道徳性にも強く働きかける傾向があることである。
世界観の共有をめぐる暴力の典型例は、異なる世界観をもつユダヤ人に対するホロコーストを行ったナチス・ドイツである。アドルフ・ヒトラー(1889-1945)の『わが闘争』(1925-1927)の中でも「民族主義的世界観」という表現が活用されている[22]。では、どうすれば、世界観の共有が強要や排除という戦争的な態度と結びつかないようにすることができるだろうか。世界観が自覚される場を、遊び場とすることが必要である。それを具体的に考えるために、西田の個人(「個物」と表現される)に対する考え方がヒントとなる。
全体的一に属しては、我々は唯動くといふことがあるだけである。孤立的な個物としては、我々は唯思ふと云ふことがあるだけである。Bxのbxとしての我々がMxのmxとして、我々は真に個物的に働くと云ひ得るのである。[23]
ここでいう「全体的一」とは特定の社会的集団のことであり。私たちが、その中の単なる一員として、その集団内の仕組みやルールに従っているだけでは、「唯動く」というだけで自由はない。しかし、そういった仕組みやルールを無視して「孤立した個物」として遊離していても「唯思ふ」だけで現実を動かすことはできない。「Bxのbx」というのは西田が世界の構造を図式で説明する記号による表記で、特定の社会的集団の一員を表している。それに対して、「Mxのmx」というのは、「創造的世界の創造的要素」や「世界的個物」とも言い換えられるもので、さまざまな集団を越えた場である世界の一員としての私たち一人ひとりのことである[24]。これは、集団に反抗するだけの単なる個人でもなく、また単なる集団の一員でもない。それは、集団の中で活動しつつ、集団を越えた立場から、集団の仕組みやルールを変えることができる在り方のことである。社会の仕組みやルールを改定できる個の働きによって、社会の仕組みやルールは出来上がっていくのである。
このような西田の考え方をヒントに、世界観を自覚する方法について考えてみよう。世界観も、集団が共有している仕組みの一種である。「世界的個物」としての私たちのもつ世界観は、集団の世界観の影響を受けながら形成されるが、私たちは、それぞれ独自の経験を持ち、複数の集団に属することも、集団を移動することもできる。また一つの集団に属しながらも、別の世界観に触れることができる。したがって、私たちの世界観は、自らが属する集団の世界観と部分的にしか重ならないものである。また、集団の世界観は、多様な個人の世界観が照らし合う関係の網の中で形成されていくものである。
このような構造にヒントを得ながら、「共有の暴力」に陥らない企業の世界観の自覚の仕方を実現することもできるだろう。例えば、それぞれのメンバーが自分の属する組織の世界観として感じているものを語り合う場として、時にぶつかり合ったり、時に化学反応が起こったりするワークショップを実施することができる。。そこでは、私たちの世界観はこういうものだ、という全員で共有できる文章のような統一見解を作ることを目標にしないことが重要だろう。そこで浮かび上がるものは、それぞれのメンバーの捉え方が絡み合っている複雑な構造体であり、その中には相対立する見方も含まれている。むしろ、目標にすべきことは、そのような自覚から、日々の業務の捉え方が変わったり、新たなアイデアが生まれたりすることである。
私は、ここまで、批評における論争的側面を、対戦型の遊びとして遂行することによって、異なる思想的立場を持つ人たちが関係しあう場を「遊び場」へと変えていくことを提案してきた。そのような場で働く「遊びの精神」は、ゲームに熱中するだけのものではない。それは、自分がプレイするゲームのルールを問い直し、場の仕組みを協議していく力を持っている。
[1] 争いは、利害の対立と思想の対立のどちらか、あるいはその両方から生まれる。例えば、同じマーケットで利益追求を目指している企業同士が争うという場合、思想は同じだが、利害が対立していると言える。それに対して、現時点で主流となっている価値観を肯定する人と、それを問題視し新たな価値観を提示する人の間には、思想の対立がある。もちろん利害の対立も重要な論点だが、論争が関わるのは思想の対立であるため、今回はその点に焦点を当てる。
[2] 『小林秀雄全集』第6巻、新潮社、2001年、560頁。
[3] 『西田幾多郎全集』第9巻、岩波書店、1965年、3頁。
[4] 『西田幾多郎全集』第1巻、岩波書店、1965年、46頁。
[5] これらの実践の問題点については、注17を参照。
[6] 『西田幾多郎全集』第10巻、岩波書店、1965年、472頁。
[7] 例えば、その思索の前提に、どのように日本の近代化を進めるかを考えるための基盤をつくる、といった実践的な意図を読み取ることもできる。
[8] 『三木清全集』第3巻、岩波書店、1966年、156頁。
[9] 『三木清全集』第12巻、岩波書店、1967年、390頁。
[10] 『三木清全集』第12巻、岩波書店、1967年、112頁。
[11] 『三木清全集』第13巻、岩波書店、1967年、428頁。
[12] この推測の根拠となる箇所を挙げておこう。「西田哲学の性格について」(1936)の中で、三木は西田哲学に不足しているものをどのように補えばよいかを論じながら、「西田哲学はいはば円の如きものであつて、この円を一定の角度に於て分析することが必要ではないかと思ふ。その角度を与へるものは永遠の意味に於ける現在でなく、時間的な現在、従つてまた未来の見地である」(『三木清全集』第10巻、岩波書店、1967年、433頁)と語っている。西田は、私たちが生きている一瞬一瞬の現在が、時間上の一点であると同時に、過去も未来もそのうちに包み込む場としての側面を持っていると捉えていた。現在は一瞬に過ぎるものであると同時に、一瞬一瞬が永遠という側面を持つのである。「永遠の意味に於ける現在」とは後者の側面を表すものである。三木がいう「時間的な現在」とは時間上の一点であるという前者の側面を表すものである。「時間的な現在、従つてまた未来の見地」という表現で三木が示しているのは、今自分たちが生きているこの具体的な状況をどう捉えるか、さらにどのような未来への展望を開くか、という切り口から西田哲学を分析する必要がある、ということである。つまり、三木は、西田に対して、今という時代の認識、そして現状を変えるための未来への展望を開くことを要求しているのである。
[13] この推測の根拠として、1930年代、三木が西田を頻繁に訪問していることや、何度も座談会や対談を行っていることが挙げられる。『日本文化の問題』(1940)における19世紀は「帝国主義的人間形態」の時代だったが、これからは「創造的人間の形態」の時代であるという議論に、三木が1930年代前半に発表していた「人間タイプ」に関する理論との類似性が見られるなど、西田は、具体的な主張の内容に関しても、三木の問題意識を下敷きにしている可能性がある。
[14] 例えば『構想力の論理』の「序」(1939)での中で、「私は私自身のいはば人間的な問題から出発しながら、現在到達した点において西田哲学へ、私の理解する限りにおいては、接近してきたのを見る。私の研究において西田哲学が絶えず無意識的に或は意識的に私を導いてきたのである」(『三木清全集』第8巻、岩波書店、1967年、6頁)と語っている。「私自身のいはば人間的な問題」というのは「客観的なものと主観的なもの、合理的なものと非合理的なもの、知的なものと感情的なものを如何にして結合し得るかといふ問題」に憑りつかれていたことを指している。これは一見単に理論的な問いにも見えるが、「新しいゲマインシャフト的文化」を生み出すという実践的な課題とも結びついている。これは、三木が次の文化の方向として構想しているものである。近代以前は、主観的なもの、非合理的なもの、感情的なものが優位のゲマインシャフト(「共同社会」、あるいは「基礎社会」と訳される)的な文化であったのに対し、客観的なもの、合理的なもの、知的なものが優位の近代のゲゼルシャフト(「利益社会」、あるいは「派生社会」と訳される)的文化が支配的となった。この二つの側面の間で揺れ動き、両者が両立する生き方や、社会の在り方を求める三木の実践的な問題意識から出発した探究が、西田が理論的な問題意識を突き詰めることによって到達したものの影響を受けながら進展しているのである。
[15] 『三木清全集』第17巻、岩波書店、1968年、300-301頁。
[16] 三木は、没年の1945年の1月20日の坂田徳男宛の書簡の中で「ともかく西田哲学と根本的に対質するのでなければ将来の日本の新しい哲学は生れてくることができないやうに思はれます」(『三木清全集』第19巻、岩波書店、1968年、453頁)と述べており、最晩年には再び西田哲学から距離を取ろうとしていたことが見受けられる。三木は西田に敬意を払いつつも、西田に対しても、西田に惹かれる自己自身に対しても距離を取ろうとしていたのだろう。
[17] このように批評や実践を遊びとして行うことを提案することは、西田の実践の問題点を乗り越えることにもつながる。弟子たちに対してすぐれた遊び場を提供することができた西田だが、彼の政治的発言に関しては、太平洋戦争の推進に加担したという批判がなされている。まず前提として、西田は反帝国主義、反全体主義の立場を主張しており、「万世一系の我国体」や「八紘為宇」など、当時使用されていたスローガンを、反帝国主義的、反全体主義的な意味で書き換えることで、軍部の暴走を抑えようとしている。例えば、「世界新秩序の原理」では「英米的思想の排撃すべきは、自己優越感を以て東亜を植民地視するその帝国主義にあるのでなければならない。又国内思想指導の方針としては、較もすれば党派的に陥る全体主義ではなくして、何処までも公明正大なる君民一体、万民翼賛の皇道でなければならない」『西田幾多郎全集』第12巻、岩波書店、1966年、431頁)という。こういった発言は、三木や戸坂が治安維持法で逮捕されて獄死したように、強力な思想統制が行われていた時期のものであることを前提に考えるべきだが、結局のところ、戦争の推進にお墨付きを与えてしまうという逆効果を招いたと言わざるを得ない。このような発言に関して、西田の意図はよかったが、選んだ方法に問題があったと考えることもできなくはない。しかし、彼が自らの置かれた状況や自分の文化的アイデンティティを十分に相対化できていたのかは疑問である。そのような相対化を可能にするのが、遊びの場における他の立場の人との格闘と協力のプロセスなのである。
[18] 『三木清全集』第12巻、岩波書店、1967年、344頁。
[19] 例えば、自然を人間が自由に使える素材と捉える自然観から、人間自身もそのエコシステムの中に含まれており、他のものとの関係を考慮しながら振舞う必要があると捉える自然観に移行することで、何かをゴミとして捨てるのではなく、すべてを再活用する道を探るという目的意識が生まれてくる。
[20] このような私の探究は、三木が目指した新しい世界観をつくるという課題を継承している。「世界観構成の理論」(1933)という論文の中で、三木はドイツの哲学者ヴィルヘルム・ディルタイ(1833-1911)の世界観学が単に「観想的」で「実践的見地」を含んでいないことを批判しつつ、今日の問題は「世界観定立 Weltanschauungssetzung」であると述べている。つまり、新たな時代の基盤となる世界観を成立させることを目指すという実践的な姿勢を打ち出しているのである。
[21] その際、哲学と経営を結ぶモデルケースとして、例えば、前川製作所で西田哲学にヒントを得ながら実践の中で独自に発展した「場所的経営」や、現象学との対話の中で発展した野中郁次郎氏の「ナレッジ・マネジメント」の理論などを参照している。
[22] 例えば「民族主義的世界観は決して人類の平等を信じないばかりか、かえって人類の価値に優劣があることを認め、そしてこうした認識から、この宇宙を支配している永遠の意志にしたがって、優者、強者の勝利を推進し、劣者や弱者の従属を要求するのが義務である、と感ずるのである」(アドルフ・ヒトラー『わが闘争 下』、平野一郎、将積茂訳、KADOKAWA、2001年、22頁)。
[23] 『西田幾多郎全集』第10巻、岩波書店、1965年、329頁。
[24] なお、西田は、集合を「M」のように大文字で表し、その中の要素を小文字で表すという表記法を用いており、それぞれの集合での個は「m」のように小文字の記号で表している。これらの記号は、ドイツ語の単語に由来していると考えられる。「b」は「besonder(特殊的)」、「m」は「Medium(媒介者)」の頭文字であろう。なお「Bx」や「Mx」の「x」は集合のバリエーションを表している。例えば「Bx」はさまざまな社会のバリエーションのうちの一つの社会、「Mx」は過去現在未来の世界のバリエーションの中のうちの、ある時点の世界を表している。
人文書院関連書籍
その他関連図書
執筆者プロフィール
岡田基生(おかだ・もとき)1992年生まれ、神奈川県出身。修士(哲学)。上智大学文学部哲学科卒、同大学院哲学研究科博士前期課程修了。IT企業を経て、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社に入社。代官山 蔦屋書店で人文コンシェルジュとして活動。連載に『「ほんとうのさいわい」につながる仕事――宮沢賢治に学ぶワークスタイル」』(図書出版ヘウレーカ)、『READ FOR WORK & STYLE』(FINDERS)。寄稿に「イーハトーヴ――未完のプロジェクト」『アンソロジスト vol.5』(田畑書店)など。
次回は2月前半更新予定です。松本航佑さんが江藤淳を論じます。
*バナーデザイン 太田陽博(GACCOH)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
