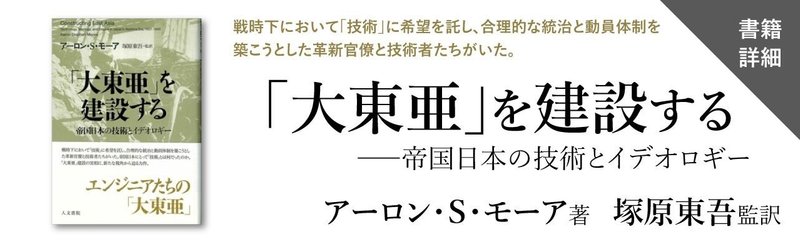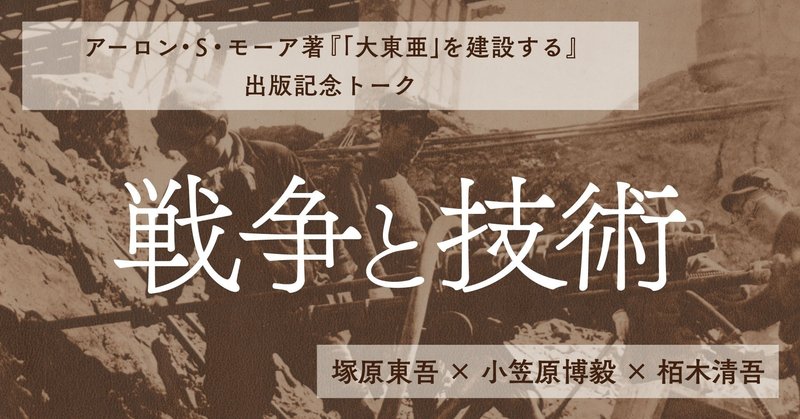
【トーク】「戦争と技術」塚原東吾×小笠原博毅×栢木清吾〈前編〉
ュンク堂書店難波店にて開催した、アーロン・S・モーア著『「大東亜」を建設する――帝国日本の技術とイデオロギー』(人文書院)の刊行記念トークの記録です。登壇者は監訳者の塚原東吾さん、訳者の栢木清吾さん、そしてカルチュラル・スタディーズ研究者の小笠原博毅さん。こちらのトークは、訳書刊行直前に47歳で亡くなった著者の追悼イベントでもありました。(※この記録は、すでに人文書院ホームページにて公開したものを、読みやすさ重視のため移行したものです)
開催日:2020年03月06日(金) 18:30~20:00 ジュンク堂書店難波店
司会進行:栢木清吾、福嶋聡(ジュンク堂書店難波店店長)
栢木 司会進行役を務めます栢木と申します。どうぞよろしくお願いします。私は本書の訳者のひとりでもありまして、第3章「大陸を建設する」の部分を担当しています。後ほどのその部分のお話も少しさせていただくつもりですが、まずは監訳者である塚原先生に、本書の内容と、著者のアーロン・S・モーアという研究者についてご紹介いただこうと思います。それにつづいて私のほうからも少し補足させていただき、その後、小笠原先生からいくつか論点を出していただいて、議論に入っていければと考えております。
では、塚原先生から、この本の基本的な紹介をお願いできますでしょうか?
塚原 よろしくお願いします。値段の高い本になってしまったのですが、すでにジュンク堂書店難波店店長の福嶋聡さんや(「書標」2月号)、東京大学の本田由紀さんが書評を書いてくれました(朝日新聞2月29日)。
まず著者のアーロン・S・モーアは、アメリカで日本史を研究していた人です。とくに植民地期に日本がその版図を東アジアに大きく拡大した時期の科学史・技術史を専門にしています。言うなれば戦時中の大日本帝国がしてきたことを議論しようとして、なかでもとくにそのとき科学や技術がどんなことをしたのか、ということについて、この本を書いています。
科学や技術はとにかくいいものである、近代化のために、世の中をよりよい方向に進ませるためのものである、科学技術によって生産や社会生活の効率が上がる、という議論があります。大日本帝国のことを考えるなら、日本の場合はファシズムをもってアジアに侵略したのだけれども、その時導入した科学技術はよかった。そういう議論はいまでもたくさんあります。現代の日本の科学技術の問題でもこのような見方は相変わらずで、そういう見方を「科学性善説」などといいます。「技術決定論」ともいいますね。技術がなんでも決めてきたのだ、そしていい技術があれば使ったほうがいい、それが世の中を良くするのだという考え方です。
では戦争のときはどうだったのか。こうしたことについてはドイツなどではすでにたくさんの研究があります。ナチズムは合理的に科学技術を使って、効率的に人殺しをした。だからそこには、けっこう反省があります。ほんとうに科学技術って無条件でよいものなのか、という議論がたくさんあるのです。
ところが、「日本によってアジアは近代化されたのだ」(だからよかったのではなのか?)、少なくとも、いい面もあったのではないか、などといまでも言われています。「大東亜共栄圏」というスローガンを掲げて、「日本はヨーロッパの植民主義からアジアを解放したのだ」というわけです。そのときに科学技術を使ったため、大日本帝国による科学技術を評価する議論がまだ強く存在している。でも、それは果たしてほんとうにそうだったのだろうかということについて、モーアは研究の対象にしてきました。
モーアが中心的に取り組んでいる一つの重要なテーマは、植民地期の朝鮮や、いわゆる偽の植民地であった満州での、ダム建設、それに植民地の都市計画です。要するに、大日本帝国によって行われていた土木技術に焦点をあてている。戦争と技術というと、直接的に戦闘に使われるもの、そしてある意味華々しい兵器、たとえば戦艦大和、零戦が思い出されます。日本の零戦は初期には強かったけれども、開戦時の主力戦闘機であったグラマンF4F「ワイルドキャット」が後継機F6F「ヘルキャット」に変わったら、優位性はとってかわられて、コテンパンにやられてしまいました。挙げ句の果てにアメリカが原爆をつくりました。技術というと、そういう物理や電気、機械が中心だと考えられていて、そちらには多くの注目が集まってきたのですが、この本で扱っているのは土木です。土木とは都市を整備したり、ダムをつくったり、道を通したり、満州での政策は鉄道帝国主義などと呼びますから、鉄道の建設という重要な仕事もあります。そういうダムや道をつくるということは、帝国であった日本にとってどういう意味のあったことなのか、また被抑圧の側にあった人々にとって、どのような現実があったのかということについて、モーアは深く、そして様々な観点から研究しました。
ここでひとつ、モーアが指摘する重要な点は、日本の技術というのはファナティック(狂信的・熱狂的)でクレイジーで国粋主義的で、ものすごくアグレッシブな(攻撃的・気の荒いオラオラ系の)人たちが、直接的な暴力の行使のために科学技術を用いていたのかというと、そうではなかったということです。わりと冷静な人たちが多くいて、軍人主導では必ずしもなかった。むしろ優秀な技術官僚(テクノクラート)が、けっこう計算ずくめの計画を立てていた。でもそういう官僚とか企業人ばかりが科学技術主導していてだめじゃないか、と思っている技術者たちも多くいて、技術者たち自身が、技術者の立場を向上させようとして、技術官僚と協力しながら「大東亜の科学技術を総合的に建設していこう」と言い出すような人たちが出てくるんです。
それと同時に、これは戦後の文脈では極めて逆説的に響くことなのですが、戦争に反対したはずの、いわゆる、社会主義者、共産主義者、唯物論者たちが、合理的な発想をもって、技術は大事だ、科学技術をもって東アジアの近代化に貢献すべきだと推奨したのです。ここはいろいろ問題があって、「戦争に反対したはずの」という言い方は、少し変かもしれないのですが、日本には、戦前の社会主義者たち、マルクス主義者たちは受難者だったので、彼らの歴史的正当性を過剰に評価してしまうような見方がまだあります。たしかに戦前のマルクス・ボーイたちは、戦争に反対したり、日本型ファシズムの犠牲者になった。ですが、彼らは、科学技術に関する限り、その立ち位置は、「微妙」です。マルクス主義の信奉者たちは、いわゆる「転向」などを経て、ソビエト的な科学技術による開発計画と大日本帝国の科学技術政策を結び付けた。ここで出てきた概念は、「総合技術」と言われるものです。
たとえば、ダムをひとつ建設したら、そこで生み出される電気でケミカル・インダストリーを起こしましょう、水をとめて農業もしましょう、それから治水も灌漑も、ついでに道路と交通網も整備しましょう。一つのものを作るのに、関連の産業や産物、地域の総合的な開発計画、そういったものを視野に入れたかたちで、「総合技術」という考え方でやるべきだ、という主張が出てきます。これは社会主義のロシアも、ドイツも、アメリカのニューディール政策期のダムも、世界でほとんど同時くらいに同じことが起こってきた当時の「技術論」の主流でもあります。そのなかで日本はどうだったのか。日本では、資本主義的な欧米の技術開発ではなく、また社会主義的なモデルによる技術発展でもなく、日本的な「総合技術」が、「大東亜」の旗の下で展開できるのだ、というのです。これは本書の第1章ではマルクス主義者だった相川春喜、第2章では技術者運動を担った宮本武之助、第5章では革新官僚であった毛里英於菟について、彼らの技術思想を、「大東亜帝国」との関係で詳しく検討しています。
当時の技術が合理的な方法でなされていたと語られてきましたが、本書では、それは本当のところでは、けっこう危ないことをしていたことがわかります。たとえば河川にダムをつくる場合、水位を実測せずに、寄せ集めのデータを使って建設してしまっている。現地の労働者をつかうとき、何人くらい募集するかも、とても雑に計算しています。そういう具体例をたくさん挙げて検討しています。
このようなことが、この本の大切なメッセージです。日本のファシズムはファナティックでクレイジーな人が進めたのではなくて、冷静な技術者たちがまともな発想をもっていたことがわかります。背後にあるのはアジアを近代化するというミッションを自認したことでした。遅れた満州や、ダメな朝鮮、そういうところを優れた日本の科学技術の力でなんとかしようとしていた。これを「大東亜技術」と自称したわけです。これをもって、ヨーロッパに勝っていこう、欧米の植民地主義を乗り越えていこうというのが、当時のスローガンでした。全然悪いことを意図していない人たちが、誠実にまともに努力していた、ということでもあります。
そしてこれらについて、第1章と終章で示唆されているのは、戦争が終わったからといってそういう技術観が死に絶えたわけではないということです。戦争が終わったあとも、そこで培った能力やプランニングの根底にあった思想や方法、そして発想は生き延びます。まさに岸信介や、その後神戸市第12代の市長(在任は1949-1969年と20年に及びます)になった原口忠次郎などが、満州のダムなどで、巨大な土木プロジェクトを運営するために培われたすべての政治的・法律的・文化的・社会的・経営的な開発のノウハウを、戦後もそのまま使うのです。最初は「戦後補償」という名前での、日本が戦争した地域に対する援助、つまりODA(政府開発援助)に連続性をもつものですが、大東亜技術の命脈は綿々と続くということは、モーアは示しています。
また技術をもって社会を運営していこうという発想自体が、戦後も脈々と生き続けます。このことは、本書ではあまり書いていないのですが、日本は敗戦後、宇宙・航空技術と原子力の開発ができなくなります。そのミッションはそのまま科学技術庁にスライドして、アメリカとの分業を進めます。アメリカが軍事部門、日本は産業や民生部門を担った、というわけで、大日本帝国期とは別に、アメリカのサテライトになるというファクターがくわわって、戦後は「科学技術立国」が叫ばれるのですが、実はその種になる発想、その淵源は植民地経営のなかでの技術についての思想にあったことを、本書では明らかにしています。
順番が逆になってしまったのですが、2015年8月の『現代思想』特集「戦後70年」で、著者がこの本のあとに書いた小さな論文が掲載されています(「「大東亜の建設」から「アジアの開発」へ」)。これはビルマに日本がどのようにダムを建設してきたかということについて論じていて、この本のいわば続編のようなもので、とてもよく書けた論文です。
非常に残念な話なのですが、まさにこの本の翻訳が終わりかけた段階で、著者のモーアが癌で亡くなってしまいました。47歳でした。学者として、もっとも脂の乗った時期だったと思います。訳者一同は、この翻訳がでたら彼を日本に呼んで、交流や検討を深めようとしていたのですが、それができなくなりました。それでも彼の書いたものを読み、僕らはこの翻訳を日本の読者に紹介することから、彼の遺志をどこかにつなげられるようにしたいと思っております。
栢木 ありがとうございました。私なりにひとつ論点をピックアップさせていただくと、さまざまな歴史的・社会的文脈から科学技術だけを抜き出して論じることはできない、という問題があります。科学技術そのものに罪はなく、使い方が間違っていた、平和利用なら大丈夫、という話にはならないということですね。この本で扱われている満州や朝鮮における建設事業は、その地における支配や暴力の形態やイデオロギー、理想や夢、さまざまな利害関係者などと分かちがたく結びつき、文字通り「総合」的に行われていました。ですから、植民地事業のなかから「肯定的な側面」といったかたちで切り出すことはできないわけです
後世、科学や技術の歴史を語るときには、日本からアジアに技術移転が行われたとか、誰々がどこを開発しました、という物語になりがちです。けれども、こういう描かれ方自体が植民地主義的なものであると著者は何度も強調します。「技術を届けた」とか「近代化した」とかいった言い回し自体が、植民者の手前勝手な言い分にすぎません。実際、たとえば満州でどのように事業が計画され、実施されていたかを見てみれば、中国人技師の多くが関わっていたり、現地にすでに存在していた知識を日本人技師が流用していたりしながら、開発なり近代化なりが進んでいたことが分かるのです。
私が担当した第3章「大陸を建設する」では、具体的に3つの「総合開発」事業が分析されています。そのひとつが、南満州の遼河という河川の治水事業です。治水と言いましたが、この事業は支流の付け替えや護岸工事による水害対策にとどまらず、河川交通の円滑化、都市へのミス供給、ダム建設による電源開発といったさまざまな目的を一挙に達成しようとしていていました。そういう意味で「総合開発」なわけです。ここにはまた干拓によって新たな農地をつくるというもありましたから、農業振興につながります。それから、モーアはそこまで詳しくは書いていませんが、満州拓殖公社が事業に参画していることから分かるように、開拓民という移民を日本から送り出す政策とも関わり、その点では、「内地」における貧困や余剰人口対策ともつながっていきます。
それでおもしろいのはですね、治水事業のためには、降水量とか流量とか土砂の堆積量とか岩盤の強度とかさまざまなデータを集める必要があるわけですが、予算や時間に限りがありますし、それから何より戦争中ということもあって、日本技師たちは十分なデータを集められていないのです。そもそも中国の河川は日本のものと規模が違いますから、日本の技師たちにはそのような大規模事業の経験もありません。それで現地の中国人の技術者の知識や、ロシアがハルピン周辺で集めたデータなどをつまみ食いして使っています。また、こういう大規模プロジェクトには、技師や官僚だけでなく、軍や国策会社、それから現地の住民など、さまざまなアクターが関わってくるのですが、それぞれの利害やプライオリティが異なり、ときにそれらが矛盾してきますから、いろいろな交渉や妥協の産物として、プロジェクトが進んでいくさまが描かれています。そういうしがらみのなかで、技術や科学はいわば場当たり的に立ち上げられていたわけです。ですから、日本の技師たちが作成した緻密な青写真どおりに日本の科学技術が現地にもたらされていくといった輝かしい話では全然ないのです。
塚原 いま栢木さんが説明してくれたように、歴史的な事実に関しては、いろいろなことが詳しく調べられていて、しかもおもしろく書かれています。もうひとつ本書の重要な点は、それをどうみるか、ということについて書いていることです。モーアは「テクノロジカル・イマジナリー(技術的想像力)」というむずかしい言葉を使っていますが、技術がどのような語られ方をするのか、それは2種類あると言っています。当時の日本人は、近代のすばらしい技術をもって大東亜共栄圏を建設するのだと言いました。それはまさに総合的な科学技術であって、これは現地に即した、立派なものなのだと主張していた。大東亜イデオロギーの一環に科学技術が入っていたのです。当時の人はどんな技術的想像力を湧き起こそうとしたか、アピールしたか、どんな宣伝の言葉を使おうとしたか。もしくは、当時の人はなにを信じていたか。それらを詳しく調べて、「技術的想像力」と呼び、それについて細かく書きこんでいます。
もうひとつは、そういった歴史上の出来事を、いまの人たちがどのようにみるかということです。やっぱり、いまだに強力な技術的想像力があるわけです。それは優れた技術や科学で、世界は変わっていく、近代化していくというものです。当時のイデオロギー批判につながる歴史的な事実の話と、いま科学技術をどうみるかという科学技術批判という二重のことが本書には書かれていますから、こんなにも本が分厚くなるわけです。(笑)そういう意味で、本書は、本格的な科学技術史の本であり、科学技術思想史の本でもあると評価していいものだと思っています。
〈後編へつづく〉
- - - - - - - - - -
略歴
塚原東吾(つかはら・とうご)*本書の監訳者。1961年生。東京学芸大学修士課程(化学)修了。ライデン大学医学部博士Ph.D.(医学)。現在、神戸大学大学院国際文化学研究科教授。専門は科学史、STS。編著に、『帝国日本の科学思想史』(共編、勁草書房)、『科学機器の歴史 望遠鏡と顕微鏡』(日本評論社)など。訳書に、ロー・ミンチェン『医師の社会史』(法政大学出版局)、ラジャン『バイオ・キャピタル』(青土社)など。
小笠原博毅(おがさわら・ひろき)1968年生。ロンドン大学ゴールドスミス校社会学部博士課程修了。社会学Ph.D。現在、神戸大学大学院国際文化学研究科教授。著書に、『真実を語れ、そのまったき複雑性において―スチュアート・ホールの思考』(新泉社)、『やっぱりいらない東京オリンピック』(共著、岩波ブックレット)、『セルティック・ファンダム―グラスゴーにおけるサッカー文化と人種』(せりか書房)、『サッカーの詩学と政治学』(共編、人文書院)など。
栢木清吾(かやのき・せいご)*本書の共訳者。1979年生。神戸大学総合人間科学研究科博士後期課程修了。博士(学術)。専門は移民研究、イギリス(帝国)史、カルチュラル・スタディーズ。現在、神戸大学国際文化学研究推進センター研究員。立命館大学・広島工業大学ほか非常勤講師。論文に「移民史と海事史を越境する」(『社会的分断を越境する』青弓社)、「グローバル化、移民、都市空間」(『出来事から学ぶカルチュラル・スタディーズ』ナカニシヤ出版)など。訳書に、ニケシュ・シュクラ編『よい移民―現代イギリスを生きる21人の物語』(創元社)など。
#塚原東吾 #小笠原博毅 #栢木清吾 #日本史 #第二次世界大戦 #アジア史
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?