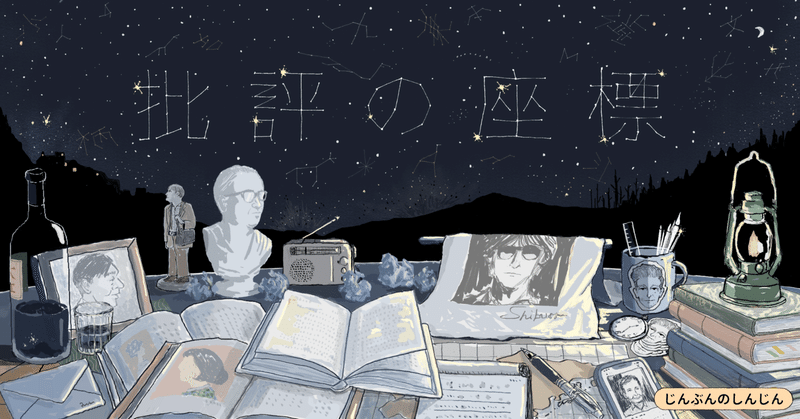
【批評の座標 第20回】実感としての「過去」――江藤淳論(松本航佑)
代表作『成熟と喪失』によって現在の批評シーンにおいても存在感のある文芸評論家・江藤淳は、「過去」と「私」をどのように考えていたのか。日本浪曼派を批判した保守派のリアリストとしても知られる江藤の思想を紐解くのは、山田孝雄、蓮田善明など近代の国学を研究している松本航佑さんです。
――批評の地勢図を引き直す
実感としての「過去」
――江藤淳論
松本航佑
1.「過去」と「現在」の距離
「私」を考えるとき、我々はどのように考えるであろうか。それはおそらく、「私」はこのような性格で、何を好み、あるいは嫌い、どのような仕事をしていて……、といったように、自身にまつわる事柄を中心にして考えるであろう。だが、「私」はそのようなものだけで本当に説明することが可能なのか。自分の属性や経歴のみで本当に「私」は語りつくせるのだろうか。
おそらくそんなことは不可能だ。「私」を説明するときに用いる言葉、それこそ一人称である「私」ですら、積み重ねられてきた日本語の歴史から切り離せはしない。日本語をもって思惟し、日本語をもって他者と関わり続ける限り、その歴史的な制約から逃れることなど、まず不可能だと断言してよい。
そういった至極当たり前で、それでいて忘れがちなこの事実について、江藤淳(1932-1999/昭和七~平成十一年)という批評家は自覚的であり続けたといえる。
江藤淳という名は筆名であり、本名は江頭淳夫という。少年期に「解放感と喪失感を同時に感じる」[1]第二次世界大戦における日本の敗戦を経験し、昭和三十一年には挑戦的な夏目漱石論をひっさげて文壇に登場した。
文学論では『作家は行動する』、『小林秀雄』等多数あり、なかでも『成熟と喪失』については、現在もなお言及されることの多い一冊である。
また、保守系知識人としても記憶されており、なかでもGHQ占領期に形成された「禁忌」の影響を紐解いた『一九四六年憲法――その拘束』や『閉ざされた言語空間』などの著作で知られている。
更に彼はエッセイも多数執筆しているが、そこには「〇〇と私」という題を頻繁に用いている。「〇〇」には今思い出すだけでも「漱石」「アメリカ」「戦後」「文学」「妻」「犬」等々……、江藤は「私」との関係から、対象を描き出す人だったのであろう。
そんな江藤は、批評において「過去」と「私」の間に横たわる緊張感を強く意識していた。そのことは昭和三十一年のデビュー作『夏目漱石』の次の文で即座に理解できよう。
夏目漱石の死後、すでに四十年の歳月が流れている。忘れ去られるには充分な時間であるが、作家の名声はいよいよ高い。しかし、これを漱石が現代に生きている証拠だと思ったら大間違いで、彼の名声にはコットウ品特有の事大主義や回顧的な匂いがつきまとっている。彼を賛美しようとする声は、すべて彼を過去へ押しやろうとする声にすぎない。[中略]ここで、過去は決して完了したものではなく、完了していない故に価値がある、といった教訓を思い出さねばならない。漱石は何一つ完成したわけではないので、彼の偉大さは、彼がなしかけた仕事を我々に向って投げてよこそうとしているその姿勢にある。それを受けとめる以外に、漱石を現代に生かすことは出来ない。ぼくらはその姿勢を支えているものを探ろうとするのである。
生前の漱石を知る門弟たちの賛美により、漱石が「神話」化され、「過去」へと押しやられていく流れに江藤は抵抗する。弟子たちが語る「漱石先生」は、江藤から見れば夏目漱石という個人の実像を忘却させ、「コットウ品」として珍重し、賞玩するようなものでしかないと江藤はいう。漱石の価値はそのようなところにはないと彼は断言する。江藤にとって漱石とは、今なお絶えず問いかけてくる「過去」であり、「現在」に生きている課題なのである。
「過去」は静的なものではない。完了しない動的なものであると江藤はいう。それが放つ問いかけを、「我々」の立場から聞こうとする姿勢から彼の批評は出発しているのだといえよう。ただしそれは、「過去」を徒らに「現在」へと引きつけ、好き放題に処断するといった類いの批評ではない。後述するように「過去」があたかも現前しているかのように語る「神話的」な表現を彼は嫌った。さらに言えば澁澤龍彦のように、「私」を超えて静的な遺物、江藤の言葉で言えば「コットウ品」である「オブジェ」と一体化することでもない(七草氏の論考を参照)。漱石をはじめ、「過去」が放つ問いと、思惟する「私」という起点とのあわいに立ち上がってくるもの。これが江藤にとっての批評なのである。
その姿勢は、彼の高浜虚子への評価に端的に現れていよう。「リアリズムの源流」で、正岡子規と高浜虚子の「写生」論を対比させ、次のように述べる。
この応酬は、いわばふたりのリアリズム観の本質に触れた応酬にほかならない。「殺風景」かもしれないが、「写生」は必然的に「空想」、すなわち対象にまつわるアルージョンやアソシエーションを「排斥」しなければならぬとした子規は、期せずして逍遙にかなり近いところに立っていた。その理論の背景にあるのは科学であり、この場合「写生」の客観性という概念は、無限に自然科学の客観性に近づく。極言すれば、子規の意識の中では、「夕顔の花」は「夕顔の花」という言葉ではなくて、「其花の形状等目前に見る」印象の集合でありさえすればよい。ここでは言葉は言葉としての自律性を剥奪されて、無限に一種透明な記号に近づくことになるからである。
これに対して、虚子にとっては「夕顔の花」はいくら「写生」的、あるいは客観的に用いようとしても、言葉という一点から離れられぬものである。それは対象を指示はするが、決して透明な記号にはなり切れない。換言すれば、この「夕顔の花」という言葉は、子規が主張するように全く自分の自由になり、自分の感受性だけに支配される透明でニュートラルな無性格なものではあり得ない。したがって、もし俳句における「写生」が言葉によって成立するものなら、それは厳密には「古人の知らぬ新たらしい趣味」などというものではあり得ず、どこかに「歴史的連想」の附着したものでしかないはずである。
子規の提唱した「写生」の概念は「「其花の形状等目前に見る」印象の集合でありさえすればよ」く、言葉を「無限に一種透明な記号」とするものである。「リアル」を事象そのものとしてベタに捉えてしまうならば、子規の立場こそが正しいだろう。だが、子規の論は、歴史的意義があるとはいえど、「極論」であったと江藤は見る。「写生」が「リアリズム」として成立するためには、虚子の立場が必要だと彼は主張する。虚子曰く、言葉には常に「歴史的連想」が附着している。そのため、「私」の言葉は日本語の歴史的な制約から完全に逃れることなどできない。だが、その認識こそが「リアリズム」の出発点なのだと江藤は説くのである。
ただし、「過去」のみが言葉を制約する訳ではない。同論考で江藤が「言葉を用いてなされる以上、それは必然的に過去に持続し、他者と社会に開かれたものとならなければならない」[2]と述べるように、言葉は他者から切り離されたものではあり得ない。「過去」と「他者」との関係こそが江藤にとっての「文学」なのである。
この「文学」観は、日本浪曼派に対する痛烈な批判となっていよう。彼は「神話の克服」内で、日本浪曼派を次のように評している。
いまかりに私は「文学作品」といった。しかしすでにふれたように彼らの書いたものは正確に「文学」ではなく、また「作品」でもない。右に述べたような「日本ロマン派」の特性は、文学者としての完全な堕落であって、彼らを「文学者」と呼ぶことには、非人間的な「自然」を人間的な「文化」と混同するのと同様なあやまりがあるのであろう。[中略]「神話」や「民俗」がそのままで「文学」になることはない。そこには必ず「自然」の次元から「文化」の次元への意識的な転移がなければならないのである。
江藤は「ロマンティシズム」を「軽蔑的呼称」として用いることを憚らない。「神話」であれ、「民俗」であれ、「過去」の物事があたかも「自然」として時間の隔たりを超え、我々の前に現前しているかのように説くロマン主義者の態度は、「文学者としての完全な堕落」であるというのである。
先に見たとおり、江藤にとっての「文学」は「過去」と「他者」とにわたっているものでなくてはならなかった。その点、日本浪曼派は「過去」と結びついていながらも、「他者」を拒絶する内閉的なものであった。詳しくは、本連載の武久氏の論考を参照していただきたいが、保田の立ち上げたエモーショナルな共同体に「他者」は存在し得ないことは明白である。保田が喚起する「過去」を共有できるのは、その共同体に身を置く人だけだからである。これを江藤はいみじくも「神託」でしかないと看破している。「神託」がその共同体の内側でしか機能しないことは言うまでもないだろう。
ともあれ、「他者」不在の表現を、江藤は「文学」などと絶対に認めない。「過去」を引き受けつつも、「他者」、つまりは「現在」と関わらせるための「意識的な転移」を「文学」は志向せねばならないと江藤は考えるのである。彼がリアリズム系の保守派言論人として名を馳せたのはこのような点によるだろう。「過去」を無批判に持ち出すことなく、「現在」の側から「過去」を捉え直すことが「文学」なのである。無論、それを行う主体は「私」以外ありえない。「文学」を成立させるためにも、「私」は「過去」を引き受けねばならず、「現在」へと開かなくてはならない。それは尚古趣味でもなく、かといって改革主義に振れることでもないのである。江藤の保守的な態度は「過去」と「現在」の関係から生まれてきたものだといえる。
「過去は決して完了したものではなく、完了していない故に価値がある」という江藤の提言を、我々はもう少し意識してみてもいいのではないか。決して我々は「現在」のみに生きているのではない。「過去」は「現在」の背景にあり続けている。そんな当たり前の話を、江藤は批評のなかで説き続けていたのだから。
2.「なごり」としての評伝
これまでくどくどと述べてきたが、それならば江藤にとって「過去」とは一体どのようなものであったのだろう。無論、彼が「過去」や「歴史」について観念的に述べている文章を掲げることは容易だ。だが、むしろ私は、江藤が「過去」をどのように実感したのか、といったところのほうが重要に見える。それこそが、江藤淳の語る「私」と「過去」との関係の起点だと思えてならないからである。
幼少のころ、江藤は次のような体験をしたという。
小学校に上るか上らないかというころ、私は一人で家の納戸にはいりこんで、薄暗い電燈の下でそこにうずたかく積んである昔の本を眺めているのが好きだった。ここで「昔」というのは、とりもなおさず「幕末から明治・大正」という意味である。それらの本にはたいていうっすらとほこりが積もっていて、「昔」のもの特有の匂いを漂わせていた。
それはもちろん湿気とかび、それにほこりがまざりあった匂いにすぎなかったのだけれども、私にはあたかもそれが「歴史」そのものの匂いであるかのように感じられた。つまり「歴史」というものは納戸の中の本や長持のように、ある匂いと重みをもって私の前に現存しているものである。
早熟の少年、江頭淳夫が感じた「湿気とかび、それにほこりがまざりあった匂い」、これこそが批評家江藤淳にとっての「歴史」であった。これまで取り出されることもなく、家人にすら置いてあることを意識されず、ほこりをかぶったものの「匂い」。本であれ長持であれ、そこから放たれる「匂い」こそ、江頭少年の体験した「歴史」なのである。「過去」は直接経験することができない。しかし、残された「匂い」を通じ、江藤は「過去」を実感したのである。
この文章は『海舟余波 わが読史余滴』のプロローグに書かれたものである。書名からもわかるように、勝海舟の評伝である。
ところで、そこに付されている「余波」とはどのような意図を持つのだろうか。これは第一に、江藤が同書のあとがきで明言している通り、明治三十二年に巌本善治がまとめた海舟の語録『海舟餘波』から借用してきたものである。「余波」とは、和語に読めば「なごり」となろう。「なごり」は「㊀風がやんでも、まだ静まらない波。㊁波がひいたあとに残る海水」とあり、古くは多く「余波」と表記された[3]。
「余波」とは、いうなれば残り香のようなものである。本体が去ってもなお、その人を今も想起させるものごと、それを「余波」と江藤は表現したのである。江藤の「過去」は「なごり」をもって感じ、「匂い」をもって想起する、そういった追想のようなものであったといえそうである。海舟の「なごり」を感じ取ることが『海舟余波』という題に表現されている。
またもう一点、同書あとがきで「「餘波」であって「余波」ではない」と断っていることに注意されたい。巌本の「餘波」はそのまま「なごり」と解してよい。しかし江藤の「余波」については「なごり」とも異なる含意があろう。「餘」の新字として現在「余」は用いられており、通常「あまる」などといった意味で理解される。だが、その他にも一人称として「余」は用いられることがある。
つまり「余波」は「餘波」であると同時に「私」と海舟との関係を示唆したタイトルといえはしないだろうか。これは江藤が度々愛用した「○○と私」という型とも通じていよう。彼は「歴史」を論じる中でもなお、「私」との関係を探っていたのである。「私」を起点に「歴史」へと分け入っていく評伝、それこそが、『海舟余波』という書なのである。
そのなかで江藤は勝海舟を「政治的人間」と定義した。「政治的人間」とは、政治家とイコールの存在ではない。江藤曰く、「政治的人間」とは「成功すべく運命づけられた人々、あるいは成功しなければならぬ人々」なのである。「成功」により「現実を保全」する使命を担う人々、それこそが「政治的人間」であるという[4]。「失敗」によって後世に名を残す「思想家」「文学者」とは全く異質な存在として「政治的人間」海舟は語られるのである。
本書では、海舟と西郷を対比させ、その両者が異質であることを説く。幕末における江戸城の無血開城や、海軍卿として海軍の創設に携わった海舟の功績は「現実を保全」するリアリスティックなものとして評価される。対して西郷は周知の通り明治政府に反旗を翻すという無謀な西南戦争を引き起こし、案の定「失敗」に終わっている。しかもそれは単純な「失敗」などではなく、思想としての「失敗」だと評されるのである。
だがこのような西郷や乃木の姿は、なんとよく小説の主人公に似ていることだろうか。しかも彼らは単純に失敗するばかりでなく、“失敗の情熱”によって生きているところが偉大であり、小説というよりはほとんど叙事詩の英雄を思わせさえする。つまり彼らは実人生に文学を生きたのであり、そのことによって決して完結しない歴史に完結の幻影をあたえてくれたのである。
「成功」する海舟と「失敗」する南洲。しかも後者は意志的に「失敗」しているのである。しかもその「失敗」は、すくなくとも直近の「現実」にはなにも寄与していない。しかし、皮肉なことに、「文学的英雄」は、「失敗」によって愛惜され、その精神は後世に広く語り継がれていくのである。西郷は「官軍」からも「古今無双の英雄」と高らかに歌われ、後世には「大西郷」と敬仰されている。
反対に、海舟は維新期の傑物ではあれども、その精神を讃えられることは少ない。「政治的人間」は「文学的英雄」と対極的に、「成功」によって憎まれ共感されず、その精神が後世に語り継がれることはない。「このような人間を救うことができるのは、神のほかには後世の追憶と共感だけではないか」と江藤はいう。神でない江藤は、だからこそ『海舟余波』を執筆したのである。
だが、江藤は「政治的人間」への「思慕」からこの書を著したのではない。「しかし私たちが愛することができるのは、大久保ではなくて西郷のほうである」[5]と述べるように、文学者である江藤の「思慕」は、政治的な「成功」を収めた海舟や大久保利通ではなく、「文学的英雄」の西郷へと向けられているのである。
それでは「政治的人間」に、一体どの立場の「私」から共感しているのか。それは、彼がこの時期に探っていた「治者」のあり方と深くかかわっていよう。
昭和四十五年に連載が始まった『海舟余波』がそうであるように、この頃の江藤は「治者」の問題を真正面から取り上げ始めていた。その嚆矢ともいえる『成熟と喪失』は昭和四十一年より連載が開始されているが、そこでは、庄野潤三の小説『夕べの雲』を引き合いに出し、「治者」の存在を次のように語っている。
私が以前『夕べの雲』について「治者の文学」といったのは、大浦が存在証明にしているこの怯えの感覚と「不寝番」の意識を指してである。もしわれわれが「個人」というものになることを余儀なくされ、保護されている者の安息から切り離されておたがいを「他者」の前に露出しあう状態におかれたとすれば、われわれは生存をつづける最低の必要をみたすために「治者」にならざるを得ない。つまり「風よけの木」を植え、その「ひげ根」を育てあげて最小限の秩序と安息とを自分の周囲に回復しようと試みなければならない。
「被治者」の姿勢に安住することは、概念と素朴実在論の世界に固執して、自己の内外に起こりつつあることから眼をそらし、結局現代を無視することになるであろう。しかし逆に「治者」の不幸を引きうければ、作家は別種の、おそらく前人未踏の難問に出逢わなければならない。
ここで語られる「治者」と「政治的人間」はほぼ同一のものであろう。「自己の内外に起こりつつあること」に眼を向ける「治者」のありようは、内憂外患への対処に奔走する「政治的人間」勝海舟と重なっている。海舟は「国家」という「「風よけの木」を植え」、「現実を保全」した「治者」であり、江藤はその内側で少年期を過ごしたのである。
その「治者」が植えた「風よけの木」を「喪失」した経験こそ、江藤にとっての「敗戦」だった。
しかし、敗戦によって、私が得たものは、正確に自然が私にあたえたものだけにすぎない。私はやはり大きなものが自分から失われて行くのを感じていた。それはもちろん祖父たちがつくった国家であり、その力の象徴だった海軍である。
「治者」が作り上げた「国家」や「海軍」は「敗戦」によって失われた。しかも、「戦後」になってもそれは帰ってこなかったのである。ことに、「海軍」の「喪失」は、江藤にとって重要な意味を持っていた。
彼の祖父江頭安太郎(元治二~大正二年)は、海軍大学校を首席で卒業した俊英であり、「国家」が持つ力の象徴たる「海軍」の中将であった。いずれ海軍大臣となることを嘱望されるほど人物であったが、惜しくも在職中に病没してしまったという。
当然、江藤は顔を合わせたこともない。だが、威厳ある肖像写真と共に、祖母や父の語りを聞き、彼は祖父の姿を知ったのである[6]。また、江藤は別の機会にも祖父を感じていたことだろう。あの「歴史」を感じた、納戸で読んだ本は祖父のものであったに違いない。こういったものから江藤は祖父とのつながりを感じていたのであった。
だが、そんな思い出も、米軍の空襲は焼き払ってしまった。
家もなくなっていた。大久保百人町の家は五月二十五日の空襲で焼けていた。父はなぜか荷物の疎開をためらっていたので、私を祖父や亡母につなげていた遺品や記録も、わずかな品物を除いて全部焼けた。
空襲により、幼少期に潜り込んでいた納戸は焼け落ち、祖父と、そして亡き母とのつながりは、彼の手元から失われてしまった。そして「敗戦」は、「祖父たちがつくった国家」と「海軍」までも、江頭少年から取り上げたのである。
『海舟余波』は、この「喪失」から書き出されたのである。海舟を描くことは、江藤にとって祖父を語ることとつながっている。「過去」である海舟を語ることは、「私」の側にある祖父を通じて果たされたのだといえよう。彼の「歴史」評伝は、「私」と不可分だったのである。
3. 日本浪曼派との「再会」
そういえば、江藤は晩年に西郷論を執筆していた。その題は『南洲残影』。海舟が「なごり」であるならば、南洲は「おもかげ」であろうか。西郷の「おもかげ」を偲ぶ海舟の姿から、この評伝は始まっている。政治の第一線を退いた海舟が、西郷を回顧し、したためた薩摩琵琶曲『城山』を江藤は聴き、つぎのような感想を抱いた。
いずれにせよ、弾奏の間から甦えるのが合戦の情景であってみれば、その曲譜が勇壮活発であることに不思議はない。実際、そこには感傷的なものはいささかもない。だがそれでいて聴く者の心に惻々と沁み入ってくるのはこれが敗軍の譜にほかならないという事実である。かならずしも詞章に、「……諸手の軍うち破れ、討ちつ討たれつやがて散る」云々という文句があるからではない。撥を叩きつけるように使って、絃を弾き鳴らすだけではなく、楽器の胴を容赦なく打ち鳴らすという、急調子の奏法に魅了されているうちに、薩軍敗退、西郷最期の悲しみが、やむこともなく身に沁みわたって来るというのである。
江藤は「城山」という曲の調べに、勇猛でありながらもどこか悲哀を感じてしまう。しかし、なぜ西郷の物語に悲哀を覚えるのだろうか。当時を知る訳でもなく、ましてや地縁すらない自分が、どうしてこのような悲劇に感動してしまうのか。江藤はそう自問して筆を進めていく。そのうち、彼はこの曲が「滅亡の曲譜」だからだと気づくのである。江藤は『城山』と『平家物語』を聞き比べ、こう語る。
栄華の頂点を極めた平家が、一人残らずみな亡んでいった。これほど由々しくもまた驚くべきことが、この世にまたとあり得るだろうか。それが稀有の出来事であるからこそ、その滅亡は語りつづけられねばならず、悼みつづけなければならない。そういう平家琵琶の曲調が薩摩琵琶に伝えられ、明らかにあの『城山』の一篇に甦っている。『城山』もやはり、全的滅亡を奏でる曲譜である。だからこそそれは哀しいのである。
平家と西郷の滅亡の物語、その共通性に江藤は感動する。平家の栄華は乱世の前にて塵と化し、私学校の薩摩隼人は「官軍」の前に露となって消えていった。あとに残った琵琶の響き、その激しくも哀しい調べに彼は心を揺り動かされる。
しかし、これは不思議な話である。先に述べた平家と西郷の悲哀に、なぜ江藤が共感し得るのだろう。どちらも「滅亡」はしたが、その物語に感動するために、江藤もまた何かしらの「滅亡」を体験していなければ共感し得ようがないのである。むろん、江藤は「滅亡」を体験している。昭和二十年の敗戦、それこそが江藤にとっての「滅亡」ではなかったか。
西南の役の激戦地、田原坂を訪れた江藤は偶然ある歌碑を見つけ、そこに刻まれた
ふるさとの 驛におりたち
眺めたる かの薄紅葉
忘らえなくに
という歌に足を留めている。
このあえかなる歌の作者は蓮田善明。三島由紀夫にも影響をあたえた日本浪曼派系統の国文学者でもある。昭和二十年八月十九日、戦地において上官を射殺し、自身もまたそのピストルで自決するといった熾烈なエピソードにおいても知られていよう。そのような最期を迎えた善明が残した、なんとも穏やかな歌碑をみつけ、次のようにいうのである。
ところで、植木町が蓮田の「ふるさと」だとしても、何故この碑は田原坂の古戦場に立っているのだろう。「烈火の如き談論風発ぶり」(三島由紀夫『文藝文化』のころ」)を謳われた蓮田の文学が、何故「ふるさとの驛」の「かの薄紅葉」という表象によって要約されているのだろう。
そう自問したとき、一種電光のような戦慄が身内を走った。西郷隆盛と蓮田善明と三島由紀夫と、この三者をつなぐものこそ、蓮田の歌碑に刻まれた三十一文字の調べなのではないか。西郷の挙兵も、蓮田や三島の自裁も、みないくばくかは「ふるさとの驛」の、「かの薄紅葉」のためだったのではないだろうか?
滅亡を知る者の調べとは、もとより勇壮な調べではなく、悲壮な調べですらない。それはかそけく、軽く、優にやさしい調べでなければならない。何故なら、そういう調べだけが、滅亡を知りつつ亡びて行く者たちの心を歌い得るからだ。
[中略]田原坂の空間には明治十年の西南の役の時間が湛えられているだけではなかった。この時空間には、昭和二十年の時間も昭和四十五年の時間も、ともに湛えられてめぐり来る桜の開花を待っていた。
桜の梢をながめつつ、また来る春に「過去」を知る。蓮田と三島の死、これらが西郷の「滅亡」の系譜へとつながると、江藤はここで悟るのである。あえかで、かそけく、そしてやさしい調べによって「滅亡」は悼まれ続ける。「滅亡」を悼む江藤の筆致はなんとも儚く、そして美しい。
だが、江藤は日本浪曼派を批判してやまなかったはずである。それにも関わらず、ここには「神話の克服」に見られたような断罪の気負いは一切見られない。『南洲残影』に至り、江藤は「偉大なる敗北」に共鳴してしまっているのではないか。麒麟も老いては駑馬に劣るように、江藤もまた耄碌してしまったのか。ことはそう単純ではない。江藤は若き日に日本浪曼派と出会っていたのだから。
昭和二十三年の晩夏、江頭少年は下十条(現東十条)の古書店で『反響』と題された詩集を手に取っている。その小さな詩集の作者は伊東静雄といい、日本浪曼派における代表的な詩人として知られている。当時十代だった江藤はそのことを知らなかったようであるが、それでも日本浪曼派との遅れた出会いを果たしたことは間違いない。そこで得た感慨の深さは、『反響』に出会わなければ「いまとはまったく違うことをしていたかも知れず、ひょっとしたら生きてすらいなかったかもしれない」[7]という言葉からも、かなりのものであったことが伺える。
そこに収録された「夏の終り」という詩は、江藤が当時抱いていた「うずき」に応えてくれたという。
夜來の颱風にひとりはぐれた白い雲が
氣のとほくなるほど澄みに澄んだ
かぐはしい大氣の空をながれてゆく
太陽の燃えかがやく野の景觀に
それがおほきく落とす靜かな翳は
……さやうなら……さやうなら……
……さやうなら……さやうなら……
いちいちさう頷く眼差のやうに
一筋ひかる街道をよこぎり
あざやかな暗綠の水田の面を移り
ちひさく動く行人をおひ越して
しづかに村落の屋根屋根や
樹上にかげり
……さやうなら……さやうなら……
……さやうなら……さやうなら……
ずつとこの會釋をつづけながら
やがて優しくわが視野から遠ざかる
一見すれば、明るい空を「ひとりはぐれた白い雲」が渡っていく様を描いた叙景詩である。ただ、この詩から「かそけく、軽く、優にやさしい調べ」を感じ取ることは許されるのではなかろうか。
実際、江藤にとって、これは「敗戦」の「悲しみと喪失」を「アイロニカル」にうたった詩であったのだという[8]。はじめに触れたように、彼にとっての「敗戦」は「解放感と喪失感を同時に感じる」ものであった。だが「戦後」の言論統制がもたらした「民主化」「解放」などの言葉は、江藤の感じた「喪失感」を次第に塗りつぶしていったのである。その抑圧こそ、彼が覚えた「うずき」の正体だったのである。
ふりかえってみると、私たちはそのころ、敗戦の悲しみをうたうことを許されていなかった。いや、私たちは、敗戦の悲しみを感じることを許されていなかった。それが国を占領されていることの、もっとも端的な意味であった。私たちは、喜ばなければならなかった。日本が「民主化」され、戦犯が巣鴨につながれ、闇市が栄えて弱肉強食の自然状態がいたるところで展開されていることを。私たちは敗れたばかりではなく、敗れたことを喜ばなければならないのであった。
「占領」によって意識することを許されなかった「喪失」の「悲しみ」を、江藤はこの詩を介して思い出すことができ、そして正しく「悲しむ」ことができた。彼が忘却させられていた「喪失感」は、「アイロニカル」なこの詩によって回復されたのであった。
そうした事情を鑑みれば『南洲残影』に残されたあの言葉は、日本浪曼派との「再会」と呼ぶべきもののように思えてならない。気鋭の批評家であった江藤が、その初期の業績において必死に否定し去ろうとした日本浪曼派と、時を経て和解する。そのような文章として理解できはしないだろうか。この日本浪曼派との和解は、自身の「過去」を引き受け、「現在」へと「意識的な転移」を行ったものではないか。日本浪曼派が「挽歌」に意義を見いだしたように、江藤もまた「追慕」によって評伝を書いた。その根元のつながりを、江藤は晩年にようやく認めることができたのではないか。
とにかく、「過去」としての「文学」や「歴史」、はたまた「なつかしい本」、江藤は一貫してそれらとの繋がりを「私」という立場から確認し続けたのである。その反復は、畢竟「忘却」の拒否という営みだったのではないか。彼は常に「過去」を参照し、「私」と結び付けることによって「過去」を絶えず再生し続けた。それは「過去」を本当の意味で「喪失」しない営みに他ならない。「喪失」を彼が口にするとき、対象と本当の意味で断絶されてはいない。「喪失」を語ることで、「忘却」という本当の「喪失」を回避する。これこそが、江藤の批評ではなかっただろうか。
江藤の自裁からすでに約四半世紀の歳月が流れている。ときの流れが早まった現代において、忘れ去られるには十分な時間であるが、批評家の名声はいよいよ高い。江藤も例にもれず「コットウ品」となりつつあるのかもしれない。だが、私は江藤を生きた「過去」として見たい。江藤は何一つ完成したわけではない。彼に学ぶところは、彼の「過去」と向きあう姿勢にある。それを受けとめる以外に、江藤を現代に生かすことは出来ない。「私」と切り離せない「過去」こそが、「私」を生かしているのだから。
[1]江藤淳「年譜」『江藤淳著作集6』、講談社、昭和四十八年、三百二十九頁。
[2] 江藤淳『リアリズムの源流』、河出書房新社、平成元年、三十三頁。
[3] 『新明解国語辞典 第四版』、三省堂、昭和四十七年、千三百三十九頁。
[4] 江藤淳『海舟余波 わが読史余滴』、文藝春秋、昭和四十九年、二十八頁。
[5] 同書、三十頁。
[6 江藤淳『戦後と私・神話の克服』、中央公論新社、令和元年、二十九頁。
[7] 江藤淳『なつかしい本の話』、新潮社、昭和五十三年、九十七頁。
[8] 同書、百三頁。
人文書院関連書籍
その他関連書籍
執筆者プロフィール
松本航佑(まつもと・こうすけ)平成八年生まれ、長崎県出身。皇學館大学大学院文学研究科神道学専攻博士後期課程所属。近代における古事記研究史を専攻しており、山田孝雄、蓮田善明を中心に国学的な古事記論を対象としている。
次回は2月後半更新予定です。つやちゃんさんが鹿島茂を論じます。
*バナーデザイン 太田陽博(GACCOH)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
