
NY Bar不合格体験記と合格体験記〜進捗管理AI活用のススメ〜
はじめに
先日の合格発表で、2023年7月のNY Barを突破していたことが分かりました。実は私、これが3回目の受験でした。ネット上には大変優秀な方々が書かれた華麗なる一発合格体験記が多数ありますが、残念ながら不合格体験記はあまり見られないようです。よくあるビジネスの成功体験記に言われることですが、成功には数多くの方法ある一方で、失敗のパターンは大抵決まっているそうです。ここでは、何故私が2回もNY Barでしくじったか、そしてそれをどのようにして克服したかを恥を忍んで共有するすることで、これからNYバーに挑まれる日本人の合格率(不合格回避率)を少しでもあげていただきたいと思っています。私のような一発ペーパー試験が必ずしも得意でない方の参考になれば幸いです。
受験1回目 不合格 (2022年7月)
元々自分の受験センスに自信のなかった私は、勉強のスタートを比較的早く切りました。冬休み明け早々にUCLAの日本人同級生と5人で勉強会を組成し、スケジュールを立てました。具体的には、週ごとに取り組む科目を決めて、疑問点を週一回共有し合うミーティングを開催しました。取り組む教材は、エマニュエルのMBE問題集(https://amzn.asia/d/jl32C10)とBarbriテキストのMEE Testiingです。
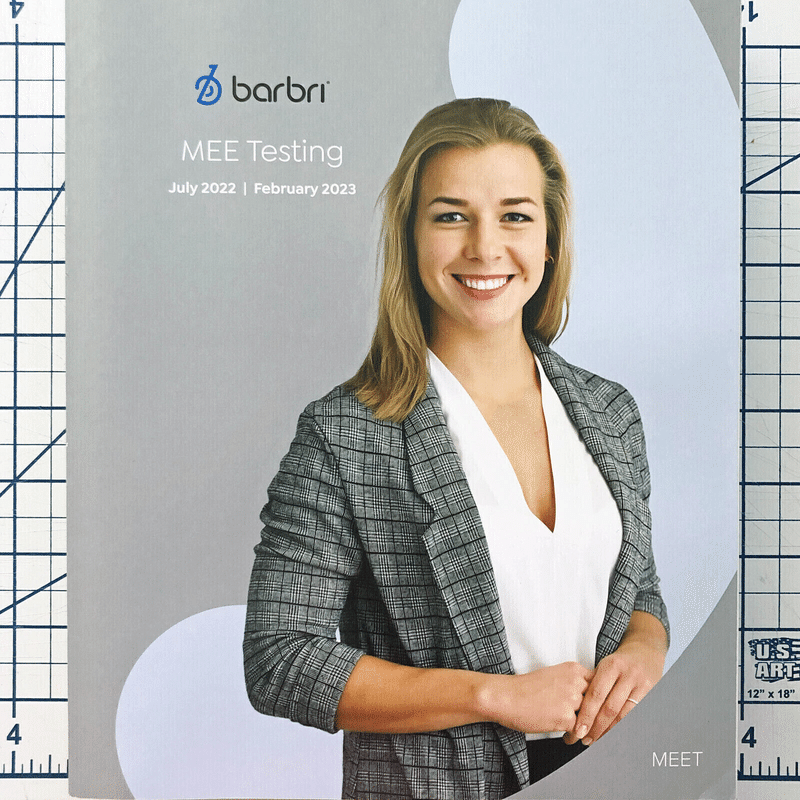
これは勉強のペースを掴むにはとても良い試みでした(が、後述のように最終的にはより良い進捗管理に気づくことになります)。この進捗管理の上で、個人的に初受験で取った戦略は①日本人ノートによるインプット②エマニュエルとAdaptiBarによる演習及び③Smart Bar Prep(https://smartbarprep.com/ube-mee-study-guides/)のSmart Sheetによるエッセイ規範の暗記です。
結果から申し上げます。20点も合格点に届かない惨敗でした。原因は次の3つです。
とにかく日本人ノートの内容理解に時間がかかることを看過していました。パッと見たところ、普段苦戦している英文のケースブックからしたら読みやすそうで、1週間もあれば全科目通読くらいできるだろうと思っていました。しかし、実際には1科目に1週間かけても読み終わることはありませんでした。
次に、やみくもにエマニュエルやAdaptibarの演習ばかりやりすぎました。自分自身の日本人ノートの読込みの遅さに痺れを切らした私は、十分な基礎知識もないまま問題演習量ばかりを増やしていきました。問題をインプット段階から解くこと自体は悪くない戦略だと思いますが、私の場合は明らかにバランスを失していました。結果、解いた問題数は4000を超えましたが個別の問題例と回答がなんとなく頭に残るだけで体系的な理解に到達できず、捻った問題やエッセイに対応する力は全くつきませんでした。
加えて、エッセイ対策にSmart Sheet一本槍で突っ込んだことも失策でした。きちんとした体系的理解なしに表面的なキーワードだけ記憶しようとしても、うまく定着しないばかりか覚えた表現も事案に即して使うことができませんでした。まさに日本の司法試験でいう論証パターンの弊害です。
このような3つのしくじりから、見事に20点ほど合格点に足らず落ちてしまいました。上記3つは氷山の三角でして、結局のところ適切な勉強計画と自分の進捗に合わせた管理ができていなかったのが根本原因です。ただ不合格にもかかわらず、とても良かったのが勉強会仲間と励ましあえたことです。異国の司法試験は孤独な闘いなだけに、このような友人の存在は試験当日含め本当に貴重でした。
受験2回目 不合格 (2023年2月)
あの極寒のバッファローを思い出しながら書いています。2月の受験は、後述のとおり7月受験の反省踏まえて戦略を変えました。2月受験の特徴として、合格率が大幅に下がることが挙げられます。その原因の主なところは、優秀な受験者は7月に合格してしまっていること、2月受験者はすでに何らかの仕事を持っていることも多く十分に直前の時間を取れないことが挙げられると思います。加えて、個人的な印象ですが、MEEの問題が7月より捻ったものが多く取り組みにくいものが多いです。
7月の敗戦を踏まえて、まず日本人ノートをじっくりと読み直しました。これは断片的な知識が線となって繋がる感覚があり有効だったと思います。ただ、2年目のLLMの授業を大切にしていたこともあり、結局、またしても勉強の時間管理がうまくいきませんでした。MBE科目の理解は深まったものの、MEEとMPT対策に十分な時間を取ることが出来ませんでした。
その結果、短答式、論述ともに7月よりアップしたものの、5点合格点に足らず、またしても敗北を喫しました。
受験3回目 合格 (2023年7月)
上記2回のしくじりから、私は大きく戦略を見直し、三本の矢をこしらえました。①Barbriシステムの活用、②ノートの自作、そして③MPTを本気でやる、です。
まずBarbriシステムの活用です。実は、Barbri自体は一回目の受験時に申し込んでいました。ただ、Barbriの講義は意味ない、価値があるのは問題集だけという風潮もあり、インプットには日本人ノートのみを使っていました(アウトプットの練習にMEEとMPTの問題集を使う程度でした)。そこから方針を一気に転換させて、Barbriのカリキュラムにフルコミットすることにしました。きっかけは、4月頃に藁にもすがる思いで受けたBarbriのワークショップです。そこでは、BarbriのシステムがISAACというAI(https://youtu.be/dFRtVTjaUrg?si=l4WSdoo1PdZIlsfI)を搭載して大幅アップデートしているという説明がありました。振り返れば、これまでの試験で、私自身の各戦術の失敗の根底にあった戦略上のミスに気がつきました。勉強計画を戦略的に立てることまではできるのですが、それを着実に実行し試験当日にピーキングさせることがどうも苦手なのです。このBarbriのISAAC、大量にあるBarbriカリキュラム上のタスクの中から、自分の得意不得意分野と進捗状況に応じて、現時点でこなすべき課題のうち最も優先度の高いものを提案してくれます。使い始めてみると、これがとにかく効きました。例えば自分は民訴が苦手だったので(最初に受ける実力確認テスト及びその後の小テストや模試で苦手科目はISAACが判別します)、その科目の優先度があがり、民訴の関連タスクが先に提案されます。民訴の講義をきちんと受け、基礎的な問題を繰り返すことで過去問の正答率も上がっていきました。なお、Barbriの講義は想像以上に良かったです。テキスト読み上げではなく、暗記のための語呂合わせを紹介してくれたり、論文で書くべきキーワードを強調してくれたりと、聴くだけで理解と記憶が深まりました。平易な英語でネイティブでなくてもロースクール留学に来られる英語力であれば十分理解できる内容です。また、ISAACには総勉強時間が平均的な合格者の勉強時間に比べてどれくらい足りないか常に表示されています。いくら勉強しても不安が尽きないのがこの試験ですが、この合格に必要な勉強時間を上回るように日々の勉強時間を設定することで、怠け過ぎやオーバーワークを避けることができます。このスケジュールリングを踏まえて、私は積極的に気分転換をするようにしました(内緒ですが毎日時間を決めてゴルフの練習もしてました)。結果、三度目のバッファローでは、最適な学習のみらなず心身共に極めて良い状態で試験に臨めたと思います。
次に、ノートの自作です。自作といっても、1から日本人ノートのような大作を作る訳ではありません。日本人ノートの目次やBarbriテキスト、Smart Sheetを使って、試験前日に全科目を見直すことができるまとめノートを作るのです。言うまでもなく、日本人ノートは極めて優秀な諸先輩方が作り、秘伝のタレのように継承してくれた偉大な財産です。これを批判するつもりは毛頭ないのですが、残念ながら最近はアップデートがされてないようです(人ごとのようですが、私も含めてそのような余裕のある留学生がいないのだと思います)。例えば、中絶に関するプライバシー権の議論はMBEの正解選択肢が全く変わってしまうような重要な判例がありますが、これは未反映です。また、日本語で米国法の体系を学べるのは大きな強みである一方、この日本語中心の理解のまま試験本番に臨むと、エッセイで苦労します。非常にタイトな時間の中で相当な分量を書くには、日本語から英語に脳内変換している時間はありません。重要なキーワードや論証は条件反射のように英語で想起する必要があります。したがって、日本人ノートの日本語は最後のステージでは邪魔になります(最初の全体理解に有用なのは言うまでもありません)。そこで、私は全て自分がエッセイで書く英文を想定して、日本人ノートをコンパクトな形にまとめていきました(MBE科目10数ページ、MEE科目数ページです)。
最後に、MPTは舐めてはいけないということです。確かに、全体に占める割合は20%と1番少ないこと、及び純ジャパに高得点は望めないであろうことから、ほぼ対策をしない戦略もよく聞きます(し、実際にこれで受かっている人も多くいるようです)。しかし、そのような戦略を語る日本人受験生の多くは、ロースクールや予備・司法試験で常に上位にいらしたであろう、事務処理能力の鬼のような方々です。私はそのような方々を羨望の眼差しで眺めていた中留学生でした。私のようなレベル感に心当たりがある方は、安易に上記のMPT無対策戦略論に乗ると致命症を負う可能性があります。実際、私の1回目及び2回目の受験では、MEEとMBEは(勿論良い出来ではないですが)、そこそこの点数は取れていました。一方MPTがとにかく悪く、MPTさえ人並みから大きく外れていなければ、合格は充分あり得ました。これを教訓に、数日に1回は90分時間を測ってMPTの過去問を解き、Barbriに添削も依頼しました。問題練習を繰り返すうちに、資料の読み方のコツがわかってきたり、タイムマネジメントも上手くなっていきました。そして何よりタイピングのスピード(英文を作りだす試行スピードとタイプする手のスピードの両方)が上がっていきました。これはMEEにも波及し、エッセイセクション全体の底上げに繋がったと思います。このように、最後に捻り出した三本の矢が見事命中し、何とか合格を勝ち取ることができました。
おわりに
以上、3回にわたる受験経験をシェアさせていただきました。数ある反省点及びTipsの中で一つ強調するとすれば、BarbriのAIシステムに徹頭徹尾従ったのが根本的な解決に繋がったということです。今や国家間の戦争でもAIの戦略に依拠する時代、人工知能は客観的な戦略立案と進捗管理については各受験生の感覚より遥かに優秀のように思われます。もしネット上に数ある受験戦略論の海に溺れそうになったら、いっそAIに舵取りを任せて、船を漕ぐことだけに専念すべきです。これを読んで下さった日本人ロイヤーの不合格率(縁起でもない表現ご容赦ください)が少しでも下がるようであれば、私の2回の不合格も報われる思いです。長文最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
