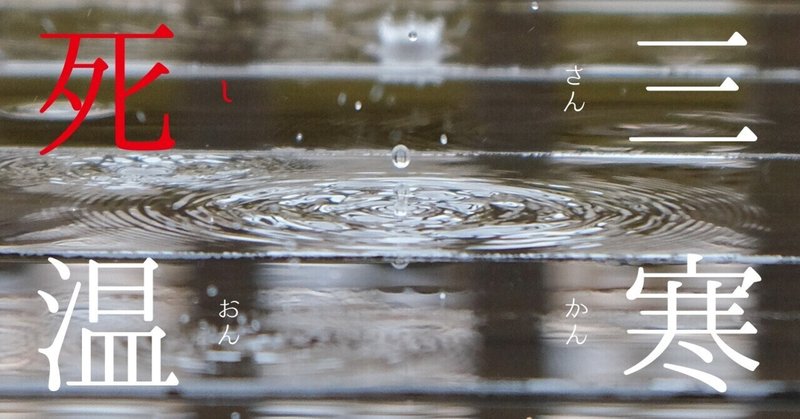
長編小説【三寒死温】Vol.13
第二話 律儀な看護師の旦那
【第五章】溺れる者は藁をも掴む
小さなため息を吐きながら、私は紙コップに半分ほど残っていた白湯を飲んだ。味も素っ気もないが、喉の渇きは癒える。
「そうやってご自分のことを客観視できるだけでも、立派なものだと思います。それによく言うじゃないですか。自分たちの子として生まれてきて本当に幸せだったのかと不安になるけど、そう気遣ってくれる親の元に生まれてきたこと自体、子どもにとって幸せなことだって。」
あれ、ちょっと違いますかね、と言って、その青年は頭を掻きながら屈託のない笑みをこぼした。
彼のそんな答えと表情に、私は軽い衝撃を受けた。
「もしかしたら、多少は自分のためという気持ちがあったかも知れない。それが、相手からすると理想を押し付けているように感じられてしまったのでしょう。」
確かに私は、話の最後にそう付け加えた。
しかしそれは、言ってみれば体のいい取り繕いみたいなもの。
正直なところ、客観的に自分の欠点として認めた上で話をしたつもりなど微塵もなかった。
まさか、字面通りの意味として真に受けられてしまうとは。
「みんな、自分に都合のいいことしか言わないもの」
「正しいことを言っているのだから、堂々としていればいい」
「厳しいことでもはっきりと言えるような、嫌われ役が必要だ」
そんな言葉が帰ってくるものとばかり思っていたので、またしても、次に用意していた台詞を言いそびれてしまう。
これでは彼に「そうです。それがあなたの欠点です。」と言われているようなものではないか。
「私は、自分の子どもが生まれた時に、一つだけ望んだことがあります。と言うか、悩みに悩んだ結果、一つに絞りました。」とその青年は言った。
「それは、どんな望みです?」
「謝ることのできる人間になって欲しい、という望みです。」
これまた最近ではよく使われているような、ありふれたものだ。
私から言わせれば、そんなことは人として当たり前であって、特に大きな意味を持つような言葉ですらない。
そもそも、謝罪など必要ないよう周到に準備するのがまっとうな大人のやることだ。
「人に迷惑を掛けない。人を傷つけない。人に嘘をつかない。
いろいろと考えてはみたんですけれど・・・
でも、人に迷惑をかけなきゃ、人の本当の怒りや悩みは分からない。
人を傷つけなきゃ、人の本当の痛みは分からない。
人に嘘をつかなきゃ、人が嘘をつく本当の理由は分からない。
こういうことって、人と人とが生きていく上では、避けられないことばかりなんですよね。人は、自分一人で生きていくことは不可能ですから。
相手がいる以上、人は必ず間違いを起こす。だからこそ、自分が間違った時にはそれを認められる人間になって欲しい。」
「人は、一人では生きられないから。」
そう呟きながら、私は柄にもなく彼の表現を噛み締めていた。
私が思っていたような、処世術としての「謝る」とは概念からしてまったく違っている。人は必ず間違いを起こすものというアプローチも、間違いを起こさないために逆算してさまざまな予防線を張り巡らす私とは、対極にあるようだ。
「はい。一人では生きられない以上、人と比べたり比べられたりするのも仕方のないことだと思うんです。人の目が気になるのも当然だし、人からどう思われているか気になるのも当然。
ある意味、自分自身への戒めでもあります。」
彼の言葉を聞いているうちに、私は夢の中に落ちていくような感覚に襲われた。私が想定したような言葉も返ってこなければ、私が想像したような言葉の使い方でもない。
話をしていて、ずいぶんと面喰らうことの多い青年だ。
ふわふわと宙を浮いているような感覚を持ち続けたまま、私は「そろそろ、午後の検査が始まりますので」と言って、食堂の椅子から立ち上がった。
◆ ◆ ◆
正月休みに久しぶりに孫を連れて帰ってきた息子の鞄に入っていた四冊の本を目の前にして、私はしばしの間、腕組みをしたまま立ち上がることができなかった。先日、息子と電話で話した時にも話題として出ていたが、私ははっきりとその気がないということを伝えていたはずだった。
しかし、どうやら息子はまだ諦めていないようだ。それどころか、その本気度はさらに上がっているようにさえ見受けられる。
恐らく、車のキーを鞄に入れっぱなしにしていたのもわざとなのだろう。
それを私が確認するように仕向けたのも計算ずくのはずだ。
私にこの四冊の本を見つけさせることが狙いだということは、火を見るよりも明らかだった。
少なくとも息子は、四冊もの本を常に持ち歩いて、同時に読みこなすことができるような読書家ではない。
自分の息子ながら、このようなあざとい部分には辟易する。
年齢的に考えれば、近い将来、必ず私の方が先に逝くのだから、残された母さんのことはよろしく頼む。
ここ数年、私は酒の力を借りてはそんなことを繰り返し息子に告げていた。息子も息子で、そんな私の気概を感じてくれたのか、どうせ転勤のある仕事なのだから早い方がいいと言って、会社に転勤希望を出していた。
一度、地方に転勤に出てしまえば、少なくとも四、五年はあちこちを転々とすることになる。でも、それほど支社が多いわけではないので、いずれ必ず帰ってくることができるだろう。家はそれまで貸しておけばいい。ローンくらいの家賃にはなるだろうから。そう言って息子が妻子を伴い地方に赴いたのは、ちょうど一年前のことになる。
それから僅か半年後の出来事だっただけに、その点だけは私も申し訳ないと思っている。思っているが、それを差し引いても、この仕打ちはいかがなものか。何か他にできることが、あるはずだ。
息子にしかできない親孝行が、他にあるはずだ。
せめてもう少し、孫の顔を見せに来てくれてもいいだろう。
彼らが転勤する前は毎週のように顔を見ていただけに、盆と正月くらいしか孫に会えないという現状は、あまりにも落差が激しすぎる。何も会社を辞めてこちらに帰ってきてくれと言っているわけではないのだ。
いや、何なら、そうしてもらっても構わない。
どうせ長くはない命なのだから、貯蓄など残しておいても仕方がない。
息子が次の仕事を見つけるまでの彼らの生活費とローンの返済分くらいは、いくらでも工面できる。
息子だって、35にしてすでに二度も転職を経験しているのだから、今さらそれがもう一度増えたところで何ら差し支えないだろう。
子どもが小さいうちに転勤を済ませておきたいからちょうど良かったなどと言っていたが、それなら最後の転職をするのだって、子どもがまだ小さい今のうちのはずだ。
そう思いつつも、もし自分が息子と同じ境遇だったら果たしてそこまでするだろうかと考えると、決して大きなことは言えなくなる。
孝行息子だったかと問われれば、大手を振って「はい」とは答えられない。
特に親不孝を働いたつもりはないが、次男という立場もあって、何かにつけ「出来る限りのことは」などと言って兄や姉に任せてきてしまった事実は否定できない。
しかしそれは、ある意味では役割分担だった。
私は兄弟の中では比較的、稼ぎが良かったこともあって、特に金銭的な援助はかなり請け負ってきた。実際に、出来る限りのことはしてきたつもりだ。頻繁に顔を出さなかったからといって、文句を言われる筋合いはないだろう。
もしかしたら、この四冊の本には、息子の「親父、オレはあんたのことをこんなに考えているんだぜ」という自己満足全開のプレゼンテーションの意味合いもあるのかも知れない。
人のことなど言えた義理ではないということか。
「そうですね。息子さんの場合、多分に自己アピールが含まれているように感じます。私にも似たような友人がいますので、何となく分かる気がします。」
すぐ目の前から発せられた突然の言葉に、私は思わず驚いて顔を上げ、背筋を伸ばした。
正面のソファに腰を下ろした男が、手にしたコーヒーカップを自分の口元に運ぼうとしているところだった。
◆ ◆ ◆
私の目の前に座っているのは、昼過ぎに中庭で出会った青年だった。
その後、食堂でしばらく話をしていたあの青年だ。
確か、奥さんがここで看護師をしている。
私が午後の検診を終えてロビーに戻ると、彼は最後列のベンチシートに腰を降ろしていた。ただし、数時間前に会った時とは服装が違っていた。
ベースボールキャップも被っていなければ、ダウンジャケットも羽織っていない。色褪せたショルダーバッグも持っていない。スーツ姿に、なぜか子ども用の傘を手にしている。
聞けば、一度は家に戻ったのだけれど、急な仕事が入って外出しなければならず保育園に子どもを迎えに行くことができなくなってしまったため、予報通り天気が崩れることを想定して奥さんに雨具を届けに来たのだそうだ。
私は、会釈をしながら「それでは」と言って玄関の方へと向かう彼を呼び止めた。そして「お仕事はこのあとすぐ?」と聞いた。
「いいえ、まだ少し余裕はあります。」と答えた彼に、「もう少し、お話させてもらってもいいかな?」と言って、施設の一角にあるちょっとした応接間のようなサロンへと彼を案内した。
午後の検査前、青年と話をして随分と不思議な気分を味わっていただけに、自分でもなぜこのような行動に出たのか分からない。
◆
私は、改めて座っていたソファから背中を離し、背筋を正した。
そして、「失礼。こんな身内の陰口のような話ばかりでは、聞いていてもつまらないでしょう。お恥ずかしい。」と言って、両手を膝の上に置きながら腰から頭を下げた。
なかなか聞き上手というか、相手に話をさせるのが上手な青年だ。つい夢中になって、彼がいるのも意識せずに喋り続けていたようだ。
元来、私は身の上話を他人に聞かせるような人間ではないのだけれど、どうしても止めることができない。
青年は「そんなことはありません。」と言いながら、顔の前で手を左右に振った。
「恐らく私の父と同じ世代だと思うので、参考になります。どうしても自分の父とは上手く話せないので、こういうところで少しでも父と年齢の近い方の話を聞くことができるのは、とても助かります。」
やはり、この青年は私の息子と同じくらいの年齢のようだ。
30代半ばにしては、やや若く見える。相変わらず抑揚の少ない感情を抑えた話し方ではあるものの、午前中の印象に比べると、青年を取り巻いている空気がずいぶん柔らかく感じられるようになった。
「でも、こちらにいらっしゃるということは、息子さんの提案を受け入れたのですね。」
「まだ、半信半疑ですが。」と言って、私は苦笑いを浮かべた。
そして、自分が座っている周囲をくるりと見回してから、続けた。
「息子の熱意にほだされたというのもあるんだけど、しっかり調べてみれば、ここは決して怪しい施設ではないということが分かった。まあ、いわゆる『溺れる者は藁をも掴む』というやつですよ。」
「ところで、こちらには入院ですか?」
「いやいや」と言いながら、今度は私が自分の顔の前で手を左右に振った。
「通いですよ。現在は週に二回。ただ、ここに来る時は朝から晩まで目いっぱいで息が詰まる。きちんと家でも生活を守っているか、徹底的にチェックされますから。ホスピスみたいに、手厚くなんて扱ってくれない。」
通常医療と並行して治療を受けていますからね。そう私は付け加えた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
