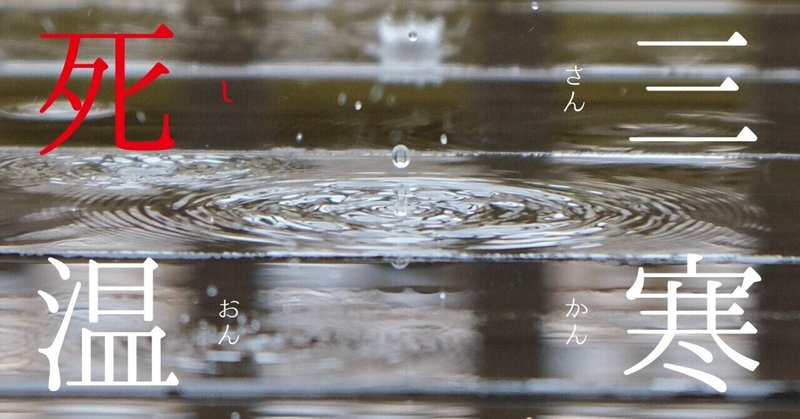
長編小説【三寒死温】Vol.12
第二話 律儀な看護師の旦那
【第四章】数え上げたらキリがない
それは、私に孫ができて一年ほど経ったある日のことだった。
息子夫婦の間に生まれた一人娘は、我々にとって初孫ということもあって、新しい命の誕生を私も妻も大いに喜んだ。
紆余曲折はあったものの、結果として息子夫婦は私たちの家から車で15分ほどの場所に家を購入していたおかげで、私も妻も気軽に孫の顔を見ることができた。息子の嫁さんも非常に気が利く娘で、生まれてから半年くらいでハイハイの真似事ができるようになってからは、毎週のように孫娘を連れて会いに来ていたのだ。
今、考えれば、その日はいつになく酒量が多かったような気がする。
そんな話をしようと前以て意識をしていたわけではないのだが、私は気がつけば、普段から思い描いていた孫娘の将来についての考えを口にしていた。そして、ふとついて出た私の「お受験でもしたいのなら、いくらでも援助する。」という言葉に対し、息子が「そんなのするわけないだろ。」と鼻先であしらうかのように言い放ったのが、きっかけだった。
そこに私は、明らかな侮蔑の感情を読み取ったのだ。
「まだ早いかも知れないが、それくらいのことは考えておきなさい。」
私が語気を強めると、息子は私を上回る強い口調で返してきた。
「早いとか遅いとかではなく、俺たちは私立の幼稚園とか小学校に行かせるつもりはないから。そういう余計な口出しは勘弁してくれ。」
息子の嫁さんの方をちらりと見ると、彼女は苦笑ともとれる表情を浮かべながら、孫娘を抱っこしている。
「今からもう、そんなことを決めているのか?」
息子は面倒くさそうに「ああ。」と返事をした。
そして小さくため息を吐いてから、
「俺も彼女も公立育ちだっていうのもあるかも知れないけれど、私立はまったく考えていない。もちろん、この子が大きくなってそれを望めば話は別だけど。」と言った。
「これからの教育は、ますます競争が激しくなるんだぞ。早いうちに終わらせておけば、その後、無駄な競争をせずに済むんだ。」
「もちろん、俺たちがモロに競争社会の世代だから、良く分かってるよ。でも、二人で話して決めたことだから。」
「分かっているなら、少しでも早いうちに競争原理の輪の中から救い出してやるのも、親の役目なんじゃないのか?」
「それはどうかしらねえ。若いうちの苦労は買ってでもしろって、言うじゃないの。」と横槍を入れてきたのは、私の妻だった。
「母さんは黙っていなさい。お前はそう言って、こいつの時にも中学受験に反対したな。」と言って、私は息子を指差した。
「別にお袋が賛成していたって、俺は私立なんて行く気はさらさらなかったけど。」
「まあ、昔の話はどうでもいい。」と私が言うと、妻が「自分から蒸し返したくせに、都合のいいこと。」と呟きながら台所へと消えて行った。
息子は男だったから、当時の私は二人の言い分に折れる形で彼の私立中学の受験を諦めた。理想論ではあるが、苦労にもまれてこそ逞しく成長するという理屈も分からなくはない。
しかし、孫娘の場合はそうはいかない。女の子なのだ。いずれ家庭に入るのなら、何も逞しく育つ必要はない。今から目指せとは言わないが、当然の選択肢の一つとして私立への進学も持っておくべきだ。
「小さい頃の競争は、ある程度はあっていいんじゃないかな。まだ小さい頃なんて自分の価値観そのものがハッキリしてないだろう。物事の良し悪しを判断できる材料が自分の中で確立されていないうちは、自分を知ったり自分を見出したりするのに、周りと競争することだって重要だと思うよ。」
そう言って嫁さんと目配せをする息子を見て、どうにもやるせない失望感が湧き上がってきた。
いいように丸め込まれていると言っては大袈裟かも知れないが、果たしてどこまでが息子自身の信念なのかは甚だ以って疑問だ。
私は、日本酒の入った猪口を持ち上げながら言った。
「しかし、競争なんて意味がないということを肌で知っているのも、お前たちの世代のはずだろう。」
「大人になれば誰だって、例えば人と比べていい学校を卒業したからって、人生うまくいくとは限らないとか、人と比べて稼ぎがいいからって、それが幸せにつながるかというとそうとも限らないとか、自然と分かるようになるじゃん。それでいいと思うけど。」と言って、息子はコップに残っていたビールを一息に空けた。
「それが分かっているからこそ、その無意味さを前もって教えてやるんじゃないか。特に今の時代は、女の子でも男の子と変わらず進学して社会に出ていく世の中なんだ。現実問題として、競争に敗れて落伍する者は必ず出てくる。何とかして、自分の子どもにはそうなって欲しくないと思うのが、親なんじゃないのか?」
「そりゃあ思ってるさ。当たり前だろ。でも、人に言われて『はい、そうですか』って理解できるものかね? それなりに経験して、争いごとに勝ったり負けたりして、初めて実感できることじゃないの?」
確かに、人には自分で経験したことしか実感できないという側面はある。
でもだからといって、わざわざ失敗や挫折を味わわせることはない。
世の中には、やってみなければ結果は分からないと言う人間も多いが、そんな連中に限って、非常に物事を楽観視する傾向にある。失敗した場合のリスクヘッジがまったくなっていないのだ。
私からすれば、そんなものは寛大を装った綺麗事でしかない。
聞き分けが良い振りをした無責任でしかない。
我々大人は、子どもと違って物事の成り行きに対して、ある程度の予測を立てることができる。それは、上手く進んだ時のためではなく上手く進まなかった時のための切り札となるはずだ。
成功を期待するのはもちろん構わないが、失敗した場合をどの程度まで想定して動いているかで、その後は大きく変わってしまうのだから。
氷河期を理由に大した就職活動もせず、フリーターなどと抜かしてその日暮らしをしているような世代の者たちには、それでも結果的に何とか食つなげてしまっているという現実が邪魔をして、どうにも危機感が足りないように感じる。
「まあ、そう言われればそうかも知れんが・・・」
息子は、孫娘の顔を見ながら呟いた。
大層なことを言っていた割には、心が揺れ動いている。やはり、必ずしも確固たる自信に基づいた深慮を経ての結論ではないのだろう。
「特に女の子の場合は、俺たち男よりもさらにいろいろな危険がある。そこはもっとしっかりと、将来の道筋を考えてやらなければいけないんじゃないか?」と言いながら、私は息子、孫娘、そして息子の嫁へと視線を移した。
すると、相変わらず笑顔を絶やさない息子の嫁が、そんな柔和な表情にはそぐわないはっきりとした口調で言った。
「でもお義父さん、私たち大人はどうして、物事の成り行きに対して予測を立てることができるんでしょう?」
普段、息子の嫁はあまり自分の意見や主張を表に出すタイプではなかったので、私は驚いて言葉を紡ぎ出すことができなかった。
「それは、私たち自身が成功も失敗もいろいろと経験したからこそ、その線引きができるようになるのではないですか?」
「それはそうだが・・・」
「大人が教えてあげるべきなのは、争っても無駄なだけだから争うなっていうことではないと思います。争った結果、勝った時には勝利なんて虚しいだけだって教えてあげればいいのだと思います。負けた時には、逃げることも世の中じゃ大切なことだって教えてあげればいいのだと思います。」
知ったような口を聞いているが、理想論も甚だしい。机上の空論だ。
これがもしかつての部下だったら怒鳴りつけているところだが、ここではそうもいかない。
私は、あえて大口を開け、声を出して笑って見せた。
「口で言うのは簡単だけど、難しいよ。」
「別にそうでもないわよ。覚悟さえあれば、大したことじゃないわ。」
またしても横槍を入れてきたのは、瓶ビールを二本持って台所から戻ってきた妻だった。
「まだ子どもが生まれたばっかりのこいつらに、覚悟もへったくれもないだろう。」
「あなたが思っている覚悟とは、少し違うかしらねえ。」と言って、妻は息子の嫁の方をちらりと見た。
「覚悟に種類なんてあるのか?」
「何が何でもやり遂げる! なんていう覚悟じゃないわよ。仕事とは違うんだから。」
息子の嫁さんも、同じように妻のことをちらりと見返した。
「何があっても受け入れるっていう覚悟のことを言ってるのよ。上手くいかなかった時のことを考えろなんて言ったって、それすら思い通りになんていかないもの。子育てってそういうものよ。」
「だからと言って、細かいことまで考えておくことに、越したことはないだろう。」
「その割には、私にはずいぶん大雑把な一般論にしか聞こえませんでしたけど。リスクヘッジだの危機感だのと難しい言葉を使って、さも尤もらしいことを言ってるけれど、それじゃあ具体的にどうすればいいのかしら?」
そう言いながら妻は、息子と自分の空いたグラスにビールを注いだ。
すでに日本酒に移っていた私の猪口も空いているのだが、誰も徳利を持ち上げる者はいない。
「何があっても動じないで、どっしり構えていてあげればいいのよ。」
息子の嫁さんが相槌を打ちながら笑顔で聞いているからだろう、饒舌になった今日の妻の口はなかなか塞がらない。
「こっちが『大丈夫よ』って顔していれば、子どもは勝手に育つんだから。」
「そんなもの、親の責任放棄ではないのか?」
「どうせ親は子どもより先に死ぬのよ? 孫なんてなおさらでしょう。そもそも自分が死んだ先まで責任なんて持ちたくないわよ、私は。」
「しかし、若者を正しい方向へ導くのは、私たちのような年長者が果たすべき使命だ。」
「その台詞、この子が小さかった頃に聞きたかったわ。定年退職して暇になった途端、そんなこと言い出されてもねえ。」と言って、妻は息子の頭をこつんと小突いた。
「正しい方向なんて、時代によって違うしな。」と言って、息子は妻に小突かれた頭を掻きながら笑った。
「その通り。私だって、あなたの親や自分の親に言われたことをすべて受け入れてきたわけじゃないもの。」と言いながら、妻はようやく徳利を持ち上げ、私の猪口に注いだ。
ただし、しっかりと嫌味を添えることも忘れなかった。
「あなただって、私の親の言うことなんて一つも聞かなかったじゃない。」
それは妻の親の言っていることがあまりにも時代にそぐわない意見だったからだ。私はあくまでも、今後の未来を予想して意見している。
そう反論しようとしたが、それよりも妻の言葉の方が早かった。
「こっちから『ああしろ、こうしろ』なんて言わずに、困った時に頼ってこられる存在でいれば、それで十分なのよ。」
「親の役割は、レールを敷いてあげることではなくて、レールを直してあげること。お義母さんがおっしゃってるのは、そういうことですか?」と言ったのは、息子の嫁だった。
「あら、上手いこと言うわねえ。そんな感じよ。」
「親父の言う落伍者って、どういう人のことなわけ?」
ビールをあおりながら息子が言った。
「いろいろだろうな。世の中には、いろいろな意味でドロップアウトしてしまう者がいる。定職にも就かずに引きこもられても困るし、犯罪者なんてもってのほかだ。女性も社会進出している時代だが、それでもやはり、子どもを産めるのは女性だけに与えられた特権だからな。その権利を放棄するなんて・・・」
「お父さんにそんなことを聞いても無駄なだけよ。数え上げたらキリがないんだから。」
私の言葉を遮って、妻が言った。そして、
「どうせ、お父さんの『こうなって欲しい』を延々と聞かされるだけ。アンタの時と一緒よ。子どもの将来のために、なんて言ってるけど、そうじゃないの。自分の理想通りに育った子どもなり孫なりを持つ自分の『未来予想図Ⅱ』なのよ。」と続けた。
何ていうことを言うんだ、と大声を張り上げようと息を吸い込みかけたが、今度は「お義母さん、ドリカム聞くんですか?」という息子の嫁の言葉に、一瞬だけ先を越されてしまった。
私を除く三人が、一斉に大きな笑い声を上げる。
その音量があまりにも大きかったからか、母親に抱かれてうつらうつらしていた孫娘が驚いて泣き出してしまった。
慌てて息子の嫁が立ち上がり、二階へと上がってゆく。
このまま私が黙っていると、話自体も終わってしまうのは明白だった。
何をしていようとも優先されるのは、孫娘のコンディションだ。
しかし、魚の骨が喉につっかえてしまったような感覚は如何ともし難く、続けるのは野暮だと思いながらも私は話を続けた。
「別に俺は、自分の理想を押し付けているつもりはない。」と私が言うと、息子が呆れ果てたようなため息とともに、ぼそりと言い放った。
「もういいだろう。親父の言いたいことも分かるけどさ、どうせ俺も親父も大した人間性なんて持ち合わせちゃいないんだし。」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
