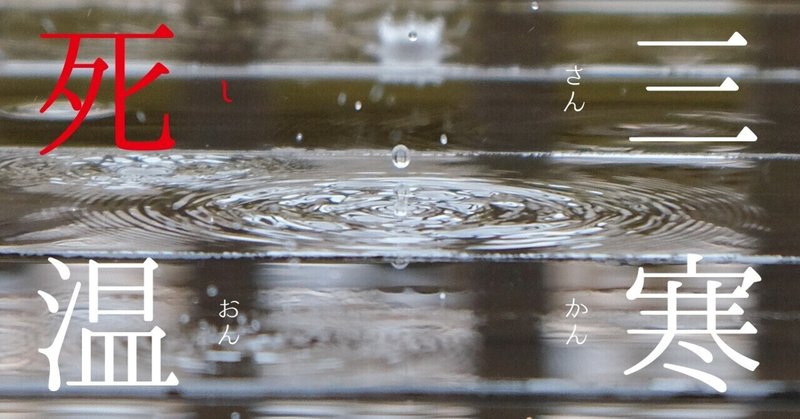
長編小説【三寒死温】Vol.15
第二話 律儀な看護師の旦那
【第七章】いい人、いい人、どうでもいい人
最初のうち、私は青年の顔をじっと見て話を聞いていた。
しかし、気がついた時には、目の前にある木目調のテーブルに視線を落としていた。そして真っ先に目についた黒い節の、幾重にも重なる丸い模様をじっと見つめていた。
痒みを覚えてその場所を掻いてもどうもすっきりしない、痒い場所は正しいはずなのにうまく掻くことができない、そんな内側から感じる痒みのように、全身がこそばゆい感覚に襲われていた。
私の視線や表情が変化したのを察知した青年は、「話が長くてすみません。正確ではないかも知れませんが、覚えている限りの話の内容だけ、簡潔に再現しますね。」と断りを入れてから、話を再開した。
◆
「端から条件に合わない施設まで入れて、数だけ集めて必死アピールか?」
「そう言うなよ。」
「北海道に呼び寄せるとかしないの? 親父さん、一人暮しなんだろ?」
「そりゃムリだよ。子どもだってまだ小さいのに、かみさんに親父の世話までさせるわけにはいかないだろう。」
「どうして子どもの面倒も親父さんの面倒も、全部奥さんだけが見る前提なんだよ。手分けするって選択肢はないのか?」
「仕事をしている身としては、限度があるじゃないか。結局、一番大変な思いをするのはかみさんになるんだからさ。」
「奥さんとは話をしたのか?」
「いや、してない。話題にするだけでも険悪になっちまう。」
「それは奥さんだって、お前が家のことに参加する意思がないって分かっているからだろ?
どうせ全部、自分に押し付けられるって分かっているからだろ?」
「まあ、そういう部分はあるかも知れないけど。そもそも、親父だって今さら見ず知らずの土地に行って余生を過ごしたいなんて思わないさ。」
「親父さんとは話をしたのか?」
「いや、してないけどさ、それくらいは分かるよ。」
「親父さんとはまだ何も話していないのか?」
「そんなわけあるか。親父が気に入りそうな施設はきちんと見つけるからって、言ってあるよ。困ってることとか、不便なこととか、あとは施設に希望する条件とか、いろいろ話しているよ。いつでもいいから遠慮せずに、何なりと言ってくれって。それに、このパンフレットだって全部二冊ずつ取り寄せて、親父にも渡してある。」
「なるほど。で、親父さんはなんて?」
「こんなもん見ても何も分からんってさ。言うだけ言って、俺にどうしろって言うんだって、ちょっとキレられたな。」
「そりゃそうだろうな。激しく同意だ。」
「どういうこと?」
「その言葉通りだろ。
口動かすだけじゃなくてお前も体動かせってことだよ。」
「もちろん、もう少し絞り込んだら、実際に行って見てみるつもりだよ。」
「そんな当たり前の話じゃない。そもそも、施設に入るも入らないも、どこに入るも、そんなことは最終的に親父さんが決めることだろ?」
「こんなところで油売ってねえで、こっち帰ってきてる時ぐらい早く顔見せてやれって?
これでも、毎晩、メールでやり取りするようにはしてるんだぜ?」
「だからそうじゃないって。お前は確かめなくても分かるって言ってたけどさ、親父さんとしては、少しでもいいからお前たちに面倒見てもらいたいんじゃないの?」
「それはないだろう。昔から『寝たきりになっても子どもの世話にはならない。施設でも何でも入れてくれればそれでいい。それくらいの老後の蓄えはある』なんて豪語していたような親父だぜ?」
「実際にそうなってみたら、変わるんじゃないの? 寝たきりとまでは言わないけれど、それでも自分ではできないことが増えていったら。」
「そんなことは、ないだろう。」
「五体満足で元気に過ごしていた頃の言葉なんて、当てにならないと思うけどなあ。」
「そう簡単に考え方なんて変わるものか?」
「例えばお前は、実際に社会に出る前と後で、仕事に対する考え方とか変わらなかったか? 結婚にしろ子どもにしろ、経験する前に思い描いていた通りだったか?」
「・・・」
◆
息子の言動を少しでも理解するための手助けになれば。
その程度のつもりで聞いていた青年の話が、いつの間にか、他人ごとではなくなってきていた。部分的ではあるにせよ、自分にも当てはまる話になってきてしまっていた。
この青年には話していないはずの、息子に対する私の要求や憤りまでもが、彼の友人の父親と驚くほど合致している。
私は何とも形容のしがたい居心地の悪さを感じ始めていた。
「すみません。置かれている状況の深刻さはまったく違うので、参考にはならないと思うのですが。」
私のテンションの下がり方を少し勘違いしたらしい青年は、そう恐縮して一呼吸おいてから、話を続けた。
「どことなく、僕の友人と息子さん、似ているようなところがあると思いませんか? 僕の友人は、何かにつけて『できない』という言葉を多用するんです。話をする前から『ムリ』だと決めつけてしまう。
全身を理論武装でがちがちにガードしながら大層な正論を繰り出すんですが、その割に、発言に見合うだけの行動が伴わない。あらかじめもっともらしい言い訳を用意して、何も動こうとしない。」
まるで自分と息子の会話のように思えるこの青年と彼の友人のエピソードが、少しずつ少しずつボディブローのように私の体を痛めつけてゆく。
真綿で首を絞めるように、じわりじわりと私の心をえぐっていった。
「そうだね。私の息子も同じようなもんだ。確かに、似ているよ。」
そう声に出すのが、私には精いっぱいだった。
「例えば僕の友人は、家を建てる際に会社から借金しているので、仕事を辞めることはできないと言います。そんな無責任なことはできないと。
でも、今どき住宅ローンの借り換えなんて日常茶飯事ですよね。それで一括返済すれば問題ないはずです。社内融資ですから手続きは面倒かも知れませんし、退社する意向を知られたら金融機関の審査も通りづらいかも知れない。でも、できないことはありません。
それは端からその気がないだけで、『できない』とは違いますよね。比較検討していないどころか、下調べすらしていないんですから。無責任と言いますけれど、そもそも誰に対しての、何に対しての無責任なんでしょう?」
もう、彼の友人のことを言っているのか、私の息子のことを言っているのか、それとも私自身のことを言っているのか、区別がつかなくなっていた。
「挙句の果てに、僕の友人は『普通、そこまでするか?』と言ったんです。結局のところ、これが本音なのではないでしょうか。このくらいまでやっておけば、誰からも悪いようには言われないだろう、というのが。」
私の反応を窺うかのように、その青年は一呼吸置いてから続けた。
「僕の友人の判断基準は、自分にできるかできないか、ではないんです。
可能なのか不可能なのか、ではないんです。もちろん、相手が望むか望まないかでもない。僕に言わせれば、これは『できない』ではなくて『やらない』です。『やりたくない』です。」
いつの間にか、恥ずかしいという気持ちよりも、怒りに似た感情が湧き上がってきた。
人から下に見られたくない。
だからこそ、他人の粗を探し自分を大きく見せ、正論を繰り返す。
人から好感を持ってもらえるような自信がまるでない。
だからこそ、嫌われ役でもいいと割り切っている体を装い、相手を貶めるような発言を繰り返す。
結局のところ、私はそんな自分自身を嫌悪しているのだ。
そして、そんな自分と同じような言動を繰り返す息子を見て、投げつけるべき場所のない憤りを抱いていたのだ。
分かった。すべてを認めよう。
お前の言う通り、私は、大した人間ではない。
だからと言って、私もお前も、そこまで断罪されるような醜く汚い心の持ち主だろうか?
いや、そんなことは決してない。
多かれ少なかれ、みな似たようなものだろう?
それが人間というものだろう?
「君は、」と言ったところで、私は一つ、咳払いをした。
そして、およそ自分の声には聞こえない、湿り気のある声を振り絞った。
「君は、その友人のことが嫌いなのかい?」
焼け石に水とは思いながらも、私は何とかこの青年に一矢報いたかった。
「そんなことはありませんよ。嫌いだなんてとんでもない。まったくの正反対です。」と言った青年の声は、中庭で最初に言葉を交わした時のような抑揚のないトーンに戻っていた。
ほんの少しでもいい。
最後に、この青年からも何か言い訳のような格好悪い言葉を引きずり出してやりたかった。
しかし、そう上手くはいかなかった。
いや、いかなくて、良かった。
「むしろ、そんな彼だからこそ、僕は今でも友人でいられるんです。」
「そんな彼だからこそ?」
「よく言うじゃないですか。『いい人、いい人、どうでもいい人』って。」
「いい人、いい人、どうでもいい人・・・」
どこかで聞いたことのある台詞だ。
「彼はお世辞にも『いい人』とは言えませんが、僕の周りで誰よりも一番、人間臭いヤツですから。」
曇天の隙間から零れ落ちた小さな雨粒が、吹き抜けに設えられた大きなガラス窓を弱々しく叩き始める。
今日、何度目だろう。心を見透かされたような気分に陥ったのは。
向かいのソファで「しまった、自分の折り畳み傘を忘れた…」と呟く青年に、気づけば私は東風のようなため息を漏らしていた。
第二話(完)/ 第三話へ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
