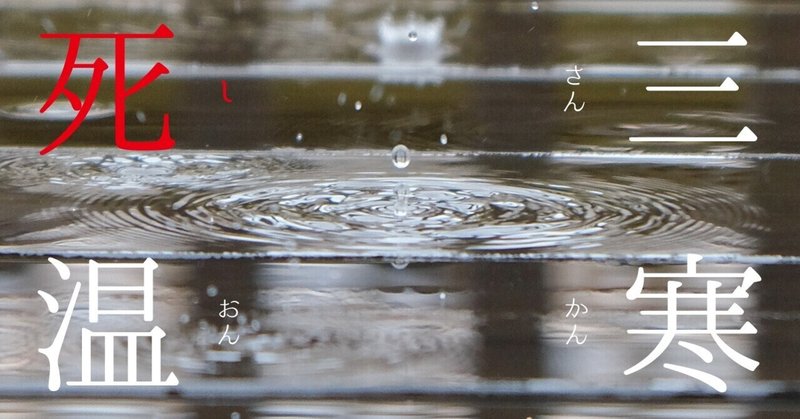
長編小説【三寒死温】Vol.11
第二話 律儀な看護師の旦那
【第三章】「少年A」と呟いていた
私とその青年は、食堂に整然と並べられた簡素な正方形のテーブルの一つに着いていた。それぞれの前には紙コップが置いてある。彼には緑茶を淹れたが、私は白湯だ。
「そのお子さんは、大丈夫だったのですか?」
「脳震盪を起こしただけで、怪我自体は軽傷で済んだみたいです。」
「それは何よりですね。」
その青年は小さく微笑んでから、呟くように言った。
「もしかしたら、その一年生の子をかばって、轢かれてしまったのかな?」
「え?」と言って、私は自分の右耳をその青年の方に近づけた。
正確に言えば、彼の台詞が聞こえなかったわけではない。独り言とも取れるような小さな声ではあったが、しっかり私の耳に届いていた。
しかしなぜか私は、もう一度聞き返していた。
「いたずらっ子の六年生が車に轢かれたのは、その一年生の男の子をかばったのが原因だったのかも知れませんね。」
それは、私の頭の中にはまったくない発想だった。
あの問題児が、下級生、しかも新しく入った一年生のことをかばう?
そんな馬鹿な。
彼の普段の行動を鑑みれば、そんな可能性はゼロに等しい。
人をからかうことしかしない彼が、他の子どもを気遣うような真似をするはずがない。
「先ほどのお話を聞いた限りでは、その一年生の男の子があなたを蹴飛ばしてまで抗議を訴える理由は、それくらいしか考えられません。
目撃していた子どもは他にもたくさんいたはずなのに、その子のほかには誰もそんな反応を示した子はいなかったのですよね?」
私は小さく顎を引いてから言った。
「果たして彼に、助けてくれるような友だちがいたかどうか。みんな関わり合いになりたくないと思っていただけではないかな。」
「例えいたずらっ子でも、友だちはいるはずです。
それに、得てして大人の手を煩わせるような子どもは、同級生から一目置かれるものです。」
確かにそう言われればその通りだが、上級生の子どもたちは、目の前で起きた突然の交通事故にただ単に驚いて、言葉を失ってしまっていただけではないだろうか。
「普通はそうだと思います。びっくりして固まってしまって、咄嗟に助けになんて行けない。小さい子なら、怖くてその場で泣き出してしまうかも知れない。いずれにしても、具体的な行動をすぐにとることなどできるものではありません。
それにもかかわらず、その男の子は明確にあなたを非難し、抗議した。」
「他人が自分をかばってくれたかどうかなど、小学校一年生の男の子が自覚できるとも思えないが。」
「僕にも保育園に通っている息子がいますが、友だちや先生に対しての好き嫌いはもちろん、優しい冷たいとか、怖い怖くないといった感情はしっかり持っていますよ。もちろん、我々大人とは視点が違う場合もありますが。」
彼は、紙コップのお茶を一口飲んでから続けた。
「先日、息子と近所の公園に行ったら、小学校中学年くらいの子どもが一人でサッカーをしていたんです。ウチの子を見つけると、一緒になって遊び始めました。正直、僕から見れば、サッカーどころかボールを蹴ることすら覚束ない小さい子を相手にからかっているようにしか見えなかった。
でも、帰り道で息子は『あのお兄ちゃん、一緒に遊んでくれて優しかったね』と言っていました。僕からは遊ばれているように見えても、息子にとっては楽しい時間だったんでしょうね。
まだ未就学児ですから、相手に対する評価や判断が正しいとは限りません。でも四歳の子どもですら、人の親切に対しては感謝の気持ちを持つし、自分がやらかしたことには言い訳もする。何なら、人のせいにもする。」
「人のせい?」
その青年は、紙コップを手にしたままこくりと頷いた。
「その一年生の男の子も、もしかしたら、自分が引き起こしてしまったかも知れない事の重大さに気づいて、どこかに感情のやり場を求めていたのかも知れません。」
その青年が口にした言葉を何度か頭の中で繰り返してみたが、私には今一つ具体的な想像ができなかった。しかし、だからといって右から左へと受け流してしまえるほど、意味のない言葉にも思えなかった。
どうしてこんなに心に引っかかるのか分からないが、ふんと鼻先で笑い飛ばすような気持ちにはなれなかった。
「ところで、まだスクールガードは続けていらっしゃるのですか?」というその青年の問いかけに、私は我に返った。
「いいえ。その事故をきっかけに、辞めてしまいました。もう一年近く前のことでね。」
「それは残念ですね。」
「いくらこちらが善意でやっていても、いつの間にかそれが普通のことだと思われてしまう。別に感謝して欲しくて始めたわけではないが、『どうでもいい』などと言われてしまっては、やっている方は浮かばれない。」
「小さい子どもがいる身からすると、保護者の方のご意見も分からなくはないかな、という気がします。」
もちろん、無償で奉仕活動している方を悪く言うつもりはないし、それはそれで立派なことなのだとも思う。
しかし、結局のところ大人同士が善意だの責任だのと言い合ったところで、犠牲になるのは子どもだ。結果として怪我をするのは子どもだし、怪我した子を見てショックを受けるのも子ども。
どのような立場であれ大人が結果に責任を持ってあげなければ、子どもは安心して暮らせない。
彼の意見を簡単にまとめると、このような感じになった。
まあ確かに、筋は通っている。
今となって考えてみれば、私の態度にも問題があったかも知れない。
どちらの言い分が正しいか間違っているかという話は置いておいたとして、とても好感を抱かれるようなやり取りでなかったことは事実だ。
「それでも、言っていいことと悪いことがある。思ったからといって、何でも口に出していいわけじゃない。」
「それは確かに。同感です。」
そう言って青年は、大きく首を縦に揺らして何度も頷いた。
これまでのところ、どちらかと言えばかなり抑え気味な反応が多かっただけに、私はそんな彼の過剰とも取れる仕草が気になった。何か、思うところがあるのだろうかと感じて、私は何も言わずに口をつぐんでいた。
◆
しばらくすると、
「実は、少し前に、僕の家の近くに単身者用のアパートが新築されたんです。」と言って、その青年は話し始めた。
「もともとその場所にはごく普通の一軒家が建っていて、お年寄りのご夫婦が住んでいました。僕たちもそのお宅も犬を飼っていたので、よく散歩でお会いしていたんです。広めの庭もあって、犬を遊ばせてもらったことも何度かありました。でもご主人が身体を壊してしまって、数か月後には、ワンちゃんも亡くなってしまった。確か17歳だったから、大往生ですね。
それで、土地を売って息子さん夫婦の家の近くに小さなマンションを買って、引っ越していきました。
更地になってからしばらくは特に動きはなかったのですが、一年くらいしてようやく買い手が見つかったようで。それは、東京の一等地にオフィスを構える聞いたこともない会社でした。最近多い、いわゆる投資型アパートのディベロッパーだったんですね。
着工してから出来上がるまで、あっという間でした。
もちろん、10戸にも満たないような小さな集合住宅ですから、大規模なマンション開発のように近隣住民に説明が必要なわけでもありません。でもそのアパートのお隣さんは、やたらといきり立っていました。
どうやら事前の挨拶に来たのが現場の施工業者さんだけで、そのディベロッパーからは紙面一枚がポストに入れられていただけだったみたいで。
そのお隣さんは、旦那さんが元々公務員だったそうで、自治会の役員をされていました。奥さんも、正義感の塊みたいな方でした。僕たち夫婦が引っ越してきてすぐ、妻がごみを出そうとしたら曜日を間違えてしまったのですが、それを自宅のベランダから大声で『今日は違うわよ!』なんて教えてくれるくらいの。」
そう言ってその青年は苦笑いを浮かべた。
そして再び、紙コップに注がれた緑茶を一口啜った。
「最初は、顔も見せないディベロッパーへの不満から始まった愚痴のはずが、いつの間にか『訳の分からない会社に土地を売っちゃって』なんていう、かつてのお隣さんに対する悪口に発展していました。
実際のところ、そのご夫婦が土地を売ったのは地元の不動産屋で、そのディベロッパーに土地を売ったのもその不動産屋のはずなのですが。
さらに不平不満はエスカレートしていって、そのアパートの管理会社に対して意見書みたいなものを提出する、という話にまでなったんです。
僕たちの家にも来て、署名して欲しいと言われました。両面がびっしり文字で埋まったA4くらいの書類を持って。その内容自体は、近隣住民だったら当然のように感じる不安要素に対してしっかり配慮してくださいというもので、決して間違ったことは書かれていなかった。
でも、『夜間の騒音には十分に注意させるように』とか『路上駐車は絶対にさせないように』とか、そんな項目も入っていました。とてもではないですが、僕たちは署名できませんでした。」
「それはどうして? 主張して当然のことではないですかな?」
「だって、騒音に関しては『明日は我が身』ですから。
今のところ、僕たちがご近所さんに迷惑を掛けるほどの物音を出すことはないですが、いかんせん我が家には小さい子どももいれば飼い犬もいる。いつどうなるか分からない。
それに、すぐ近くには、毎日のように大声で怒られている男の子がいる家もあれば、通行人が家の前の路地を横切っただけで吠え立てるような小型犬を飼っている家もある。夏になると、夜な夜な店先でご近所さんと宴会を始めるお惣菜屋さんもある。誰も、自分のことを棚に上げて人様に『騒音を出すな』なんて言えません。
路上駐車にしても一緒です。僕の家の周りは駐車禁止ではないため、自分の家の前だけでなく、広めの一角などもご近所さんの家に遊びに来る方々の駐車場代わりになっていまして。それこそ僕たちが引っ越してくる前からずっとそうだったみたいで、誰もがそれを黙認しているような状態です。
既に住んでいる人たちが堂々とやっていることを、新しく来る人に対しては『気をつけろ』なんて要求できますか?
どこにも説得力なんてありません。」
彼の話を聞きながら、私の息子が家を買う時にも、似たような話をしたことを思い出した。その土地が代々どのように使われてきたかを調べることや、いわゆる地盤の強度や周囲の土地との高低差といった地理的な条件を確認することはもちろん、会社や倉庫、単身者用アパートの近くはやめておきなさいとアドバイスした覚えがある。
夜間に人がいない建物が隣接していると、若者のたまり場になりやすいだけでなく、不審者に隠れ家として悪用されてしまう可能性もある。だから、日中の様子だけでなく夜の雰囲気もできるだけ見ておくようにと。
単身者用のアパートに関しては、もはや説明も不要だろう。
つい先日もおぞましい事件が起きたばかりだ。どんな連中が暮らしているのか分からない。奥さんや子どもが何かの事件にでも巻き込まれた日には、目も当てられない。
「そのような理由から、私は署名できませんとお話ししたんです。それでもずいぶん説得されましたけど、最後には、我々の『自分たちのことを棚に上げて』という気持ちも理解してくれたようで、納得はしていただきました。ただ、その奥さんは話をしている途中にこう言ったんですよ。
『だって、【少年A】みたいな人に来られたら、お宅も嫌でしょう?』」
私は、この青年に自分の心の中を読まれたような気がしてどきりとした。
彼の話を聞きながら、今、まさにその言葉を頭に思い浮かべていたからだ。
息子に対しても、私はその言葉を口に出していたのだ。
私は唾を飲み込んだ。一度では動悸が収まらず、二度、三度と飲み込んだ。それでもあまり効果はない。
気づけば私は譫言のように「少年A」と呟いていた。
「僕も若い頃に、単身者用のアパートで長いこと暮らしていた時期があったんです。一度引っ越しましたけれど、全部で10年近くは一人暮らしをしていたんじゃないかな。もしかしたら、その当時は自分が近所の人たちから『少年A』呼ばわりされていたのかなと考えると、ちょっと悲しい気持ちになりました。」
「そのお隣さんだって、悪気があったわけではないだろう?」
そう言った私の声は、自分でもよく聞き取れないくらいからからに乾き切っていた。きちんと言葉になっている自信すらないほどに。
「それはもちろんです。実際に、そういう気持ちになるのも分かります。小さなアパートを舞台にいろいろな事件が起きているのは、動かしようのない事実ですから。特に年配の方や子どものいる親は心配でしょう。
そのお隣さんの家には、お孫さんもよく遊びに来ていたようですし、心配するなという方が難しい。
僕たちにしたって、不安がまったくないということはありません。」
あくまでも物腰の柔らかい口調を崩さない青年の言葉に、私の動悸は少しずつ収まってきた。
「そうだろう。そのお隣さんの言っていることは正しいと思うがね。」
そう言った私の声も、先ほどまでに比べるとずいぶん言葉らしく聞こえる。
「残念ですが、私の心には響きませんでした。すべては『少年A』という言葉です。」
「確かに、余計な一言という印象はあるが。」
「それでもやはり、相手のことを考えたら言わない方がいいこと、使わない方がいい表現はあるのではないでしょうか。相手のことをよく知らないからこその配慮が。
おっしゃる通り、その奥さんはどこも間違ったことなんて言っていない。それどころか、正論です。でも、正論のはずなのに私の心に響かなかったのは、その『少年A』という配慮のない一言によって、僕がそのお隣さんの人間性に疑問を感じてしまったからです。」
人間性。
私はまたしても、この青年が使った言葉にどきりとさせられてしまった。
かつて、その言葉を浴びせられた自分のことを、思い出したからだ。
どうせ俺も親父も、大した人間性なんて持ち合わせてない・・・
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
