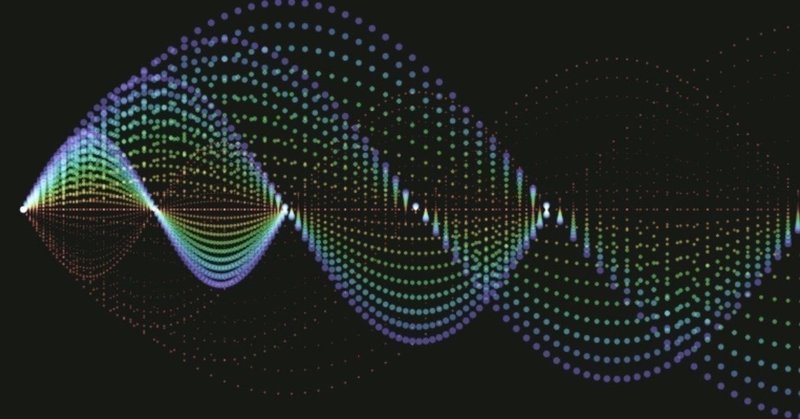
組織を変える力は「経営者」にも「組織そのもの」にもある 【世界標準の経営理論11:ダイナミック・ケイパビリティ理論】
ここまで3回は、「組織学習とイノベーション」というテーマで、イノベーションプロセスを分解して理論を紹介してきた。
第8回 知の探索・知の深化
第9回 組織の記憶理論
第10回 知識創造理論(SECIモデル)
ここでぶち当たる問題は、「イノベーションのプロセスは分かった。だけど、現実にある組織を、どうやって変えていくのか?」ということ。
多くの組織は、「頭では分かっているが変われない」、というのが現実だと思う。
今回は、「組織が変わるために持つべき能力」とは何か?について「ダイナミック・ケイパビリティ理論」とその前提となる「進化理論」を通して考える。
【読解】進化理論
進化理論は、その名の通り、「組織はどのように進化していくか」に焦点を当てている。
そして、進化理論で決定的な役割を果たすのが「ルーティン」という概念である。
ルーティンの定義
繰り返し行われ、しかし状況の変化によって変わることもある、行動パターン
一般的に使うルーティンとの違いを明確にすると、これが、個人の習慣ではなく、あくまで組織・集団が繰り返す行動パターンである、という点である。
またポイントは「行動」である点だ。無意識に組織に埋め込まれており、社員が疑問も思わずに繰り返している「行動」である。
ルーティンという一見ネガティブな印象も受けるが実際にはルーティンは組織にとって非常に重要な役割を果たしている。
ルーティンの効果
①安定化 :業務・行動プロセスが平準化され、社員の仕事への目線が揃う
②記憶 :ノウハウなどが社員に体得されていく
③進化 :余裕が生まれるので、新しい知を受け入れられるようになる
特に③進化は、イメージとして持っていたルーティンとはかけ離れた効果であるが、よくよく考えてみれば当たり前の話である。
「考える余裕」、「探索する余裕」を生み出しているのは、業務がルーティン化することで余計な時間を減らせているためである。
つまり、進化理論の「ルーティン」が意味する最も重要なことは、「進化・変化のためにこそルーティンが必要であり、むしろ進化を促すようなルーティンで出なければならない」ということだ。
本書では良品計画のMUJIGRAMというマニュアルが紹介されているが、このマニュアルは「常に改善する」姿勢を行動パターンとしてルーティン化されているそうだ。
--
ルーティンによる組織の変化の特徴を一言で言えば、「組織は急には変われない」ということだ。漸進的であり、経路依存性があり、また硬直化しやすい。
つまり、急激に組織を変えることはそもそも難しい、ということである。
では、どうすればこの変化の激しい時代に組織は変わっていけるのか。
その例としてあげれているのは、アメリカの新聞社でデジタル対応に成功したケースだが、要は、組織を切り離し、責任者もIT企業出身者にした、という話である。
つまり、組織を急激に変えたければ、ルーティンを根こそぎ変えるしかない、ということだ。
この結論は、以前紹介した「両利きの経営」に重なる話である。
【読解】ダイナミック・ケイパビリティ理論
ダイナミック・ケイパビリティ理論も進化理論同様、「企業の変化」を説明する理論だ。
実際、多くのグローバル企業が事業環境の変化に合わせて大きく業態を転換し、生き残ってきた。そのまた一方で、変化できず潰れてしまった会社も数多くある。
その違いは何か?というのを説明するのが「ダイナミック・ケイパビリティ」であるが、本理論は、2回目で紹介した「RBV」と「進化理論」が土台となっている。
ダイナミック・ケイパビリティとは、「急速に変化するビジネス環境の中で、変化に対応するために内外の様々なリソースを組み合わせ直し続ける、企業国有の能力・ルーティン」であるとされており、大きく2つの考え方が提示されている。
①センシングとサイジング
一言で言うと、「知の探索」をすると言うことであるが、そのための仕組みづくりとして、IBMとアマゾンの例が紹介されている。
IBMは各部門のマネジャークラスを戦略部門に配属させて戦略立案に関わらせ、一方で各部門と連携して共同で問題解決や戦略的意思決定をするプロセスを組み込むなどをした。一方で新しい事業機会に対して、既存部門から独立した組織でリーダーシップや予算が確保され、投資活動などを行なった。
アマゾンは、社内のカニバリを積極的に推奨する文化があり、既存事業を潰すことを社員に要求しているそうだ。恐ろしや〜
--
②シンプルルール戦略
「変化の激しい環境下で企業がダイナミック・ケイパビリティを発揮するには、数を絞ったシンプルなルールだけを組織に(ルーティンのように)徹底させ、後は状況に合わせて柔軟に意思決定をすべき」と言う考え方だ。
例として紹介されているのは米インテル、米シスコ、デンマークの玩具メーカーのレゴである。
インテルは、1980年代に日本の半導体メーカーが低価格戦略で世界市場を席巻し始め、事業環境が急速に変化した時、インテルは「メモリーの粗利率が下がってマイクロプロセッサーの粗利率が上昇するなら、マイクロプロセッサーを増産する」と言う極めてシンプルなルールだけを組織に徹底させることで、効果的な資源配分を行うことに成功した。
シスコは、「買収先企業の従業員は多くても75人まで、うち75%はエンジニア出なければならない」と言うシンプルなルールを買収先の選定基準として徹底した。
レゴは、「子供が本当にその製品を使って、楽しみながら学べるか」「親が認めてくれるものか」「子供の創造性を刺激するものか」と言った限られた事業選定のルールがある。
--
ダイナミック・ケイパビリティのここまでの研究からは、変化をさせる力が、①センシングとサイジングのように、少数の個人(経営者)に宿るとする考え方と、②シンプルルール戦略のように、組織のルーティンに埋め込まれるという考え方、の2つに大別される。
そして、学術的にはこの2つの関係性は解き明かされておらず、組織の変わる力=ダイナミック・ケイパビリティは未完成理論であり、今尚世界中の経営学者が研究を続けている。
組織を変える力は「経営者」にもあり、「組織そのもの」にもある
昨今、会社をはじめとして自分が所属している組織を変革したいと考える人はとても多くなってきているように思える。
また、CX(Corporate Transformation)なる概念も生まれるほど、その社会的要請も高まるばかりだ。
しかし、多くの、ほぼ全ての人がぶち当たるのが、「どうやったら組織は変われるか?」ということだと思う。
ダイナミック・ケイパビリティ理論は、そのヒントを提供してくれる。
よく耳にするのが(私自身の声も含め)、「トップがビジョンを示さなから変わらない」「人事制度が柔軟ではないから、イノベーションが起こせない」など、、変われない理由をボヤキがちだ。
そうしたボヤキについて、進化理論とダイナミック・ケイパビリティ理論からみてはっきりしていることは、以下の点である。
組織は急には変われない。
しかし、「経営者」次第で組織は変わり得るし、また、ゆっくりとかもしれないが、ルーティンを埋め込むことで「組織自体」が自律的に変わり得る。
ただし、仮にこれからの社会の変化のスピードが速くなるとすると、ルーティンによる変化でそのスピード感についていけるのか?と言った疑問は残る。
また個人個人が望む成長スピードも異なるし、以前よりキャリアの選択肢の柔軟性が高まり続けている昨今、「なかなか変わらない組織」を見限る人は今まで以上に増えていくだろう。
そして、その分「変われる力を持っている企業」が魅力的になっていくことも予想できる。
いずれにせよ、あらゆる手段を講じて、企業は変化する力(ダイナミック・ケイパビリティ)を身につけていく必要があると思われる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
