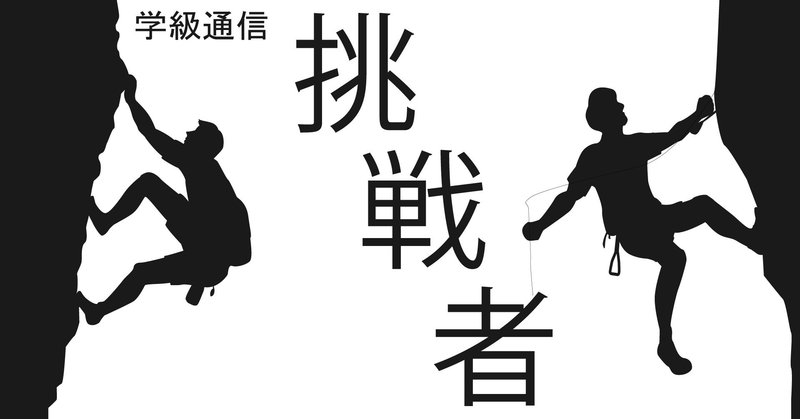
特別支援教育(担任の独り言)
※学級通信「挑戦者」vol.178(2015年3月10日発行)より
かつて高校1年生の担任だったとき、ほぼ毎日発行していた学級通信には、「担任の独り言」という欄を設けて、自分の日常がらみの話をつらつらと書いていました。
以下は、週末に道高教組の定期大会に参加したあとの発行日の独り言です。
担任の独り言
こないだの土日。某大きな会議に参加してきた。いろいろと印象深い話はあったのだけど、ちらほら新聞とかにも出る「特別支援教育」ってことについて”みかた” を変えないとねって話がとりわけ印象的だった。
ってのは、別に教育の方法とか体制とかって話ではなくて、これからの社会が向いていって欲しい姿、一人ひとりが人として尊重されて、健康で文化的に暮らしていける社会になるために必要であろう”みかた” だったからだ。
大ざっぱに言えば、発達障害とかを抱えた子がうまく成長していけるように支援していくのが「特別支援教育」なんだけど、みんなが受けている教育と意外と変わりは本質的にはないように聞こえた。
学校というのは、できないことをできるようになるように、一定の決まりの中で訓練する。一定の決まりの枠の中で訓練するから、例えば「じっと座っていることが難しい子」とかは、座って勉強するってのは難しい。
ただ、”みかた” を変えて、その子は、自分の周りのいろいろな事に強い興味関心があるという風にみれば、その子がそのとき強く興味を示しているものについて、話をすることで、学習になっていく。学習ってのは椅子に座って机の前でするもんだって既成概念にとらわれていれば、その子は怒られてばかりだろうけど,”みかた” を変えることで、何も問題なく学習をすすめられる。
この”みかた”を変えるってことの根っこには、「他者への寛大さ(あたたかく包み込む)」気持ちがある。なんだか最近の社会が忘れてしまっていることのように思えてならない。
発達障害とか特別支援教育ってのが必要だってとりだたされるのは実は、そういう社会の寛大さの欠落が生んだモノなのかなって思ったりしてならなかったのである。
みんなが住みよい、よい社会を目指して、一人ひとりが意識を変えて
いくことは大切なんだな。(独り言だからまとまりがない…)
◇◆◇◆
時代的なこともありますが、教員時代は、普通高校の教員ではあれども常に「特別支援教育」について意識させられることが多くありました。「特別」「支援」というのが重なってかなり仰々しいことになってしまっているのが悲しいです。
いただいたサポートに応じて、「環境に左右されない楽しい学びの場をすべての子ども・若者へ」をミッションに活動する認定NPO法人Kacotam(カコタム)へ寄付をします!
