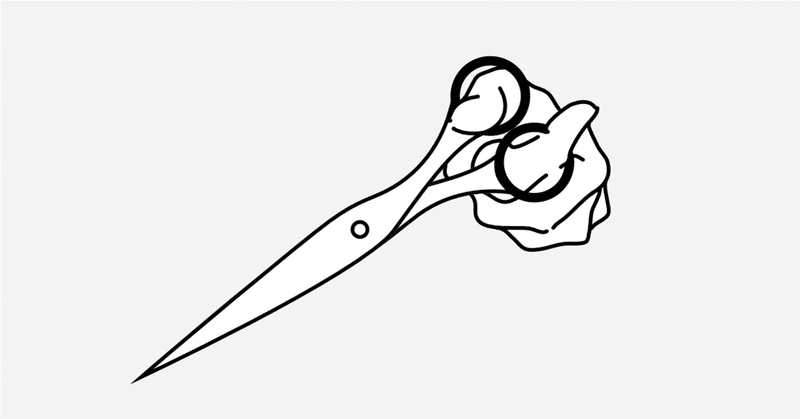
人畜無害
「人畜無害」漢字辞典から好きな四字熟語を引いて、揮毫するという習字の授業で僕の気を引いた四字熟語だ。前の席の角谷君は、年中半袖半ズボンで季節感がまるでない活発少年だが、
「俺は、『疾風怒濤』にする!」
と声高々に宣言した。周りの席の人たちは角谷君の明るさの波を受けて自然と笑みをこぼして賛同したり揶揄ったりしていた。僕はその様子を見て、サッとページを捲り、急いで周りから見て違和感のない四字熟語を探した。人畜無害なんて四字熟語を気に入って書いたとしたら、それこそ癖のある人間だと公表しているようなものだ。自分のアイデンティティーを見出していながら、図々しさを醸し出さない。そんな四字熟語がここでは求められている。現に窓際の席に座っている襟足が長く高身長で大人しい高橋君が「唯我独尊」という四字熟語を選んでいる様子を後ろの席の女の子達を中心に嘲笑されている様子が僕の席から伺えた。身長も高くなく、どこにでもいそうな容姿で、陰キャラでも陽キャラでもない僕は、どんな四字熟語を選べばいいか決めあぐねていた。
「田中君、そんなに悩んでいるの?」
隣の席の橋下さんが小難しく悩む僕を可笑そうに見つめて尋ねてきた。恥ずかさに耳を赤らめてしまった僕はそれを隠すように、パッと目に入った「酔生夢死」を指差して橋下さんの意識を自分の顔に向かないようにし、
「この四字熟語みたいに、ただぼんやりと生きていけたらなぁって考えてた。」
「なにそれ、小六で悟るなんて早すぎだよ。」
橋下さんはクスクス笑いながら漢字辞典から僕に視線を動かして珍しい動物を見るように見つめてきた。僕は更に顔が赤くなり、もうどう振る舞えばいいかわからなくなっていた。すると、僕らの会話を聞いていた角谷君は振り返り、赤面している僕を見ては、
「おいおい田中どうした?顔が真っ赤じゃないか。」
と大きな声で言うもんだから、クラス中の人たちが僕の方へ振り返り視線を向けた。脇や額から汗が結露したグラスのように滲みだしてきたが、何か少しでも弁明しようと、
「別にどうもしないよ。ただ四字熟語が決まらなくて悩んでただけだよ。」
「田中、橋下のこと好きなんだろ?だからそんなに顔真っ赤にしてるんだろ?」
「なんでそうなるんだよ。」
「はいはいそこ、あんまり私語しないように。みんなもちゃんと前向いてね。」
先生はしばらく面白がって静観していたようだが、僕が場を上手く和ませることができないと察知すると、角谷君の態度が目に余ると言わんばかりのトーンで注意した。だが僕には、それが僕自身の無能さ故の尻拭いなのだと分かっていた。クラスのみんなも、なにやら面白いやりとりが見れると見物しに来てみたら期待外れのイベントだったときのように呆れた表情を浮かべながら僕に後頭部を向けた。
「橋下さん、なんかごめんね。」
僕は、そう橋下さんに謝罪したが、橋下さんはただ苦笑いして気まずそうにしているだけだった。僕は、匙を投げるように、「一生懸命」と言う四字熟語を揮毫した。
家に帰ると、僕の髪の長さを鬱陶しがった母が、「明日にでも散髪してきなさい」と口うるさく言い、明日は土曜日ということもあり散髪に行くことにした。いつも散髪はおばあちゃんについて来てもらっていたのだが、三日前から肺炎で入院していたので、一人で行かなければいけないことになった。一人で行きたくなかった僕は母について来てもらおうと考えたが、仕事があるらしい。そこで歳の離れた兄に打診してみることにした。高校生の兄は一人部屋をもらって悠々自適に過ごしてる。部屋のドアをノックすると、
「ちょっと待ってな。」
と少し慌てた声が帰ってきた。5秒ほど待つと扉を開けて兄が部屋に招き入れてくれた。一体なんの5秒間だったんだろうと部屋を見渡しながら考えたが、机も部屋も人に配慮した綺麗さとは言えない雑乱さだった。僕はベッド脇に座り背中を預け座った。
「明日、散髪行ってこいって言われてさ。」
「うん。」
「一緒について来てほしくて。」
「どうして?」
「一人では行けないかなって。」
「だからその理由は?」
「怖い?とかになると思う。」
「美容院のなにが怖い?」
何が怖いと聞かれても具体的に説明する言葉が見つからず、兄の膝をただぼおっと見つめていた。兄は人差し指で机をトントンと叩き、苛立ちを抑えながら僕の言葉を待っていた。
「上手く言えないけど、雰囲気とか、どんな風に注文したらいいかなって。」
「普通に言ったら大丈夫だと思うよ。」
僕はこの頃、「普通」というアドバイスを聞くと眩暈がするようになっていた。周りの人たちは「普通にすればいい」という指示を受けると、安心したように行動し始めるように見えた。だけど、僕にとってみれば指針を奪われたような感覚になってしまう。何が「普通」で何が「異常」か。その境界線を決めるのは自分以外の大多数であり、自分が考えた「普通」の行動が世間の「普通」に当てはまっているのかと耐えず篩にかけられ、少しでもはみ出たら淘汰されてしまう。そのような観念が物心ついた頃から私の心に宿っていた。具体的な「普通」の行動だけが僕の行動指針だった。
「どんなセリフで言ったらいい?」
「セリフ?!うん、まあ「カットしに来たんですけど。」って言えばいいよ。」
兄は、若干リアルに演じてくれたので、僕もそれを真似て、
「カットしに来たんですけど。声のトーンはこんなかんじ?目線は相手のどの辺り見てた方がいい?」
「トーンはそんな大袈裟じゃない方が自然かな。目線は相手を見つめ過ぎない程度にレジ台を見たりした方が不快じゃないかも。」
「なるほど、なるほど。」
「いやこれ演劇での散髪の話じゃないよな?何で演劇指導みたいなことが始まってる?」
僕は兄のツッコミを笑って応えた。兄もその様子に笑い、僕は兄と調和できたことが嬉しかった。
「でもとても参考になるからこのまま練習させて。」
僕はそうお願いして、接客時の客の振る舞いの練習を続けた。
「まず、店に入って、さっきのカットしに来たんですけど。って言えばいいんよな。その後は、何聞かれる?」
「ポイントカードをお持ちですか?とかかな。」
「その場合はどう答えたらいい?」
「持ってないから、持ってないです。言えばいいよ。」
「ジェスチャーはした方がいい?」
「いや必要ないと思うよ。」
「その後は?」
「混んでたら、座って待つように案内されるだろうし、空いてたら、そのまま席に案内されると思うよ。」
僕は忘れないように一つ一つを頭の中で反芻して覚えていた。
「座って待ってるときは、何をしてたらいい?」
兄は呆れたように笑い、口調も先生みたく答えた。
「姿勢を正して、近くにある雑誌でも読んでたら違和感ないと思いますよ。」
「なるほど。次が、一番気になってるところで、「今日はどんな風にしますか?」って聞かれるイメージなんだけど、この時の答え方が分からなくて。」
「髪型とか髪の長さを要求する時の言い方ね。どう言えばいいか悩むぐらいだったら、写真見せたらいいと思うよ。それで、こんな感じにして下さいと言えば、それだけで済むと思うよ。」
「この時、キモいとか変って思われないかな?「こいつこのモデルのようになれると思ってるのかよ。」とか「この髪型似合わないのに、センスのないやつだな」って思われないか心配なんだけど。」
兄は僕の卑屈な妄想に少し嫌悪の態度を示し始めていた。
「大丈夫、誰もそんなこと思わないって。逆にイメージがつきやすいし、美容師さんとしても助かるよ。」
兄は、美容師の思いを代弁するように僕を諭そうとした。僕はそういうものなのかと思う反面、自分の中にあるこの不安を未だに拭えない側面があった。だけれど、これ以上この話題で不安な表情を見せると、兄から部屋を追い出されてしまうと危惧した僕は、深く納得した表情を見せて、「なるほど」と言っておいた。
「切ってもらってる時も普通に座ってればいいし、ずっと目瞑ってたら、寝てると思われて、そんなに話しかけられないはずだから、大丈夫。」
「他に気をつけておくことはある?」
「最後の確認は適当に頷くことと、ワックスつけますか?って聞かれると思うから、お願いしますって答えとけばいいと思うよ。」
「ありがとう!大変参考になりました!」
僕はそう言って一礼し兄の部屋を出た。そして母のところへ行き、明日の散髪代をねだると、細かいのがないからと一万円を僕に渡し、お釣りをちゃんと返すようにと念を押された。僕はリビングの机に座って、テレビを見ながら、先程の兄との練習を頭の中で何度も思い浮かべ、独り言のようにボソボソと呟き練習を続けた。
8時半のアラームで目覚めた。雨が降ってるらしく、水滴が窓を叩いていた。洗顔と歯磨きを済ませると、今日出かける服装について考え始めた。美容院へ行くのにふさわしい格好は一体どんな服装だろう。自分が美容室の一席に座ってる姿を想像をして美容師や他のお客さん、店の前を通り過ぎる人間がふとガラス越しに僕を見た時に違和感がない服装は何だろうかと。幸い、僕の服は殆どが兄のおさがりだったので、普通をこなせる兄の服装を組み合わせて模倣すればいいだけだった。黒のジーンズと白いシャツを着て、リビングで朝食を食べている兄の前に行き、
「服装はこれで大丈夫かな?」
と尋ねると、兄は軽快に微笑み、
「大丈夫だと思うよ。デートに行くわけでもないんだからそんなに気負わなくても。」
兄は流すようにツッコミ、トーストをコーヒーで流し込んでいた。
僕はいつもおばあちゃんに連れられて行っている駅前の小さなビルにある美容院へ向かった。おばあちゃんと行くときは、おばあちゃんが全てやってくれた。僕はただおばあちゃんの後ろを犬のようについて行き、おばあちゃんの言うことを聞いていれば、散髪の時間は終わっていた。だけど今日は自分で始めて、終わらせなければいけない。僕はビルの前で立ち止まり美容院を眺めた。眺めれば眺める程、帰りたい気持ちが込み上げてきて、前に進むには、足が沼にはまったようで強い力を要した。美容院から見える場所でウロウロするのは、異常な振る舞いなので、ビルに入りエレベーターが開くと迷わず一直線で店に入るシュミレーションをビルに入る前に行う必要があった。何度も練習した僕はエレベーターに乗り右足から踏み出すイメージを強く抱いて2階まで上昇するのを待った。店の前まで、自然に歩き、自動ドアの前で自然に一度止まり、受付へと進んでいった。受付に座っていた若い女性は僕を前にすると立ち上がり、
「今日はどうされましたか?」
と園児に話しかけるように優しく声をかけてくれた。僕は練習通りに、
「カットしに来ました。」
と答えた。お姉さんは、頷き聞いてくれて次の質問に移った。
「予約はしましたか?」
僕は、想定していなかった質問がきて頭が真っ白になった。
「よ、よ、予約は、恐らくしてないと思います。」
僕は顔を真っ赤にしながらそう答えた。お姉さんは何か自分がまずいことでも言っただろうかと申し訳なさそうにしていた。
「そっかそっか。いつも来てくれてる浩君だよね。」
「はいそうです。」
「今日はカットだけでいいのかな?」
カットだけでいいとはどういうことだろうか。他に何か要求するのが普通なんだろうか。そもそも「カットしに来ました」って僕が誰かをカットしに来たみたいじゃないかな。考え出したら止まらない。こんなときはどうしたらいいんだっけ。練習を思い出せ。
「あの、こんな風にしてほしいです。」
僕は兄に言われたアドバイス通りに、兄が読んでいた雑誌に写っていた自分の髪型と近い髪型の人間を選んで、切り抜き持参したものをお姉さんに渡した。お姉さんは、更に優しさを込めるように、
「なるほどね。分かったよ。持ってきてくれてありがとうね。すぐに案内できるからね。」
「ありがとうございます。」
そして、いつも僕を担当する30代後半らしき顎髭だけをお洒落に整え生やしている美容師さんがやってきて、
「浩君、今日は一人で来たんだね。こっちの席に来てくれる?」
「はい、おばあちゃんが体調悪くて、今日は一人で来ました。」
僕は歩きながら、美容師さんの後頭部にボールを投げるように言葉をぶつけた。体調が悪くてというワードで美容師さんはこちらを見て、
「そうなの?それは大変だね。お大事にって伝えといてね。」
僕は頷いて返事をした。席に座ると、お姉さんが僕の席に小走りで駆け寄り、美容師さんに僕が先程渡した切り抜きを渡し、「こんな感じというリクエストでした。」と何故か耳打ちするように囁き、美容師さんもお礼を耳打ちするように囁き、お姉さんは受付に戻っていった。美容師さんは少し、渋い表情を浮かべた後、
「浩くんね、この髪型、少しパーマかけてるんだけど、どうする?」
完全に予測していなかった質問だったので、僕は完全にフリーズしてしまった。目の前の鏡に映る自分を見つめて、ただ呆然としていた。頭の中で思考しようとしても、「パーマ、パーマ、パーマ」とパーマの三文字しか浮かばず、何も考えれなくなっていた。はいと言うのが普通なのか、大丈夫ですと言うのが普通なのか、僕には全く分からなかった。恐らくどちらも普通で、どちらか一方を選ぶこと自体に普通性が宿っているわけではないのだろう。一方を選んだ理由と言い方に普通性が宿っているのだと思う。だけれど、この具体的な振る舞いが思いつかない僕は、自分がどうすればいいか分からなかった。余りにも沈黙している僕を見兼ねて美容師さんは、
「ごめんね、難しいよね。この髪型に近づけるならパーマ当てた方が再現率高くなると思う。雰囲気だけでいいよって言うなら、別にパーマは当てなくてもいいかな。」
僕はそう言われても、自分の髪型に対する拘りなどないし、願望もない。ただ、切り抜きまで持ってきておいて、雰囲気だけでいいと言うのは普通なのだろうか、パーマ当てたいと言うのは、この髪型に強い憧れを持ってるのだと変に思われないだろうかと、考えてしまう。
「どっちの方がいいと思いますか?」
「パーマかけるのも似合うと思うよ。ただお金が少しかかるからね。」
「なるほど。いくらぐらいになりますか?」
「うーんとね、5400円かな。」
「わかりました。それでお願いします。」
「はい、じゃあそんな感じで進めさせてもらうね。」
そう言って、僕に雨具のような髪よけを着せ、道具を揃えるために一度席を離れた。1分もしない内に三段ワゴンを押しながら戻ってきた。
「髪の長さとかはあの写真通りでいいのかな?」
「はい。」
そうしてカットが始まり、僕は兄のアドバイス通りに目を瞑ることにした。サイドの髪を切り始めた頃に、
「写真の人、好きなの?」
唐突の質問に身体がビクッと電流が流されたように反応してしまった。その様子が鏡越しに見て取れたので耐え難い恥ずかしさが僕を襲った。それを誤魔化すように咄嗟に質問に答えた。
「いや、特に誰かとかは知らなくて、髪型だけで選びました。」
美容師さんは僕のさっきの反応にはリアクションせずに会話を進めてくれた。
「そうなんだ。みんな好きな人の写真を持ってきてお願いする人多いから、ファンなのかなと思ってね。」
「そうなんですね。」
僕は全く広げられず、再び目を閉じた。5分ほどのカットを終えると、パーマに取り掛かった。母親が夜によく頭に巻いている器具がたくさん出てきて、一つ一つ丁寧に僕の髪を巻いていき、そこに刺激臭がする液体が掛けられ、ゴムで固められた。髪全体がその巻物で覆われると、30分ほど放置するとのことで、待っている間、ドリンクを提供してくれた。オレンジ、アップル、烏龍茶、アイスコーヒー、ホットコーヒー、紅茶の中からどれが良いかと聞かれ、僕は二つ離れた席で同じくパーマを受けてる女性客が烏龍茶を飲んでいるのを見ていたので、烏龍茶を頼んだ。
30分の間、ただカットしにきただけなのに、僕は今、どうしてパーマをあてているんだろうと考えていた。家に帰ったら勝手にパーマをあてたことを母に怒られるだろうか。学校に行ったらイメージチェンジしてきたと笑われるだろうか。5400円の重みも分からぬまま自分の容姿を変えるサービスを受けている自分がひどく滑稽に思えてきた。鏡に映る、昭和の下町の母を代表するような自分の頭を見るとその滑稽さがより増し、僕はニヤニヤを抑えきれず微笑を浮かべていた。
鏡横のタイマーが鳴り、美容師さんが駆け寄り、頭についた巻物の一つをとり、パーマのかかり具合をチェックした。そうして納得したように全て剥がしていくと、僕は予想以上に強くパーマがかかっているのを見て焦り始めた。自分が普通から逸脱していく過程をありありと見せられているようで、悪い夢でも見てるようだった。全て外し終えるとシャワーで軽く洗い流し、再び席に戻り鏡を見ると、すっかり変貌した自分が映っていた。
「濡れてると結構強くパーマを感じるけど、乾いたらそれほどでもないから心配しないでね。」
「そうなんですね。」
気休めの一言に僕は希望を抱くことはなかった。ドライヤーで乾かされ、美容師さんの言う通り幾分かは萎んだパーマであったが、以前の自分との雰囲気はガラリと変わっていた。まるでポップスターに憧れた中坊みたいで自分の性格とかけ離れた髪型になっていた。僕は急いでこの髪型に合うテンションとセリフを演じなければと強迫観念に駆られた。
「後ろはこんな感じかな。」
美容師さんは手持ちの三面鏡で僕の後頭部を見せ、僕は定型通りの、
「大丈夫です。」
を練習よりもテンションを高めに返事をして、ワックスをつけてもらい支払いを済ませ、店を出た。外は雨が降りビルの外を濡らしていた。
「田中さん、お待たせしました。ご案内いたします。」
待合室で旅行雑誌を読むふりをしながら回想に耽っていた僕は立ち上がり、案内された席に着く。僕と同い年ぐらいの美容師さんがやってきた。
「よろしくお願いします。今日はどんな感じでカットしましょうか?」
僕はズボンのポケットからスマホを取り出し、ロック解除すればすぐに表示されるように準備してた写真を見せる。スライドさせると側頭部と後頭部の写真も表示できるようにしており、
「こんな感じでお願いしたいんですけど。」
と言い、写真をスライドさせて正面、側頭部、後頭部の写真があることを示してから、美容師さんにスマホを手渡し、より深く観察してもらった。
「なるほどなるほど、長さはどうしますか?」
「長さも写真のと同じくらいで大丈夫です。」
「では、前髪は眉にかかるくらいで、耳は出す感じで切っていきますね。後ろも少し刈り上げるですね。」
と確認する際も僕は一つ一つに頷き理解を示した。カットクロスを僕に着せる際も腕を伸ばして作業に煩わしさが生まれぬように配慮した。
「田中さんって今何歳なんですか?僕と歳近そうだなと思いまして。」
片手に鋏を持ち僕の髪を触りながら質問した。
「27歳ですね。」
「そうなんですね。僕は今年で30なんですよ。20代ってあっという間ですよね。」
「そうですね。」
「今日はこの後お出かけですか?」
僕はすでに出かけているのだからと思いつつ笑いそうになったが堪えた。こういう質問の場合は、適当に出かける口実を答えるのが無難と友達に教わっていたので、
「服を買ったり、映画を見に行こうかなと思ってます。」
「良いですね、映画お好きなんですか?」
別に人並みにしか映画は観ないし、人よりも映画を観て何かを感じているという自信もない。どれくらいの情熱を持っていれば、それを好きと思うのに、「普通」なのかが分からない。こういう質問は少し謙遜を持って答えるのが無難だと、ネットのコラムに書いてあったので、
「そこまで詳しいわけじゃないですけど、たまに見るのは好きですね。」
「そうなんですね。」
ようやく美容師さんも会話を止めてくれて、カットに集中し始めた。僕は目を瞑り、ただ時間が過ぎるのを祈った。だが飽くなき妄想が僕の頭を支配した。今にも美容師さんが予想だにしない質問をしてきたらどうしようか。僕はその度にうまく答えれるだろうか。鋏が髪を切る度に僕は安堵し、次の一手では、もしかすると僕は普通ではいられなくなるのかもしれないという恐怖と居合わせながら、次の鋏の音を待っている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
