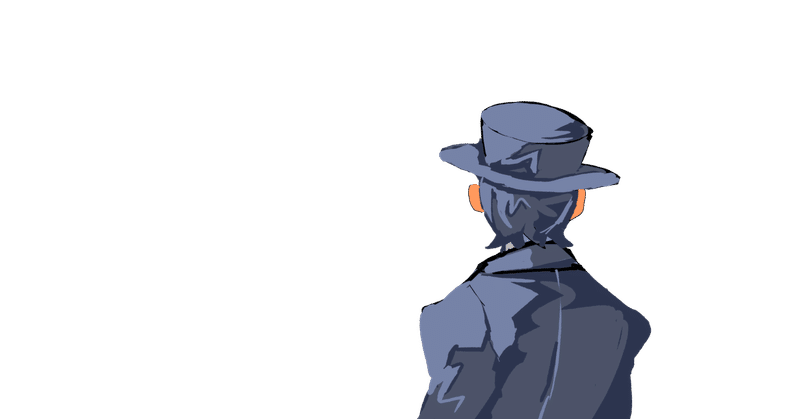
喋る葬儀屋-信仰と実在のイコール-
実在するものを信仰するのか、信仰があるから実在するのか、それをはかることはできない。卵が先か鶏が先かという問題であり、そして実際に信仰されるものが実在していたかという証明を行うには、文献、口伝、遺跡を辿らねば知ることはできない。それらを辿った上で否定される実在性は、いっそ暴力的ですらある。実在性を否定された信仰の行くあてはどこか、信仰を否定された実在性の行くあてはどこか。
●
男の生まれつきの跳ねッ返りは、しかし生育環境はすこぶる良かったために、その跳ねッ返りっぷりが発揮される場面は四十七を迎える今に至るまでさほど無かった。立場上は葬儀社の跡取りであるが、葬儀社はまごころだのなんだのではなく結局のところ、葬式から火葬までを行うセールス、サラリーで成り立っているからして、ヤレ株式だのヤレ経営だのの話になるとそれは専門の人間が行う、ご遺体に慣れないのであれば無理をして就く職でもなし、サッカー選手にでもなるかと彼の両親は言っていた。しかし二人とも葬儀社の人間であったので、当時少年だった男も当然そうなるものと思っていた。幼少の時期は運動に勉強にそつがなく、話しは上手く常にクラスの中心に居て人気者だった。文系の大学へと進路を進めた時にはサークルに入ることはなく、両親の経営する葬儀社のアルバイトに勤しみ食べ歩くための金を得ていた。通学の帰りには常に数人と居て、成人してからは何軒も呑み歩いた。恋人は当然のようにできて、葬儀社への内定が決まり、しばらく働いてから結婚して、当然のように子ができた。明るく順風満帆、思うがままの人生、男は男自身の素質と生まれ持った環境で、それを約束されていた。
●
男が葬儀社へ進路を進めたのは両親がやっていたから、という理由以外にも、とにかく男の弁が立つという理由から、両親ではなく社の人間からアルバイト中に声がかかった。基本的に彼の両親は放任主義であり、社への勧誘は行わなかった。そして社の人間は、息子に取り入ることで上司たる両親に媚びへつらうというせこい気はなく、単純に男のよく回り、時として沈黙を選ぶことのできる上手な口を信頼していた。貴方は勉強すればセールスが上手くなる、葬儀社に居る以上はいくらかの資格があればよろしいと言われて、男はそれも難なくこなした。資格を得るための資金をアルバイト代から引く程度には勤勉であったために、流石にそこまでしてここに来てくれるのならば忍びないと両親は先行投資と言ってお小遣いをくれた。良い歳なのにと少しの跳ねッ返りを見せる男に、学生のウチに甘えときなさいと男の母は言った。
●
クルーズで散骨を行う、海域をぐるりと回ってお別れ、サヨウナラ。散骨を希望したのは男の妻の祖母であった、男は彼女と対面はしたことがあり、あらお葬式をやる人なの、だったら私死んだ時海にお骨を撒かれてみたいわね、そんなことを言われたのを覚えていた妻が希望したのだ。散骨は自分がセールスで取り入れたものだが、まさか身内の不幸でそれをやる立場になるとはと思いつつ、心の底から愛する妻の祖母の死を悼んだ。良く笑い、冗談を言う明るい人であった。老衰で大往生であった。黙祷の時間に目を閉じて開ける、するとどこぞから低いおのれを呼ぶ声がするものだから、黙祷が終わってから妻に誰かが僕を呼んでいただろうかとたずねた。妻は不思議そうに首をかしげ、三歳になる子もまた不思議そうに自分を見ていた。
●
クルーズが終わり、船酔いした子を、妻は介抱のために近くのコテージに連れていく。当分海は嫌がりそうだと子を見て苦笑いしていると、ぐり、と右眼を直に触られるような、酷い違和感があった。
「その眼、その眼だ、お前の眼、実に、実に。ここに来た、ここに訪れた。お前が」
嬉しそうな声だった、男は硬直したまま、疲れているのだろうかとクルーズのためにはるばるここまでのフライトを思った。思えば長旅である、散骨の許可が降りている場所はそう多くはないのだ。それでもぐりぐりと右眼を指でなぞられるような違和感は止まらない。じりじりと身を焦がすような苛烈な違和感と気持ちの悪さ、船酔いもしていないのに胃から何か出そうだった。
「彼岸に繋がる眼だ、ああ、ようやく――」
男は目を閉ざそうとした。しようとして、できない、何かに開かれているように。
「お前、私のところに来い。私もようやく『あちら』に行ける」
目の前に居たのは人のかたちをとって、しかし明確に人とは違う『何か』が居た。男はわけのわからないまま、しかしこの言葉に答えてはいけないと直感が告げていて、常日頃軽快に喋る口はこの時固く閉ざされて、そして開くことをしなかった。頑なな男に眼をなぞる感覚は次第に強くなり、そしてぶち、と厭な音がして、男から大きな悲鳴が上がった。周辺がその異常を察知すると、どよめきや悲鳴が伝搬した。男の右眼は空洞になっていて、血溜まりができていた。妻もまた悲鳴を上げて、救急車のサイレンの音が響くのは間もなくだった。
群衆の中、男にしか見えない『何か』は笑っていた。
「返してほしくば、私のところに来い。なに、悪いようにはしない」
手で転がしていたのはおのれの眼だった、男は激痛の中左眼でそれを見ていた。それからだった、男がのちに居ないものと判じた『それ』がつきまとうようになったのは。
●
根比べでは負けない男だった。『それ』は、自身をあの海域を支配する龍神と言った。どこまで信憑性があるか、男は信じようともせず、そして会話も一切交わさなかった。ただ右眼をあの場で抉り、それを手で弄ぶ存在が居ることは事実で、男は妻子にしばらく怪我でつらいからと言って一人で居る時間を作った。
その間に龍神を名乗る存在は、自分がいかにして龍神と成ったか、なんでも人身供養を発端として歪められた逸話が故の存在であるらしい、それらの話は男にとってそれは至極どうでも良く、信じがたいことであったが、男以外にも見えないという事実が男に厭でもその実在性を信じさせてしまう。
「私はね、この世界にうんざりしているんだ。信仰の失せた世界なんて楽しくもない。かといって常世に行くには些か私一人では力が足りない」
耳元で謳うものの言葉に男は返事の言葉を持たない。
「お前の眼は『向こう』へ繋がる扉だ。お前自身もなろうと思えばそうなれる。だから私のところに来い、悪いようにしない。常世で楽しく暮らそう」
男はその言葉にとうとう耳を貸して、そして口にしてしまった。
「妻子がいるので、結構です。その眼ひとつだけでどうにかできないのですか」
それが文字通り逆鱗に触れたらしい。
●
男の両親が運行中の車の追突事故で両名死亡した。男はつつがなく葬儀を終えたが、火葬炉から出てきた両親がすっかり小さな箱に収まってしまったときに、残った左眼からは涙が出た。子は泣かないでと服をつまみ、妻は男の背を撫でた。あなたの目もあるのに、どうしてこんなひどいことになってしまうのかしら、共に悲しみ寄り添う良い妻であった。その一ヶ月後に妻の祖父が亡くなり、そして男にとっては忌々しい火葬炉の大火が起こる。火葬炉からの出火なんてものは、通常あり得ないよう、業務にあたるものが厳密に管理されるものであり、起こりうるものではないのだ。しかし燃え上がる火葬炉のそばには男の妻と子がいた。男は周りの声も聞こえないまま、あそこに居るのだ、あそこに妻と子が、叫びながら手を伸ばし続けた結果、その手は焼けただれ落ちることになる。火の中で龍神とやらは笑っていた。
「これで、お前の失うものはないな」
●
がちゃんと落ちたカトラリーをスミマセンと言って拾って、交換してもらう。男は元通りではないが動くようになった手でハンバーグを切り分けていた。ステーキを切るにはまだ握力が足りない、切り分けて肉の塊を食べる。まさに命の行う行為であり、龍神は妻子を亡くした男を期待の目で見ていた。男はそれを無視して、火葬炉の出火は奇跡的に妻子の死だけであったことを想う。ともすれば葬儀場全体が焼失したかもしれないのに、葬儀社は残り、火葬炉はメーカーの不備として社は存亡の危機には立たされなかった。メーカーにとっては悲劇的であろうが、葬儀社もサラリーによって成り立っているのである、事故があれば一番に人が離れてしまうのは危機的であった。なので、奇跡的に、そう、奇跡的に妻子の死だけで済み、社の人間が路頭に迷うことはなかった。これは社の人間として喜ぶべきだった、だから男は喜んだ。そして同時に、妻子の葬儀を妻の両親に頼み、自身は出席しなかった。両親の死と妻子の死で立て続けに病んでしまったのだろう、周囲はそう判断してつつがなくことを進めた。いつでもお墓参りに来て頂戴ねと妻の両親は優しく言った。男はそれにお辞儀を返すばかりであった。残された左眼にはただ昏い願望が宿り、ひとつのアイデアが男の口に食事をねじ込ませていた。しかし龍神とやらはそれを知る由もなかった。
「あの海で待っていてください。一週間もあれば『準備』は整います」
男がそう言うと、龍神は目を輝かせて頷いた。煩わしい存在はその言葉を信じて気配が失せた。愚かだと男は思った。
●
その時に男を支配していたのは、執念だった。徹底的に相手を調べ尽くして、徹底的に相手を判ずるための材料を探した。資料館、伝聞、なんでも良いから取り寄せて、学者先生にアポをとったりなどもした。自分の体験した不可思議と理不尽については語らず、自分の妻の祖母が散骨された場所だから由縁が知りたいと通した。男はそうして心の中の火に薪をくべる。そうして心を殺していく。相手がどれだけ哀れだろうと知ったことではなかった。眠らずに資料に向かい頭の中にすべてを叩き込んだ。とはいっても風化している話で、出自すら怪しかった。だからおのれが成す行為は『とても簡単だ』、そう思った。
●
「あなたと話をつけに来たんです」
男はフライトを終えて一週間、近隣を見て回ったあと、海の前でごく軽い言葉で語りかけた。嬉しそうに寄る『それ』に、男は笑顔を浮かべた。セールストークの時と変わらない笑顔だった。
「あの火事、あなたが起こしたものですよね?」
それに『それ』は無邪気にそうだと言った。お前を呼ぶためならなんだってするから、と言った。
「時に、あなたについて調べてみたんです。えーと、あなた、人身供養の伝承から歪んで龍神伝説になったとか?」
男は笑顔のまま。
「なんですか、それ」
男は、そう言った。
「そんなものどこにもありませんでした。郷土資料館とか見たんですけどなーんもなくて。石碑とか? も探してみましたがどこにもない。誰かの言い伝えでしょうか? でも誰も知らないんです」
「……何が言いたい、おまえ」
「あなたをあなたたらしめているものは何なのでしょう?」
「そんなもの、私はここにいるだろう。お前の眼を奪い、お前から――」
「例えばそうですね、おれの眼はクルーズ中の不幸で脱落しました」
「私が、目の前で抉ったじゃないか」
「いいえ? そして、火事も、ええ。メーカーの不備でした」
「お前が、さっき私が起こした、と」
「錯覚ですよお。おれと、あなたの」
男はあっけらかんとして言った。
「おれとあなただけの錯覚、とするのならば、おれが錯覚と思えばあなたも錯覚。ただの脳の誤認、あなたはどこにもいません。おれの錯覚としてだけ存在します。あなたは錯覚なんです、おれの脳の機能が都合よく、おれにとって悪く起きたことをオカルトに仕立て上げている、おれ自身の現実逃避として。だからあなたは居ないんです、おれの思い込みでしか存在しません」
「何を――私は」
男はそして、笑みを消した。
「おまえはいない。どこにもいない。だれにもしんじられていないだれにもかえりみられていないおまえはどこにもいちゃいない」
呪詛ではなかった。ましてや言霊でもなかった。そもそもそれに言葉すら向けていなかった。そして男はまた笑顔になった。
「ああ、なんと人間の錯覚の恐ろしいことときたら! 本当に起きた事実から目を逸らすために空想を作ってしまう。だからおれは空想とお別れするために『お話』に来たのです。これは『おれ』と『僕』の対話、それ以外のなにものでもなくて……」
ふつ、と男の言葉が切れた。
違う、違う、と嘯く『それ』の姿はにじみ、海に溶けるようにゆらいでいる。これだから根拠のない存在は、男は内心そう思ったが口にしなかった。徹底的な無視、否定、実在性の疑わしいものにそれを行えばどうなるのかという一介の興味と報復だった。
「私は、どこにもいない?」
ぽつりとこぼれた言葉は、いつだかの尊大さは失せていた。
「わは。本当に信じちゃった」
今にも消えそうな姿から背を向けた。充分に意趣返しはできた。跳ねッ返りの精神が行き着くところは相手の無視、全否定、そしてそれを受け入れさせることだった。
「んじゃ厄介なことになるまえにおさらばー」
失せろ、その言葉は失うという言葉と同時に相手の実在性を確約してしまう、だから心の中で吐き捨てた。帽子をかぶって手をひらつかせる、残った左眼がひりついた。
「あ、あぁ、いかないでくれ、おま、えは――」
振り返らなかった。
「お前はだって、もう、『そちら』に居るのに」
ひりついた左眼にばちりと衝撃が伝わって、男は尚も振り返らなかった。背後の気配と声は次第に消えた。
●
実在性を否定された信仰の行くあてはどこか、信仰を否定された実在性の行くあてはどこか。言ってしまえば無である。此岸、彼岸、どちらでもない、完全な断絶と存在すら許さない、存在した痕跡すら否定し尽くす、男はそれを軽々しく乗り越えてしまったものだから、左眼はすっかり彼岸へと繋がって男は『あれ』の同類に好かれるようになった。踵を返して海に身投げでもしてやろうかと考えた、妻の祖母の骨が眠っているのだから、おしゃべりなあの人のならば快く自分を迎えてくれるだろう。しかしあの人が行くところが天国で、妻と子が行くところもそうであるのならば、おのれの行くところはどこなのか、生傷は絶えなくなり、今日もフォークを、ナイフを、スプーンを、箸を取り落としては生きるための食事をして、死ぬために生きる行為をしているおのれはまっとうなところにはもう行けまい。森林の中で見つかった首吊り遺体を火葬炉に送ったことを思い出す、腐敗臭と取り切れない草木のにおいに、骨になるまでの有様と役所サマの手を煩わせる気が知れなかったが、今なら分かる、他人にどう迷惑をかけようと完遂したいことがあれば人は存外突き進めてしまうということを。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
