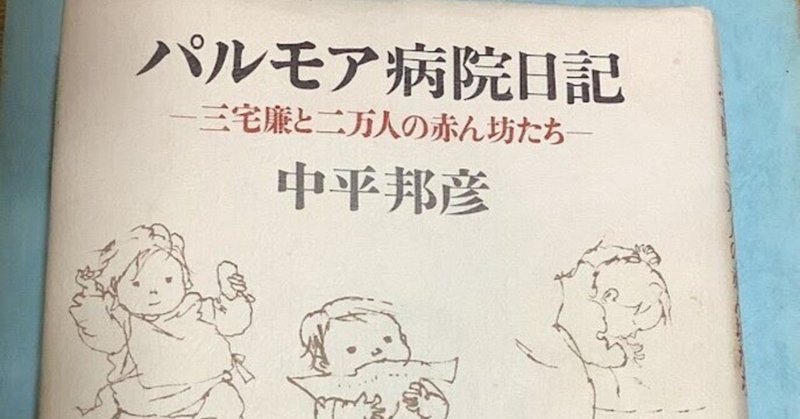
『パルモア病院日記 ―三宅廉と2万人の赤ん坊たち ― 』
中平 邦彦 著
哲学者の顔
初めての出産から数カ月後のある夜、たまたま見たNHKのドキュメント番組で三宅先生を知った。小児科医だが、赤ん坊が産湯に漬かる写真をうれしそうに一眼レフで撮っている。どう見ても孫の写真を撮るおじいさんの顔だ。写真は、新生児の朱染めの手形と共に一人一人にあげるのだという、月に何十人もの子どもを取り上げる神戸のパルモア病院での話だった。
見終わってから不思議な親しみに包まれて、何のためらいもなく手紙を書いていた。「生まれたての赤ちゃんはみんなクシャクシャと聞いていたのですが、息子はまるで世の中のことをみんな分かっている哲学者みたいな顔をしていました」、それはずっと心に秘めて、初めて表に出した言葉だった。
間もなく、小さな文字を一杯に敷き詰めた1枚のはがきが届いた。「高く積み上げられた反響のお手紙の中から、真っ先にお返事を書いています。まさにおっしゃるとおりです……」。思いもしなかった返事に、胸を熱くしながら何度も繰り返し読んだ。
再読できて良かった!
その返信で知ったのが本書だった。慣れない育児のはぎれのような時間の中だったが、それでも一気に読んだ覚えがある。今回35年ぶりに再読してみたが、親交のあった人に聖路加病院の日野原重明氏や、『幼稚園では遅すぎる』の著者、井深大氏がいることを知った。パルモア病院設立までの細かい筋立てやエピソードなど、読みこぼしたり、覚え間違っていたりということを多々見つけた。それは決して些末な情報などではなく、人となりをより深く知る大切な1行だったりした。黒子に徹した著者、中平邦彦氏が信頼を得て引き出せたであろう事柄、「神は細部に宿る」というが、その大切な細部でもあった。
1万人までは出産にも立ち会ったというが三宅医師は小児科医なのだ。産科と小児科が分かれていることで、多くの新生児の疾患が見落とされ死に至る時代がかつてあった。大学病院では小児科医が出産の立ち会いをすることもままならなず、周産期医療に取り組むには両科が連携する病院が必要だった。こうしてパルモア病院が造られたのだ。臨床をしながら医学書を執筆したり、教授として人を教えたり、53歳でこの病院を始めるまでの長い経歴をあらためてたどることができた。再読できて本当に良かった。
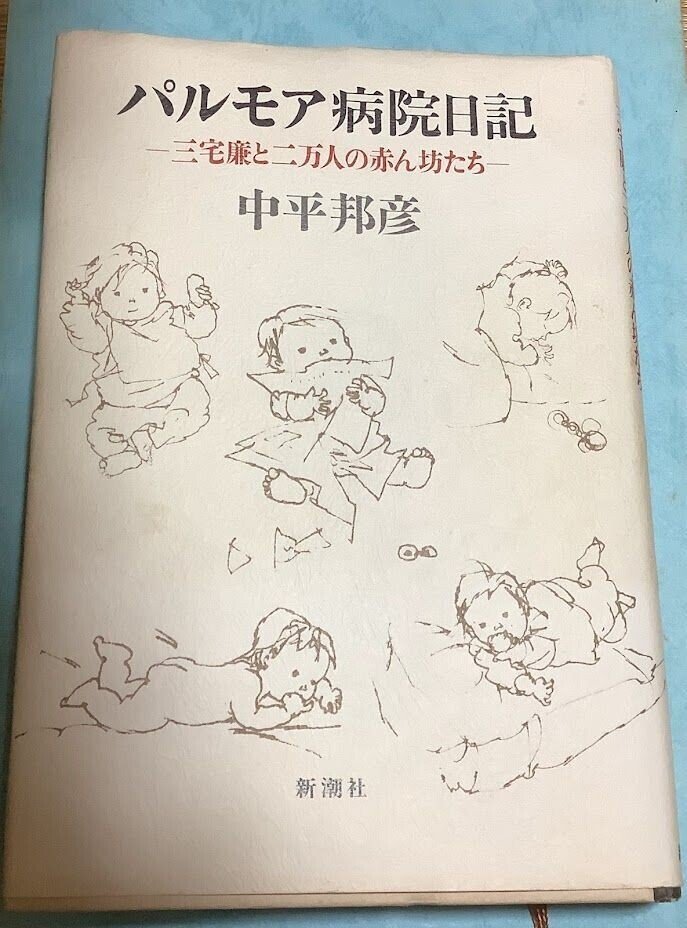
15年後に親子と再会
当時読んで心揺さぶられた箇所では、やはり今でも涙がこぼれた。冒頭の同籃記念会の場面もその一つだ。いったいどこの世界に、出産に関わったからといって同年生まれの新生児の同窓会を毎年開こうと思う小児科医がいるだろうか。そして親にとっても命懸けの出産で、そこに携わった人との再会は何という喜びだろう。子どもを産み落とした社会に、わが子の成長を見守るこんな医師がいてくれる、そう思うだけでも胸が温められて涙腺が緩むのだった。
だが、三宅医師の境遇を思うとき、必ず浮かび上がる光景がある。それは第二次世界大戦の始まる少し前、洋行帰りの人たちを出迎えるために群衆が集まった雨の神戸港。「バンザイ」を叫ぶ歓喜の声の中に、赴任先で病死した弟の遺骨を抱いて下船する彼の姿がある、何ともむごい場面だ。
あまりにも早く親兄弟に死に別れてしまったから、命の問題に強く引き寄せられていったのだろうか。クリスチャンの家庭に生まれたから、自分のことは二の次にまい進できたのだろうか。新生児の小さな命を「闇の谷」といわれた窮地から何とか救おうと働き続けた人生。80歳を過ぎても、病院経営が苦しくなっても、歩き続けるひたむきな背中を尊敬の念なく見ることはできない。

障害を受け入れる
出産にまつわるさまざまなエピソードの中で、産んだ子が障害を持っていたとき、誰がどのように母親に知らせるのかという深刻かつ重大な問題があった。子を産んだばかりのときも、35年たった今も、身につまされひりひりするような思いで文字を追う。誰が話すのか。やはり、それは、子どもへの愛情が人一倍強く、専門学校や大学で教鞭を執る、老練な三宅医師の役目だった。このときの言い方の間違いは許されない、その大切さを彼は誰よりも熟知していた。
若くても立派な父親、母親がいることもかつて本書から教わった。読みながら涙するのは親の不運を悲しんでではない、周囲の心配をよそに、その子を「かわいい」と受け入れる、母親の柔らかな愛にこそに深く揺さぶられるのだ。
重い障害を持った子ほど、親や祖父母が育てることを拒否するというのは世の常のようだ。だが、三宅医師は何カ月掛かっても説得することをやめない。どこまでも懸命に生きようとする無告の小さき命の側に立つ。きれい事では済まない、延々と続くせめぎ合いの中でとうとう親の折れる日が来た。
理想から遠く
新米ママだった私も、今日までにたくさんのお母さんたちと出会った。幼稚園児なのに子どもに熱があっても休ませないという人は、その理由を皆勤賞が取れなくなるからと言った。こんな小さなころから親たちは、学校や習い事に子どもの優秀さを競って求めていた。どんな人間になるのかということよりも、どんな高校や大学に行くかのほうに関心が傾いてしまった。
そして、その対極には、障害児を抱えるお母さんたちが同じ時代を歩いていた。ダウン症はもちろん、ふいに攻撃的になる自閉症の子。1人ならまだしも、兄弟が続けて難病に襲われた友人もいた。また、三宅医師があれほど危惧した出産時のトラブルが今も起こっている、何の罪もない若いお母さんが、自らでは何もできない子を、ありったけの愛で懸命に育てている。
当時は全く目が向かなかった医療の現実も、私の少ない経験からいえば三宅医師の懸念した方向に進んでいるように感じる。医者は普通の人ばかりに見える、否、医者は積極的に普通の人であることを主張している。「医者だって自分の生活がありますから」「訴訟をされると困りますから」、信頼よりも自己防衛、人間よりもデータや数字ばかりを見る、温かみのある医療からはどんどん遠ざかってしまっている。否、それが多くの現実だと自分の少ない経験から決め付けるのはよそう。ただ、もはや理想を求めることなどしていないこの自分に、読めば読むほど気付かされていくのだ。

慈愛の書
もう絶版になり、手に入る可能性は低くなって本当に残念だ。お産の近い人、これから子育てをする人に、本書は慈愛にあふれた一冊になると思う。紙の色はもう茶色く変色しているだろうし、読みにくい箇所もあるかもしれない。先生は、頑固なまでの母乳育児の推進者なので抵抗のある人もいるだろう。それでも、手に取ることができた人はそれだけで選ばれし者だと思う。なぜなら、三宅先生は希有な人で、その言葉のみならず、考え方や生き方には人を動かす不思議な力があるからだ。せめてきれいな状態のまま、この本を次の世代へとつなげたかった。

先生が亡くなられて、もうすぐ30年になる。
「世の中を良くするのも、お母さんの仕事ですよ」
そう締めくくられたはがきの文字が、今も優しく語り掛けてくる。
2022.1.25
創作の芽に水をやり、光を注ぐ、花を咲かせ、実を育てるまでの日々は楽しいことばかりではありません。読者がたった1人であっても書き続ける強さを学びながら、たった一つの言葉に勇気づけられ、また前を向いて歩き出すのが私たち物書きびとです。
