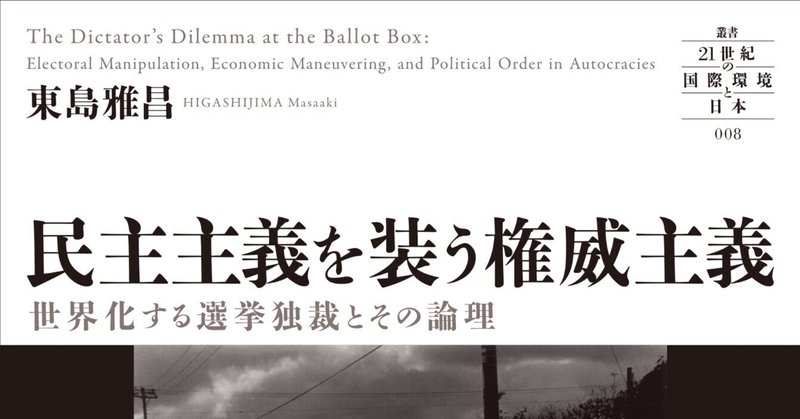
さまよう権威主義、うつろう民主主義
(2023/12/06記)
第二次世界大戦が終わった一九四五年から、おおよそ一九八〇年代末までの世界政治は、米国を中心とする民主主義陣営とソヴィエト連邦を中心とする社会主義陣営が対立する、東西冷戦という図式の下にありました。
一九九一年のソ連解体と冷戦終結によって、民主主義が勝利を収めたかに見えましたが、その後、宗教対立、民族紛争、中国の台頭などを経て、世界は新たな対立の時代を迎えています。現在、民主主義の対角に置かれるのは権威主義といってよいでしょう。
ところが事態は以前ほどシンプルではありません。
権威主義体制の国家といえばプーチンのロシア、習近平の中国、金正恩の北朝鮮といった名前が思いつきます。しかし、民主主義の根幹であり、その政治体制を担保するといっても過言ではない「選挙」を実施している国で、その結果、選ばれた政治指導者が、民主主義や国際法の原則に反する行動を取るというケースが少なからず散見されるのです。
フィリピンのドゥテルテ、トルコのエルドラン、近年では「世界最大の民主主義国家」とも呼ばれるインドのモディに対する評価もたいへん厳しいものです。
なにより民主主義陣営の盟主を標榜しながら、自国第一主義を掲げてパリ協定を反故にし、TPPを脱退した米国前大統領トランプの振る舞いなど、その端的な事例と言えるのではないでしょうか。
権威主義とはどのようなものか、その探求の手がかりには、東島雅昌さんの『民主主義を装う権威主義』(千倉書房・六一六〇円)が役立ちます。
著者は独裁者が経済的果実を分配し、暴力や不正を慎むことで体制の基盤を固めること、その一方、民主主義を装いそこなった権威主義者は、たとえ独裁体制下であろうと選挙(大衆の力)によってパージされる可能性が高いことなどを見出し、「両者は実は私たちが思っているよりも近似した存在なのかもしれない」と分析します。
その意味で、権威主義は民主主義の合わせ鏡と見るべきなのかも知れません。
東島書の事例研究の舞台となったのはキルギス共和国とカザフスタンという中央アジアの二カ国です。私たちの知る政治や社会とはかなり風土が異なりますので、それらに関しては、同じく市場経済化後のカザフスタン社会を描いた岡奈津子さんの『賄賂のある暮らし』(白水社・二四二〇円)で実像を押さえておきたいところです。
近年、権威主義に関する書籍がやたらと刊行されている大きな理由があります。
それはかつて私たちが「現在は様々な政治体制が並立する世界だが、やがて自由民主主義に則った政治体制に収斂していくのだ」、「その大きいな流れは不可逆だ」と考えていたことに由来します。
社会主義とは異なる道筋で台頭した権威主義と、それと平仄を合わせるような民主主義の後退に、誰もが動揺しているのです。
独裁政治の歴史と変貌を描き、民主主義が賞揚され続けた二〇世紀以降の国際社会においても、じつは世界政治のトレンドの中で権威主義は一定以上の勢力を保ち続けたことを明らかにしたフランツの『権威主義』(白水社・二七五〇円)や、冷戦終結後の世界で燎原の火のように広がった民主化が当初期待された成果を得ることなく、人々の失望を招く様子を各国の事例から鋭く描きだした川中豪さんの『後退する民主主義、強化される権威主義』(ミネルヴァ書房・五五〇〇円)、あるいは「民主政治の黄昏」というサブタイトルを掲げ(原書ではこちらがメインタイトル)、トランプの登場とそれを支持した米国(民)に対する疑念、そこから生まれた民主主義に対する深い制度的不信の行方を追ったアプルボームの『権威主義の誘惑』(白水社・二四二〇円)などは、そうした動揺の心理を適確にえぐりだしたものと言えるでしょう。
同じ論理的帰結を、民主化の模倣に失敗して右翼政党の台頭を招いた東欧諸国と、トランプを生み出した米国政治の連環の中に見出したクラステフの『模倣の罠』(中央公論新社・三七四〇円)が、結果的に自由主義の没落過程をなぞるようなことになっているのも象徴的です。
世界がコロナ禍に逼塞した時期、個人の権利が公共性に優越しがちな民主主義より、為政者のコントロールが強く効く権威主義のメリットを指摘する声が挙がりました。
無論、そのメリットを統治に活かすための政治体制の重要性は言うまでもなく、その建設に成功している事例として中国に焦点を当てるのが呉国光さんの『権力の劇場』(中央公論新社・四一八〇円)です。
中国が改革開放に向かっていた一九八〇年代後半、当時の趙紫陽総書記の政策スタッフとして民主化の道筋を描き、八九年の天安門事件直前に渡米した呉さんは「共産党一党支配の正統性を担保するための機関」として用いられる中国共産党大会に注目し、その制度と運用の特質を描き出します。前述の東島書と同じく、キーワードは「選挙」です。
呉書と併せて、大澤傑さんの『「個人化」する権威主義体制』(明石書店・二七五〇円)も読んでおきたい一書です。
制度に着目した呉書に対し、大澤書は独裁者による「個人的」意思決定に焦点を当てます。予測不可能で、何より理不尽極まりない政策決定にはどのような条件があるのでしょうか。
ウクライナ侵略で世界に衝撃を与え続けるロシア、台湾有事をめぐって日本に緊張感を与え続ける中国、国連決議に反するミサイル発射を繰り返す北朝鮮という三カ国の政治動向を「個人化」という観点から読み解くことは、「制度化」の一方に用意しておきたいツールだと思います。
それはプシェヴォスキが『民主主義の危機』(白水社・二六四〇円)で述べているように、制度の重要性は言うまでもないことながら、政治的対立が激しくなれば、どのような制度の下であってもそれらが平和裏に処理されることはない、という現実から見てもやむを得ないことでしょう。
今日、自由民主主義の置かれる厳しい状況を分析した多くの書籍が指摘するように、問題の背景には、社会の二極分化とポピュリズムの問題があるようです。
福祉や治安の維持といった社会政策の在り方をめぐる議論を手がかりにネオリベラリズムと権威主義を架橋するという、驚くべき離れ業を見せたシャマユーの『統治不能社会』(明石書店・三五二〇円)は、じつは統治という行為が本質的に秘めているジレンマを露わにします。
これは、二極化した政治が独裁を招来する、というロジックで問題に接近しようとするレビツキーらの『民主主義の死に方』(新潮社・二七五〇円)と、一見矛盾するように思われるのですが、もしかすると独裁や権威主義が向かう道筋は一つではないことの証左なのかもしれません。
かつて東西冷戦の終結を「歴史の終わり」と呼んだフクヤマが、いま世界の状況をどう見るのか、という意味でも関心を向けざるを得ない『リベラリズムへの不満』(新潮社・二四二〇円)ですが、一般に包含関係にあると見なされがちな民主主義とリベラリズムを「国民による統治」と「法の支配」として峻別し、そこに発生している機能不全への不満がリベラリズムに向くことを危惧します。それが社会を分断する強いベクトルとなることは現在の米国を見るまでもないでしょう。
民主主義の発展に大きな役割を果たしたポピュリズムを論じたミュデたちの『ポピュリズム』(白水社・二二〇〇円)に、日本語版は「デモクラシーの友と敵」というサブタイトルを付しました。
同書が「ポピュリズムの成功と失敗をどう説明するか」という根源的でありながら、これまでほとんど手をつけられてこなかった問いに挑んだ重要な書籍であるだけに、その含意は重く受け止めねばなりません。
あらためて、いま民主主義はどこへ向かおうとしているのか確認したくなったとき、その議論の前提となる足場を固めたいと思ったかたには、ムーアの『独裁と民主政治の社会的起源』上下巻(岩波文庫・一二四三円/一五八四円)とリンスの『民主体制の崩壊』(岩波文庫・一一一一円)をお勧めします。
世界各国で近代社会が生成されていくなか、領主と農民関係をはじめとする社会経済構造が如何なるものであったかから説き起こすムーア書、そして民主主義は突然崩壊するのではない、として危機に瀕した政治体制の崩壊、再均衡に至る流れを論じたリンス書、ともに古典として、長い歳月の彫啄を受けてきた安心感があります。
また、日本の独裁研究として長らく定番書であった猪木正道さんの『独裁の政治思想』(角川ソフィア文庫・一三二〇円)と『新版 増補 共産主義の系譜』(角川ソフィア文庫・一二三二円)も、その輝きを失ってはいません。
もっと軽い読み物としては、古代ローマ研究の第一人者である本村凌二さんが、長い世界の歴史を独裁という切り口から描いた『独裁の世界史』(NHK出版新書・九三五円)があります。
もっと直近の民主主義についてレビューが欲しいかたのためには、山本圭さんの『現代民主主義』(中公新書・九四六円)と待鳥聡史さんの『代議制民主主義』(中公新書・九二四円)があります。
いずれも、今日的で多様な論点をカバーしており、現代民主主義にかんするもっとも篤実な見取り図と言えます。
そもそも民主主義は、議会の発展、大統領制や議院内閣制の確立、選挙権の拡大など、近代化に伴う多くの政治的試行錯誤の上に確立してきたシステムです。
ところがグローバリゼーションの行き詰まりや経済成長の鈍化によるフラストレーションが、イデオロギーの分極化やポピュリズムのトレンドを生み出し、民主主義もまた機能不全のように見えています。
でも、そこに新しいシステムとしての進化、更新はあり得ないのでしょうか。そうした可能性やヒントを垣間見せてくれるのが、この二冊の優れた点です。
何度か触れたように民主主義と権威主義の決定的な差は、正当性を担保する支持の獲得の仕方にあるようです。
メスキータらの『独裁者のためのハンドブック』(亜紀書房・二二〇〇円)は強い皮肉を交えながら、国際社会が独裁国家に向ける視線について警鐘を鳴らします。
たとえば独裁者が統治する開発途上国への人道援助が、独裁者の支持獲得の原資に用いられ、体制の延命が結果的に同国民の利益を損なうというケースがそれに当たります。じつは、これは冒頭に紹介した東島書の分析でも強く示唆されている点です。
合わせ鏡たる民主主義の足許を見つめ直すためにも、やはり今、独裁主義を考えることは必要な知的作業だと思うのです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
