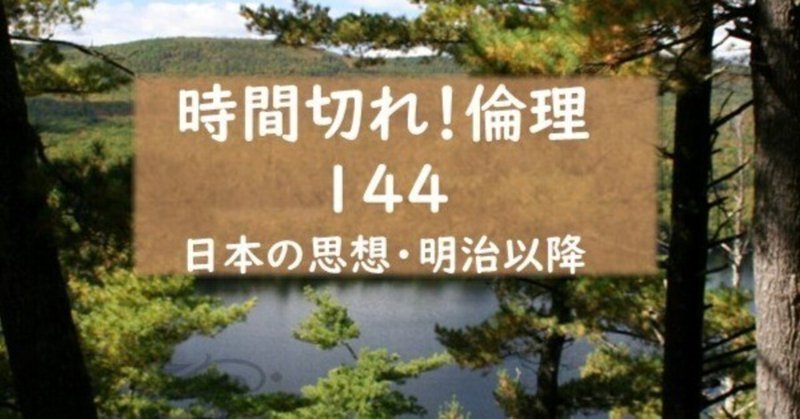
時間切れ!倫理 144 国粋主義・国家主義
明治以降、西欧文明はどんどんと日本に入ってきます。福沢諭吉も西欧文化を日本に紹介した。革命思想、自由民権運動のバックボーンとなった社会契約説を紹介したのは中江兆民。そしてキリスト教。新島襄や内村鑑三。
こんな風に、どんどんと西洋の文化が日本に流れ込んでくる中で、当然それに対する反発も生まれてきます。日本の伝統文化を守ろうという思想です。日本にだって誇れる文化があるのではないか、という考え方。これが国粋主義思想。ここから出発して、日本の国に誇りを持とうという考え方になると、これを国家主義思想と言います。
このような立場に立った思想家を紹介していきます。
教科書には徳富蘇峰が載っていますが、この人は、初めは国家主義の立場ではなく、西欧文化をどんどんと日本に紹介していく立場に立っていました(横井正楠は母方の叔父)。この頃の彼の立場を、平民主義と言います。『国民之友』という雑誌を出版して、西欧の思想を紹介していました。この雑誌は非常によく売れて、徳富蘇峰は言論界のリーダーのような立場になっていました。
平民主義というのは、啓蒙によって、民衆を尊重する社会を作っていこうという考え方だと思います。だから福沢諭吉や中江兆民の立場と相反することはない。徳富蘇峰自身若いころ京都の同志社でキリスト教に入信したこともありました。
徳富蘇峰は『国民の友』の発行によって、言論界の名士になるのですが、日露戦争の頃に松方正義内閣によって政府に誘われて、高い役職を与えられたことがあった。これをきっかけに彼は自分の立場を変えていく。平民主義を唱えていたときは、反政府的な言動も多かったのですが、政府寄りに立場を変えていく。そういう意味で国家主義に立場を移すわけです。
このことによって彼は信用を落とし『国民の友』も売上を大きく減らしていきました。
入試的には、徳富蘇峰は平民主義や『国民の友』の発行者として名前が出てきます。平民主義から国家主義へ立場を変えたのは誰ですかという聞き方をされれば、徳富蘇峰しかありません。
三宅雪嶺(せつれい)・志賀重昴(しげたか)は、雑誌『日本人』を発行して国粋主義をとなえました。
陸羯南(くがかつなん)は、新聞『日本』を発行。国民主義、日本の伝統の優秀性を主張しました。
この人たちの区別はつきにくい。試験対策としては、雑誌と関連付けて覚えておくしかありません。
西村茂樹は、『日本道徳論』。西洋文化に対抗して日本の伝統文化は何かと問われれば、これは結構難しい。そこで、西村茂樹は儒教をよりどころにして、これを国民道徳の基礎とすることを主張しました。
しかし、儒教は中国から入ってきたものであるので、純粋に日本の伝統文化ではない。仏教も同じ。純粋な日本の伝統文化は何かといえば、本居宣長が言っている「もののあわれ」になってしまう。しかし恋愛を価値あるものと考える「もののあはれ」を旗印にして西欧文化に対抗するのは難しい。
結局、日本の伝統文化をどんどん突き詰めていったところで出てくるのは神道でした。神道の中心には天皇がくることが多い。明治時代の三宅雪嶺や陸羯南の時は、それほど激しくはないのですが、天皇中心の思想がだんだんと重視されるようになっていきます。
以前に紹介した山本常朝の『葉隠』という本が明治時代になって再発見される。「武士道とは死ぬことと見つけたり」というあれです。しかし武士はもういないし、殿様もいないので、「死ぬことと見つけたり」の対象は、殿様から天皇に置き換えられて考えられるようになります。天皇のために死ぬことが日本男児のあり方なのだ、こういう国家主義的な思想は政府や軍人たちにとっては都合がいいので、このような考え方がどんどんエスカレートしていき、軍国主義の時代となり、第二次世界大戦に突入していく。こういう流れの思想的な源流となります。
このような国家主義的な考え方は政府も主張します。その象徴的なものが1890年の『教育勅語』。天皇の言葉として、天皇を中心とした国民道徳を説きました。国家主義的教育です。
話はそれますが、昭和に入ると、こういう考え方を極端に推し進めた一部の軍人や右翼思想家たちは、天皇を中心とする軍事独裁政権を樹立しようとした。超国家主義とも言います。これが実際のクーデター事件となったのが有名な二・二六事件です。その思想的な背景となったのが北一輝という人です。彼は元老・財閥・政党を除去し、天皇と民衆を直結させる国家改造論を唱えました。今話している明治時代の国粋主義思想とはちょっと違いますが、ここで教科書に載っていますので紹介しておきました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
