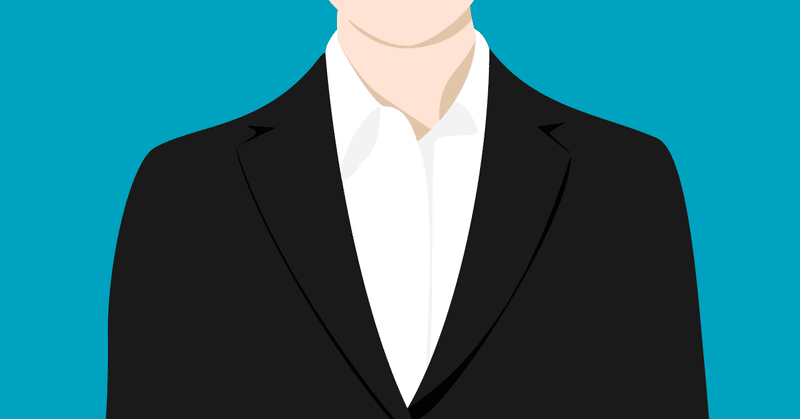
【掌編小説】見下す目
――忘れはしない。あれから10年。まだ元気に働いているのかな。
街中で同い年くらいの子が社会に揉まれているのを見るとつい見入ってしまう。青と白の縞模様の運送会社の子。今日もキツツキみたいにノックしている。かわいそうだと思う私。馬鹿にしている訳ではない。私も同じなのだ、そう今から10年前、言った本人はもう忘れているだろう。蒸し返す私もセンスがないと思う。でも、深い心の傷になっている。グループ面接の担当者の私に何も期待していない目。まだ話しているのに「はい」を被せる。間接的な疎外感の応酬。あいつは確かあの時29歳だと言っていた。もう今の私より何歳も年下になっている。
あの日の私はただ怯えていた。あの29歳の、結婚指輪をした、毎朝ミスドでビジネス書を読むことを自慢していた担当者。あぁ、あぁ、これ以上声を聞くと「耳が腐る目が腐る。耳が腐る目が腐る」と何度も唱えながら私は面接が終わるのを待っていた。
その会社には勿論落ちたけれど、ただただ合法的に傷つけられたと思っている。今も私とあいつとの戦いは終わっていない。10年経てばどうでもよくなる、許せる。かもしれないと思っていた。そんなことはなかった。僕は君よりも優れているんだ、と信じ切った丸い瞳。それを表には出していないと言いたげな顎。社会はそんな人ばかりなのかと思ったが、そんなことはなかった。いや、最初の1~2年はいたかもしれない。私は努力をした。そういう人がいない場所を目指した。でも傷は残っている。あいつからの具体的な実害があった訳ではない。でもそれは言い換えれば、いじめの痣が残らないように蹴るいじめっ子とやっていることは同じではないか。
大人になってもいじめを止められない人間を罰したい。という欲望に、私は毎晩駆られている。真っ暗な部屋、スマホの電源を切り、何を考えても良い時間に思う。きっと、世界一周の船旅に出てもやめられないだろう。
となると不幸なのはあいつではなく、自由を奪われた私なのだろうか。私は罰したい。罰せられるべきだと思うのだ。
小説を書きまくってます。応援してくれると嬉しいです。
