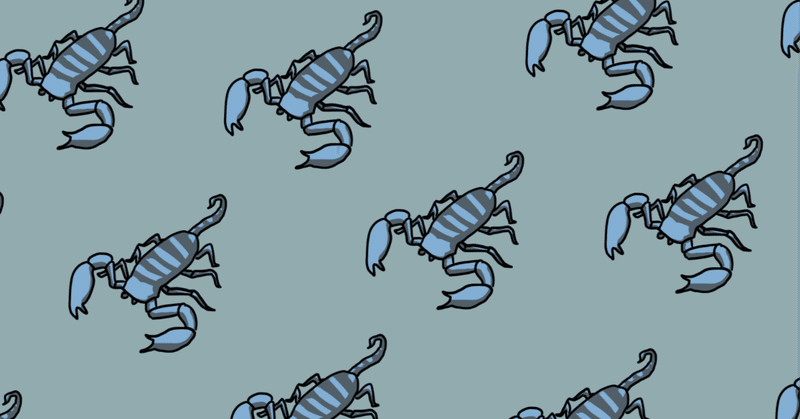
「ヘビとサソリ」サソリの章
生理的嫌悪ということでは、会社の同僚だった山王丸さんのことも忘れ難い。転職すれば、去る者日々に疎しで、慕っていた上司や可愛がっていた後輩のこともしだいに忘れてゆくものであるが、山王丸さんの記憶は墓場まで持って行くのだろうな、とふと思う。転職ばかりの半生で、どこに行ってもソリの合わない人はいるし、サイコ野郎、ハラスメント上司、犯罪者も見てきたけれども、嫌悪を催すことにかけては随一であった。中途採用でほぼ同じ時期に入社したのだが、年長で業界経験が長いから先輩と言える。
倉林くんとは違って、自分の話ばかりするヒトであった。自分大好き人間の一人語りワンマンショーである。だから知りたくもないのに、彼の情報はどんどん入ってくるのである。
彼にかかれば、一流大学出は、「学校の勉強だけはできるタイプ、クスクス」となり、三流大学出は、「箸にも棒にもかからないよね、クスクス」となる。彼のように二流どころの大学出身者こそが、仕事のできるエキスパートになるのだろう。
ちなみに、この「クスクス」というのほ、クスクスと笑っている様子を表しているのではなく、何か喋ると必ず最後にクスクスと付け加えるということである。その度に身の毛のよだつような想いをしたことは言うまでもない。
「そのクスクス止めろよ!」と怒鳴りつけてやらなかったのが、一生の悔いとなって残った。
バブルの頃は表参道に友だちとデザイン事務所を構えたというのが大の自慢で、国民的アイドルグループのCDジャケットのデザインやベストセラー作家の装丁を手掛けたという。
話を盛っているのかもしれないけれど、おそらくは嘘ではない。息をするように意味のない嘘をつく虚言癖のある輩、自分を嘘で飾り立てる輩、全く現実が見えてなくて歪んだ自己像持っている輩など見てきたが、山王丸さんはそういうタイプではなかったし、業界に明るく仕事もできた。
ダニング=クルーガー効果といって、無能なヒトほど自分はデキると思い込むという心理実験の結果があるけれど、山王丸さんは例外であったと思う。ただ過大な自己評価を押しつけてくるタイプであって、他人を導くよりは貶めるのである。
「その歳で、この業界初めてなんて、信じられない。よく雇ってもらえたよね、クスクス」
私は、自分の耳を疑った。
「向いてない、辞めた方がいいよ、クスクス」
言った方はとっくに忘れているかもしれないが、言われた方はまあ、そう簡単には忘れられないインパクトのある言葉ではないか。
もちろん、自分ばかりが標的になったわけではなくて、相手を選ばない。たとえ電話で取引先とやり取りしているときであっても。
電話となると、ただでさえ嫌らしく不愉快な山王丸さんの声が1オクターブ高くなって、なんだかこちらの頭脳を素手で掴まれてグラグラ揺すられているような気分がして、具合が悪くなった。具体的な症状は、めまい・動悸・バランス感覚の喪失・意識障害・不安などで、今思えばハバナ症候群とピタリと重なる。
「さようでございますかあ!」と何度も馬鹿丁寧な合いの手を入れるのが、恐ろしく耳障りでこちらは仕事どころではない。「はい、はい、さようでございますかあ! はい、はい」
そのまま受話器を置いたから、おや、さすがに取引先にはクスクス言わないのかと思ったら、「ほんと馬鹿だな、こいつ、クスクス」と呟いた。見事なまでに一貫しておる。
いつも鼻が詰まっているようで、口呼吸しかできず、妙に息が荒いけれど、ごくたまに鼻から呼吸が抜けた、ヒュールルヒューと。
自惚れが強く傲慢な山王丸さんであったが、お金に困っているようで、眼鏡のヒンジが壊れたのをガムテープで補修していた。目立たないようにその部分をマジックで黒く塗って隠そうとするから、余計に目が離せなくなる。
マンションの一室を改造して事務所にしているような小さな会社で、昼は皆んなで揃ってランチに出かけたり、弁当を買ってきたりするのだが、「いや、ぼくはダイエット中ですから、クスクス」と山王丸さんだけ輪に加わらない。どうやら、昼飯を抜いているようだった。それどころか給料日前になると、もはや何も食べていないのか、仕事中にぐーっと腹が鳴るのである。
さすがにこれは、と社長が直々に呼び出して、給料の前貸しを持ちかけたところ、「ぼく自身の個人的事情ですから」と、頑として受けつけなかったという。フルタイムで働く壮年のひとり者が空腹に苦しむとは、余程の借金を抱えていたものと見えるが、自慢話ばかりの輩に限って、そういう側面については一切口を噤むものなのである。もちろん私が1ミリの同情も感じなかったことは言うまでもない。
あるとき、山王丸さんと二人で参加した出先での打ち合わせが終わると、ちょうどランチタイムだった。
「せっかくだから、この辺りで食べて行きましょうよ」
「俺は先に戻ってるよ、やることがあるしな、クスクス」と山王丸さん、まるでお前は閑で羨ましいよとでもいうように。
「大丈夫、奢りますよ」
優しさからでは決してない。あのプライドの高い彼が、普段から馬鹿にしている後輩に奢られるのか、そんな好奇心もあったのだろう。果たして、一瞬の逡巡がその瞳に読み取れたが、それはしかし、ほんの一瞬でしかなかった。飢えは人をさもしくする、誰だって飢餓には勝てまい。さすがにちょっと気の毒になった。
山王丸さんが選んだのは、ランチタイム食べ放題1500円のカレーバイキングの店で、ライスとルーを三度ずつお代わりした。ライスは普通の白米、レーズン入りサフランライス、バターライス、ルーはシーフード、ビーフ、バターチキンである。サラダバーには近づきもしない。
制限時間内にどれだけ食べられるか、哀しいまでに貪欲、浅ましいまでに真剣だった。そして鼻呼吸できない人が、口の中いっぱいに食べ物を頬張ると、仕方なく鼻からヒュールルーヒューと息が抜けてゆく。見ているだけで、胸が悪くなり、食欲が失せる。空きっ腹に急に詰め込むと体に悪いかと思ったが、別に目の前で死なれても構わない、いっそ今死んでくれないかな、とも。
ようやくタイムアップし、ひと回り大きくなった腹をさすりながら、「いやー食った、食った」と山王丸さんはご満悦であった。それから、不意に我に返って、バツの悪い表情を浮かべる。
「給料が出たら、倍返ししてやるよ」なんだか傲慢な口調であった。
そんなに食えるわけがない。それで私はこう切り返した。
「さようでございますかあ! でも、山王丸さんみたいに貧しい人からご馳走になるわけにはいかないですう、クスクス」
あのときの彼の眼、もし視線で人が殺せるなら、今頃私は生きていないだろう。今や蛇蝎の如く嫌われていたのは、私の方だった。
(了)
【追記】
本作品は穏当とは言えない言葉遣いや個人攻撃・誹謗中傷と受け取られかねない表現が見受けられますが、著者の意図と文学的試みを尊重するというよりは、恨みつらみを汲み取って、削除・修正せずに発表することに至りました。読者の皆様におかれましてはご賢察の上、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
