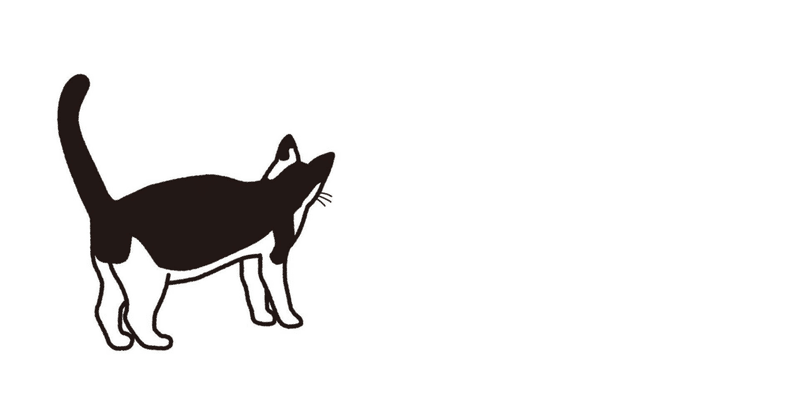
【短編】何も起こらない退屈極まりない田舎の話
山小屋で一泊して下山し、麓の登山口まで戻るともう昼過ぎで、次のバスまで1時間以上あった。
さて、どうするか。このままここでのんびり待つか、それとも歩くか。1時間あれば駅に着く。しかし、それは疲労困憊した自分には、ウンザリするような選択肢だった。かと言って、バスを待ちながらベンチでスマホをいじっているのも面白くない。腹が減ってきた。ザックの底には半ば潰れかけた非常用のチョコとカロリーメイトが残っていたけれど、こういうものは山では美味いが下界ではなんとなく食指が動かない。
そのときである、道路脇の茶屋の存在に気がついたのは。はて、こんなところに食堂があったっけ。来たときに気がつかなかったのは、まだ朝早く閉まっていたからだろう。幟が出ていなければ、仕舞屋風で、周囲の田舎屋に紛れ込んでしまう。
先客はすでに食事を終えて茶を呑んでいる老夫婦のみ。鍋焼きうどんを注文したが、なかなか来そうにないので瓶ビールも追加で頼んでひとりで乾杯した。
夫婦が会計を済ませて帰り、中瓶の二本目も空になる頃、やっとうどんが来て、早速蓋を開けると温かい湯気が上る。
「いただきます!」
ところが、割烹着姿の女将がそのまま立ち去ろうとする気配がないのである。
「お客さん、山ですか?」と話しかけてくる。
そりゃ、格好を見れば一目瞭然でしょ、ザックにストックでドライブする者があるものか、と喉元まで出かかったのをぐっと堪える。
「はあ、山です」
「昨夜は小屋ですか?」
「はあ、まあ」
「混んでましたか?」
「まあ、五、六人でしたか。雪のせいで、みんな山頂へ行かず先に下山したみたいですね」
飯食ってるときに話しかけられるのは苦手だ。これから飯を食おうするときなら、尚更だ。閑なのか。閑なんだろうな、他にお客もいないし。
「雪はどうでしたか?」
「ああ、夕方から降り出して朝にはやんで、元々踝までしなかったのが、深いところで膝まで積もりましたよ。難儀しました」
「こちらも降りましたが、積もるほどではなかったです」
「そうですか」
このままでは、せっかくの鍋焼きが冷めてしまうではないか。頼むから、うどんに集中させてくれ。
「お客さん、どっから来なさった?」
箸で挟んだ麺を口元で持ってゆき、同時に背を曲げて顔の方も土鍋へと持ってゆく、まさに麺を啜ろうというその動作の途中で話しかけられて、ピタリと動きを中断する。そして、そのままの姿勢で首だけ回して女将を見やると、またそこで動きが止まった。
美人である。染めていないから白髪が目立つが、すっと背筋が伸びて良い齢の重ね方をしている。物腰に品があって、淡々と質問を重ねてゆく、その声も柔らかく心地よい。そのことに今気がついた。
「東京から」
「あら、先ほどのご夫婦も東京からドライブしてきた、と」
「自分は電車です」
「ああ、じゃあ駅からバスで。バス会社さんも大変でねえ、もう火の車で。それなのに人手が全然足りないんですよ」
昨日の行きのバスを思い出す。運転手は驚くほど高齢で、ハンドルと比べると遠近感が狂ったように小さく、まるで縮んでしまったようで、運転席の先端にちょこんと掛けている様子にちょっと、いやかなり不安を感じるほどだった。しかし、技術は問題ないどころか、巧みであった。おそろしく慣れているんだろう。
「東京のどこから来なさった?」
「新宿から特急で一本ですよ」
「新宿ですかの?」
「いえ」
「では、立川ですかの?」
「いやいや、その間の特急の停まらない駅」
「わたしは東北からここに嫁ぎました」
地元の人ではないんだ……。
「あ、自分も東京出身ではありません」
「この辺りも、もう若い人たちが皆出ていってしまって、年寄りばかりで、子どももおりません」
質問ではないから、答える必要はなく、とりあえず食いながら聞くことができる。なんとかバスの時刻までに食べ終わらないと。
「子どもらの声が聞こえなくなって、もうずいぶん経ちます。登山者も減って、お客さんは週末にちらほら。それ以外は猫一匹、通りゃしません」
日がな一日、窓の外を眺めているような退屈な日々。たしかに外を見ると、人っ子ひとりいない。もちろん、猫もいない。日曜日の昼下がり、何もかもがひっそりとしている。この集落で暮らしている人たちは、どうやって生計を立てているのだろう。
それからバスが来るまで、女将は喋り続けて、数えてみると「猫一匹通らない」というフレーズを合計で4回も繰り返したのだった。
行きのバスの運転手は小柄で幼な子のように縮んでしまった年寄りで、帰りの運転手も同じく高齢者だったが、長身で枯れ木のように痩せ細っていた。
客は自分ひとり。途中の温泉で中年女性二人組みが乗ってきたが、昨夜山小屋で一緒だった登山客で、軽く会釈する。
バス通りの両脇には農家が並び、その向こうは休耕地がずっと丘まで広がっていた。こんな鄙びた地方で、猫一匹通らない、何も起こらない日々をひとり(というのは勝手な空想だが)で過ごし、年老いてゆくのはどんな気持ちだろうか。自分も元はといえばとんでもない田舎者で、とにかく田舎を嫌い、都会に憧れたものだった。田舎であればあるほど都会への憧憬はいや勝る。
今では連休になると山へ登るが、麓での暮らしなど考えたこともなかった。それが、人手不足で火の車のバス会社で、大型二種の免許を取らせてもらえないものか、そうしたら、あの茶屋の常連になって女将の話を聞きにいくことができる、などと考えている。それとも、彼女の方が都会へ出てくるというのは、どうか……。
「猫一匹、通らないか……」ふと呟きがもれた。
と、急ブレーキが踏まれ車体が大きく揺れて、その反動で体が前へ持っていかれる。後部座席の方から悲鳴が上がった。もの想いから不意に我に返り、慌てて手すりを掴んで何事かと身を乗り出す。
すると黒猫が一匹、舗装道路を走って横断してゆくのだった。フロントガラスに切り取られた田舎の光景の中を、右から左へ一目散に。わからないのは、他に車一台走っているわけでもないのに、一体なぜこのタイミングなのかということだ。
いや、通ってるじゃん、猫! 思わず指差して突っ込んでいた。
(了)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
