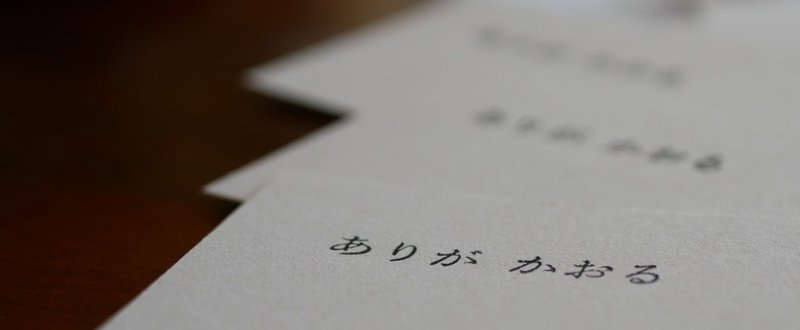
アウトプットが一番の学習
リクルートワークス研究所の研究プロジェクト『人生100年時代の学び方』レポートの中で、“学びの進化形”として、私自身について紹介していただいた。私のここまでのキャリアと、スープ作家になるまで何をどう学んできたかという話だ。
積み上げてきた「好きなこと」を統合し、スープ作家という新しい道を創り出す|人生100年時代の学び方
実は私は飲食店で働いたことも一切なく、料理学校へも通ったことがない。いわゆる修行というものとは無縁なまま食の世界に入ってしまった。そもそも、食を仕事にしようと真剣に思ったのが50歳からなのだ。正直なところ、修行を積む時間など残されていなかったし、たとえ時間があっても同じ修行をした20歳にはとても勝てない。
そこで私は、ぶっつけ本番でやることにした。「ここにスープ作家がいますが、本を作りませんか?」と出版社にかけあい、SNSでスープ作家としてレシピの発信をはじめた。そして「スープ・ラボ」というスープのイベントを月一度、開催した。書いてみるとあまりのお粗末さに恥ずかしくなるが、そうした活動が、記事ではこうなる。
その中心にあるのは“発信力”。SNSを活用したり、展覧会やイベントを企画したりと、有賀氏はアウトプットの機会を積極的に設けることで、他者から得られる反応、評価を学びに変えてきた。つまり、アウトプットと質のいいインプットを循環させ、自分を拡大しているのである。
学びのプロが「これは学びだ」とお墨付きをくださったので、ここからは堂々と学んできた、ということにして。
ライターとして長年やっていたので情報の集め方や記事としてのアウトプットには問題がなかったし、絵を真剣にやっていたことがビジュアル面では役立った。展覧会の開催にも慣れていたし、短い会社員時代にはイベントも企画していた。問題はやはり料理の知識や経験だ。ここにアプローチしたのが、スープ・ラボだ。
スープ・ラボで「塩」「豆」「だし」など、決めたテーマをしゃかりきに詰め込み、食材を何種類も味見して、スープレシピをいくつも作る。お客さまは知り合いが多かったが、食いしん坊ばかりだから手抜きもできない。毎月ごとに期末試験がやってくるようなものだった。
目的のあるインプットは身につくというのは、本当だ。料理の知識だけではない。人が何に関心を持ち、どんなものをおいしいと思うか。それは現場で出してみるとすぐわかる。お金をとると、またその価値が変わる。毎回が大きな勉強だ。それを体感することは、プロとしてとても重要なことだ。
一流のプロたちはよく、仕事を勉強の場にしてはいけないという。まあ、私もそうだろうと思う。けれど、誰もが正しい修行の道を踏んでプロとして育っていけるとは限らない。私のように子育てを終えてから仕事に真剣に取り組むとき、一から学ぶのではなく、これまでの経験を集めて不揃いな寄木細工のように組み合わせ、足りないところを走りながら補っていくような学び方もある。なしだとしても、そう思わなければ、あきらめるしかなくなってしまう。みっともない方法かもしれないが、恥ずかしいよりやりたいという気持ちが上回ったら、そうするしかない。
まだ私の活動は始まったばかりで、これからどうなるのかは全く想像もつかないけれど、こうして自分のことを書いてもらったことは、人生100年時代の学びや働き方について、考えるいい機会になった。
noteはクリエイターの集まるプラットフォームなので、こんな話もいいかなと思って書いてみました。記事、良かったら読んでみてくださいね。

スープラボで自分としては一番勉強になった「豆」の会。
読んでくださってありがとうございました。日本をスープの国にする野望を持っています。サポートがたまったらあたらしい鍋を買ってレポートしますね。
