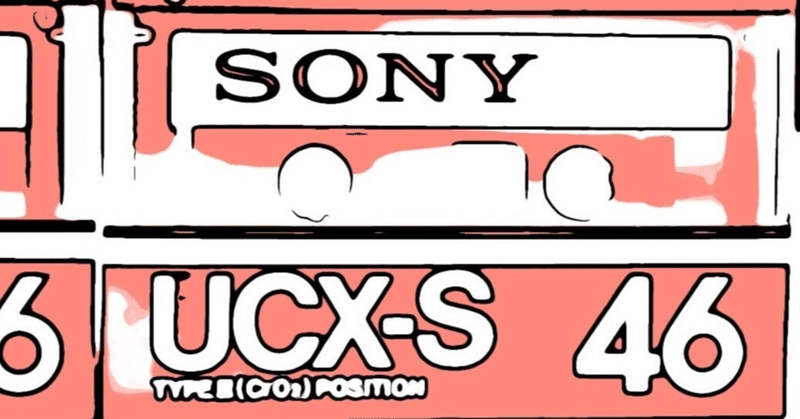
倍速人生について
情報処理能力の個人差は著しい。
平均に合わせるよりも、能力別クラスの方が効率が良いという話を前に書いたことがあるが、同じ理屈で、動画撮影された講義をそれぞれの理解度に応じて視聴するようにすれば、わからなければ同じところを何回も繰り返して視聴できる一方で、できる学生はどんどんと先取り学習することも可能となろう。
コロナ渦で大学の講義のオンライン化が当たり前になったが、大教室に何百人も詰め込んでマスプロ講義をするよりも、オンラインによる動画配信の方が「使える」ということになれば、仮にコロナが沈静化しても、講義のやり方を元に戻す必要はないように思う。
一方通行の情報提供のような講義については、基本的に動画配信。それぞれの理解力やスピードに応じて、在宅で各自が学習を進める。オンライン配信中心の大手予備校チェーンと同じ理屈である。そちらの方が効率的である。
オフラインでやるのは、ゼミとか実習の場合に限定する。ゼミだってZoomでオンラインでやれなくもないが、対話というのは、やはりリアルに同じ空間でやった方が良い。1on1であっても同様である。何でもすべてオンラインにこだわる必要はない。
教官サイドも、そちらの方が絶対に効率が良い。同じことを何回も喋る必要がない。ちゃんとしたコンテンツを作れば、リニューアルは必要だとしても、オンラインでやれることには手を省いて、対面で取り組むべき教育や研究に注力可能となる。
そうなると、学生も教官も、できる人とできない人の差がどんどんと開いてくるのは避けられない。
普通の学生のスピードで学期中に100のレベルまで到達することが期待されているカリキュラムがあったとして、いくら頑張っても70までしか到達できない学生がいる一方で、200や300まで楽々と到達できてしまう学生が出現することになる。マスプロ講義と違って、各自のペースと裁量に任されてしまうからである。ぐんぐんと進む学生は、大学4年分の過程を1年くらいで終わらせてしまうかもしれない。
教官も同様である。「十年一日」のごとく同じノートを読み上げて、仕事をしたフリをしていたような教官は、空いた時間を使って何をやれば良いのかわからなくなる一方で、「水を得た魚」のごとく研究活動に邁進して目覚ましい実績を上げる教官もいる。この差は大きい。
企業も同じである。新卒一括採用である一定の年次までは横並びというのが、日本企業の慣習みたいなものであったが、こういうやり方は、もう時代遅れなのであろう。そもそも、若い人たちの支持は得られない。特に優秀な層をスポイルする危険性がある。
これまでのやり方、すなわち平均値に合わせる教育や、横並びの人事というものは、「右向け右」と命令されたら右を向くような従順な兵士を育てたり、可もなく不可もない標準的なサラリーマンを育てるためには適したやり方であったかもしれないが、もはや、AIに代替される凡庸な人間ばかり育てて仕方がない。
同じ人間はいない。皆んな、それぞれの向き不向きがある。鋳型にはめるのではなくて、向いているところで自由にやらせる。各自の心地よいスピード感に基づいて学ばせる。心地よいスピードと言っても、アマチュアランナーと、箱根駅伝に出場するトップランナーとは違う。それぞれの心地よさを邪魔しないことが大切なのである。
いまはIT技術の発展もあって、やろうと思えば、そういうことが可能な時代なのである。にも拘らず、教育現場は明治時代と基本的に何も変わっていないところに問題がある。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
