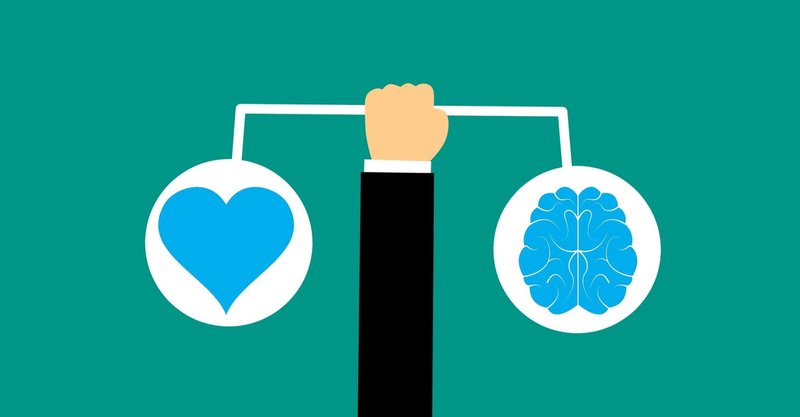
ストレスへの対処行動とその意義
ある日、ストレスが溜まったり気分が落ち込んだりしているときに「すると良いとされる行動」や「ついしてしまう行動」は身体にとって本当に理にかなっているのか?という疑問を持ち、考えうる対処行動を列挙してそれらがどんな生理的反応を引き起こすのかを調べてみました。
100近く挙げた対処行動は、6つのカテゴリに(勝手に)分類しました。
▶対処行動の6分類
1.栄養
2.運動
3.睡眠
4.社会活動・交流活動
5.文化活動・創作活動(個人活動)
6.投薬
そしてほぼすべての行動が脳内の3つの神経伝達物質の少なくともいずれかへ働きかける作用があることが分かったため、行動単体ではストレス状態からの回復に効果があると説明できました。(特に「ついしてしまう行動」群にもはっきりとした意義があったことは発見でした。)
▶ストレスや鬱に関係する神経伝達物質(モノアミン)
ノルアドレナリン
ストレスに反応するホルモンで、思考力や集中力、積極性を司ります。過剰になると攻撃的になったり、ヒステリーやパニックを引き起こしたりします。
ドーパミン
ドーパミンは楽しみや快楽を司ります。欠乏すると、無関心や疲労、気分のむら、倦怠感を招きます。逆に過剰分泌は、幻覚や妄想、依存症を引き起こします。
セロトニン
正常に分泌されていると、ノルアドレナリンやドーパミンの過剰放出を抑えて心のバランスを正常に保つ役割を果たします。セロトニンの低下は、やる気の喪失や食欲減退の原因となり、体温や社会的行動の変化にも繋がります。
ただしここで「行動単体」としているのは、あくまでこれは特定行動の一次結果と神経伝達物質との関係性のみに着目したにすぎないということです。
例えばストレスが溜まってギャンブルに走るという行為は、ドーパミンの分泌を助ける一方で、過剰分泌による依存や多額の金銭を失うことにより社会生活を困難にするリスクがあります。また仮に本心では「ギャンブルはいけないことだ」という価値観を持っているとすれば、ギャンブルに対する否定的イメージとその行為に走る自己否定感情が一致して「負のコンフォートゾーン」から抜け出せなくなる可能性もあります。
一方で、私がお会いした方の中に筋トレで鬱病を克服されたという方がいらっしゃいました。これは運動自体にセロトニン分泌を促す効果があることに加え、トレーニングによる体型変化がポジティブな社会的認知の変化を招くと期待することで、ドーパミンの分泌も同時に促したのだと考えられます。
このようにひとつの行動をとってみても、それが影響する範囲や二次以降の効果を考えたうえで「マイナス効果が少なそうなもの」や「多方面にわたってプラス効果がありそうなもの」を選択するのが望ましいのではないかと思います。そういう意味で、6分類の何れかに綺麗に収まるものよりも、複数の役割を持つ方が高い効果を期待できそうです。
以上のような観点からおすすめの対処行動をピックアップしてみましたので、次回以降ご紹介していきたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
