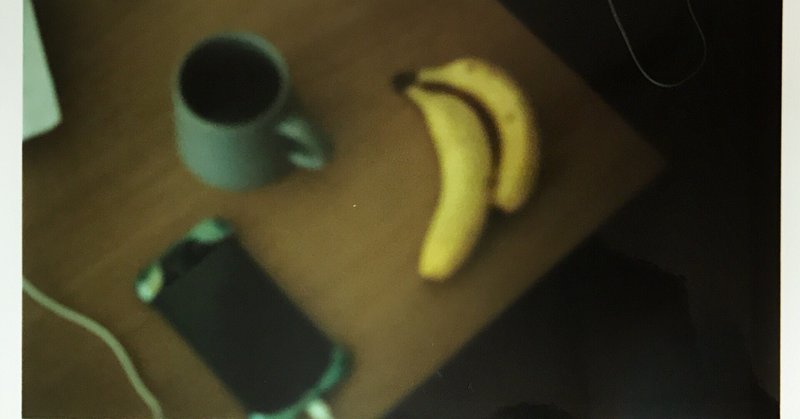
聞く、話す。
尹 雄大さんの『聞くこと、話すこと』を再読している。
なんといってもドライブマイカーの濱口竜介監督へのインタビューが収録されていることが僕にとっては垂涎ものです。
濱口監督の作品では”聞く”や”話す”という中で何かが展開していってしまう様が描かれていると思う。
それをカメラで撮って映画という形で出しているのでフィクションといえばフィクションなんだけど、ドキュメンタリーみたいに見える時がある。
本の中で印象に残っている箇所を引用する。
見たい演技が現場で起きているとき、「自分の目の前で今、空間の質が変わったような感覚」が立ち上がる。カメラは”それ”をすべてでないにせよ撮っている。そうした変容がどうしてかはわからないが時折起こる。
濱口監督の作品には確かにこういった瞬間がログされており、それが再生される。僕も人生の中でこれに近しい瞬間を経験した気がするがそういったものは現実的に日常生活の中で起こるので当然録画などしていないし、狙って引き起こすようなものでもない。通常は。
人と人との関わり合いの深淵を覗くようなタイミング人生にはあると思う。
ところが、濱口監督の作品の中にはたびたび上記のようなシーンが映し出される。
また別部分を引用してみる。
「ああ」という語そのものには意味がない。意味はないけれど、私たちは心がひどく揺さぶられると「ああ」とうめく。うめくとは唸ること。意味を考えて「ああ」とうめくわけではなく、思わず出てしまった。そこに意味はない。
声というチャンネルは音だ。
喋るということは音を出すということで、必ずしも我々は意味だけを吐いているわけではない。
相手の言っている言葉の意味を受け取ることよりも、音を聞くことのほうが大事な時は多々ある。
僕の理解では話を聞くというのは、一緒にいるということに近い。
解釈や思考ではなく感じながら一緒にいること。
さらにこれに表情や抑揚、身振りや体の動きなんかも投入されるので人が話すときには様々なパートが同時進行的に楽曲を演奏していることになる。
この演奏をたっぷり感受することは随分に豊かだと思う。
養老孟司さんは、社会が脳化しているという。
いろんなことが数字や言語で処理されているけれど、「わかる」ことの本質は共鳴だと書いている。それは「なんだか気持ちがいい」とか身体性を伴った感覚のことで、情報処理的というより感覚的な話として了解できる。
こちらも指し示していることは感覚や感受の話かと思う。
僕らは今、自分たちの身体性をしっかり守らないとあっという間に機械みたいになってしまう重力場(社会)に暮らしているのかもしれないね。
茨城のり子さんが今生きていたら
「自分の感受性守るの、、割と大変ですよね みなさん」
と口籠っただろうか。
最後に、コミュニケーションに関する記事で最近気になったものを。
本音を押し殺して指示に従う。パトリアルキー(支配構造)を超えて自由になるためにできることとは? ソーヤー海が考える。(前編)
という取り留めもないことを。
お読みいただきありがとうございます!
