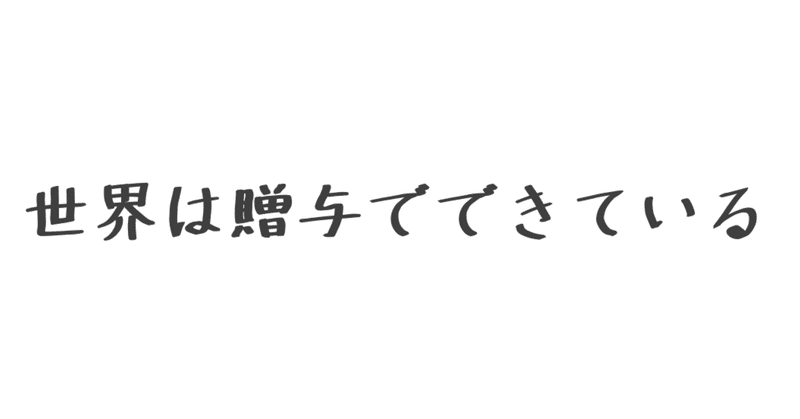
壮大なる贈与に気づき、流れの一部になることで、人生が少しだけ豊かになる。
「なんで周りのことを考えられないんだ!」
「自分のことしか考えてない人が許せない!」
他者に対して、そんなことを思ったことはないだろうか。もしくは、
「こんなに頑張っているのに!」
「これだけ尽くしているのに!!」
と嘆いている人に出会ったことはないだろうか。
私はある。当事者であることもあれば、他者でそういう人と遭遇したことも。
その度に私は、違和感を感じていた。みんなが誰かのために動けば、良い関係性を作っていけるのに。なんでそんな当たり前のことができないんだろうと。
その違和感についての答えのヒントが、「世界は贈与でできている」という本の中に書いてあった。
たまたま手に取った本書だが、私にとっては納得感が高かったし、読んでよかった。冒頭の悩みに対しても、これまでと別の角度の視点を手に入れたし、何だか腹落ちした。
なので今回は、本書を読んだ私の解釈を書いていこうと思う。
与える人も受け取っている
本書では、人は贈与する事によって、与えられるだけではなく自分も何か得ている。むしろそちらの喜びの方が大きい。とされている。
この主張に対してパッと思いついた言葉が「貢献欲求」である。人の役に立って良い気持ちになった経験は、誰しもあるだろう。おそらくこの感覚が、もっとも身近でわかりやすいのではないかと思った。
これは最近聞いた話なのだが、電車で席を譲る人は、譲られた人の3倍の幸福感があるらしい。与える側の方が、幸福感が高いというのだ。
また、つい「自分でやった方が早い病」という書籍にも近しいことが書いてあった。
この本によると、してもらう喜び→自分でできる喜び→してあげる喜びの順に、喜びが大きくなっていくらしい。ここでもやはり、最上ランクは「してあげること」とされていた。
となると「してあげること」、つまり贈与の数が大きくなるほど、世の中の幸福度が最大化されるのではないか。率直にそう思った。
あげる人が嬉しくなるから世の中が成り立つ。もっと大きな話をすると、そういうマインドを持った人が多い国は、必然的に豊かになっていくのではないか。
逆に、もし仮に貢献欲のようなものが存在しない世の中になったら、きっと冷たく、そしてつまらない世の中になってしまうだろう。ある意味では合理的で完璧なのかもしれないが、それではさすがに寂しすぎる。少なくとも私は嫌だ。
そもそも、本書によるとそういう経済社会の隙間こそが贈与でてきているらしいので、おそらくその隙間を失えば、どこかでうまくいかなくなる。
人間らしい暖かい社会を形成していくためには、贈与の循環を回していく必要があると感じたし、そのためにまずは私のできることをしていきたい。
「贈与」に気づくことから始める
とはいえ、自分自身は贈与されていないのに無理に与えようとすると、偽善や自己犠牲に繋がる。本書では以下のように書かれていた。
結局、贈与になるか偽善になるか、あるいは自己犠牲になるかは、それ以前に贈与をすでに受け取っているか否かによるのです。
まずは自分自身が受けなければならない。もしかしたら無条件な贈与に批判的な人は、これまで十分な贈与を与えられて来なかったのかもしれない。
人によっては、これまで十分な贈与を受けて来なかったかもしれない。そんな人がいきなり「圧倒的なGIVE」をやってしまうと、おそらく自己犠牲的になる。
「こんなに頑張っているのに!」「こんなに尽くしているのに!!」という人はそれの典型かもしれない。先に与えようとするから、おかしな事になってしまうのだ。
ただし、誰かに「贈与してください」というのも違う。じゃあどうすればいいか。本書に答えがあった。
それは、すでに受け取っている贈与に気づくことだ。
本書からそのまま引用すると以下になる。
つまり、被贈与の気づきこそが全ての始まりなのです。贈与の流れに参入するにはそれしかありません。
つまりどういうことなのか。
感覚としては、SF映画を見た後の日常の感覚がそれに近いとのこと。ハラハラした気持ちの後には平和な日常に感謝できる。そういう特別なシチュエーションの後にしか実感できないが、当たり前の毎日でも、実は誰かから何かを受け取っている。この平和な生活そのものが、既に先人たちからの贈与なのだ。
その他の例として、「歴史を学ぶ」ことも、贈与を実感する手段として挙げられていた。昔の人はどんなことに悩んでいたのか、どんな気持ちだったかを考えるだけで、今の自分がどれだけ先人の贈与の中で暮らしているかがわかる。
もっと身近な話をしよう。めちゃくちゃ面白い文章をnoteで無料で読めたとする。これはもう立派な贈与なのだ。だって無料で楽しい気分にしてもらったのだから、良い可処分時間をいただいたと言っても過言ではない。だから自分もその分、何かしら世の中に還元したいと思える。
スマホアプリで楽しめるのもそうだ。ゲームには人類の叡智が詰まっている。楽しむ事に関して追求してきた結果だからだ。江戸時代の人間は将来、あんなものができるなんて、誰も想像していなかった。当時からスマホゲームがあったら、年貢も米ではなく魔法石だったかもしれない(それはない)。
ハンバーガーが100円で食べられるのも、お風呂がすぐに沸くのも、ボタンを押せば部屋が暖かくなるのも、ネトフリで動画見放題なのも、全て先人の恩恵を受けている。圧倒的な贈与なのだ。
そういった見えない贈与に気づかないと、時には自己犠牲的気分になるかもしれない。ひどい場合では、他者から「搾取」されている感覚を受けるかもしれない。そうならないために、まずは受け取っているものに気づくところから始める必要がある。
恩送りで、世の中をもっとよくする。
まずは贈与に気づくことからはじめ、受け取ったものを次に送っていく。本書でもペイフォワードの映画の話があったけど、「恩送り」のようなマインドを皆が持てば、きっと、もっと良い世の中にできる。
ビジネスにおける知見なんかもそうだ。最近では企業に務める社員が発信をするケースも増えているが、学んだことは発信して、後世に語り継いでいくべきなのだ。
もちろん何でもかんでも発信すれば良いという訳ではないし、すでに世にある情報を複製しても仕方がない。でも、自分自身が経験を通して発見した知見があるならばリリースしていった方がいい。そもそも自分自身も他者から学んできたのだから、そのくらいは世の中に還元したい。
人類が積み上げてきた現代の環境や叡智、そして日常で得ることができる贈与を次の世代に送っていく。その行為こそが、自分への贈与にも繋がるし、タスキを繋いでいくことになる。そして自分も大いに受けてであろう。それ自体が、贈与にもなりうるのだから。
...と、偉そうに書いてしまったが、私としては楽しい人生を歩ませてもらっている分、楽しいコンテンツを提供していきたいし、関わる人を楽しませていこうと思う。1人ではどうにもならないかもしれないけれど、せめて受けた分の贈与はどんどん世に送り込んで、大きくしていきたい。
少なくとも自分と自分の周りがそういうスタンスになったら、自分の生きている生活圏の世界は平和になると思う。大きな世界と小さな世界、色々あるけども、結局自分ができることをやるしかないのだ。だからまずは、この壮大な贈与に気づくところから始めたいし、気づかせてあげたい。
本書にも以下のようなことが書いてある。
逆説的な事に、現代に生きる僕らは、何かが「無い」ことには気づくことができますが、何かが「ある」ことには気づけません。
その通りだと思う。不健康な状態には気づくが、健康を実感することはあまりない。だから、気づいてもらうには、実感できる何かなのだ。それを押し付けてはいけないが、自ら気がつくための援助はできるかもしれない。そう、『アンサングヒーロー』として。実は、それが一番難しいのかもしれないが。
「世界は贈与でできている」って、正直最初は大げさなタイトルだと思ったけど、あながち間違いではないのかもしれない。そんなことを思った。さて、この受け取った贈与を次は誰に送ろうか。
冒頭に書いた他者への違和感は、おそらく贈与の流れへの参入者を増やすことで減らすことはできる。ただ、強要はよくないし、伝え方は気をつける必要があるのはわかっている。その上で、自分ができることからやる。結局はそれしかないのだ。
ひとまず今回は、本書から学んだことを、感想文として世の中に還元する。受け取った人は、ぜひ次の誰かにこの贈与を繋いで欲しい。
この記事では贈与の明るい面ばかりを書いたが、本書では贈与の持つ「呪い」や注意点も多く記載されている。もし、気になる人がいたら、手に取っていただきたい。
今回は以上。
小木曽
Twitter→小木曽
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
