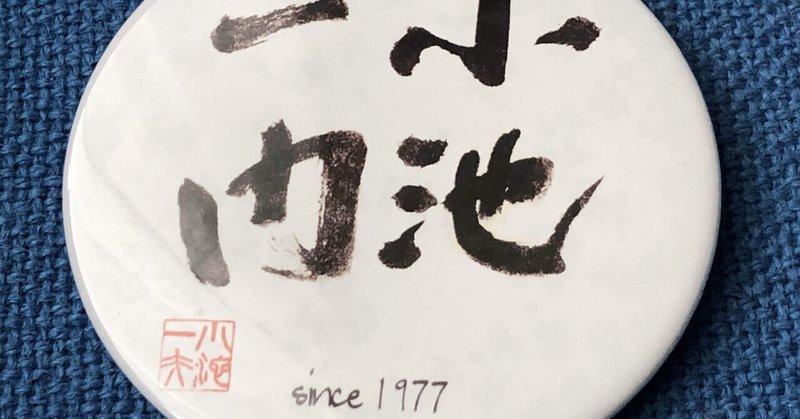
"キャラクターを起てろ!"劇画村塾第4期生 第1章(4)
<課題作品提出一度に十本も?!〜先輩の伝説の提出本数に衝撃驚愕!そして、小池一夫御大の面接へ>
いずれ課題が出されるということは、最初の講義で、小池先生からも、事務局のSさんからも告知はされていた。
さらに、先に”伏線”と記したが、それは以下のようなお話を、あらかじめ聞いていたからだ。
狩撫麻礼先輩が、入塾生に向けたメッセージの中で、
「皆さん、課題が出されたら、できるだけちゃんと提出したほうがいいと思います。プロになったら、締め切りに追われます。僕は、デビューしてから、課題で出したネタは、すべて使っちゃってます」
そのように話されていた。
そして、それを補足するような形で、小池先生が講義の中で、
「狩撫は凄いぞ。一度に十本くらい書いて出してきたからね」
と、おっしゃられていたのだ。
一度の課題作品提出時に、一気に十本!
大きな衝撃を受けた。驚愕した。
(そうか、プロになったら、締め切りがあるのは当然として、もし何本か同時連載を持ってるとしたら、商品として認めてもらえるレベルのものを量産していかなければならない。狩撫先輩ほどの人でさえ、塾時代に作ったネタをブラッシュアップして使う必要が生じるということは、やっぱり半端ない世界だな、こりゃ……)
同時連載とか量産とか、ちょっと考えただけでも気が遠くなりそうだった。
(ちなみに、この当時の小池先生の同時連載本数は凄まじく、その記録は、おそらく今現在も誰にも抜かれていないものと思われる)
(それにしても、十本も作品を提出するなんて……狩撫先輩は確かに凄い!)
素直に感動感嘆し、次に単純にこう思ったのだ。
(十本なんて、逆立ちしても無理だけど、二本くらいなら、俺でも、なんとかデッチ上げられるかもしれない。とにかく、それくらい書かないと、小池先生に認めてもらうことはできないってことだよなあ……)
このエピソードには後日談があって、後年、狩撫麻礼先輩にそのことを話すと、
「バカヤロー、俺がそんなニューミュージックの連中みたいな真似をするかよ!ただ、大友克洋みたいな凄い漫画家が組んでくれるとなって、嬉しさのあまり何本か書いて出したけどな。さすがは大友克洋で、俺が一番出来がいいかなと思ってたやつを選んでくれた」
と、言われた。
小池先生の御発言はここからきていたものと推察できる。
しかし、当時は、そんな"真相"など知る由もない。
周囲を見回すと、同期生は六十人近くいる。
一年後、ふるいにかけられて、それが半数に絞られてしまう。
残った半数が、”特別研修生”として、完全無料の講義を引き続き受講できるのだ。
プロになれるかどうかは別として、せっかく借金までして入塾したからには、せめて残る半数には選ばれたいと思った。
そのためには、なんとしてでも、それなりの課題を提出して、小池先生の目に留めてもらうしかない。
“伏線”となった話とも相俟って、課題提出が求められた、その講義の帰り道から、さっそくああでもないこうでもないと、ネタの練りを始めた。
不思議なもので、そのタイミングに合わせて、もう一つ、課題絡みの出来事があった。
劇画村塾での講義風景が、テレビ番組で取り上げられたのだ。
(自分達の時の講義風景が収録されたものだったのか、それより以前のものだったのか、記憶は曖昧なのだが、オンエアされたのは間違いない。テレビで観たことだけは、今も鮮明に覚えている)
その中で、小池先生が、自分の原作原稿をサンプルとして提示されていた。
(初めて見るプロの原作原稿! それも小池一夫御大のだ!)
食い入るように見入ってしまった。
小池先生の原作原稿には、なんと、表紙が付けられていた。
そして、その表紙は、自らの手作りでもあった。
池上遼一先生が作画を担当された『I・餓男(アイウエオ・ボーイ)』の原作原稿だった。
タイトルが筆文字で書かれ、そこに写真がコラージュされたものや、アヴァンギャルドな絵が描かれたものなど、とにかくダイナミックで目立っていた。
(表紙まで付けるんだ。さすがプロ! ……というか、そこまで作品に心血を注いでいるのか!)
感動を覚えて見ていると、小池先生が言われた。
「こういう表紙が付いた応募原稿が送られてきたとすると、選ぶほうはどう思う? 素っ気ない原稿用紙だけの中に、お! なんか妙なのが混じってるぞ、と真っ先に手にとってくれるかもしれない」
(なるほど!)
またしてもストレートに膝を打ってしまった。
(作品が書き上がったら、俺も目立つ表紙付けなきゃ!)
さっそくそう決めた。
とはいえ……。
そんなに簡単に作品が書けるはずもない。
いくら考えても、いっこうにまとまらない。
ただ、自分の中のテンションだけは、ずっと高いままだった。
それだけ、小池先生の講義は面白く、ど素人の身にとっては、目から鱗の連続だった。
そのテンションにだけ支えられて、寝ても覚めても、課題の原稿のことを考え続けた。
生活のために、映画館のアルバイトには、ほぼ毎日通っていた。
当時の映画館のアルバイトのいいところは、映画の上映中は、途中入場のお客さんさえ捌いていれば、あとは座っているだけで許されたことだ。
その時間を利用して、ひたすら課題のネタを夢想した。
才能などとは関係なく、考えつづければ、それなりに何かは浮かんでくる。
課題提出日は刻一刻と迫って来るので、いつまでも考えてばかりいるわけにもいかない。
意を決して、原稿用紙に向かった。
(ちなみに、劇画村塾の原作用原稿用紙は、小池一夫先生の特注品とまったく同じ体裁で作られたものだった。デビューしてからしばらく後まで、自分はこの原稿用紙を使っていた)
頭の中で、ある程度はできているのだが、いざ実際に書き出してみると……これが思うように書けない。
おまけに手書きなので、ちょっとミスしたり、書き直したりとなると、修正液を使ったり、切り貼りしたり、最初に戻って一から始めたりと、大変な労力を要することになる。
アルバイトは午後からのシフトだけにしてもらって、日々、夜から朝まで課題原稿を書き続けた。
結局、なんとか頑張って、強引に複数本の原稿を書き上げた。
(正確な本数は記憶していない。たぶん、二本か三本ではなかったかと思う)
そして、雑誌から切り抜いた写真をコラージュして、表紙を作って付け、紐で原稿を綴じた。
アルバイトが終わるやいなや、一目散に電車を乗り継いで、都立大学へと向かった。
いよいよスタジオ・シップ本社で、第一回目の課題原稿を提出することになったのだ。
同期のメンバーも、きっとそれぞれに力作を書き上げて、持って来るに違いない。
そんな作品群の中から、果たして自分のものは小池先生のお眼鏡にかなうのだろうか。
不安と期待がごちゃ混ぜになった思いで、社屋までの坂道を歩いた記憶がある。
課題は、事務局のSさんが受け取って下さったと思う。
もちろん、すぐ読んでもらえるわけではなく、小池先生の講評は次の講義の時にでも、ということだった。自分の中の不安と期待は、さらに延長されることとなった。
同時に、近いうちに、全塾生に対して、小池先生の面接があるという告知が行われた。
御大自ら面接!
聞いただけで、緊張のあまり心臓が縮んだ。
〈続く〉
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
