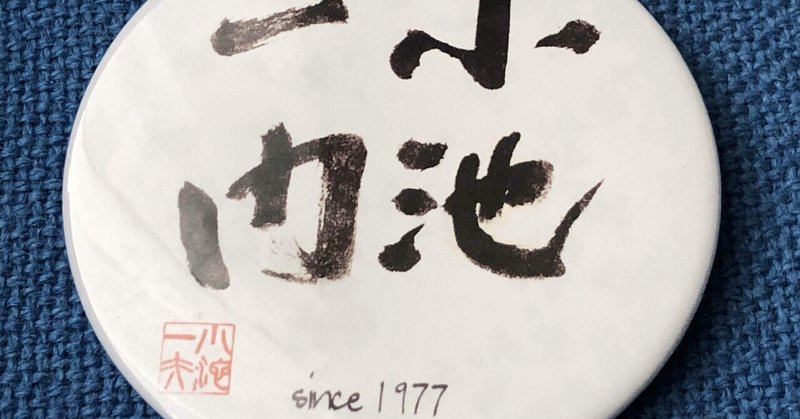
"キャラクターを起てろ!"劇画村塾第4期生 第2章〈5〉
<漫画原作者デビューが決まり、六本木のショーパブに取材にまで連れて行ってもらったにもかかわらず……原稿がまったく書けないという根本的な大ピンチ!>
小池先生の、まさしく鶴の一声で漫画原作者としてのデビューが決まった。
が、嬉しいとか、やった!とかいう高揚感は、まったく湧いてこなかった。自分も『コミック劇画村塾』に作品が載ったらいいな、と考えていたにもかかわらずだ。
あまりに突然ということもあったが、
(俺なんかに商業誌に載せてもらってもいいレベルの作品が書けるのだろうか? それに、漫画家さんは誰になるんだろう? こんなド新人の原作を作画してくれる人なんて、いるんだろうか?)
たちまち、その不安に捉われてしまっていた。
自分のリアクションがちょっと薄かったせいか、小池先生は、
「漫画家は彼にしたぞ」
と、雑誌から切り抜いた作品を手渡してくださった。
その作品には、”愛川哲也"という名前がクレジットされ、純朴な感じの可愛らしいキャラクターが描かれていた。
「女の子のキャラクターがいいし、おまえの原作とも合うんじゃないかと思ったんだよ。あとは編集長のKと話してくれ。取材も行っていいからね」
「え? 取材ですか?」
「ほら、劇村の講義でもちょっと話した、六本木にある店だよ。原作で使ってもいいし、使わなくてもいいから、とりあえず勉強のために行ってくればいい」
「あ……あの先生がお話しされていた……」
六本木にある某店の話は、小池先生が特別研修の講義でも紹介されていた。
ニューハーフの人達のショーを売り物にした人気店とのことだった。特に店長を務めるLさんは、テレビや雑誌などでもしばしば取り上げられるほどの”美女”だという。
小池先生御自身が編集者諸氏に連れて行かれて、Lさんのキャラクター性とメンバー達のショーにすっかり魅了されてしまったというお話だった。
とにもかくにも、自分のデビューを決めてくださった小池先生に御礼を述べると、さっそく『コミック劇画村塾』の編集長のKさんと対面することになった。
Kさんは、いかにも叩き上げの編集者といった感じの人で、関西訛りの口調で、粘り強く話される方だった。(ちょっと話が長いのが玉に瑕だったが……すみません、Kさん)
小池先生原作の名作『御用牙』を起ち上げたり、望月三起也先生の『秘密探偵JA』や『ワイルド7』などを世に出した立役者でもあった。漫画界劇画界の裏話をずいぶん聞くことができて楽しかったが、それはもっと後年になってからの話である。
まずは、Kさんに連れられて、コンビを組むことになる愛川哲也先生のところへ御挨拶にうかがった。
愛川先生は、その作風からも想像していた通り、気さくなスポーツマンタイプの方で、新米の自分にも構えることなく、フランクに接してくださった。
まだ、どんな原作を書くのか、書きたいのか、まるで浮かんではいなかったが、とりあず、小池先生が紹介してくださった六本木の店へ、K編集長、愛川先生と共に行ってみることになった。
それまでにも、アルバイト先の社員の方に連れられて、六本木で飲んだり食べたりしたことはあったが、ニューハーフの人達がやっているショーパブというのは初めてだった。
小池先生がおっしゃっていた通り、そのショーは確かに見応え十分だった。(今でもはっきりと覚えているのは、マイケル・ジャクソンの『スリラー』のダンスを、メンバー全員で完コピしてパフォーマンスしていたことだ)
さらに、噂の店長のLさんが、自分達の席につきっきりになって、いろいろと話してくださった。
これまた小池先生がおっしゃっていた通り、めちゃくちゃ綺麗な人で、なおかつ話も異様に面白かった。若い田舎者の自分は、とうてい取材どころではなく、ただただ見とれ、聞き惚れていただけだった。(それが、後年、六本木や西麻布界隈で毎夜遊びまくるようになってしまうのだから……人間というやつ、ホント分からない)
その後も、K編集長は、新宿の歌舞伎町にある、やはり有名なショーパブに、愛川先生と自分を連れて行ってくださったりした。
K編集長にしてみれば、これからデビューする新人作家に、少しでも構想のプラスになれば……という親心だっただろうが、なにしろこちらはまだ素人も同然、見るもの聞くものに魅了されるばかりで、構想らしきものは影も形も浮かんではこなかった。
『コミック劇画村塾』は月刊誌だったが、ひと月など、たちまち過ぎてしまう。
愛川先生と自分がコンビを組んで連載を始める作品がスタートする号は、すでに決められていて、日々締め切りが迫ってくる。
生まれて初めて経験するプロの締め切り。
漫画家の先生方のインタビューなどで、いかに締め切りが苦しいものか、知ってはいた。あくまでも他人事としてだ。それが実際に我が身にも降りかかってきてみると、まさに地獄の苦しみだった。
劇画村塾の課題の締め切りであれば、作品ができなくて提出できなくても、漫画家さんに迷惑がかかるとか、雑誌に穴があくとか、そういう問題は起きない。
が、今や、曲がりなりにも"プロ"のハシクレとして、期限までに”商品”を仕上げなければならない。
そのプレッシャーが、日々、全身にのしかかってくる。
当時はまだ携帯電話などないので、K編集長から、アパートに催促の電話がかかってくる。
(この当時は、すでに、長年住み暮らした池袋から、スタジオ・シップ本社のある都立大学の安アパートに転居していた。このことが、さらなる劇画村塾絡みのエピソードへと繋がっていくのだが、それは後述する)
最初のうちは電話に出ていたが、そのうち、受話器が取れなくなってしまった。
電話が鳴り出す寸前、ほんのわずかにカタッと電話機が震える。その音を聴いただけで、両手で耳を塞いでしまう始末。
しかし、まったくといっていいほど、作品の構想が捻り出せない。
だからといって、いつまでもK編集長の電話から逃げているわけにもいかず、気分転換に外へ出た時に(本当はアパートの電話から逃げ出した時に)、公衆電話から連絡を入れた。
K編集長は、怒鳴ったりするような人ではなかったが、それでも、その口ぶりから、
「おまえ、ええかげんにせいよ」
というニュアンスが嫌というほど伝わってきた。
もう待ったなしである。
アパートに戻って、とにかく、書き始めた。
が……。
我ながら、ひどい出来のものしか書けない。
そんなものを出すわけにはいかない。
また、一からやり直し、書き直し……もはや、自分でもいいのか悪いのか分からなかったが、いちおう最後まで仕上げたものをK編集長のところへ持参した。
後から、電話がかかってきた。
予想通りの全没。
自分でも分かっていたので、特にショックを受けたりはしなかったが、どうしようか、と思った。
(小池先生の御厚意でデビューは決めてもらったが、まだ、とてもそんな実力はなかったんじゃないのか、俺……)
しかし、いくら思い悩んだところで、締め切りはなくなりはしない。
何晩か徹夜して、やっとの思いで書き上げたのが、『危(やば)めのヴィーナ』という作品だった。
ギリギリ形にはなっていたが、まだまだ稚拙な作品で、愛川先生やK編集長にフォローしていただいて、なんとか『コミック劇画村塾』でデビューすることができた。
嬉しさよりも、疲労困憊しきっていて、
(なんとか間に合った……)
という安堵感だけが残る、いかにも凡人作家らしい船出となった。
そして……。
先述したように、スタジオ・シップ本社近くの、都立大学駅裏手に住まいを移したことから、またしても想像もしていなかった、"漫画血風録"が始まるのだ。
〈続く〉
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
