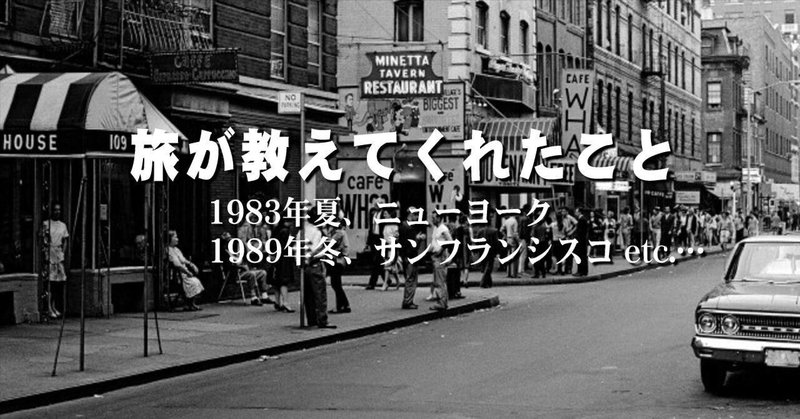
旅が教えてくれたこと (1) 1983年夏、ニューヨーク
はじめに
僕は旅が好きだ。子供の頃からずっと旅が好きだった。今も大好きだ。
小学生時代には、やはり旅行が好きだった両親に連れられ、夏休みや冬休みに日本中あちこちと家族旅行をした。中学生の頃から登山が好きになり、自宅のある愛知県や隣の三重県、岐阜県の山によく登った。高校時代は長野県や岐阜県、静岡県での登山を中心に、1人で、また友人と旅行した。長距離夜行普通列車をよく利用したのもこの時代だ。その頃からバイクに乗り始め、10代の終わり頃にはバイクで北海道から九州までくまなく旅をした。20代に入ってからは海外旅行に目覚めた。バックパッカーとしてアジアをあちこち旅行し、アメリカ大陸もあちこちバスで旅をした。30代の前半からは、仕事でアメリカに行く機会が増え、西海岸のサンフランシスコやロサンジェルス、シアトル、バンクーバーそしてシカゴなどを何度も訪れた。その間も国内ではバイクに乗り続け、休日ごとに日帰りツーリングや週末の1泊ツーリングで北陸や東北を回った。春や夏には長期休暇をとって、北海道や山陰・山陽、九州などを回った。バイク熱が冷めた40代になってからは、やはり仕事で東南アジア諸国を訪れる機会が増え、年に5~6回のペースでタイ、マレーシア、ベトナムなどを訪れている。またこの時期には、アメリカやヨーロッパにも何度も訪れている。そういった仕事の合間に、タイやマレーシアの田舎や、ラオスなどに何度も小旅行をした。ちなみに、アフリカ大陸にはまだ足を踏み入れたことはない。
年をとって居酒屋で過ごす時間が増えてからは、国内出張の合間にふらりと各地の居酒屋で飲むのが好きになった。そういえば、つい先日の休暇には、青春18切符を使って神戸・大阪の立ち呑み屋を回ってきた。
ともかく青春時代から現在に至るまで、いったい何回国内外の旅をしたのか、どこへ行ったのか、誰と行ったのか、もう思い出すのも面倒なぐらいたくさんの旅をしてきた。
つまるところ、自分には放浪癖があるのだと思う。または、騎馬民族のように移動して生きるDNAを持っているのかもしれない。何かあると旅に出たくなるし、旅をすることでいつでも本当の自分を取り戻せるような気がする。
僕は、同じ場所に定住・安住することが嫌いだ。現在居る場所、つまり自分の居場所のようなものが固まってくると、かえって落ち着かなくなる。実際に僕は、この年になるまで「マイホーム」を所有したことがない。さらに「物理的な場所」だけでなく、「社会的な場所」「自分のポジション」が固まって安定してくると、それをぶち壊したくなる。どこか別のところへ行きたくなる、そして別のポジションに身を置きたくなる。でも、旅をしている間だけは、自分が自分らしくいられる。要するに、僕は本質的な部分で社会不適合者なのかもしれない。でも、そんな自分が決して嫌いではない。
旅はいろいろなことを教えてくれる。特に一人旅の旅先では、いろいろなことを考える。第一に、旅には新鮮な出会いがある。世界を旅すれば、社会の多様性、文化の多様性、人間の多様性について、それが当たり前のことだとあらためて教えてくれる。社会の矛盾や不合理を見せつけてくれる。旅の途中で越える国境は、「世界」という共同体の本質、「国」の本質について考えさせてくれる。ある土地が持つ「歴史」に思いを馳せることで、現在世界で起きている問題を解決する方向性が見えてくる。
そして、旅先で異文化に包まれていると、自分の本質と向き合うことができる。一人旅の旅先で孤独な時間を過ごす中で、自分が何者なのか、自分にとって何が重要なのかが少しづつ明白になってくる。普段の人間関係についても客観的に考えることができる。「日常の重要性」と「非日常の楽しさ」を秤にかけることで、人生で最も大切な「バランス」を身に付けることができる。
旅に出ると、注意力が高まる。というか、周囲のもの、風景や些細な出来事を細かく感知できるようになる気がする。考えてみると、自分も含めて多くの人は、普段の日常生活の中であまり周囲の風景や出来事に注意を払わずに過ごしている。例えば通勤途中に通るいつもの道で、長くそこにあったお店が1軒無くなって更地になっていても、すぐに気が付かなかったりする。そしてお店があった場所が空き地にっていることに気付いても、そこが以前どんなお店だったか思い出せなかったりする。つまり、周囲の風景や状況の変化に対して、無関心に過ごしている。ところが旅に出ると、周囲の光景の細かい部分まで、意識の中に入って来る。「見るもの」や「起きていること」に対する感度が飛躍的にアップする。だから、旅先で得られる情報量は、日常生活の中のそれよりも格段に多い。
ただし、ひとつだけ誤解されたくないので明言しておく。僕はけっして「自分探しの旅」をしてきたわけではない。第一、僕は「自分探し」という言葉が大嫌いだ。多くの脳科学者が言うように「…人間は思考も感情も外界から『学習』する。外界を遮断して、自分の内側をじっと覗き込んでいるうちに自生してくるような思考や感情などというものは存在しない」…と思っている。旅から得るものは、あくまで視覚・聴覚・嗅覚など自分の五感で得られる情報であり、その得られた情報をどのように受け止めるかが「旅の途中の思索」であるに過ぎない。先に「一人旅の旅先で孤独な時間を過ごす中で、自分が何者なのか、自分にとって何が重要なのかが少しづつ明白になってくる」と書いたのは、「旅の中で自分とは何かを深く考えることで新たな自分を見つける」ということではけっしてない。「旅」という非日常が、普段日常生活を送る社会とその社会と自分の関り方について、少し離れた視点から見せてくれ、それによって相対的、客観的な自分のポジションやあり方を知ることができるという意味で書いたものだ。
このエッセイ集は、僕の20代から50代までの旅の記録である。どれも緻密な計画などない、行き当たりばったりの個人旅行だ。多くは2003年に個人で開設して10年以上続けたWebサイトに書き散らかした文章が叩き台になっている。もしかするとWebサイトの読者がいるかもしれない。今回は、あらためて昔の旅を思い出して、今でも手許に残っている資料や写真などを見ながら、より正確に当時の情景を描こうと加筆・訂正を加えた。
面白い話、珍しい体験…というのなら、もっと他にいくらでもある。バックパッカー時代にはアジアの辺境の地へ何度も足を運んだ。あまり人の行かないところへも行ったし、危険な目にも遭っている。でも、そんな旅の記録を残す人はたくさんいる。僕の旅の体験など、別にたいしたことではない。また10代から20代前半の頃の旅をしながら考えていたことは、今思うとあまりに青臭く、恥ずかしい。だから、あえてここでは「大人になってからの旅」だけをピックアップした。奇抜な旅、特殊な旅はあえて排除し、誰にでもできるような普通の旅の記録に限定した。そんな普通の旅の中で知ったこと、感じていたこと、考えていたことを書いた。
今になってなぜ書籍(本稿は一度電子書籍化している)の形でまとめようと思ったのか、その理由はいくつもある。1つは、例えば80年代前半のニューヨークの街の様子、当時のカルチャーなど、現場に居合わせた僕の世代の人間がきちんと書いておかなければ、記録・記憶が風化してしまうと思ったからだ。約40年前のニューヨークは、2023年現在のニューヨークとは全く異なる顔を持つ街だった。もう1つは年をとって、なんとなく自分が体験してきたことをまとめてみたくなった、というのがある。あまり他人に読まれることを意識して書いてはおらず、むしろ自分自身の「記憶の確認」ために書いている。
本稿では、基本的には自らの旅の体験をそのまま過不足なく書いたつもりだ。旅で見聞きした内容については「事実」だけを書いた。むろん細かい部分での記憶違いや、前後の旅での出会いや出来事との混同はあるかもしれないが、嘘や作り話は書いていない。一方で、個人的な背景やそのときの心情を書いた部分には多少「フィクション」が入ってる。このあたりは、全て事実を書くと自分と周辺の個人情報が特定されるというのもあるし、正直に書くのが恥ずかしいという気持ちもある。ご容赦頂きたい。
旅なんて、楽しければいいと思っている。別に、何かを学ぶために旅をしているわけではない。でも、結果的に旅をすることで新たに知ったこと、旅の中で学んだこと、旅をしたおかげで考えるようになったこと、旅のおかげで心が豊かになったこと…は、たくさんある。少なくとも僕は、数多く旅をしたことで、多少は楽しく豊かな人生を送ることができている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
