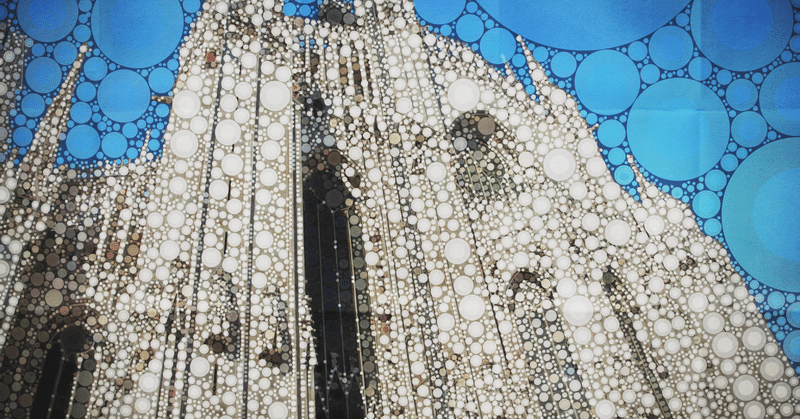
王国のあさ(1)
…それは、王国。
かつて夢見し者の、永遠の楽園。
けふのうちに
とほくへいつてしまふわたくしのいもうとよ
うすあかくいつそう陰惨な骸から
血のりはびちよびちよふつてくる
青い葡萄のもやうのついた
これらふたつのかけた陶椀に
おまへがたべるあつものをとらうとして
わたくしはまがつたはうちやうをふるひ
ちちははのざうもつを掻きだしたのだ
ああ
わたくしのけなげないもうとよ
ゆくといふいまごろになつて
わたくしをいつしやうあかるくするために
こんなさつぱりした血のひとわんを
おまへはわたくしのためにのんでくれたのだ
ありがたうわたくしのけなげないもうとよ
わたくしもまつすぐにすすんでいくから
「吉澤さん。なんですか、これは」
若い刑事が、床に落ちていた紙切れを拾いあげる。
呼びかけられた、年かさの刑事が目をあげた。
「…ん」
「犯行予告でしょうか。…日記? 詩ですかね」
「予告じゃなかろう。被害者はもう、殺されちまってるんだ」
吉澤保は懐からタバコをとりだそうとして、肩をすくめる。
長年の習慣が、一連の動作をやめさせずにいる。
都市とも呼べない集落は、町というより寒村と呼ぶほうがしっくりくる。
北日本のある工業地帯で、鉄工所を営む夫妻が惨殺された。
夫の藤原忍、五十八歳。
妻の藤原聖美、五十七歳。
次女・土田アゲハの夫――土田聡からの連絡で様子を見にいった警察官のうち、気の弱い者は吐いた。
犯行現場となった住宅の、寝室の布団には大きな血の染みができていた。
頭部を切断された二つの遺体は、工場の休憩室で徹底的に解体されたらしい。
骨を外して切り分けられた部位が、静かに唸る大型冷蔵庫に眠っていた。
臓器は傷つけられることなく取り出され、きれいに洗ってひとつすつポリ袋に入れらていた。丁寧に部位の名前を書かれ、並べられている。
大きなボウルには固まりかけた血液がたたえられ、陶器とお玉が添えられている。
奇妙なのは、遺体の損傷部位である。
致命傷となった頸椎のほかに傷は少ない。
切り落とされた頭部は、大皿に乗せて居間のテーブルに飾られていた。
被害者夫妻の額には、油性マジックのような筆記具で王冠が描かれている。子供の落書きのような、下手くそさだ。
夫妻には、二人の娘があった。
次女の土田アゲハは、三十五歳である。夫の土田聡は、三十二歳。
ふだんは夫の任地である大阪に住んでいたが、里帰り中に事件に巻きこまれた。
殺害された夫妻とともに発見され、病院に搬送された。
土田アゲハは、無傷である。
口の中に臓器の一部を押しこまれ、奇怪な声をあげていた。…けけけっ。きひっ。
唯一の目撃者と思われるが、証言できる状態ではない。
「…別居している長女――三十七歳か、藤原アケヲは」
「勤務先に休暇届けを出していて、連絡がとれません。現在のところ、捜索中です」
「…ふむ」
吉澤保は、惨劇の舞台となった住宅を出た。
住宅のすぐとなりには、藤原忍の経営する鉄工場の建物がある。
分厚い鉄板を加工するための機械や工具が埃をかぶり、所狭しと置かれている。
工場主である藤原忍にとっては、作業効率を優先した並べかたであったのかもしれない。
吉澤保の目には、雑然として見えた。
「…何でもアリだな、これは」
凶器となりそうな、道具だらけである。
町はずれの工業団地の、一番隅という立地が、発見を遅らせた。
日中は周辺に建つ同様の工場が騒音を発しているため、よほどの大声でもかき消されてしまう。
夜は無人に近い状態になるため、近所からの通報もなかった。
妻から返事がないことに不安を感じた土田聡が警察に相談しなければ、発見はもっと遅れただろう。
吉澤保は工具が散らばる工場を出て、天をあおいだ。
若い刑事が後を追い、手袋をはめた指先につまんだ紙片を掲げた。
「…どうします?」
「…並木。おまえが調べろ」
――わたしのトモダチが、殺されました。
きのうの、ことです。
電気鏝を挿しこまれ、頭の芯を焼かれたのです。
天井から逆さに吊るしたら、とってもコウリツよく、血が落ちるんですって。
…ぼとっ、ぼとり。
床にはいっぱい、血だまりができたでしょう。
涙みたいな、赤い色。
せめて、それを見とどけたかったのに。
知らされるのはきまって、殺されたあとでした。
殺さないで…! と。
泣き喚いても、叫んでも。ムダなことは、わかっています。
でも、会うのが最後だと知っていたら。
なにか、声をかけたでしょう。
いつもよりおいしいごはんが食べられるように、できたかもしれません。
父と母の目をぬすんで、食事を――彼らはなんでもわたしに押しつけるから――サラダぐらい、用意してあげられたかもしれません。
…明日は、わたしの番…?
…ワタシの番、でしょうか……?
…ビニールのテーブルクロスがかけられた食卓の上に、黄色っぽくあぶらの浮いたシチューが置かれています。
冷めるとあぶらの固まるそれは、わたしのきらいな料理でした。
ほかにあるのは、白いごはんだけ。シチューだけをおかずに、食べられません。
ワガママだ、としかられても。
ふりかけなんかで、ムリヤリ食べるしかないのだけれど。
わたしがもっと小さかった頃、ふりかけをかけた妹は、父によって車に閉じこめられたことがあります。明かりの消えた夜に、です。
妹の泣き声が、耳の奥に残っている気がして。わたしは、ふりかけのビンを上手につかめません。
シチューのルーは鍋の中でとかすだけのもので、メーカーまで知っています。
スーパーでいちばん、安いものです。
買いものは、わたしの役目。安いほど母が喜ぶことを、知っていました。
学校が終わるとわたしは、家に帰らずにスーパーによります。
その日一番安い食材をさがして、数件回ることもあります。
自転車のカゴは教科書の詰まったカバンでいっぱいなので、買い物袋はハンドルからぶら下げます。
バランスが不安定になるけど、がんばってうちに帰ります。
それが、唯一母のよろこんでくれたことだったので。
…金くさい味がするスプーンで、平らなお皿からひとすくい。
知っているはずのシチューから…ヘンナアジガシマス。
エタイのしれない、肉が入っています。
わたしは、肉がきらいです。
肉はいつも、イヤな匂いがするから。
…ダシがでるから、いいんだ。
母はそう言って、なんでも料理に肉をいれるのだけれど。
ぜんぶきらいなんだと、いえずにいました。
ムリやり、飲みこもうとしました。
固い肉が、ノドの途中でつかえます。
食べられたくない…とがんばっているみたいに。
赤身もあるけれど、白いところも多いのです。
あまり煮こまれていないから、脂身もかたちのまま残っています。
威勢がよいぐらいに弾力があって。憎らしいくらいに、ぶりんとしています。
ほとんど、噛みません。
なのに、あぶらの味がしみだしてきます。
ようやくひとかけら、飲みこめました。
母の目が、ねっとりとわたしに絡みつきます。
「…今の、それね。あんたのオトモダチの肉だから」
「――え」
「――……の、肉だから」
「――…、っ、まって…っ! … 殺、したの…?」
…えへっ、と母は笑います。
…へへっ、に近い発音が間延びして、空気がもれたような音を響かせます。
…コワレテイル。こわれています、なにがが。
わたしは思わず、さけびます。
「…殺さないって…。前に、そう言ったじゃない!」
その理由まで、わたしはきいていました。
だから、大丈夫だと思ったのに。
また会える、はずだったのに。
母は、大きなスプーンでシチューをすくいます。
肉のかけらを、口のなかに放りこみます。
犬歯で引き裂き、奥歯ですり潰して。わたしの友達の肉体の一部を、完全に消滅させてから、言いました。
「…いまさらそんなこと、言われてもね。もう、遅いんだよ。片付かないから、早く食べて」
…この、家。
ぜんぶ、壊れてる!
…わたしは、吐きました。
いいえ。
吐きたかったけれど、もう飲みこんでしまっていました。
食卓では、よけいなことをいうのはゆるされていません。もう、これ以上は…。
わたしはお皿をそのままにして、立ちあがりました。…そのはずだと、思います。
記憶が、途切れています。
そういうことは、めずらしくないのです。
わたしはだんだん、つなげてものを考えないようになった、かもしれません。
うまく歩けなくて、ベッドに横たわります。
へんな、あぶら汗がでてきます。
…あの子はあれを、食べたのかしら。
二つ年下の、わたしの妹――アゲハは。
彼女がいたのか、記憶にありません。
…食べたんだわ、たぶん。
おかずはそれしか、なかったから…。
事件発覚から数日後、捜査は大きな進展をみせた。
惨殺された夫妻の長女・藤原アケヲがあらわれたのである。
同町より三十キロ余り離れた町村の交番に、彼女はみずから出頭した。
藤原アケヲという女の、周囲の評価は概ね一致している。
未婚であり、現在も独身である。
地方公共団体が直轄で営む畜産公社に長く勤める。同社の業務は、九時から十七時までである。日曜日と祝日は休みであり、きわめて安定している。
給料は、一人の生活を支えるにはじゅうぶん過ぎるほどの額が支給されている。
藤原アケヲは、きわめて真面目な仕事ぶりということだった。
「おとなしい人ですよ。あの人が怒ったの、見たことがないですね」
「自分の話はほとんどしなかったけど、本は好きみたいだったね。休憩時間にいつも、なにか読んでたよ」
「少しかわってるな、と思ってました。あの人が笑ってるところ、みたことがないし。あんまり話、しなかったなぁ。同期でしょう、って? そりゃ、つきあい自体は長いですよ。でも、何を話しかけても、乗ってこないもんで。だんだん話さなくなったなあ。…いじめとか? ないない、ないですよそんなの。みんな、そんなに他人に興味ないですもん」
藤原アケヲは、表情にとぼしいほかは落ち着いて見えた。
もっとも、職場の人間に言わせれば、藤原アケヲとは元々そうした人間だったようである。
警察署内の一番奥にある取調室に案内されたときも、動揺の色をみせない。
並木陽斗は、その横顔にちらりと視線を走らせた。
…図太いだけなのか、感情を抑えているだけなのか。
吉澤ほどの経験と勘をもってすれば、見抜くことができるのだろうか。
古狸とあだ名される吉澤保は、飄々とした態度で廊下を歩いてゆく。
きわめて重要な参考人が手中に飛びこんできたときにも、彼は毛ほども感情の色をみせなかった。…そうですか。自分からね。
パイプ椅子が、三つの軋む音を立てる。その残響が完全に消え失せたところで、乾いた声が静けさを割った。
「…藤原アケヲさん。あなたのご両親の、事件についてだが。あなたの知っていることを、我々に詳しく教えてくれませんか」
パイプ椅子が、みしりと鳴く。
自然と、前のめりになっていた。
並木陽斗はうっすらと赤面して、握りこんでいた拳を開く。
ごま塩色の後頭部に、静かにみていろと言われた気がした。
粘つく唾液を飲み下す。
藤原アケヲは膝の上に拳を置いて、伏し目加減に斜めから射す高窓の光を受けていた。
結ばれた黒い髪の、毛束がうなじにほつれている。
化粧っ気のない頬の、血色は薄い。薄い唇にも彩りがなく、肌と同化していた。
整っているといえなくもないが、精細がなかった。
その唇が、かすかに動く。
空中に、吐息が吐きだされる。
そのわずかな震えが肌に触れた気がして、並木陽斗は戦慄した。
――藤原アケヲが、笑ったのだ。
…この、女……。
吉澤保は、ぽりぽりと頭を掻いた。
「…協力していただけると、大変ありがたいですがね。我々は、あなたに強制することはできないんですよ。…だから、あなたは一切答えなくてもいいんです。伝があるなら、弁護士を呼んでもかまいません」
「…弁護士」
女はそう言ったのだが、並木陽斗の耳にはベンゴシ、とカタカナで響いた。聞いたこともない、異国の言葉のように。
「心当たりがなければ、国選弁護人がつけられます。どちらを選ぶのも、あなたの自由です」
藤原アケヲは、はじめて目をあげた。
取調室の二人の男たちを見つめてから、ふたたび笑った。
今度は、晴れやかに。
「…弁護士は、必要ありません。なぜなら、弁護をしていただく理由がないからです」
「…そうですか」
吉澤保は、耳に挟んでいたボールペンをとってくるりと回した。
「…あなたが不要と申し出た場合でも、国選弁護人はつけられます。少々、時間がかかりますが。…それまで、どうしますか。今日のところは、お帰りいただくとして。しばらく、留置所をホテルがわりにしていただくしかありませんがね」
「…かまいません」
藤原アケヲは、よどみなく答える。
…本当に、わかっているのだろうか。
逮捕こそされていないが、吉澤は身柄を拘束すると言っているのだ。
吉澤保のごま塩頭が、ひょいと左に傾く。
「…あ。ひとつ、忘れていました。質問しても、かまいませんか」
…ええ。どうぞ」
「…弁護が不要な理由を、教えてくれませんか」
無辜の一般人に見えるであろう、平凡さを寄せ集め、コートのように羽織っている。
藤原アケヲという、その女の。薄い血色をした皮膚の内側で、なにものかが蠢いた。翼を広げたその声が、静けさを撃ちおとす。
「――わたしが殺しました。あの人たちを」
取調べ室の床におちた影が、淡い縞模様を描いていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
