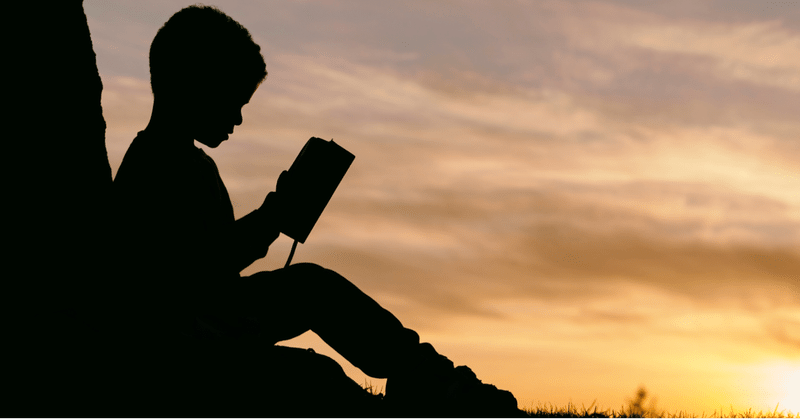
ルージャより愛をこめて(5)
ジャイロは、本当に故郷に連れて行ってくれるのか、と聞いているようだった。とても頭のいい子のようだ。すくなくてもわたしよりも、彼にとっての外国語であるわたしの言葉を理解している。筆談やみぶりをまじえているが、彼の意志は不思議なほどよく伝わった。
ここからは便宜上そのまま会話を書いていく
「近いうちにここをでて首都を目指す」
とわたしは言った。ジャイロが一緒に来てくれれば、通訳や道案内になりそうだから、わたしにも都合がよかった
「なんで、わざわざ」
ジャイロはわざわざ危険地帯に赴くわたしに、疑問を抱いていた。
「ここに死にに来たんだよ」
とわたしは当然のように言った。ジャイロの目はその時、純粋なこどもように輝いた。それはジャイロにって、わたしという同じ目的をもつ同胞に出会えた喜びだった。誰にも理解してくれない、支持してくれない、ゆがんだいびつな希望、絶望が常態となった死への希求。わたしに共感をいだくなんて、もうすべてが手遅れだ。それは一筋の光がさすような、悲劇のはじまりだった。
「おとうさん、おかあさん、おや」
とジャイロはいって、両手をぱっと広げて、BAN、と唇をまるめながら、閉じるのを繰り返した。空中に指を向けて、ゆらゆらとゆらしながら、指先を地面におろし、手をぱっと広げた。
ジャイロのいうことを解釈すると、空から降った爆弾、砲弾かミサイルかに両親が巻き込まれた、といったところだろうか。真偽はよくわからなかったが、すでに両親は死んでいて、ジャイロもその後を追いたいと、思っているようだ。
わたしは目を細め、だきよせるようにジャイロに両手を向けた。かれははじめはとまどっていたが、ゆっくりとわたしにむかって上体を寄せた。
「ボクの母親も死んだ。たった一人の家族の、母が」
二度と、もう二度と、思い返したくなかった、母親の死を思い出さざるを得なかった。わたしの死んだ母の面影は、見たこともないジャイロの死んだ母の面影どこ重なった。そして母親の死を、はじめて誰かに伝えたいと思った。母の死を、何かに捧げ、祈りたいと思った。わたしはひとりだということを、どこか世界の真ん中で叫びたくなった。
物心ついたころから、父親はいなかった。遺影もなかったので、死んだわけではないのだろうが、ついに一度も、父のことを聞くことはなかった。
母は女でひとつでわたしを育ててくれ、大学まで卒業させてくれた。しかし当のわたしは、まともに就職もできず、アルバイトもしだいにしなくなった。せめて養育費ぐらいは返したかったが、それもかなわなかった。何十年もただめしぐらいで、親のすねをかじって生活していた。何も、育ててくれた恩返しもできずに。
「ごめんね」
と、今際の母は言った。それはどう考えてもわたしが言うべき言葉だった。何十年も世話になり、独立もできず、恩返しもできず、手間もお金もかけさせて、結局最後まで、何もできなかった。情けなくて謝罪の言葉も出なかった。わたしの命を、かわりに、あげたかった。心臓をわしづかみにして、ひきちぎり、母の胸の中に押し込めたかった。
母に背を向けたとき、わたしはぼろぼろと涙を流した。悲しさなのか、悔し涙なのかもよくわからなかった。
「どうか、わたしがいなくなっても、いつまでも元気でね」
母はやせ衰えた手を伸ばして、かすかに笑っていた。
わたしは葬式もまともにせず、にげるように国外にやってきた。
はじめてこのことを誰かに話した。言葉のわからないジャイロにそんなに伝わることはないだろうが、逆に都合がよかった。誰も聞いていない場所で、ただ口に出していいたかっただけかもしれない。
わたしは失望をされると思った。ジャイロだけではない。この話をきいたすべてのヒトに。形だけは同情や慰めてくれるかもしれない。しかし、その裏にある失望は、容易に見通せた。
ジャイロはわたしに手をのばした。それはみじめなわたしの首をはねる刃だろうか、無力なわたしの心臓を貫く槍だろうか。その手はわたしの頬に置かれた。ひやりとした感触があった。手は温かかった。いつのまにかわたしは泣いていた。静かな、まっすぐな涙だった。
ジャイロはこぶしを握って、わたしの胸にとん、と手を置いた。
わたしはこの施設にきたとき、何度かこれをされたことがあった。深夜に一人で働いていると、施設の人がなんどか、それをすることがあった。
それは感謝と敬意の証だった。
「ずっと母親のそばにいたあなたはすばらしい。長い間大事な家族を、守っていたのですね。僕は結局、守れなかった」
ジャイロはそう言っているようだった。
つづく
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
