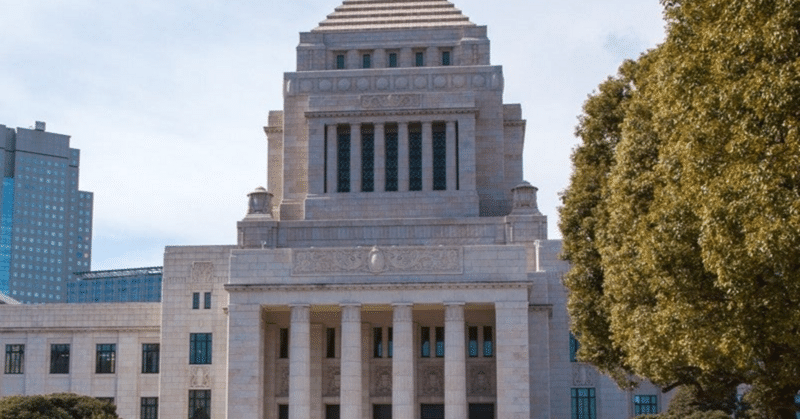
第76回「公共ってこういうことですか?」(「公共」研究チーム)
第76回の研究会は、兵庫県内の工業高校に勤められている報告者より「公共ってこういうことですか?」というテーマで公共の授業実践を報告していただきました。
学習指導要領に見る公共の構造
まず、学習指導要領の「公共」には以下のような構造を見て取ることができます。
・大項目「A 公共の扉」= 価値判断の手掛かりとなる考え方や公共的な空間における基本原理を獲得する。
・大項目「B 自立した主体としてよりよい社会の形成に参画する私たち」 = 法・政治・経済に係る具体的な社会の課題について、価値判断を行う。
※具体的な社会の課題をより深く理解するためにしくみ等の学習を行う。
※大項目 A で獲得した考え方や基本原理を用いて価値判断する。
・大項目「C 持続可能な社会づくりの主体となる私たち」= 現代の諸課題について、法,政治及び経済などの各領域を横断して総合的に探究する。
学習指導要領では、
「大項目『C 持続可能な社会づくりの主体となる私たち』において、共に生きる社会を築くという観点から課題を見いだし、…その課題の解決に向けて事実を基に協働して考察、構想し、妥当性や効果、実現可能性などを指標にして、論拠を基に自分の考えを説明、論述する。」
と述べられており、「妥当性や効果、実現可能性」を指標として社会の課題解決に向けた考察や構想を行う必要がある。大項目Cにおける生徒の課題解決や構想が机上の空論で終わらないためには、大項目Bで法・政治・経済にかかる具体的な課題についての価値判断をとおして、法や政治・経済に関する仕組み等をしっかり学んでおくことが重要だと考えられる。その大項目Bは以下のような学習の流れで進める。
①現代社会の諸課題の提示→②課題解決のために課題の背景・構造を学ぶ(解決に向けた取り組みなど…)→③価値判断
報告者の思いと公共観
公共の授業を通して、工業高校の生徒を社会が“わかる”子にしたい。また、現代社会の諸課題を“自分事として捉える”子にしたいという思いで報告者は公共の授業をデザインされている。
一方で、報告者が勤務している工業高校の生徒は、概念的なものの理解がすごく苦手で、具体的なものでないと理解しようとしない。抽象的な話になると、すぐにどこかに意識が飛んでしまう。生徒にとって具体的な事例などを用いながら、いかにして生徒を概念的理解へ導いていくかがカギである。
そんな生徒たちにとって、「公共」は具体的な社会的事象や社会が抱える課題から学習を始めることができる科目であるということが良い点であり、 「何のために学ぶのか」や「自分とのかかわり」が明確になりやすいという特徴がある。また、現代社会の諸課題に関する教材研究はそのまま歴史総合などでも使うことができる。
しかし、教育内容を包含する現代の諸課題の選定をする際、生徒が自分事だと感じることができる課題を選定することは容易ではない。また、「金融教育」や「消費者教育」「主権者教育」など、多方面からの期待にどう応えるかも難しい課題である。さらに、公共の扉で登場する概念の関係性を理解するのが難しい。例えば、人間の尊厳と平等、個人の尊重、民主主義、法の支配、自由・権利と責任・義務などの憲法学、法学、公共哲学等で提唱される概念の理解へ生徒を導くにはどうすればいいのか。
1学期の実践について
1学期は大項目A「公共の扉」の授業を行った。例えば、功利主義と義務論を理解する授業では「トロッコ問題」について生徒に考えさせ、そこで獲得した知識を使って次の授業で「自動運転システムはどうあるべきか?」について価値判断を行うといった授業を行った。
そのほかにも、漫画の世界を例にして「法の支配」を理解させる授業なども実践した。多くの授業で、具体と抽象を往復するような形の授業であった。
テストは、授業中の生徒の思考の流れに沿う形で会話文形式のリード文や設問を作成した。
2学期以降の実践について
単元構成を
1,現代社会が抱える諸課題を単発でひたすら投下していくか?
2,小テーマを貫く大テーマを設定して、小テーマのつながりをもたせるか?
で悩んでいる。
個人的には単発授業の連続投下でいきたい。以前、大テーマを設定して実践したが、テーマが大きすぎたため、生徒にとって学習の目的がぼやけてしまうということがあった。また、大項目Bで行う現代の具体的な諸課題についての価値判断は、単元を通した大テーマを設定しなくても可能であると考えられる。
一方で、大項目Cで探究的な学習活動を行うためには、大項目AやBである程度探究的な学びの作法や手順等に生徒が慣れておく必要があるため、その点を重視するなら単元を通した大テーマを設定する方が良いとも考えられる。
質問
Q.概念理解、自分がどれだけ理解できているか自信ない。先生はどうやって理解しようとしているか。生徒に教えるのも難しいが、そこはどうされているか
A.本を読んでも余計にわからなくなるところもある。法の支配など。自分が納得できる理解に至るまで勉強したいが、そこに到達できなかった。
Q.「妥当性、効果、実現可能性」…人って、イメージとか理想で動く部分もあると思うが、そのへんはどう考えているか
A.生徒からは理想が出てくればいいが、教師からは実現可能性からぶった切りたい。そこから生徒にもう一段階考えてほしい。
Q.なぜ大テーマが嫌になったのか
A正直、学校の文脈がある。大テーマをやっている間は概念的な学習をやっても学ぶ意義をもてると思うが、今の学校ではそれに耐えられない。それよりは、一回一回「今日はこれについて考えようぜ」って感じでやったほうが生徒も主体的に考えられると思う。
Q.プリント1枚につき1時間?
A.だいたい1時間で終わる。Teamsで生徒間で情報共有や意見の書き込みもやっている。
議論
以下、ブレイクアウトルームにて以下の2点について議論しました。
① 公共ってこういうことですか?
② 授業で扱うテーマにつながりやまとまりは必要でしょうか? 必要ならば、どんな大テーマが良いでしょうか(公共は単発授業の連続投下でも十分おもしろい気がする)
・ 考えさせるテーマがはっきりしている
・ カリキュラム全体で「公共的な空間」を意識することが大事
・ 毎回価値判断しながら大テーマを考えていくという形はどうか?
・ 生徒にとって身近な例から概念的な理解へと導くために、学校生活の中で生徒が体験していることを最大限活用する。例えば、学校生活の中で校則を変える時、どうやって変えるべきか。アンケートで校則を変えることに多数の票が入ったので校則を変えるというのは良いか?など
・ 公共にかわったことで、「公に奉仕しない人はダメだ」とならないようにしたい。そのような道徳を強制する危険性もある。
・ 大項目Aに時間をかけすぎてしまうという問題が全国的に発生している。Aは10コマ、Bは50コマ、Cは10コマ時間数を考えると、単発じゃないと難しそう。
・ 大項目Cでは、生徒は探究の成果を書かないといけないが、Cで生徒はいきなり書けない。大項目Bで書く練習をしとかないといけないので、その時間確保が難しい
・ 共同体の中の一員としての自分を考える。どんな社会を構成していくかを考えないと、小中学校公民と一緒になる。小中学校からの流れを分かったうえで考えたい。
・ 教科書によって取り上げている課題も違うので、どんな課題を取り上げてもいいのでは?
・ いろんな科目の探究がケンカしそう。あまりにも真面目に学習指導要領にのっとりすぎることで、生徒も教師も疲弊しないか?うまく交通整理すべきでは?
25名
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
